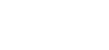041. 京都は多様な生活演出、訓練の舞台
京都に生まれ京都で育った私にとって、大学を卒業して昭和40年、東京の設計事務所に就職するまで、京都の文化・風土や生活慣習の中で自分が如何に育ったのかをそれほど意識することはなかった。
うどん屋での薄口、濃い口醤油、味付けの違いから、初めての寮生活の1人暮らし、自炊のための食材買出し、市場ではなく、渋谷のデパートの地下、魚売り場でも関西では見かけなかった金目鯛の赤い姿。何かが違うと感じた東京生活の始まり感はいまも鮮明である。
勿論、言葉使いも違う。仕事での電話の応対にもしばらくは苦戦。身近に地域社会を感じられない。これが大都会か。
やがて生活舞台となった渋谷、新宿、六本木・赤坂あたりを同僚や友達仲間とアングラ劇場での演劇公演、コンサート、色々な社会問題の研究会、新しいタイプの商業施設など、若い世代のすさまじいエネルギーが溢れかえる混沌の中でその新鮮さに感動もしていた。
アメリカの月面軟着陸成功、小型IC化電卓の発売、男子服のカラー化、女史雇用労働者1000万人を越えるなど、1960年代後半からの社会の変化はあらゆる生活舞台に変化をもたらし、その渦中に日々の暮らしをしていると「進歩」「拡大」「変化」全てが自分の成長感とイコールな気分であった。日本の高度経済成長期といえるこの時期にグローバル化の潮流が起こりはじめ、生活価値観の変化が日本の文化の成育の方向性を見失わせ、表層を意図なく無差別に覆い尽くすことになったと思える。
6年間の東京生活を終えて、京都に戻ったとき、京都駅の静けさに「これはなんだ。」とわけなく驚くと同時に、本当にほっとした安息感を記憶している。
再び、祇園祭の鉾町に暮らし始めて、子供の頃と比較すれば形骸化したとは言え、町内の祭事、学区の行事、京都の四季折々の祭りごとなど生活を彩る出来事は身近で、地域社会の一員として生きている「場」の実感がある。祖父、母親、自分、そして子供と4代が通った明倫小学校が都市のドーナツ化現象による学童減少で廃校になったが、校舎がなお、芸術センターとしてそのまま、その姿をとどめていることは、不思議なほど自分の歴史、時の流れを原点化してくれる。
ヨーロッパの都市における、旧市街、新市街といった明確に区分された歴史的計画性はないが、京都には地名(町名)に名残を残すようにちょっとした一画が色々な伝統や名残をとどめて渾然と存在し続けている。そのため、いまだ市民レベル、生活者の身近なところで自然に受け継がれていく文化の土壌を失っていないと思う。
社会の変化、伝統産業の衰退にあわせて、ほんの隣にも職人のおじさんが住んでいて、色々な分野の技や芸を身近に見聞できた子供時代のようには行かないが、今でもまだまだ色々な職人魂からにじみ出る所作や言動が、自治会活動や日常の生活の中に息づいているのを知る。
「ハレとケ」「究極のコモンセンス」「特殊解と一般解」「右脳と左脳の働き」など、いずれにもバランス感覚を如何に取るかの才覚がとても重要であるが、京都は都市と田舎、伝統と現代、生活価値観としての美意識と感性が実に程よく日常生活の中に感じられるところである。
それは、1000年以上にわたる「都」としての歴史が育んだ誰もが簡単には捨て去ることが出来ない精神的、感性的DNAとでもいえるものがあるせいであろう。
時々仕事の関係で、東京に行くことがあるが、ますます複雑になった地下鉄の路線図に戸惑うように、霞ヶ関に始めて高層ビルが建ったときから、都心の開発、建築技術力世界一の日本の力がいたるところに見られ、即、インターナショナルであることが、かえって日本人の美意識の根底に潜む特殊解の魅力を捨てて一般解にしすぎてしまったように感じる。
東京には近・現代の機能主義、合理精神を象徴することに於いても、巧みに日本人の感性を表現しているところもあるが、その存在のスケールや固有性において、一人一人の人々の生活との絆を希薄にしてしまったために、日本の伝統、文化価値につながりながら新しい未来への文化創造のエネルギーを全体として育成できない「都市」になってしまったと感じる。
一方、京都は戦争による爆撃をまぬがれ、奇跡的に世界一歴史のある都市として生き残ったばかりか、その後の都市機能としての経済力の弱体化もあって大きな変貌がなく、歴史的な観光資源を始め、日本文化を担ってきた伝統的な工芸、技術や様式文化が今も残され、継続している。日本人の営みの歴史を垣間見たり、実感できる機会が身近にあるという都市環境は、やはり、生活を彩る感性を磨き、明日を生き抜く才覚を共有しながら鍛えあえる格好の「場」であるといえる。
042. 継承の大切さ
先日、ニュースで定年のない機械・機器メーカでは60歳以降も定年がないので、給料もダウンすることなく、熟年技術者と若手がペァーになって楽しく、生きがいを持って働き、技術の継承をやりながら、会社経営を見事ささえ、発展させている事例を取り上げていた。 社長は技術が継承されるこうした仕組みがなければ、会社そのものが存続できないともインタビューに答えていた。
近年、利益追求のため、能力主義偏重、デジタル的雇用が巾を利かせてきたが、人類の営み、生活を踏まえたものづくりにおいては、プラスもマイナスも含めてじっくりと継承されるシステムが必要である。
漫然とした終身雇用制をよしとは思わないが、従来の日本の企業風土は、終身雇用による共同体意識が、人々の精神的健全性をも育むゆとりをあたえてきた。
物の生産性のみならず目に見えない国家の質を維持・発展させることにも大いに寄与していたと思う。
生物としてDNAが継承する人間資質も勿論のこと、親子の間に継承される品格も、日々の生活習慣や倫理観などの伝え方、伝わり方によるところが大きい。
つまり、代々継承されるものの内、何が伝えられなくてはならないのか、色々な状況の中で正しく理解され伝わっていくかが大切である。
しかし、単身者世帯の増加、競争社会の中で切断される連帯や信頼感は、伝えるべきものの姿を見えにくく、伝わりにくいものにしている。
自然に継承されるべき日本人の特性、品格がぼやけてしまっては、将来、日本が多民族国家に移行していくとき、一層の混乱を生じるかもしれない。
環境問題は生命存続の喫緊事項ではあるが、民族の資質、文化継承は生きる意味の大切さ、人類存続の重要問題である。色々な教育環境、方法も時代に合わせて検討されるべきだが、終身雇用制が持っていたような職場生活と一体化した生活建築力の継承制度は大いなる日本の人間教育制度の一つではなかったかと思う。
現代、終身雇用制が崩壊しつつ、能力主義、非正規社員制度の拡がりの中で、新しい工夫や知恵を生み出す「場」、目に見えない大切な人の資質を育み磨く連帯感、利得抜きの思いやりが交流するチャンスが奪いさらわれようとしている。
長い間培われてきた日本人の力、戦後の経済発展を支えた力もその根底に日本の終身雇用制度や、江戸時代からの寺子屋など文化力を含めて伝える教育制度のおかげではなかっただろうか。
親子の間で継承すること、私が孫にも伝えたいことは何か。子供の頃、銭湯帰りの道で父親から色々聞かされた話を思い浮かべながら、まじめに考え込んでしまう。
姿も見えないネット交信者も、本心、何を伝えたのか聞いてみたいなと思った。
043. 新年のはじまり
元旦の朝、近くに住む長男、次男夫婦もそろって、毎年のごとく私宅で新年を祝う。
結婚以来、京都にいても山荘にいても、変わらずおせち料理をつくり続けてくれる女房殿には感謝。
「今年の黒豆の煮具合は」などいつも料理の出来具合に御託を並べる息子たちには、口にはしないが「文句を言うなら自分の嫁に作ってもらえよ」とちょっと気色ばんでいる。
それぞれ世帯を持ちながら、実家めぐりでおせち料理など作らない息子たちの気楽さ加減にそれぞれの家族のあり様はいかがかと思うものの、その実、こうして何時までも皆が集まって正月を祝える平安な時を我ら夫婦は大切にうれしく思っている。
暮れからお正月、女房殿の忙しさのストレスのはけ口は、全て私が受け止めて、小言を聞き流しつつ、ちょっとお手伝いの真似事で切り抜けて、無事新年というわけである。
次男の嫁は、今日明日にも出産という事態で、「何とか元旦、お雑煮も食べられて良かったね。」と皆で談笑。それでも12月31日に2歳になったばかりの孫の一挙手に、はらはらの連続、皆の目線を独り占め、にぎやかなことである。
私は今年も和服を着てことさらに日本の正月を味わっている。今年は帯がさっと一発で締めこなせたので気分が良い。それにしても和服は暖かい。環境問題、省エネ時代、昔の人、日本の文化は結構、循環型、自然に優しかったのだと想いが飛ぶ。
2日の夕方頃からなんとなく次男の嫁が「おなかが痛くなりだした」。夕食の後、これはいよいよだな。2歳の孫、はるちゃんを我が家に預けて夫婦でいったん帰宅し、その後、病院に行く手はずとなった。孫は一応聞き分けた様子であった。
いつものお泊りどおり10時前にはお風呂にいれって寝かしつけようとしても「母さん、心配」となんと目に涙浮かべて12時になっても眠らない。女房殿が抱っこしたりおんぶしたりでやっと寝付く。 病院のほうはどうなったやらと思いながらラジオを聴きながら寝室で添い寝をしていたら午前の4時に目を覚まし、また「かあさんは」としくしく泣き。女房殿はダウン。2階に下りて「DVDを見る」と言い出す。気を紛らわすのも致し方なしと私が抱っこして居間に降りる。機関車トーマスの物語は不安を取り除くにはだめとみえ、Kiss、キスという色々な歌が流れ、調子よくダンスが流れるDVDを所望する。
真夜中というか、あたりは静寂の中、薄明かりの中でDVD画像のみ元気よく流れる。
時々画面に反応しながら何か歌真似。もう寝るかと思いきや、「もう1回」とお目めパッチリ。とうとう朝の7時まで3度も同じDVDを見るハメになる。4度目に入るかと思いきや私にもたれてコックリコ。寝室に運んで、又、起きられてはとソファにねかせる。
あたりはすっかり夜が明けて、結局「徹夜か」と寝顔を見ながら覚悟を決める。
044. 日中関係の行方
ここ数年、日本と中国の関係は経済活動の相互関係が拡大するにつれ色々な軋轢、摩擦も又、人的、文化交流もすべてにおいて抜き差しならない関係段階になってきていたが、特に、経済活動における利害関係の先行突出が最近の尖閣列島における領有問題を機にあらわになり、隣国同士の平和な関係を築こうと目指す多くの願いを、暗雲の彼方に吹き飛ばしてしまいかねない。
共産主義と元々の中華思想に洗脳された中国の人々の色々な生活局面での振舞いは、日本人には馴染めぬことも多く、アンケート調査などでも日本人の対中国への好感度は低い。
自国民の先達が営々と築いてきた文化や技術に対する尊敬の思いなどに対する対応の違いなどは中国に、「井戸を掘った人を忘れない」などということわざがあると聞かされるのに合点がいかないことが多い。
日本の企業も,経済的合理性を,収益性を求めて、集中的に中国に投資、生産基地化につとめてきたが、すこし目覚めても良い時期なのかもしれない。
国家間の平和関係を考えるとき、冷静に正義の判断が出来ないくらい、経済関係(利害関係)の駆け引きがキーポイントになるようなことは、卑近な男女関係に等しい情けない関係とも言える。
アジアにも多くの国家民族があり、最近の中国の中華思想による覇権主義の行動は周辺国にも多大なプレッシャーを与え、アジア圏の日常的な安寧を脅かし始めている。
情報化社会、グローバル化時代、もはや確かに1国だけで色々な問題が解決されるわけではないが、だからこそ、世界の諸国は、ひと時、中国への投資を控え、中国の覇権主義への熱を冷ますことに一致協同する必要があるのではないか。中国が今の経済的発展は決して自国の力だけで達成されたものではなく、多くの国の援助があってのことだいうことを認識する時間、チャンスが必要かと思う。
日本もまた、経済効率ばかりを追い求めるのではなく、国内において人類に必要な技術開発などの研究、製品作りを人材育成、雇用創出もあわせながら智恵を出していかなければならない時代である。 20世紀後半からの人類の進歩思考はその成果の中で曲がり角、転換を求められている。現実問題としての世界、いたるところの紛争は同じ種から火を噴いている。 これからの日中関係のゆくえは?日本の政治家はどうしようとしているのか。
最近の日々の新聞、テレビなどのニュースにごまめの歯軋りをしている。
045. 孫と夜の公園遊び
いつも孫が来た時、夕飯を終えても、家に帰る寸前まで遊びの相手に爺ちゃんをこき使うのだが、今夜は夜の梅小路公園に行きたいと言い出した。ちょっと前に一度夜の公園を散歩させたことがあったのだが、「肝だめしに行こう」という今日の誘いは、きっと幼稚園でも「お化け」とか妖怪の話しが出ることがあるのだろう。
小さなLEDの懐中電灯と孫は自転車のLEDランプを取り外し、すつかり暗くなった公園に向う。今日は3歳の妹も行きたいというので、二人の孫がそれぞれにランプを握り締めて昼間は何度も来て土地勘充分の公園だが、夜はほとんど人もなく、周回小道の坂を登る。 コオロギノ鳴き声が、やたらするどくあたりの空気を震わせている。植え込みの下草の一点にLEDランプをかざして、鳴き声の主を探そうとする孫だが、姿は闇の中。妹は何度と爺ちゃんの手を握り締めて緊張している。「冒険したいのなら、二人で先頭を歩かな」というと「お爺ちゃん、絶対おどかさんといてや。いいなぁ。」と念を押して、ゆるい下り道を大きな声で何かに負けまいと叫びながら駆けていく。 公園の南側はJRの線路で、長い照明器具に変身した電車が行過ぎる。「あれは、はるか号やなぁ。」「きれい」と一瞬、昼と夜の公園の時をつなぎながらつぶやいている孫たち。ぐるっとまわって中央の芝生の広場に出る。天を仰ぐと、日頃忘れかける都会の中の星空があって、ピカリと光る金星だけは名指しで教えることが出来た爺さんは、昔はもっと無数の星たちのこともはっきり見えたし、覚えてもいたのに、星のロマンから遠のいた我を発見。 野外ステージにきたら孫が「お爺ちゃん、あっちからライトで照らして。琴ちゃんと僕がお歌唄うし。」とランプを押し渡す。何事かと思う間もなく、ふたりはステージの中央で、二人で一緒に、歌を唄い、同じ振り付けで踊りを踊る。了解。爺さんは照明係り。
LEDランプを二台一緒に、時には一人ずつライトアップ。なかなか様になっている。すっかりスター気分で心地よく二人で大きな声で唄い踊る。婆さんや息子夫婦に見せてやりたい可愛らしさがあふれていた。周りに人はなく、この公演は爺さんだけのうれしいものであった。それから遠く前方に光立つ京都タワーに向けて、はぁはぁ息ききって走る。「さ、今夜はこれくらい。お父さんが待ってるかも知れんぞ。おうちに帰らんと」といったら、孫はすかさず、「まだ帰ってきいひんわ」と父親の遅い帰宅への不満がいっぱいの返事。今の社会情勢、父親が目いっぱい働いて、子供との日常生活時間が少ないのは、やっぱり子供にとって寂しいことだなと感じる。公園からの帰宅道は「お化けは出なかったね」等と言いながら孫たちと仲良く、仲良く手をつないで帰った。
046. 日本の厄年
人には厄年があって、男女それぞれの歳に厄払いをするという風習は日本では各地に見受けられる。
厄年が何となく成長の節目に当たるところもあって、それなりに用心を心がけるのも良いかと思い、私も、神社でのお祓いを受けたものだ。
新聞の死亡事故ニュースを見て、当事者の年齢が42歳だったりすると、「この人、本厄や」などと思わずおもってしまう時がある。
日常生活において、姓名判断や縁談、家相など、ことを起こすについて占いや厄除けは身近にしみこんでいる。
今年、日本は3月の東日本大震災、津波、原発事故、真夏の熱中症、先の9月の台風による災害、円高、政治の混乱。日本の厄年と言ってよいほど酷い年である。
想定外、未曾有のなどといって災難の結果を何とか運命と受け入れようとしても、まるで人災と言えるものも目に付いて、お祓いの世界とはちょっと次元が異なる想いがする。
けれども、ノーサイド、日本にヤオヨロズの神がいるなら、総力を挙げて被災地の復興の祈願に答えて欲しい。
日本人は過去に色々な苦難を乗り越えて、再生、復興を成し遂げてきたが、どこか厄払いを身近に実行、気分一新、未来に向かって、日々の努力を惜しまなかったからかも知れない。
047. 時の止まった喫茶店
この喫茶店は京都中京区室町、呉服問屋が居並んだ街中にある。
昔は呉服関連で働く番頭さんあたりが、情報交換や、休息にたむろしていた。そのため、外から目が差さないよう、入り口以外は明り取りの小さな窓があるだけで、昭和、平成と50年以上、そのままの姿である。
室内、インテリアと言ってよいのか、空間の全てが、マスターの想い入れで満ち溢れ、それぞれが知り合いのような、それでいて思い思いに雑誌を読んだり、何をするでもなく寛いだ老齢の男女の客が演劇の一シーンのように浮かんでいるのが日常だ。
マスターは何時の頃からか、夜間、自動車でドライヴしている時に、市内の民家や会社の前に廃品として放り出された品を見付けると、その中から自分の気に入るものや、まだまだ捨てるに惜しいものを集めることが「趣味」になったといえば嘘を言ったことにはならないと思う。
そんなことでマスターがいまだ命あるものと集めた家具や、生活雑貨、工芸品、着物や帯、置物、生活用具など全てが床から壁から天井まで、薄暗い照明の中、それでも、ちゃんとマスターのセンスでふさわしい輝きをするように配置されている。
自由に触れることも出来る気安さも流れている。
客の一人が、その一つについて尋ねごとがあると、マスターの見識が炸裂する。ばらばらのように見えたお客さんたちは、一気にその語りに聞き入って絆の輪にすっぽりと心地よく浸る。
祇園祭見物の時や、たまに知人を驚かすつもりでこの喫茶店につれて行くと戸惑いながらも、わけなく「ベリーグッド」を体ごと現してくれる。してやったり。とてもうれしい時である。
マスター一家とは子供同士が小学校以来の友達で、長い付き合いである。
マスターの不思議な人脈のお蔭で私も男物の着物をゲット。孫も遊具を。特筆ものは、マスターの知人に花屋さんがあって、高級な花が売れ残れば直ちに頂けるという夢のような仕組みである。
喫茶店のほの暗い中に鮮やかなランの花などがいつもカウンターやテーブルの上に息づいているのも時の止まった思いを抱かせる。私の家の玄関におすそ分けのランが旅をしてくることも誰にも言わない秘密である。
街中の知る人ぞ知る秘密の空間。マスターは若いころファッション関係の仕事をされていたので、その目利きは半端ではない。土曜日には、店の前に集めてきた収集品や衣服(新品もある)布地などを無償で台の上に出しておかれる。数時間後にはほとんど誰がもらっていったのかなくなっている。リサイクルなどと社会現象で語られることも多いが、マスターがこうしたことを自身の生活サイクルとして楽しんでおられるのを見るたび、何とも言えない爽やかな嬉しさでいっぱいになる。私にはまねのできないことである。
048. 2011.夏、別荘生活雑感(1)
今年は次男の仕事の関係で、毎年よりも1週間ほど早い時期に別荘に出かけた。
3月の大震災の影響で、長野の別荘もどこか壊れているかも知れないし、何より、今年もハチが軒先に巣を作っているのではないか等、女房殿は心配性の優等生。
幸い出発の日は天候も回復、高速道路もお盆にはまだ遠くスイスイ。出発間もない時から、[まだお山のおうちに着かないの]という孫たちに「まだ、まだ、まだ」とその都度、何度も外の景色や、雲の形に気をそらさせながら、サービスエリアに立ち寄って、日本一長い恵那山トンネル体感を印象付けたり、指相撲やジャンケン遊びをしながらお昼前には安曇野あたりに到着。
いつも安曇野では地元の野菜などを売っている店に立ち寄り、新鮮な野菜や果物をこれからの数日の山荘での生活のために仕入れる。
それから、お蕎麦屋さん。何度もいくお店もあれば、なにしろ安曇野には蕎麦屋さんが多いので、今年は別のお店に行ってみる。
こうしたことには次男夫婦のこまめなネット情報についてゆくのみ。
3歳と5歳の孫もそばには[つう]と言っていいくらい慣れ親しんでいるので、大人が天ぷらそばなどを注文していても、「ざるそば」が好き。
わさびもネギも抜きにして、とにかくそばをつゆに付けて黙々と食べるその姿は不思議と[つう]と言いたくなる。
[ここのお蕎麦、美味しかったな。]などといわれるとなおさらである。
あと少し、白馬のスーパでビールやワイン、色々な食材を買い込んで、やっとこノンストップで別荘に着く。
スキー場の中にある別荘は夏の草の中。隣のペンションも閉鎖されて久しく、今は、私たちのみが通る小道を少し下る。敷地の数本の大きな胡桃や雑木の間は雑草が生い茂っている。先発隊として次男と私が心配性の女房殿が用意してくれた蜂よけのネット帽子をかぶり別荘に近づく。蜂は一匹ブーンと羽音を聞かせたが、軒先や外壁には巣はなさそうだ。
とにかく、皆で荷物を運び込む。5歳の孫が結構小荷物を運ぶ手伝いをしてくれるようになった。
次男が初めて、率先して草刈機で草を刈り始める。今までは私が草刈をしてきたが、そろそろ世代交代と感じてくれたのだろう。しばらくして、「意外と草刈ってしんどいな」なんて今頃、笑っている。私はほぼ40年近く、草刈をしてきたが、草刈の楽しさはもっと先に分かるだろうと言いたかったが、[そやろ、そんなに楽なもんやないで]とだけ言った。とりあえず、小道からの通路や、ハンモックを吊るスペースや、屋外テーブルや椅子をしつらえる部分の草刈の格好がついた。あたりに、かじか蛙の鳴き声が響き、すぐそばを流れる小川のせせらぎの音が、木々をすり抜け吹き渡る風は、ひゃっと心地よい。温度は24℃。夏はクーラ不要。自然のありがたさをしみじみ感じながら1日が暮れる。
049. 2011,夏、別荘生活雑感(2)海水浴へ
山の別荘に滞在しているうちの1日は、孫の「あそび気分」の充実を図って、朝、天気が良い日に日本海に海水浴に出かけることにしてる。
糸魚川に1時間足らずで出られるので、親不知のほうに向うか、直江津方面に向うか、その時の気分次第である。このあたりは若狭の海水浴場のように遠浅とはいかず、ほとんどすぐに背丈の届かぬ子供にも大人にも不安を抱かせる海である。
次男たちが子供の頃に連れて行った親不知の海岸も、孫の水遊びには不向きかと、とにかく、車は、直江津のほうに向うことになる。
糸魚川のすぐ近く、一昨年行った小さな名もなき海水浴場は地元の人専用のような、トイレの設備もないところ。
昨年行った、能生海水浴場まではちょっと距離がある上、浜茶屋の印象も良くなかったなどといいながら、走っていると、ちらりと小さな赤い文字の矢印看板。
[大和川海水浴場]「行ってみよう」車をUターンさせて海岸方向に細い道を入る。
海岸沿いに防潮堤が数百メートルも続き、その外側にテトラポット。一見何処に海水浴場があるのかと言う景色だが、よく見ると、猫の額ほどの小石が敷き詰められた海辺に2,3のパラソルが経って、20人は越えないかと言う親子ずれの声が、かすかにさんざめいている。駐車場も有料シャワールーム、監視員搭も簡易トイレもあり「今年はここにしてみよう」と意見がまとまって海水浴のモード。
持参した浮き輪や小さな浮きボートに揺られて、孫たちは大はしゃぎ。今時の浮き輪は、一部分が透明になっているのでそこに目をつけると海底が見え、小魚が泳いでいる姿も見ることが出来て大喜び。私は大きな覗きめがねを持って浮き輪に乗って、沖合いに伸びるテトラポットと岩礁群のそばを遊泳。波のうごきに合わせてゆらゆらさぁーと動く海草の中でしがみつく巻貝や藤壺を遠い昔の記憶、子供の頃の海水浴を思い出しながら、眺めていた。小アジの群れが元気に通り過ぎる。
海岸はほとんどが研磨されつくした丸い小石で、それが又、色々な色、特に、真っ黒な溶岩石の中に色々なガラス質の粒がデザインされたように散りばめられ、輝いているのは美しく、この海岸との出会いをうれしく思った。
お昼に、パラソルの下で持参したおにぎりやちょっとした嫁姑合作のおかずを食べながら、本当に周りに数人しかいない静かな海水浴場はプライベートビーチの贅沢さだねと皆で幸せ気分。防潮堤の上に組まれた看視塔には赤いユニフォーム着た2人のおじいさんが時々吹き渡る海風に白髪をゆだねながら穏やかにこの夏の景色を眺めている。
昨年、病院通いをした[日焼け]の失敗はしないぞと、日焼けとめを塗って、長袖Tシャツで防備。それでも午後の陽射しは「太陽さん、元気過ぎるよ」と言いたくなる。
水泳教室で技を見につけた孫の[はるちゃん]は昨年とは段違いに海を友達として飽きずに父母と思い出になるひと時を過ごし、それを眺める老夫婦は時の流れとその行き先がどちらも幻のようで定かでない。小っちゃな孫の[ことちゃん]はやっと浮き輪に身を任せる心地よさが体感できたのか、一人で水際でゆれ遊んでいる。
夕方、帰り道の温泉で、皆ですっきりさっぱり。それから、白馬村のイタリアレストランによって夕食と乾杯。山荘に戻れば庭のハンモックが所在気に落ち葉を寝かせていた。
050. 別荘生活雑感(その3)
何ヶ月も空けて山荘を訪れると、大抵は何かの痕跡が静かに残されている。
オーディオ機器の後ろを掃除すると、丸くかじりとった胡桃の実がいくつも転がって出る。これは野鼠の仕業だ。
何時の年だったか、クリスマスの頃訪れた時、食堂のカウンターの上をあわてて逃げる小さな薄茶色の野鼠を発見。思わず童話を思い出すほど、可愛い印象だった。
「野鼠が棲んでいるんだ。」と心和んだ記憶が深い。
その後も越冬時には、家の中のどこかにひそやかにすんでいるのだろう。
暖かい時期に訪れると、地下室のダンボールの空き箱の中、もう履かなくなったスキー靴の中などに胡桃の食べかすを置いてどこかへ引っ越している。
冬以外は野外でのどかに暮らしているのだろう。
屋外には、リスが食べた胡桃の実がいっぱい散乱している。リスの場合は、感心するくらいきれいに胡桃の実を真っ二つに割っている。
庭の胡桃はヒメクルミなので小さく一度食用を試みたが、あまりにも手間が掛かったので、その後はこうして本来どうり、リスや野鼠のご馳走になっている。
蜂が家の中、リビングに巣を残していった年もあり、その痕跡に大騒ぎしたこともあった。
ごく当たり前に、いたるところで色々な虫がサナギの抜け殻を残していたりする。
たった一人で山荘を訪れたときなどは、ことさらにこうした痕跡が、不思議なぬくもりを感じさせてくれる。生き物の痕跡…。 それは生きる命の一瞬一瞬の記録でもあり、透明なくせに、私には重さを感じさせてくれるのだ。
廣瀬 滋著