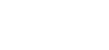081. ゲレンデにて
暖冬で雪が降るのかと心配していたが、年末列島に雪が降り、今年も雪景色の白馬乗鞍の山荘で正月を迎えることが出来た。
元旦から小雪ちらつくゲレンデに、新年、初すべりを楽しんだ。なんと、初めてマスター用のリフト券が発売されている。マスター券といえば技を極めた人という意味ではなく、50歳以上のスキーヤのための約37%割引リフト券である。
スポーツにシニヤーやシルバーはなじまないとの気配りも感じ取れる。スキー人口は下降の一途をたどり、ゲレンデも往年の賑わいが無い。此処にも高齢化が急速に進む日本の現状が感じられる。割引券を発行して、かってスキーを楽しんだ人々を呼び戻したいのだろうか。60歳を超えた私にしてみれば、同じ発行するならもっと早く発行してくれれば良かったのにとケチな想いに一瞬とらわれたが、割安な一日リフト券で存分に滑れるという満足感はなかなかうれしい。
リフトで相乗りになった男性が、「ボードが増えましたね。私は7年ぶりのスキーで、すっかり体力が落ちて、息切れがして大変です。」と話しかけてきた。聞けばかろうじてまだ40代にしがみついているという。「私は60歳を超えました。シーズンはじめはやっぱり一気にゲレンデを下りきれませんね。」「いや、60代になってもスキーが出来るなんて、憧れですよ。そうなりたいと願ってるんですが。」山頂に着くまでマスター同志の会話をしながら、眼下に広がる雪山を眺めると、若かりし頃、子供とその友達数人を引き連れて、あちこちゲレンデをツァーした日々も懐かしくオーバラップ。
同じゲレンデに30年以上来ていると、周りの施設の変化は勿論のこと、営業をやめてしまった喫茶店のマスターの行方、長い間顔見知りだったリフト会社の経営者の息子、色々世話になった村人・友人とのたくさんの思い出が雪をかぶった木立の間に幾重にもよみがえってくる。「やっぱり年を重ねたな。」という実感がとても深い。さぁ、いくぞ。一気に斜面を滑降すれば、何もかも考えなしの爽快感。
転びまくった初心者時代の充満感から、ボーゲン、クリスチャニア、パラレル、ウエーデルなど技術の習得に一喜一憂した感慨も今は無く、雪面に我を問うという、ほとんど答えの解らない時空の中で、今年もスキーが楽しめたという「ほっと」したひと時が静かにゲレンデに溶けて流れる。
長い間、ほとんど新年をゲレンデでのひと滑りで重ねてきたが、真っ白な雪景色は、「いつも原点に戻る勇気を持とう」という私の信条のひとつを確認するのにふさわしい背景でもある。
082. 花いっぱい運動
私の住んでいる京都・下京区内でも、街づくりの基本計画の中に「みんなで支え合うやすらぎのまち構想」というテーマがあり、その中で区民による花いっぱい運動やまちの美化運動に取り組もうという課題が提示されている。
ここ2,3年、行政の少ない予算をもとに一時的、ごく一部の地域にフラワーポットを並べると言う表面的な活動が、町衆フォーラムのメンバーによって展開されたが、コミュニテイの育成と言う点からも効果をあげているとはいえない。
このたび、町会長、役員の賛同の下、身近な私の住む町内(23世帯)の方になんとなく薄れてしまった近隣のコミュニテイを再生することもかねて、「みんなで企画した花いっぱい活動をしませんか。」と言う呼びかけをしてみた。
ただ花をそれぞれの家の前に植栽すると言うのではなく、たとえば、今年の秋は選別した色の組み合わせの花を咲かせると言う方法で、皆のメッセージを表現できること、花を咲かせることや飾ることの過程を通じて、近隣のお年より世帯も含め、お互いのコミュニケーションの機会をより自然に多く持てるようにする事など,そして、もし私たちの町内が、花いっぱい活動でより美しくなれば、やがて、お隣の町内もより意識されたかたちで家の前の植栽などが整備され、皆で町の美化に取り組もうという共有意識が芽生えるのではないかというような趣旨書を回覧した。
その後、参加の意向や、方法について簡単なアンケートを実施した結果、1世帯以外は賛成と言う結果で前向きに取り組む方向になった。
しかし、よく説明を聞きたいという方、園芸には知識が無いので心配という方もあり、継続性や成果を考えると活動開始前に充分話し合う場を持たなければならない。事のはじめを慎重にしなければならないと云う思いに駆られる。
幸い町会費に少しゆとりのあることと、町内に古くからの花屋さんがあり、今年の町会長の奥さんが花屋さんの娘さんであることが、この提案をしたキッカケでもあるが、2,3人の園芸愛好家の奥さんが居られることがわかった事も、計画を実行するのには好条件。
都会の道端での園芸がどの様な町の美化に役立ち、また花いっぱい活動がどんなコミュニテイの創出に繋がるのか、身近な、ささやかな試みではあるが、人々の連携の原点を確かめてみたいと思う。
また、楽しみながら、色々な花のありようを学ぶことで「花」の持つ美しき可能性を味わい知る機会にしたい。勝手に「多忙」を作り出していると家人に笑われながら、町内会の皆さんとの地縁を実感できることを願っている。
083. コミュニケーションデザイン
私が高校生のころ、これからはデザインの時代だと美術部の先輩が言うのをなんとなく直感的に信じて、自分の好きなことを生かしながら社会に役立つことをしたいと今日に至る人生の道を歩むことになった。
この40年余り、デザインの領域は拡大し続けてきた。はじめは最も理解しやすいかたちで、ファッションデザインとともにデザインは流行というような軽い受け止め方をされ、やがて、ビジュアルデザインやプロダクトデザインが成長する資本主義経済活動の一翼を担うことになった。
色や形、質感、それらのプロポーション、バランスのセンスがデザイン性と同義に捉えられていたが、日本の経済成長とともに、建築、インテリアの分野にもデザイン性が意識され出すと、単なる美意識上の問題より、生活、時系列を踏まえた人間との関係、環境との関係が重視されるようになった。
実務においても、デザインはハンドワークの時代からヘッドワークの時代へと変転した。パソコンとデザイン関連ソフトの普及によってさらに一段と拍車がかかり、いまやWebデザインも花盛りである。アナログデザインワークからデジタルデザインワークと捕らえたほうがわかり易いかもしれない。
そして,今、最も求められるデザイン領域は人類の平穏のため、平和のため、のぞましい人間性の再構築のためのコミュニケーションデザインではないだろうか。
身近なところでは、家族の関係デザイン、地域コミュニテイのデザイン。
ユニバーサルデザインやサステイナブルデザインというような技術解決型思考ではない、もっと感性の交流が図られ、知らず知らずのうちに倫理的ルールが育まれ、生活習慣行為や文化が生まれる仕組み、システムのデザイン回路が望まれる。
人と人の間に、あらゆるチャンネル、メデイアを通して出会い、接触のチャンスを生み出すことが求められる。具体的な「場」、「時」の設定、その演出、コミュニケーションデザインが必要となる。
考えるに、過去から、「祭り」や宗教、農漁業などの生業の共同作業などが、コミュニケーションデザインを立派に成育してきたと思うが、グローバル、情報ネット社会・時代においては、あまりに複雑に個別のコミュニケーションデザインが複層・混合したために、もともとの美しい人間の知恵のデザイン結晶は輝きを失なってしまった。
一方、もはや後戻りのできないデジタル時代のコミュニケーションデザインは、すべての人類が共通のOSで動くロボットのようになった時、初めて究極の姿を現すのだろうか。そんなこんなに思いをめぐらせながら、アナログデザインの極上の住宅設計手法を模索している。
084. 継続と転換(改革)
「継続は力なり」と言われるように、物事を継続して積み重ねることは、結果として大きな成果をもたらすことは誰しも知見したことがあろう。
継続の評価は、継続がそれなりのエネルギーを注ぐ努力行為が伴うので、大概は諦めたり、挫折して成果を残すことがないことへの戒めを含むといえる。
一人の人生に於いても、企業、サークル活動にも何かを継続することの大切さは自明の体験としてそれぞれ意識される。「三日坊主」は継続に対する自嘲の念と言える。
そんなに短期間に成果が上がらなくても、我慢強く、時には意地になってひとつの行為を、信念を持って貫くことは、やがてそのことに喜びを感じたり、その流れの中で起こりうる色々な事象を体感・体得することによって、自身の、企業やサークルの歴史を刻む安らぎを知ることが出来る。
それは自己存在の確認でもある。継続行為・活動の中で、色々な人に出会うことによって、定点観測にも似て、多くのことが客観的に見えてくるのもなかなかのメリットである。
中でも他に対する奉仕の精神の継続は、時にはお節介になったり、誤解を生むこともあるが、私の継続ごとの原動力である。
これは自己のパワーアップ、自らの成果に集中力を持たない相対的なもので、「継続は力なり」と言うものの、目覚しい評価を得られないことも多い。奉仕精神、活動の継続は、生きていることへの自己確認と死に至る瞬間へのイメージが描ける時、初めて納得出来るものかもしれない。
気づかずに悪癖や悪行を継続してはいないか。転換を図り、新しい局面を切り開くことも人生における「力」である。「原点に返る勇気を」を座右の銘に生活を駆け抜けているが、これはプラス思考のひとつであり、結構、ズブトイ楽天家でもある自覚がなせる処世の継続かもしれない。
2009年雇用問題も深刻な時節、本当の意味でサラリーマン経験もなく、基本的に転職経験のない私は、家族を養い生き抜くために、多様な継続、多様な転換をいつもパラレルに行ってきたと言える。ゲリラ的生き方。「怖いもんて、ないよ。」
いやぁーほんと、毎日が継続と転換。「鬼は外、福は内。」
085. 出会い川と心の旅路
人生、今まで多くの人々と出会ってきた。出会いを思い出せる人とは、出会いが一瞬であったとしても印象に残る人、色々な出来事も含めて記憶に残る人、心深く私情に漂い続ける人である。
その時々には思いもしなかったが、振り返れば、「心の旅路」といえば大袈裟かもしれないが、自分の感受性や考え方、生き方・生活のあり様に大きな影響を受けたのは、川の流れのような多くの人々との出会いであったと思える。
激流であり、清流であり、それぞれの人が年齢や職業、性別、などに関係なく、私の知らなかったいろいろな世界を感じさせ、考えさせてくれた。
時に、1対1の密度の高い出会いは、自身の未熟さを思い知る修練の場でもあった。ガキ大将で自分中心だった幼少の頃を思い出すと恥ずかしが、初めて恋をして、自分以外の他人・相手の存在、心を実感したときの大人への入り口から、出会い川は身近に意識されるようになった。
なるべく身構えることなく、自身を白紙状態にして、いろいろな人と出会うことで、その出会いの香さえも大切にしたいと心掛けるが、そうした姿勢を持とうとすること自体が心の旅路を曇らせる時もある。
住宅設計において、住まい手の生活シナリオを共に思い描く作業をしながら、クライアントの出会い川と心の旅路を垣間見るとき、求める生活空間がフラッシュする。
十人十色のこだわり、自分流暮らし、心の旅路が見えてこそ、住空間の具体化が図れるのだが、実際にはなかなか心の旅路のコラボレーションは、それが「今」という生々しい時間の中では正体をつかみかねる。
しかも、最近の携帯電話社会に育つ人々には、きっと今までとは別の出会い川が流れ始めているので、自ら傷つき、葛藤しながら味わい深い旅路が思い出として残ることもないのではないだろうか。
そんな時、人々は住空間に何を求めるのだろうか。地球環境の保全も重要課題だが、人々の出会い川が血も涙も笑いも忘れ去ってしまうことのない様にと願う。
住宅設計の楽しさのためにも。
086. 深夜のラジオ便
3年ほど前の、なかなか寝付けなかった夜、明け方の4時前、枕元においておいたポケットラジオにスイッチを入れた時、「NHK深夜のラジオ便」なる番組に出会った。
丁度、ニュースに続いて、「こころのたより」というコーナがはじまり、どこのお寺の僧侶かは忘れてしまったが、人間の生きる道について、いたく感心させられるお話が聞けた。
以来、なんとなく気になって、「日付が変わって午前0時のニュース」というくだりから、世界各地に居住している日本人のホットな話題や、色々な分野の方のナイトエッセー、朗読、演芸、テーマを絞った音楽、日本の歌謡、そして始めに感心した「心の便り」ではその道で色々と研鑽努力された人の体験談が語られるのを聞いている。
時々、イヤーホーンをつけたまま、うとうとと寝込んでしまうことも、(90分のタイマーセット付きラジオ)ふっと気が付いて又、耳を傾けている。
とにかく、あらゆる意味で世界は広い、色々な人生があること、ひたすらに信念を持って努力して生き続けた人が、実に美しいと感動させる人生の軌跡を残されていることを知らされる。
又、南半球ブラジルからの便りをきいていると、寒い寒いと震えている日本と反対に、真夏のクリスマスやカーニバルの様子が伝えられ、灼熱の砂浜、波の音などは想像するだけで暖まる。
時々リスナーからの便りが紹介されるが、日本の北から南、高齢者時代、全国には夜に眠れぬ人が多いのか、この番組を聴いている人が結構多いのに驚かされる。
日々交代でアンカーを務める方々も、すでにNHKの一線を退いたベテランアナたちで、そのリーデイングは安心感が漂い、人気がある。
書店に行って、深夜便の冊子をパラパラとめくってみると、ああ、あの人、こんな顔してるんだとか、この人なら以前テレビでも見たぞ等ラジオの音声の印象が新しい。
週に一度ある浜田さんと云う料理の先生は身近な材料を生かしたシンプルなメニューを大変可愛い声で指導される。音声だけではあるが、その語り口に引き込まれ、翌日には女房にかわって、その一品を私が手作りすることも2度、3度。
もし、眠れぬ夜があったら、0時前後の海外からのたより、ナイトエッセー、4時からの心のたよりがお薦め。
歌謡番組や、音楽、演芸は、人によっては好き嫌いがある上、他のラジオ局でも類似内容がある。多分NHKでは深夜トラック便を走らせている方や、多様なリスナーにも配慮しているのだろう。すっかり、うとうと寝が習慣化してしまった。
087. 運命の一瞬
人生を振り返ってみると、もし、あの時こうしていたらという決断、決心の一瞬は誰にでもあるだろう。それほど自己の意思に因らないまでも、たまたま居合わせた、偶然の出会い、ちょっとした思いつき等も運命というのか、人の人生の流れを大きく変える。
また、自らでは本当にどうすることもできない運命の一瞬。ニュースで知る事故や事件のように、ほんとうにもし数秒、そこを早く通り過ぎていたら災難に巻き込まれなかったであろうにと、なんとも不思議な一瞬、運命という閃光を感じさせられる。
日々の平凡な生活の流れにおいては、運命はこれといって音を立てるでもなく、姿を潜めているが、(社会の常識に合わせて)幸せなこと、おめでたいことが起こった時や、逆に病魔に倒れたり災難にあったりすると、途端に運命は巨大な力で「運命、ここにあり」と躍り出てくる。
その一瞬に至り、その因縁を振り返って反省したり、さらに乗り越えて自らの運命に立ち向かおうと自身を鼓舞したりする。
運命に翻弄されて、波乱万丈の人生を送る人や、数奇な運命といわれる稀なる一瞬を積み重ねて生命を終える人など、様々である。
しかし、考えてみるに、平凡と思える日々の流れの中では、自動的「運命の一瞬」がぐさりと我が身に突き刺さることがないとするなら、お金持ちになりたいとか、有名になりたいとか、出世をしたいとか、我欲を出さなければよいとも思えるが、あまりにも刺激のない人生に我慢できないのが文明人である。
太平洋の孤島で一生同じような生活を自然と共に暮らす人たちのドキュメンタリーを見ると、運命はやすらぎそのものだと思える。
しかし、人類がどうしょうもない天災のごとき他動的「運命の一瞬」に遭遇すると、もはや「神」「仏」に祈ることで「運命の一瞬」にさらされた傷を癒そうとする。
日頃から、「運命の一瞬」の力の凄みを知る人たちは、心に「神」を棲まわせて、その閃光に耐える身支度をしている。
私は今日まで、幾たびか楽天的に「運命の一瞬」をやり過ごしてきたように思うが、早くに、弟、父親、祖母(母方)の死に出会いその後も祖父母、祖父、叔母と母親、身近な家族との別れの無常、厳しさ、「運命の一瞬」に立ち会ったことと、小学校から大学まで、その時々に恩師に出会えた有り難さが、大いに運命に耐える力を支えてくれたと思う。
ここまで生きてきて、「何とかなるものだ」と運命の一瞬を振り返りながら、わけなく、誰にともなく感謝の献杯。無事の一瞬。
088. 春の息吹
日本の春は、庭木も山々の木々もいっせいに芽吹く。「サクラ咲いたか、まだかいな。」
私宅のムクゲの新芽が葉っぱに姿を整えるのをみていると、春はことさらに生きていることが実感される時である。
先日、清水寺、成就院で森清範貫主の法話を聞く機会に恵まれたが、先祖代々、脈々と流れる「縦の流れの命」を心することの大切さを話された。
35億年前、地球上に生物が誕生して以来、花や草木、動物、虫、魚、ありとあらゆる生物が、全てひとつの生命から生まれてきたことをイメージすると、確かに生きているというより生かされているという捉え方のほうが適切だと思われる。
十数年前、人間の中には、ゴキブリの持つ遺伝子さえも含む、多種の遺伝子が組み込まれていて、しかも単純な遺伝子しか持たない大腸菌のような生き物と共生することで生命が維持されているという話しを聞いた時以来、なるべく謙虚に感謝して生きることを心がけてきたつもりではあるが、命の営みを顕著に感じる春は、本当に生きることの意味をより考えさせられる。
人生の結果=能力×熱意(努力)×考え方(生き方)という人もいるが、授かった「命」を大切に生きるかという点では、生き方はその決め手になるのではないだろうか。
生き方というのは、人生において色々な局面、特に艱難辛苦に出くわした時、どのような判断を下し、どんな行動・言動をとるかということで示される。
うろたえることなく、適切な決断、行動が取れるためには、自己中心ではなく、自らは生かされていると言う観点にどれだけ身をおけるかということなのだろうか。20代の頃、究極のエゴイストに憧れていたが、今やっとその本当の姿が理解できるような気がしている。日々の設計やデザインの仕事の中では、やはりクライアント、オーナとの出会い、コミュニケーション、コラボレーションの流れの中に、どれだけ互いの存在、家族、「命」のあり様を感じ取りながら、もの造りが出来るかということかと思うが、地域社会活動も含め、より多くの人々との出会いの中で、「命」のすばらしさを確かめ合えれば良い。
そんなことを、切に思わせる春の息吹である。
089. 京都新光悦村
江戸時代初期、本阿弥光悦によって京都洛北・鷹ケ峰の地に形成された「光悦村」には、様々な分野の工人が移り住み、交流機会が創出され、次々と新しい技や表現が生み出されて行ったと言われています。
日本の美術や工芸の発展に大きく貢献した、この「光悦村」の精神を継承し、これからの産業やものづくりのあり方を示す新しいスタイルの産業拠点が「京都新光悦村」です。(京都新光悦村パンフレットから)
先日、この事業の拠点の造成工事がほぼ完成したということで、現地見学会に参加した。
21世紀の京都の新たな生活文化の創造と産業の活性化を目指す新産業拠点というコンセプトは従来の産業団地造りと比べ、最大で約1ha,最小は300㎡と言う区画割の小ささ、里山をイメージさせる景観作りなどにその基本姿勢がうかがわれた。
近くにある京都伝統工芸専門学校が、卒業生を中心とした人材の更なる産業への貢献を目指してインキュベーション的な施設を建設することが決まっているそうだが、他の参加企業の実質的な選定基準、その連携・全体運営のさせ方などは明確ではなく、光悦というすばらしいリーダによって推進された光悦村のように成果を出すためには、何か近代産業と伝統産業のコラボレーション、異業種の技術的コラボレーションなどを創造的に運営したり、調整しながら成果に結びつけるためのプロジューサ的人材・組織を考案し、運用しなければ、せっかくの新しい産業拠点も形骸化してしまうのではないかと心配がよぎる。
行政は拠点の造成工事を行い、分譲してしまえば、取りあえずこの事業にけりをつけられるのだろうが、税金の無駄使いに終わらないためには、むしろこれからの「京都新光悦村」の実行にこそ、何かの形で積極的に力添えをするべきである。
私が現地見学会に参加したのも、関西デザインオフィスユニオン京都本部のメンバーとして、何か役立つことが出来るかを見極めるためである。あるNPOが、今後の運営をリードしようとされているとも聞くが、新しいビジネス創造と光悦ブランドの産業化という現実の命題を考えると、よりダイナミックな開かれた新光悦村コミュニテイ育成のプログラム、タイムスケジュールの作成、総括するブランド戦略の創造が求められる。
長年、デザイン活動を通じてこうしたことに経験をつんできたデザインオフィスユニオンのメンバーが助力できることは少なくないと感じた。また、その活動プロセスに観光・集客、教育・学習など南丹市の地域振興に結びつけるというコンセプトが並存されることで、光悦の根本精神が今の時代に、よりよく理解され、少しでも実業として芽吹くことが期待される。世界に発信できる新・光悦ブランドの誕生を夢見よう。
090. 通勤電車
時々大阪で会議があったりすると、いわゆる通勤時間、ラッシュ時にJR新快速列車を利用することがある。つい最近、確かに座席に坐ることが出来ない状況であるが、ぼんやりと立って運ばれていると、昔のラッシュ時とはずいぶん様相が違うことに気が付いた。
昭和40年代、私が小田急線を利用していたときの身動きも出来ず、斜めになったら、次のゆれ戻しでもない限り、そのままの姿で荷物のごとく運ばれていた苦痛のラッシュ時間。
あるときは、中央線新宿から御茶ノ水の途中で、ドァに押し付けられていた肩に一瞬凄い圧力がかかり、強化ガラスのはずのドァのガラスが、びしっと言う音と共にひび割れた思い出は忘れることが出来ない。
今は、冷房もよく利いて、少し隙間もあり、たいてい携帯電話でメールを無線機を打電するように打ち続けている人や、社内テストでもあるのかパソコンのマニュアルを受験勉強風に読み込んでいる人や、I-potやミニデイスクで音楽の世界に嵌っている人たち、マンガを読んでいる人たち、疲れきった人達がわずかな仮眠?の息使いをしていたりする。
勤務時間帯も多様になり、以前のように誰も彼もが同じ流れにがむしゃらに乗っかっているというイメージはない。たまたま乗り合わせ、それぞれが自分の生活をしている瞬間の集まりである。
これからは少子化で、日本の人口は減り続け、乗客数も斬減すると鉄道会社幹部の心配顔がTVに映し出されていたのも最近のことだ。
あの凄いラッシュ時が昔のことと思えるのに、ここ数年、痴漢対策として女性専用車両が運行されるのは、今の通勤電車にかえって痴漢をする余裕や隙間が出来たからか、運輸サービスの質的改善がやっとここまで気配りをするようになったのだろうか。
外国のビュフェ付き通勤電車と、そこで和みながら家路に着く乗客を知ると、生活が途切れなく人間らしさで輝いているようでうれしくなる。
やがて、通勤電車、ラッシュはどの様な有様になるのだろう。駅のホームに吐き出される時、今も昔もまだまだ荷物扱い、単に運ばれた「一人という荷物」を感じさせられるのは寂しい。
廣瀬 滋著