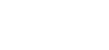091. 輝きの一歩
宮里藍選手をはじめ諸味里しのぶ,横峯さくらなどの台頭で女子ゴルフプロのトーナメントはテレビ中継を見ているだけでもなかなか楽しい。私は、もう自らのゴルフの才のなさに見切りを付けて久しいが、選手がコースマネジメントを巧みに、しかも技とパワーを発揮するとき、過って克服できなかった前下がりなど傾斜面からのショットやアプローチ、グリーン上の芝目の読みなど懐かしく思い出される。
それにしても、8000人を越えるギャラリーを従えての宮里藍の勝利のパットの瞬間、その野外劇場のような有様は、なかなか感動のシーンである。
最近は、ゴルフをする人だけでなく、子供をはじめ、ゴルフをしない人もギャラリーとして多く参加しているとのこと。緑いっぱいの自然の中で繰り広げられるスター選手の活躍を、ピクニックのように、そぞろ歩きで追っかけるひと時は、ゴルフ場の爽快感を知るだけにうなずける。
何よりも、女子ゴルフプロトーナメントにこれだけのギャラリーを集め、テレビ中継視聴率をアップさせるのは宮里藍人気であろう。今までの女子プロ選手にはなかった爽やかさと可愛さに加えて、安定した確実な技術の向上、キャリアを重ねるにつれ、精神面での強さが色々な発言やしぐさに感じ取れ、とても20歳になったばかりとは思えない奥行きを感じさせる人間性も、多くの人々をファンにさせるのだろう。
宮里選手のように、自らがマネジメントした通り、ことが運ぶ技術、パワーは一体どれほどの練習、努力、研鑽の継続の上に築かれているのだろう。
私のゴルフは、たしなみ、所詮遊び程度のものに過ぎなかったのだが、取り組む姿勢によって、何事も人生を豊かにさせるものであることを、つくづくと感じさせる。スポーツの世界はこのことを単純明快に勝者と敗者という結果の積み重ねによって示唆する。
勝ち負けにこだわらないで最善を尽くそう等と言うが、勝ち負けが身にしみて分かるからこそ人は深まりを知る機会を得られるのだ。日常生活では勝ち負けを言うと角が立つことが多いが、時には潔く勝ち負けを感得することが、明日への一歩を確かなものにしてくれる。
西陽を浴びて18番グリーンに上がってくる宮里選手の姿は、その一歩一歩が輝くための戦いの大変さを引き連れている。しかし、それが美しく、彼女の笑顔に包まれているため、私たちは一瞬、我を忘れて拍手喝さいを送るのである。
だが、感動し、浮かれてばかりは居られない。人それぞれの輝きの一歩はどんな時からでも、自身の決意と勝敗に怯まぬ継続した行動からはじまると思うから。わが道なりの輝ける日をめざし、一歩前進の努力をし続けようと静かに思う。
092. ゴールデンウィーク
日本の社会人にとって、ゴールデンウィークはお盆や正月休みと比べて時候の良さとあいまって唯一、行楽や気休めに自由に過ごせる休暇期間といえる。
勤勉な日本人には1ケ月をこえる長期休暇を生活設計の中に取り込むことは不得手だが、近年、欧米と比べ、ささやかながら10連休くらいのゴールデンウィーク休暇は、こなしきれるライフスタイルは一般化してきた。
今年は約6400万人(昨年を1000万人上回る)の人々が日本各地の行楽に出かけたと言う。海外旅行も含めると、多くの日本人が余暇の取り方、過ごし方に多様な自分なりのスタイルを発揮しているといえる。
30年ほど前、アメリカのフェニックスでキャンピングカーを借りてグランドキャニオンに行こうとした時、3日間のレンタルを申し込んで断られたことを思い出す。そんなに短いレンタルは無かったからである。その時、休暇というものに対する考え方の日米の違いを体験した。
帰国後、自分の生活の中に緩急を取り入れようと、ささやかながら別荘を白馬乗鞍スキー場に持った。当初数年は、自然とのふれあいの楽しさもあり、年間、約50日間くらい利用していたように記憶している。やがては、遊びや周辺観光よりも、敷地の整備、別荘のメンテナンスなど都会では出来ない労働作業に汗することが楽しくなり、その為の道具や資材の販売店などを地域で探すうちに、色々と周りの地理や人々との関係が織りなされ、自分の中に山荘での生活というものが実感できるものになった。
何しろ、地下室にはスキー関連のもの以外に、雪かき用具、鍬、鋤、斧、スコップ、草刈り機、電動工具,セメントを煉る船、長い折りたたみ梯子、塗装用具など色々ものがあり、その上、30年間、時代の進化の中で使い捨てた暖房機器や家電品、住宅機器の残骸もあって、地下室はまさに山荘での私の休暇生活の歴史館の感がある。
一方、建設時、小さな山村部落の18軒目として参加させてもらったのだが、いまや150軒以上のペンションや別荘が建ち並び、10数年前に開通した栂池高原への谷超えの道路や、新しいホテルの完成、温泉の試掘成功など、周辺環境も大きく変化。早くからの有線によるテレビ視聴、湧き水の上水道化、一昨年の下水道整備などインフラの向上は利便性の有難さを感じさせてくれるものの、折角のミネラルウォーターでのコーヒーの味を減滅させてもいる。
今年のゴールデンウィークは好転に恵まれ、山菜採り、ブシュ刈りや周辺整備に汗することが出来た。「山荘の 庭にぽつぽつ フキノトウ」、「水芭蕉 群れて際立つ 岩清水」なんて俳句を詠んでハンモックで一休み。女房殿は「うぐいすと 共に目覚める 山の春」と詠んでご満悦。ゴールデンウィークは「非日常」という「時」の断片でもある。
093. 新年に想うこと (初孫誕生)
あわただしくも、昨12月31日夕方、孫が誕生。カンガルー何とか方式とやらで臍の「緒」が繋がったままで30分余り赤子は嫁の胸の上に素肌のままで抱かれていたそうだが、病室を見舞ったときは、産衣にくるまれ、この世に小さな一人の顔を輝かせていた。
その時、私は、父方の祖父母、父・母、私、息子、孫と、母方の曾祖母、祖父母と実際に出会った家族5代(6代)の顔を一瞬に思い出していた。一般的に普通は夫々5世代のつながりを実体験できるが、祖父母、両親、子供達との色々な思い出とともに「命」の繋がりが「時」の連続として存在することをあらためて思い知る。
墓参りの時などは、遠い先祖をも漠然とイメージしながら自分の存在の今日あるのはあなた方の存在あればこそと感謝して「手」を合わせ、不思議な「命」、「時」の脈絡を静かに追想している。
子孫存続という「命」の連続は、生々しい生活事象の中では、繁栄、衰退というような「命」・「時」を力の世界で征する為の悲喜劇を繰り広げさせて来たが、一人一人の「命」は二度とない人生、大切に生きることを目指し、その本懐を願っていよう。
このことは、ただ自分の「命」が時の連続、時をつなぐだけの存在ではなく、他の「命」とのかかわりにおいて、命そのものの生きる背景、「時代」をどのように築くか、新たに生誕する担い手のための「時代」の美しき連続のために何が出来るか、少しでも尽くすことがないのかを考え、ささやかなことであれ実行することである。
自らの「命」は生まれ出でた時代、家庭・家族環境等により、出自、「運命」と言う束縛を受け、誰もがその「命」を平等に羽ばたかせることは出来ないのかも知れないが、自らの「時」の使い方、生かし方は、ちょっとした心掛けで大いに多くの命との交流・交感、共鳴から命の存続そのものに意味を、輝きを与えることになるだろう。
今、日本は少子化時代ということで、日本民族、社会の衰退が懸念され始めているが、子育てに関ることで「命」、「時」のあり方を自然に学習できる体験の場を逃してしまう世代が、自らの個としての「命」を思いやることに気付くだろうかと心配する。
「命」は「時」が省みられず、「時」は金なりが「時」の大切さを戒めることから逸脱して強欲に走る人たちの旗印になってしまっては大変だ。
孫がどんな「命」の使い方をしてくれるか、私の人差し指をぎゅっと握り締める小さな手に「時」がバトンタッチされて行く。
094. 食初め
孫の生後100日にあたり、「食初め」を行った。
父親方の祖父、つまり私が食べさせるのが丈夫な子に育つという「ことの慣わし」と云う嫁の調べによって、その役を仰せつかる事になった。
本当はどうなのか,私に華を持たせてくれる心遣いかも知れないが、素直にうれしく息子の家に出向いた。息子のときにも使った朱塗りのお膳の上に睨み鯛、吸いもの、野菜の煮物、かまぼこ、だし巻、お赤飯、香の物、それにそら豆大の小石が2個塗りの器に盛り付けられている。
ちょっとあらたまった気分である。鯛の身をほぐして、おもむろに孫の口元に運んでやる。次々に食べさせる真似事をして、最後に小石を鋏んだあと、箸を歯茎に当ててやると、丈夫な歯性の子になるとかで、そのことを執り行う。
いたずら心で、梅干を口もとに持っていったときは、孫君は身震いをして今にも泣き出しそうであった。息子は「もうこれでトラウマになって梅干は食べなくなるかも」と爺の子供じみた振る舞いを静かにたしなめた。
振り返って思うに、自分の子供の時の「食初め」の記録写真はあるのだが、まったく細やかな記憶がない。30数年前のことであれば、当たり前かも知れないが、そのとき親として、何を願っていたのか。幸い息子たちも健康に今日まで来たのは、結構、願い事が天に通じていたのであろうか。もし、孫と話し合う時が来たら、「お前の元気な成長を願って、お父さん、お母さんは気合を入れてビデオも写真も撮っていたよ」と教えてやろうと思った。
親は案外照れくさくて、そんな当たり前のことは伝えないかも知れない。赤子が母乳だけで、あっという間に7kgにも成長し、子供らしい表情を振りまくことも楽しい驚きであるが、やがては少しずつ離乳食に始まり、色々なものを食べ、母親以外との関係を紡ぎ出すのだろう。
毎日眺めているわけではなく、1週間に一度くらい観察するというスタイルでの孫との出会いは、自分の子供の育児よりも、かえって確かな実感がある不思議な気分だ。
抱いてあやした孫の、ほのかにセータに残る体臭は、DNAを引き継ぐ生命の営み、役目を、まさに遂行した安堵感を知らせている。ときの流れ、命のつながりを爺として感じさせる「食初め」であった。
095. 健康のレベル
経済成長の後、高齢化の進む日本社会にあって、多くの人々の関心は「健康」に向けられている。如何に健康に美しく、楽しく余生を生き抜くか。古来からの人類の願望でもある。
昨年来、東西医学の補完・統合型医療を基軸に如何なる健康サービスが創出、提供出来るかというプロジェクトにかかわる機会があったが、「健康」と言う概念が実に微妙で奥深いものであるかを知らされた。
従来の西洋医学における検査では、血液のある成分の数値が通常より少し異常であれば、自覚症状もなく、本人は健康という認識であるにもかかわらず、たちまち病名がつけられたりする。
また、逆に、検査の結果、数値に異常はないにもかかわらず不快感がぬぐえず、本人にとって不健康と思える状態(未病)もある。
試みに、プロジェクト調査事業の一環として、東西医学統合型「人間ドック」が実施された。従来の人間ドック受検者に、同時に東洋医学による検診(問診、脈診、舌診等)を行い、その診断評価と合わせてトータルに見直すと、健康に対する個人の認識と症状のずれが、比較的合点が行くものになると言う傾向がつかめてきた。
学術的にこうした「健康」のレベルを明確に把握するためには、東洋医学における診断と評価の因果関係を証明するバイオマーカーの検索がぜひ必要なことになるが、とても高価な分析検査機械が必要なこと、分析手法充実、さらに、唾液や血液の分析は、昨今の個人情報保護の立場から慎重を期すことが求められ、有効データとして蓄積されるにはハードルは高い。
しかし、やがて東西統合型診断が一定の成果を挙げるようになれば、「健康」のレベルは連続的に評価・認識できるようになり、そのことは個人の許容範囲・偏差を踏まえた治療方法や健康維持・増進への対応が出来ることにつながると思われる。
ホームヘルスケァの観点に於いても、血圧計、心電計、体温計など検査機器がユニバーサルデザイン化の流れの中で、家庭での測定・検査値が信頼できるものとなり、データが即、医療機関に電送され、迅速に健康管理などが行われる時代となった。我々の「健康」レベルは色々な段階、生活局面でサポートされるようになって来ている。
とはいえ、究極、病は「気」からとも言う。ストレスのない生活の過ごし方は本人の「生きかた」心構えにもあると思えば、どのレベルの「健康」を望むのかを自身に問いかけねばならないのかも知れない。
096. 規則のきわどさ
先日、地域の交通安全対策活動のひとつとして、朝の通学時間帯に、婦警さん、ボランテイア達と中・高校生の交差点での交通指導を行うことに立ち会った。
横断歩道での自転車と歩行者の分離ゾーンの通行という指導を担当したが、これがまったく大変である。
確かに、路面には自転車マークまで印されているが、信号が「青」に変われば、歩行者も、自転車も少しでも近道しようと気忙しく、斜めに突っ切って、入り乱れて思い思いの方向に進む有様である。
指導をして、殆んどの学生も一般人も、「分かりました」という顔つきをするが、「この急ぐ時にそこまで言うなよ」という気配が態度に隠されている。
イヤーホーンで音楽を聴きながら通学してくる学生は、こちらが何を訴えているのかもお構いなく、自転車のスピードを緩めることなくさっと通り抜けるのだ。
私自身、自転車通行ゾーンのあることはよく承知しているが、いつも規則どおり走行しているかと言われれば「ゴメンナサイ」と言わなければならない。
ちょうどその日、歯医者に行くのに自転車に乗ったが、努めてゾーンを守る走行を試みたが、みんなが規則を守っているわけではないので、状況によってはかえって危険なこともあると感じた。
世の中には、憲法に始まり、色々な規則までが定められるが、全ての人がそれぞれの法律・規則を知っているわけでもなく、理解していることも少ないので、法・規則に基づく行動が決まってとられることがない。
法・規則を悪用して抜け駆けで得する人達がいることをニュースで知れば、人は決め事を軽んじてしまいかねない。生活における規則、慣習レベルなどは、まず「私の勝手でしょ」と言う戦後の個人主義、自由主義の誤用の下に吹き飛んでしまうのだろう。
色々な時代、人は色々な規則を作り、そのためにかえって不都合を感じざるを得ないことも多かった。規制緩和は今の政治テーマでもあるが、自転車ゾーンの通行と言うちょっとしたことでさえ、問題ありで、人間が穏やかに安全に暮らすための智恵は、出し合わねばならないが、安易な規則化は守れないことによる苛立ちを喚起し、ことの判断基準から慈愛を失わせ、人間の持つ「業」に押し切られてしまう。
決め事をしなければ生きられず、その呪縛から逃れたい願望も永遠であるのか。
まあ、交通規則は守らねば、事故死につながると言う分かり易さがあるので、努めて遵守する人達が街中を闊歩することを祈りたい。
097. 気さくな人、気難しい人
世の中には気さくな人、気難しい人がいる。
しかし、はじめから天性気さくな人なのか、その老婦人は、電車に乗り込んで、ぽんと座席に座るや否や隣の夫人に「今日は暖かね。」と声を掛け、相手がうなずく間もなく「出かけにシャツを一枚脱いできたの。夕方には寒くなるかも知れないけど。」というと昼下がりの比較的ガランとした電車の中で、今乗り込んできた駅周辺に住まいがあるのだろう。そこに移り住んだ事情や、不動産の値段の話。
山陰の香住にカニを食べに行く旅行の話。主人に死なれ、一人息子の嫁もなくなったため、孫も居ないという身の上話。御主人のガンの発見が遅かったこと。
話し相手に選ばれた婦人も、時々相槌をうまい具合に打ってあげているのか話は途切れることなく、周りのちらほら乗客も老婦人の人生物語を走行車音の中で、途切れ途切れに聞かされている。黒の帽子、黒のパンタロンスーツ、黒のコート、指に真珠とダイヤの指輪、もう片方に金の印鑑タイプの指輪。小さめのキャスター付きバッグをもって手振り身振り、めがねの奥で光る目が、「人生色々あるのよ。」と隣の婦人に力強く迫っている。
終着の京都駅に着くまでの僅か15分ばかりの間に、老婦人は自分の心の中にあった思いも込めてどっと何かを吐き出したような気がする。なぜかその時、気さくな人は愛情いっぱいを知った寂しがりなのかなとふっと思った。
私の孫も、私の母も気さくな人タイプである。先日も孫は、信号待ちの間に中年のおばさんに何か話しかけたらしく、後から小さいほうの孫と追いついたときに、「気さくなお子さんですね」といわれた。 自販機の飲料交換の青年にも話しかけ、気に入られたのかカルピスをただでもらった事もある。
誰もが自分のことを受け止めてくれると信じきっているのだろうか。
大人になっても気さくな性格を持ち続けられるだろうか。
孫に思いがけず話しかけられた人が、なんとなく和やかな笑顔になる様を何度となく見てきたが、電車の老婦人もまた現代失われてしまった人の絆の結び方をあっけらかんと示していたのかとも思うのだ。
外国人のようにハグすることも、挨拶代わりに抱き合うこと、キスすることも少ない日本人にとって、気さくな人柄の表現は気軽な挨拶、共感できることの瞬時の発見とメッセージの伝達能力を身につけることから始まるのではないかとおもう。
共感できることの瞬時の発見は、愛情に満ちた世界で育まれるとも考える。子供の時にこそ、その感性の基盤が芽生えるのだから、子育ては実に重要な瞬間、瞬間である。
気さくな人と気難しい人は対極にあるのではなく、気難しい人は後天的な環境、学習によって共感できることの発見が論理的になりすぎるため表現の機会を失いやすい人とも言える。
気さくさを失わずまわりを眺め感じてみよう。今まで見知らぬ人が身近な人になるかも知れない。一期一会の連鎖の世界平和さえイメージできるかもしれない。
098. 生活の先を読む
今の日本、いや世界中で明日を、これからの生活の先を読むには難しい状況がいたるところで垣間見える。そんなに振りかぶらなくても一寸先は闇、いつの時代も人の行く末は分からないのだが、こと、住まいづくりにおいて、生活シナリオを描き、出来るだけ長きに渡って快適に対応してくれる住まいづくりを心掛けましょうと提唱してきたが、30代、結婚間もない若い施主の方と住まいづくりコラボをしていると、果たして自分もあの頃、それほど生活の先を読めていたのかと、同じ迷い道に共感してしまう。
子供だって果たして希望通り一姫二太郎なんて具合に生まれてくれるものやら、夫婦の仕事、社会との関わり方もどの様に変転するのか。時代の変化がすさまじく早く、大きなうねりと言うより日常の文明生活にも振り回される現代人にとって生活の先を具体的にイメージすることは本当に困難なことと言える。
思わず、テレビや雑誌などメデイアのトレンド特集に思いを重ねてしまうのも一つの割り切り方でもあろう。しかし、メデイアとて、これからの日本人の生活をどれほど先読みできるのだろうか。
先日、テレビ放映された映画「やさしい刺繍」の主人公は80歳になってスイスの小さな山村で主人に先立たれた落胆の日々、ちょっとしたキッカケから若い頃に夢に描いていた下着制作を始め、主人と共にやってきた雑貨店をランジェリーショップに変えてしまう。
保守的な村人からはひんしゅくを買い、牧師の息子からも妨害を受けるが、その地域の伝統的刺繍を下着にくわえることでインターネットでも売れ始め、大成功。80歳の老婆の生活は仲間の人たちと共に輝くものになると言うストーリ。夢を持ち、諦めなければ、自分の願う生活空間が手に入ると言うストーリにはおおいに心うれしくさせられた。
現実ばかりにとらわれていると、本当に先を読むことは難しいが、自らが主体的に夢を描き、その実現のための手立てを少しでも住いの中に取り入れておけば、それなりに悔いのない納得の住まいづくりが出来るのではないか。
生活シナリオには想像たくましい虚構の企て、虚像の自分を何パーセントか閉じ込めることが必要である。現実には先の読めない時代であればこそ、住まいづくりにおいては、先の夢を読まなければならない。建築家はコラボの作業の中で、大いに夢を虚構を語る役割を担う事になるのだろうか。
099. 晴れとケのけじめ
近年は年末の慌ただしい日常生活から、元旦に一転して晴れやかな改まった時を実感するということが希薄になった。以前のように、元旦はお店も閉まっている。ほとんどの人は盆と正月というくらい、休みの人が多く、国中の人たちが日常活動をとめて、けじめの時を迎えるという風潮がすたれてきた。
わざわざおせち料理を作るまでもなく、元旦から色々なお店が開いているのだから特別に構えることもないのだろう。
初参りに出かけても、デートのカップル。女性は多分、親御さんが思い入れをしたのだろう、着物姿の晴れ着であるのに、相方の男性は、ヨレヨレのジャンパーにジーンズ、髪の毛もぼさぼさ。常着と晴れ着の道行はまさに今の日本文化の混沌さを感じさせる。
わきまえたカジュアルさではなく、知性を放棄したルーズさは気分が悪い。
今年も我が家では元旦の朝は、二人の息子夫婦、二人の孫が一同に会して女房殿手作りのおせち、二人の嫁が其々一品の料理を持ち寄って新年を祝った。長男が三脚をたて、自動シャッターで記念撮影。小梅と昆布の入った福茶のあと屠蘇で献杯。
孫もわけなく神妙に「おめでとうございます」と言って、白味噌じたての雑煮を「茶色じゃないよ、ちょっと甘い。」などといいながら味わっている。
女房が、ゴマメや数の子、黒豆、たたきごぼう、蓮根などを食べる意味を孫に説明しているが、どこまで通じたことやら。
殊更、何がどうと言わないまでも、いつもと違う食生活、作法を経験することで、孫にも生活のあり様を考える気風を身に付けさせたいと思う。
息子たちが結婚した当時数年は、そろって信州の別荘で正月を迎えたのが習慣化して、こうして元旦は朝から皆が出向いてきて共に新年を祝うのが我が家の習いになったが、そろそろ各自の家庭の正月料理も手作りしてはどうかと女房は提案して、嫁たちに手始めに一品を持ってきてもらったのだが、ローストビーフと胡麻団子が加わって、いつものおせちに変化のきざし。 新しい我が家のハレとケの生活習慣がどの様に展開するかは分からないが、次世代にも、こうした生活習慣の原点を忘れないでほしいと思う。
厳しい日本経済事情の中で、サービス業の方々などの祝祭日関係なしの就労はやむをえないのかもいのかもしれないが、其々の家庭の晴れの生活空間がなし崩しに消滅していくのは寂しい限りでもある。
100. 景観・街並との調和
日本において、建築のシステム、資材がさほど多様でなかった戦前までは、たとえ成り行きで個々の建築が集積した結果の街並も、それはそれなりに美しさを持っていた。
江戸時代からの木割り術なども木造建築に秘められた規律感をもたらしていたと言える。
戦後、都市化の流れの中で人々の活動が都市に集中し始めると、経済活動の発展は時間や空間の多様な使い方を追い求め、いつか都市におけるインフラ、住宅や一般建築をはじめとする文明・文化の構築物は景観という概念ではコントロールを失ってしまった。
ゴミゴミした街、都市などは人々の営みの発展途上の証のように受け止められていた。しかし、無節操な都市化、建築行為は日々の生活の利便性や、安全・安心、健康、地域コミュニテイなど本来求められるべき生活基盤の根源を脅かし始め、結果として犯罪などマイナス事象も多発することとなった。
先進国としてこれではいけないと言うのか、景観法も定められ、環境・景観に対して気配りが必要であるという社会的コンセンサスがたちあがった。
ヨーロッパの都市を旅すると、新市街、旧市街と言うように歴史的な景観を持つ町並みとが対極的に計画された例を多く見るが、日本ではせいぜい歴史的保存地区程度の空間構成規制くらいしかないので、景観破壊のエネルギーの方が大きいといえる。又、開発や建築行為には経済活動が伴うため利害関係の対立もあり、建築協定などもなかなかスムーズにまとまりにくいのが現状である。
個人住宅においても、施主の方が計画当初から近隣環境、景観の配慮を第1に上げられることはまずありえず、住まい手の趣味や希望をむしろ法規制に如何に対応させるか苦労することが多い。
個々の建物が仮に景観を意識してデザインしても、隣地の建物が同時に同様の条件で建築されるわけではないので、周りとの調和を考えることの努力や配慮はその評価を未来にしか確認できない。
つまり、未来の街並をイメージできる「力」を身につける、あるいは了解しやすい景観コンセプトの一般化を行うことが必要であろう。
最近の京都の町屋再生プロジェクトや開発行為も見ても時流に乗った経済活動に過ぎないものが多い。
「京都の土地は京都人以外に売るな。」「地上権、空中権だけ売ればよい。」と痛烈発言が出るくらい、平安京の心をトータルに長い目で見据えた景観デザインが望まれる。
東京資本、中国資本といわれる魔の手が率先して日本の文化遺産・京都の平和・安寧の「美」を理解して日本人共有の調和の精神を京都人と共に再構築することも現実的な方法、めざす一歩であるかもしれない。
廣瀬 滋著