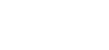たらちねNIPPON主宰:廣瀬滋
■はじめに
多分初恋の頃からか、人の営み、人間関係の一筋縄でいかない所に不思議な面白さを感じていた。やがて、建築設計の道に進んだが、設計事務所に勤務して、所長のカバン持ち、駆け出しの頃、公共建築や大手の企業の施設設計打ち合わせ会議などで、最終的にその建築に関わる人々の想いや願いが深く考慮される以前に、予算をはじめハードな与件や建築条件で計画の概要が決定されていくことに、さらに計画が実行される過程では業者の取引などに若輩の正義感では納得のいかないことも垣間見て、違和感を感じた。
自分はもっと個人、身近な人間の営みとの関係を建築したいと思うようになり、住宅や店舗施設など、オーナと直接対応しながら建築設計活動が出来るようになりたいと考え、大学卒業後4年ばかりで建築研究所(設計事務所)を設立した。
若造がいきなりオーナ直の仕事を受けるというのは、なかなか大変なことであるが、幸いにも叔父や知人のお蔭でスタートが出来た。
しかし、仕事には波がある。下請け仕事をしないために、デザイン専門学校の講師、住宅設計でご縁の出来たオーナの関連会社の施設設計や嘱託顧問、友人との色々なプロジェクトに参画するなど、結果として多様な経験の「場」に出会うことが出来た。
色々な状況、局面で色々な人々の生活に共感し、生活シナリオを想起、住宅をはじめとする建築として、その答えをかたちにする訓練は、とても楽しい自己研鑚でもあったと思う。
今、そうしたプロセスの中でに感学したことを通して、これからの日本、そんなに振りかぶらなくても、まだ小さい孫が、いつか爺ちゃんはこんなことを考えたり思ったりしていたんだと知ってくれたらうれしいかなと思いつつ。
それぞれの人が、身近な生活のあり様、活動を通して自分の感性や思考のあり様を自覚して、それがまわりの社会、日本、世界のコモンセンスとどの様な繋がり、関わりを持つのか、「自分みえる化」の一助として、又、「たらちねNIPPON」活動の一面になればと考え断片的ではあるが、想いを綴ってみた。ご意見、ご感想など頂ければ幸いです。
■21世紀、世界の母は「たらちねNIPPON」
2012年、世界中が人類の吐きためてきた文明と文化、民族の「業」、あざとい欲望のつけの嵐に加えて地球規模での自然異変にたじろいでいる。
人類の歴史は世界遺産と言われる様ないろいろな地域、国家の歴史上の遺跡や記録文書などで知るところであるが、産業革命以後、「進歩」という概念意識のもと、性急な文明、技術革新などによって局所的に先進国「強者」、後進国「弱者」を生み出してきた。
情報革命による情報化社会がもたらしたグローバル化は地球規模で瞬時に全体の関係を見抜ける世界を創出したため、人類の生み出す文明の英知、技術力は文化を醸成するゆとりを持ちえず、あらゆるところでプラスマイナスが同時にぶつかり合い、混乱、混沌の嵐を巻き起こしている。
強者の論理で突っ走ろうしても、瞬時にそれが破滅的であることを知らされるIT時代。
にもかかわらず、人々の身近な生活を仕切る経済システムは数式で、あたかも証明されるものこそ正しいと云うばかりに、どん欲に効率化、収益を上げることに執着している。
見えないものの価値、人の心の幸福度を置き去りにした結果、もはや思想や宗教の違いを超えて解決しなければならない問題が山積しているのだ。
今、世界のいたるところで日本が見直されているのは単なる現象であろうか。
日本のポップカルチャーと言われ、アニメやフィギュア等が受け入れられているが、その背後に東北大震災後の日本人の冷静な共生をイメージさせる行動の映像が世界に発信したものは如何なる意味合いを感じさせたであろうか。
世界の人々とどこが違うのか。日本人の何を考えているのか分からないと揶揄された微笑の深奥が誤解から信頼に変わるのだろうか。
古来から日本は、その時代の流れの中で他国の生活文化や風習を受け入れ、日本の環境になじませ、やがて独自の技術や智慧を生み出し、海外にその評価をされてきた。近代以降、又、第2次大戦後も、その特質は大いに発揮され、経済大国としての立場をも築き上げてきた。しかし、長らく、その背景にある日本人の資質は、特に奥ゆかしさ、イエス、ノウをはっきりと答えないなど論理的な発信力の弱さのために欧米人には理解しにくいものであった。
したがって、次々と繰り出される日本の高い商品力生産の事象と日本人との間は、ある意味不可解な神秘性を持って受け止められていたと思われる。欧米に日本文学や文化の熱烈な研究者がおられるのも、そのせいかも知れない。
昨今、日本の経済力をベースに展開された海外経済援助活動の効果や情報化時代の民間レベルでの情報発信力によって、クールジャパンと言われる様な発見視点は、今まで外国人が知見していた背後にある日本文化、日本人の資質、才覚の存在を探り出す興味を喚起し始めている。
日本が海に囲まれた島国で単民族国家であったという与件は大変大きかったと考えるが、国家の根幹をなしてきた天皇制は現憲法における象徴としての存在と言われる以前から、基本的に支配者のつかさどる政事と祭事の内、もっぱら祭事を執り行ってきたと云う事実、そして日本の民主主義と云うのは、階層間の紛争や革命などと云う欧米の社会システムの成り立ちではなく、天皇みずからが政事より祭事に主点を置いて国を治めてきたことに起因すること。それ故に、千年を超える長い国家体制、平和な社会体制を維持し続けてこられたことを顧みたい。
世の中を収めるに当たり、支配者である天皇は最高位にありながら祭事を取り仕切り、幕府は政事を執り行なう。このバランス関係は、ジャンケンポンにおけるグー、チョキ、パーの関係の様なもので、歴史的な時間の流れの中では基本的に国家の安寧、安泰を維持してきたと考えられる。
又、祭事は国民の平安を祈る祭りごとであり、最高支配者が国民の平安のために祈るという関係が、どこかで時の政治支配者の横暴をも破滅的結果に至らずに乗り越えさせてきたのであろう。
日本の気候、風土、環境が元々そうした日本人の資質、人格を形成させたのか、そこに神道や仏教が生活規範として成立、又は入り込む必然性があったのかは、学舎、研究者でない私には解答力はないが、日本人のみならず自然の脅威に畏怖の念を抱いた人類の多くが、八百万の神的存在を置くことで想像、想定を超える事象に「祈り」「お祓い」等で対峙したのはうなずける。一方、キリスト教に代表されるように、人々にとって、理不尽な事象も含めて、すべてが神のもとに創造され、神の意思によるという設定を信じることに原点を置けば、論理的あいまいさはなくなるが、アダムとイブの原罪に始まる人類の「罪」というものが積み重なり、あふれていけば、現実には戦争も聖戦として肯定されていく。
「罪」といえる人間の行為を如何にコントロールできる手立てを準備するのか。法的裁きを設定しても、幾多の罪は繰り返し噴出する。そのために神の絶対の「愛」を信じる心を育て「罪」へのブレーキを掛けるか。それとも輪廻転生を含む尺度で命の永続性をイメージさせ、「罪」を犯すことを抑制するか。
今、世界中で経済格差がもたらす貧困に起因する社会問題が起こり、連鎖的に多様な紛争が絶え間ない。人々はその解決を願ってどの様な努力をしなければならないのだろうか。神のみ心のままにという理解を超えて現実に流す「血」は人々の忍耐を超えるものである。
そこから逃れるすべとして、その理由を国家や民族の集団が、個々に其々の絶対の神の存在を示しあうことを求めれば、現実の諸問題を解決する糸口を見つけ出す前に互いの存在を消滅させるという矛盾した衝動の呪縛に落ちる。
ここで思い起こしたいのは、戦後の復興、又、3.11大震災後の冷静、沈着、穏やかな絆の中での生活復興への動きに表れた日本人の姿である。論理化、形式化された規範にのっとると云うより、「美徳」というか、生活の色々なシーンの中で何が最も美しい、納得がいく解決であるかを瞬時に見つけ出す素養、日本人の問題解決の才覚こそが世界の人々にも不思議な安堵感を与えたのである。
苦境の中での「救われたい思い」が、国家、民族、文化の違いを超えて人々に安寧の、人類のための存続のための可能性を感伝させたのだ。この力こそが、「たらちねNIPPON」と名付けて、これからの世界の平和を築く起源、「世界の母」になれるものだと思う。しかし、今日、日本でも震災の様な究極の場面がなければ、日常ではこうした美徳のような目に見えないものへの価値観を重んずる風潮は廃れ、21世紀、これからにこそ必要とされる日本文化や日本人の中に培われた美意識や才覚は継承されない危機にある。身近な生活の中で、日本人のあり様、日本文化、感性、才覚、生活の知恵などに気付くこと、そのための意識的な「日々感学のすすめ」を模索し、名付けて「たらちねNIPPON」を合言葉に元気な世界に誇れる日本の再生を願いたいと考える。
■明日を生き抜く「感性」+「創造力」と「才覚」
人々は日々、生きていくために感性に負うところが大きい。感性には「知識・経験」「感覚」「感情」「表現力」等が複雑に絡み合うのでなかなか捉えがたいものでもある。したがって、明日を生き抜く感性を持つ、育み磨くと言っても一つの決められたアプローチがあるわけではない。
ただ、感性がなければ生活が始まらない。あえて言うなら、主体的生活と環境との共生生活と云った「たらちねNIPPON」の命題の一つが意味を持つことが出来ないとも云える。日頃、日本人一般は、感性ということについて意識的に考えて行動する人は少ない。少ないというより、感性に含まれる「表現力」の部分において奥ゆかしい、又はあまりにも同質的なせいと思いこみ、刷り込まれ方のせいかも知れない。日本人の意識しない感性に、今、世界の人々が何を感じ、その感性のあり様にいかなる意味を見出そうとしているのだろうか。
一人一人の生活、生き方に於いて基本的な出発点、原点になる感性について心を留めることは、今求められる大切なことである。
よく感性は生まれつきのもので、「私にはセンスがない」とその表現力の部分のみ重点を置いて自らを誤解している人が多い。確かに、感性には表現されて初めて他人にも理解され、想いも伝達できるので、表現のための訓練、技術は必要である。
芸術家は、まさに、色々なスタイルで表現することが出来る感性の達人たる人達であるが、一般の人々に於いても日々の生活の中で感性は至るところにその姿を現わしている。例えば、その日の身なりを整える時、来客を迎えて居間のしつらえをする時、食事の時にテーブルの飾り付けに気配りをする時など衣食住の生活行為にその時々のその人の感性が演出されている。
日常は、こうしたことが習慣化されていることが多いので、さほど意識されることが少ない。さりげなく行われている感性の日常表現を意識化することで、人は必ず新しい次の表現、演出方法などを「ちょっと変化を持たせよう」というステップで思い浮かべ始める。これが創意の始まりである。
創意は創造性の流れを作り出し、人は次々と自分の感性を動かし流れを生み出し、その表現、演出の流れにまわりの人々が反応することを心地よく楽しむことを知る。
「ちょっとオシャレをしてみる」と云う様な気軽さが、創造性を高める出発点でもある。
そして、その後いろいろな生活シーンでの感性を生活の中で演出、表現することが自分の存在そのものをも実感させることに気付くのである。
さらに、一歩進んで、如何により効果的に演出しようかと思う時、何をどのようにと云う生活シナリオのストーリの組み立てや、手元に満足な道具だてがない場合、代用品の活用など、その時、その場の最適の表現、演出を実現させる「才覚」が求められる。
一般に、色々な場数を踏む、体験を重ねることが大切と言われるが、まさに、才覚はこうした感性の表現、演出の場数を踏むことによって応用力を養い、力を大きくする。
豊かな生活感を持って過ごすためには、其の基になる日々の感性の観点の幅を生活のあらゆるシーンの中で広く持つことであり、その色々な局面に、ちょっとした創意を込め、それを実現するための算段に思考回路を回転させる訓練、エキササイズが重要となる。
何事も訓練は苦しいものであり、長続きさせ訓練そのものが習慣になるまでは大変な努力をも必要とするが、今、世界の人々が注目する日本人の文化・文明は、日本人の多様な職人道、芸道などに於いて修練されてきた感性、創造力、才覚、技術力等の集体性に他ならない。
「たらちねNIPPON」これからも日本人が、日々の生活の中で一人一人が自らの感性を身近に意識付、創意を育むことに楽しみを感じ、過去の生活の知恵・技にも学びの姿勢を磨けば、増々日本は人類の生き残りにかける道を築くことに寄与できると思われる。
■輪廻を含む生活尺度の持ちかた
昭和24年、私が小学2年の頃だったと記憶するが、ある日、突然、見知らぬ男の人が母と私だけがいる昼下がりに自宅を訪れて、「お宅の御主人が会社で仕事中に事故にあわれて病院に入院されました。すぐに病院に行ってください」と告げた。
母は聞いた途端に慌てて風呂敷に何やら包み込んで、私の手を引いて、駆けだすように家を飛び出た。父の会社は「買うたり」というところにあったので、とにかく京都駅に行かなくてはと、京都では一番早くから走っていたチンチン電車(北野神社から京都駅)の四条西洞院の停留所に急いだ。
母も私もとにかくドキドキしていた。まもなくきた電車に乗って、松原あたりに来た時、一瞬、思考回路が平静になったのか、「滋、病院の名前聞いたか」と私に尋ねる母。「そんなん知らん」「えらいこっちゃ、何処や分からへんな。」「どうしよう。」途中下車。反対に戻りの電車を待って引き返す。
あたふたと家に戻ってみると、戸締りしたはずの玄関の引戸は半開き、もしや?と思った悪い予感通り、家の中はタンスの引き出し、柳行李などがひっくり返され、母の着物だけがほとんど無くなっていた。空き巣である。 まんまと私達を外出させ、その隙に。
母の落胆というか、自分が冷静さを失くし、人にだまされたことの無念さか、しばらく黙って亜然と部屋を見つめていた母の姿が今も思い出される。
以来、ことあるごとに、母は「騙されても、人をだましたらあかん」と口癖のように私に言った。又、被害者になっても、加害者にはなるなということで、結局、自動車の免許証を生涯今に至るまで私に取らせなかったのも、母のたっての願いからである。
「紙の無駄使いをすると、地獄で神の橋を渡らせられる」「天に唾すれば自分に降りかかる」「飯粒を粗末にすれば目がつぶれる」「そんなことしてたら、生まれ変わったら餓鬼になる」等、因果応報、輪廻転生的生活感は日々の生活の中で嫌というほど刷り込まれた。
一方、戦後のアメリカに影響される教育風潮は、個人主義、個性の尊重、合理的考え方などを助長したので、道徳を含めて、従来からの日本的生活価値観は次第に力を失っていった。
マラ、産業構造の変化や情報社会の到来で、生活が多様化したため、なおさら一律の価値観、「和魂」と言われる様な価値観では社会順応性がない、協調性がないということになりかねなかった。団塊の世代と言われる人達はそうした肌で感じる精神的矛盾を生き抜いてきたとも云える。
戦後70数年を経て、そうした日本人の精神世界における矛盾と葛藤は、今、新しい局面を迎えているのではないだろうか。欧米の合理主義は短期的には論理的納得度のある効果を生むが、時間の経過と共に、見えなかったもの、切り捨てていたもの、負の蓄積がその効果をも帳消しにすることを、公害問題や環境問題に於いて示している。原子力発電に関わる問題もそうであろう。一方、従来からの日本の時間列を考慮した合理主義は、江戸時代に始まるリサイクル、循環システム、節約主義などにみられるように結果として自然との共生、持続可能な人類の生態社会を可能にする理念に繋がる。
このことは、輪廻を含む生活尺度を持ってライフスタイルを築くこと、その集約、集合がこれからの人類の生き残るための道しるべになることを予感させる。
今、話題になる「幸福度」なる人々の価値観を分析した指標も、現実に起こる不公平や差別感を単に運命と云う人々の価値観を分析した指標も、現実に起こる不公平や差別感を単に運命という諦観を横に見つめて進むものでないこと、死後も含めた今世、来世を連続的にイメージできる感性があればこそ納得度が生じるのではないだろうか。
このことを日本人は比較的穏やかな恵まれた自然、風土の中に生かされることによって、知らずと身に付けたて生きてきたと云える。
天(自然)に対する尊厳、道徳、礼節といった輪廻の尺度を身近に持ち合わせることで日本人は、「命」の運営にそれなりの才覚を発揮しながら歴史を刻み、時に反省を繰り返し、その反省のための智慧を生み出す力を蓄えてきたことが、今、世界から注目される日本の底力となっているのではないだろうか。
■特殊解を一般解にする工夫
人との体つきは様々である。仕立て屋さんに頼んでスーツを作ってもらった自分の体型に合った服は、スタイルは自分なりの体系それなりであるが、少々太ったりしても、それなりに着ることが出来る。既製服のシルエットは美しいプロポーションに仕立てたあげられているが、チョット体形が変わるだけで部分的に窮屈になり着用できなくなることを体験した。
オートクチュールの世界からプレタポルテ、そして既製服という流れは、まさに特殊解から一般解への事例でもある。特殊解の良さは、限られた条件、事例に程よく対応していることであり、当事者にとっては、してやったりの好感が伴う。その好感や利便性をより多くの人々にも適応できるようにすることは、多くのビジネスチャンスを生み出す。
その変換のためのアアイデア、技術、特殊解と一般解のバランスのとり方などの才覚は幾多の経験則、思考錯誤の蓄積から磨かれる。
このことは、特殊解を浮かびあげる個の感性とその特殊解の特性を観察分析し、一般解に移行させる手立て、コンセプト化を意味する。特殊と思われる生活背景を、ストーリの組み換えによって如何により普通の情景に置き換えられるか、1人の「おしゃれ行為」を流行に変えるマネジメント力は多くの経営者やデザインプロデユーサにとって求められる重要な素養でもある。
もし、東洋の島国、日本が特殊な場景に於いて特殊な文化や文明の素養を育んできたとすれば、その総合力を如何に世界に通じるものに変換できるか、認知されるものにするかは、今日の日本の喫緊の課題でもある。
日常生活の中で、ふっと感じること、思い浮かぶ自分なりのこんなこと、あんなことがあれば、ノートなどに書き留め、その特殊解や一般性を検証してみることの習慣化も私の提唱する「生活美人」への道の一歩として細やかではあるが、大切なポイントではないだろうか。「たらちねNIPPON」活動へのささやかな努力行為に繋がるとも考える。
■「ハレ」と「ケ」けじめの意識付け
日本の生活、文化には四季折々の変化が色濃く反映されてきた。農耕社会をベースに催事(祭事)に伴う日常性と非日常のけじめが生活の流れにも多くの影響を与えてきた。
又、貴族社会、封建社会をはじめとして人々の階級における差異も、一つのけじめを伴って生活の習慣、衣・食・住のあり様にもそのスタイルをかたちづくってきた。
そのベーシックな生活の流れがあればこそ、そこにそれぞれの人々の工夫や智慧が育まれ日本人の生活文化が変遷・発展してきた。
しかし、第2次世界大戦後の混乱期以降、日本再建の社会変動の中で、生活は多様化、近年は更に情報化時代にあって、日本人の生活はその基本的なあり様、姿を見失ってしまった感がある。
個人の自由、気軽さ、合理主義などの拡がりと共に、分別のないカジュアル化が生活のいたるところで蔓延し、かなりの生活シーンは略式、略礼は当たり前の状況にある。昭和40年代には年末・12月31日(大晦日)と元旦との街の様相の一変、人々の服装の晴れ着姿の清々しさがあった。そのことを想起すると、昨今の「ハレ」と「ケ」のけじめの希薄さは具体的な日本人の生活基盤の喪失につながっているのではないかと直感してしまう。
昔の生活、過去の価値観に戻るべきと云うつもりはないが、無意識のうちに存在した日本人の生活の底流を、わかりやすく言えばカジュアル化で無くしてしまったという思いが強い。
これからの日本人が生き残るための才覚を見出すためには、身近な生活のシーンにおいて季節感や日本人としての感性を意識して衣・食・住に関わる生活行為を明確に表現、演出する習性を身に付けることが重要になるのではないか。
これからの時代の流儀を提示できるリーダの出現と、それを共感、共有できる「場」や仕組みづくりが求められる。都市生活は人々を人間として鈍重にするBOXであり、情報をはじめ過度の刺激は受容体としての人々をマヒさせ、均質化させている。
「ハレ」と「ケ」のけじめをつける意識付から、一人一人の日本人が「個」を取り戻し、自らの感性、創意を発揮するゆとりの心地よさを実感し、その出会いや交流がトータルな新しい日本の感性、才覚に収斂して世界に生き残れる日本、日本文化の再構築に繋がることが望まれる
■日々感学・生活シナリオを描くことから始まる生活建築力
人が生活をしているということは、家庭、社会、自然という舞台で各自が色々なシーンを演じていると云える。日常、ほとんどの場合、演じている人々には、そのストーリ性・シナリオなどは意識されることはないでしょう。 むしろ、与えられた環境の中で「何となく生活している」といった感覚でしょう。
身近な住宅(家庭生活)に於いて住い手は主演者であり、同時に観客でもあると思ったことはありませんか。色々な生活シーン、色々なドラマが繰り広げられ、演じられるためには、そのためのシナリオとそれを支える空間、装置(家具・道具など)が用意されなければなりません。
シナリオは(1)大きなライフサイクルの流れ、(2)日々のアドリブ、(3)季節の移り変わりや催事(4)自然や社会、未知の人々との出会いによる新しいストーリ展開などが寄り合わさって展開され、人は365日同じようで違った芝居(生活)を繰り広げています。
さらに、住い手に自分達の生活をより楽しく生き粋としたいという積極的な意思や気持ちがあれば、住宅という生活舞台は、心地よい緊張感や穏やかな優しさに包まれて輝くでしょう。
心通う友達が訪ねてくる日を想像してください。朝から、そわそわとして部屋の「しつらえ」に気を配り、ティタイムにはどんなケーキを出そうか等と思いを巡らす楽しさは「友、来る」というシナリオがもたらすものです。
結婚から子育て、やがて子供の独り立ち、老いた両親との同居など、それぞれの人生模様に如何に対処するか、ストーリ・シナリオの描き方によって、住宅のプランニングは十人十色と言われます。たとえ今、予算や時間的余裕がなくても、いずれ試みてみたい趣味のためのスペースはいずれかの部屋の転用であれ、増築であれシナリオの一つとして考慮しておかなければなりません。生活のシナリオ化が行われなければ、そのために必要な設備、家具、道具などの選定、インテリアデザインなども決定することが難しいと云えます。
実際には、「条件の整理とまとめ」、「全体構成とバランス」と「生活シナリオ化」は、順序立てて行う作業ではなく、大まかな条件設定がなされ、その中でシナリオが想い描かれ、その実行、演出のための条件設定がなされ、全体のバランスが検討され、そしてまた、生活のシナリオがあらためられるという行きつ戻りつの思考、設計作業が繰り返されます。
とは言え、限られた時間内に決断をしなければなりません。「住まいに何を求めるのか」住まい手の生き方に対する価値観の持ち方、優先順位の決断が、どれだけ多様な、どれだけ多くのストーリ・シナリオを確保するのか、実現するのかを決定するのです。
同様に仕事をはじめ社会生活との関わりに於いても、人々が如何に取り組むか、それぞれの職業、企業活動を通じて何をめざすかという点に目標や指標が意識されて初めて、そのシナリオのためのこだわりを持ち、主体的ストーリ・シナリオを描くことが出来るのです。
そのために、日々、同じような生活の流れの中にあったとしても。昨日とは異なったやり方、考え方で行動してみることで、新たな感じ方を発見、自分の生活の中に新しいストーリを見出す、組み入れていくことが可能になると云えます。
何事もない平穏無事も人生における幸福度の一つではあるが、日々、自らが自分の中に変革の可能性を見つけ出しながら、自らの存在の確信を高めながら生きていく、その道筋を創り出す、自分の生活シナリオを描き、演じてみる楽しさを実感する時、周りの人々との人間関係も能力、財産、器量、社会的地位など表面に現れたものの生活シナリオ実現の装置や道具立てを超えて、より見つめなければならないものが見えてくるのではないか。
より多くの人々が、日々感学、自分の生活シナリオを色々描こうと感性を磨き、自らの創意あるシナリオを演じることをすれば、日本人にはこの日本の風土、環境、文化を背景に日本人独特のシナリオを描ける才覚が甦る可能性がある。日々の生活のあり様の中に日本人の潜在的創造力、文化力を生かす努力の大切さは、結果として「たらちねNIPPON」の具体的な活動指標の思考+行動のトレーニングとしても役立つことであると考える。
■めざすは生活美人
色々な人間活動、その「道」のプロフェッショナル、達人はよく知られています。
私は身近な日々の生活の中で生活建築力(自分の生活を活性化出来る感性と才覚)を持っている人、日常性と非日常性のバランス感覚を持って仲間と共に快適、美しい、落ち着く、便利など生活を左右する感性と意識を空間(環境、現実の住空間も含めて)、もの(家具や道具など)、システム(手段、手順、作法、所作などを含めて)と対応させて発想、考案、演出、表現、展開出来る人を「生活美人」と命名しています。
別な言い方をすれば、生活美人は日々の私生活、職場生活、学校生活などに於いて生活環境を感学して新しい気付き、問題意識を発見、その解決のために具体的な生活シナリオを想い描き、周りの人達と生活建築力を交流、その実現、具体化のために必要なプロデユースが出来る人といえます。
生活美人として限られた人生の時間に於いて、自己の存在感を持って生きる楽しさを味わうためには、日々の感学能力を高め、生活建築力を育み磨くことの重要性に気付くことがスタートになります。
生活美人にゴールはありません。人間国宝とか技能士と云った資格検定もありません。
生涯、せいかつ美人としての資質を磨く一歩一歩の努力は大切です。生活美人として生きるという自覚を持つことが出来れば、そこから色々な展開に可能性が生まれます。
日々の生活、行動の中に絶えず新鮮な感性情報(主観)を取り込み、その客観化のための学習や周りの人達との意見交流などの習性を身に付けることから新しい生活スタイルをイメージする生活シナリオ化を試みることで生活美人への道が開けます。
生活美人としての資質、感性、才覚は人が今までどの様な人生、生活環境を体験してきたかという背景にも大きな繋がりがあります。しかし、私は体験的に生活美人へのプロセスはデザイナーやプロデユーサ、経営者などのスキルの訓練の中でその体験を通じてパラレルに磨かれると考えています。
具体的に生活行為を社会現象を観察し、意識して問題点に気付き、そこから新しい発想で問題解決まで取り組む姿勢を持てば、先天的に生活美人の資質や才覚、感性が備わっていなくても、ものの見方、考え方が意識的になれば、日々の生活のあり様は自然と生活美人的に変化するのです。
日本人は四季折々の変化のある風土・生活環境の中で色々な創意工夫をして伝統工芸や生活空間に生活美人的素養や才覚を発揮してきています。その素養や才覚が戦後日本の産業を支えたことは多くの人の知るところです。しかし、今、日本人の生活環境は自然・社会環境よりも情報環境にさらされ過ぎて、本来の日本人の感性や才覚を認識したり感学する機会を失っています。
東北大震災以降、日本の存在が色々な局面で知られることが多くなり、海外の人達が単に技術・貿易立国としての経済国家という見方から、その背景をクールジャパンとして見直し始めています。つまり、日本には多くの生活美人がいるということを感じ始めているのです。
勿論、ヨーロッパにおけるルネッサンス期にも日本文化はその芸術や工芸に於いて少なからず評価を受けていますが、文化と生活をとを巧みに融合する「才覚」には気付かれていなかったと思います。これからの日本人が生き残るコンセプトは「生活美人」への研鑚が市民レベルで重要なこととなると考えます。
■究極のコモンセンスについて
辞書にはCommonsense(コモンセンス)とは、常識的な、常識で判る、明白な等の意味付けがされているが、元々、Commonには普通の、共同の、公衆の等の意味があり、Senseには感覚、観念、思慮、意味、多数の意見等の意味合いが込められている。
日本語の「常識」には、普通一般人の有す、又有すべき標準知力。専門知識でない一般知識と共に、理解力、判断力、思慮分別を含むとある。
何が一般的なのか、世間の常識に照らし合わせて如何なる言動を振る舞うか、日々の生活の中で人々は刻々とコモンセンスという規範袋の中から生活観念、判断指標などを選択しながら生活を営んでいる。常識を超えた判断力が時と場合によって色々な窮地を救うこともあれば、常識に従ったお蔭で災難から逃れることもある。
つまり、一般に生活シナリオは、いわゆるコモンセンスを基軸に成り立っているのだが、それぞれ個人が自分なりの生活シナリオを描こうとすれば、ストーリの展開される場所(空間)や、時、意味合いなどによって異なった表現、演出を巧みに選別しながら行動をしなければならない。異なったストーリ展開、演出であればこそ個性が感じられ、人々は自らも、又、他人にもその存在を確認させることが出来るからである。
しかし、ここで大切なことは、よく言う「相手の立場に立つ」などコミュニケーションの原則のように、自らのシナリオが相手に理解されることが必要になるので、コモンセンスの許容範囲、容量を如何に捉えておくかという問題が生じる。究極のコモンセンスとはまさにこうした変幻自在の状況変化の中で、いかにバランスを取りながら自らの感性、才覚を発揮させうるかという極意のもとの様なものである。
究極のエゴイストとして生きる等と訳なく粋がっていた私の若い頃の思考回路はどこか似かよっているように思える。分かったようでわからぬ「究極」という見解であるが、ある意味、決めつけて捕らわれた感覚、思慮、意味などを持たず、自由に生活シナリオを展開するという心意気を持って、且つ、天下に、人々に迷惑を掛けない、何処か「美」という価値尺度を掲げた道理、それを究極のコモンセンスと呼んでみたいと考える。
■京都は多様な生活演出、試練の舞台
京都に生まれ京都で育った私にとって、大學を卒業して昭和40年、東京の建築設計事務所に就職するまで、京都の文化・風土や生活習慣の中で自分が如何に育ったのかをそれほど意識することはなかった。
うどん屋での薄口、濃い口醤油、味付けの違いから、初めての寮生活の1人暮らし、自炊のための食料買い出し、市場ではなく、澁谷のデパートの地階食品魚売り場でも関西では見掛けなかった金目鯛の赤い姿。何かが違うと感じた東京生活の始まりは感は今も鮮明である。
無論、言葉使いも違う。仕事での電話の応対にもしばらくは苦戦。身近に地域社会を感じられない。これが大都会か。
やがて生活舞台となった渋谷、新宿、六本木・赤坂たりを同僚や友達仲間とアングラ劇場での演劇公演、コンサート、色々な社会問題研究会、新しいタイプの商業施設などでの体感・体験、若い世代の凄まじいエネルギーがあふれ返る混沌の中で、その新鮮さに感動していた。
アメリカの月面軟着陸成功、小型IC家電卓の発売、男子服のカラー化、女子雇用労働者1000万人を超える等、1960年代後半からの社会の変化は、あらゆる生活舞台に変化をもたらし、その渦中に日々暮らしをしていると「進歩」「拡大」「変化」全てが自分の成長感とイコールな気分であった。
日本の高度経済成長期と云えるこの時期にグローバル化の潮流が起こり始め、生活価値観の変化が日本の文化の育成の方向性を見失わせ、表層を意図なく無差別に覆い尽くすことになったと思える。
6年間の東京生活を終えて、京都に戻った時、京都駅の静けさに「これはなんだ」と訳なく驚くと同時に、本当にホッとした安息感を記憶している。
再び、祇園祭の放下鉾町に暮らし始めて子供の頃と比較すれば形骸化したとはいえ、町内の祭事、学区の行事、京都の四季折々の祭りごとなど生活を彩る出来事は身近で、地域社会の一員として生きている「場」の実感がある。
祖父、母親、自分。そして子供と4台が通った明倫小学校が都市のドーナツ化現象による学童減少で廃校になったが、校舎がなお、芸術センターとしてそのまま、その姿をt止めていることは、不思議なほど自分の歴史、時の流れを原点化してくれる。
ヨーロッパの都市における、旧市街、新都市といった明確に区分された歴史的計画性はないが、京都には地名(町名)に名残を残すようにちょっとした一画が色々な伝統や名残をとどめて存在し続けている。そのため、未だ市民レベル、生活者の身近なところで自然に受け継がれていく文化の土壌を失っていないと思う。
社会の変化、伝統産業の衰退に合わせて、ほんの隣りにも職人のおじさんが住んでいて、色々な分野の技や芸を身近に見聞できた子供時代のようには行かないが、今でもまだまだ色々な職人魂からにじみ出る所作や言動が、自治会活動や日常の生活の中に息づいているのを知る。「ハレとケ」「究極のコモンセンス」「特殊解と一般解」「右脳と左脳の働き」等、いずれもにもバランス感アックをいかに取るかの才覚がとても重要であるが、京都は都市と田舎、伝統と現代、生活価値観としての美意識と感性が実によく日常生活の中に感じ取れるところである。
それは、1000年以上にわたる「都」としての歴史が育んだ誰もが簡単に捨て去ることが出来ない精神的、感性的DNAとでもいえるものがあるせいであろう。
時々、仕事の関係で、東京に行くことがあるが、ますます複雑になった地下鉄の路線図に戸惑うように、霞が関に初めて高層ビルが建った時から、都心の開発、建築技術力世界一の日本の力が至る所に見られ、即、インターナショナルであることが、カエッテ日本人の美意識の根底に潜む魅力を捨てて、一般解にし過ぎてしまったように感じる。
東京には近・現代の機能主義、合理精神を象徴することに於いても巧みに日本人の感性を表現しているところもあるが、その存在のスケールや固有性において、一人一人の人々の生活との絆を希薄にしてしまったために、日本の伝統、文化価値に繋がりながら新しい未来への文化創造のエネルギーを全体として育成できない「都市」になってしまったと感じる。
一方、京都は戦争による爆撃を免れ、奇跡的に世界一歴史のある都市として生き残ったばかりか、その後の都市機能としての経済力の弱体化もあって大きな変貌がなく、歴史的な観光資源をはじめ、日本文化を担ってきた伝統的な工芸、技術や様式文化が今も残され、継続している。日本人の営みの歴史を垣間見たり、実感できる機会が身近にあるという都市環境は、やはり、生活を彩る感性を磨き、明日を生き抜く才覚を共有しながら鍛え上げる格好の「場」であると云える。