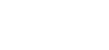011. テイータイム
女房が『母の日』に長男の嫁から中国茶の茶器セットを貰った。
以前から興味があったのだが、その時から、かつてコーヒのあれこれに凝ったことがあったように、我が家では中国茶のテイータイムが少なくとも1日3度は持たれる事となった。
中国茶のいれ方から道具、茶葉の種類など、手ほどきの入門書を買ってきた女房が、数種類の茶葉を買い入れてきたので、次々と入れ方や茶葉の味わいを賞味することになった。
東寺の弘法さんに出かけ、私はうまい具合いに、小さな錫製の茶托を掘り出すことに成功した。食器棚の中から多分叔母が過って使っていたと思われる銅製銀メッキの急須が雰囲気よろしく日の目を見ることにもなった。
さらにウイーンの骨董屋で買って置いたフインガーボールとおぼしき錫の器と嫁に貰った工夫茶器の朱泥の蓋がぴったりのサイズ、組み合わせるとグッドセンス。
おおいに気分が盛り上がる。しかも、朱泥の茶器の時と違って、湯を注ぐと錫の器に滴る湯音が風琴窟のように音を立てるのには感激した。
なにより、色々と作法のように手順を繰り返している間、息子達ともあれこれ会話が弾むのも楽しいことである。極めれば、中国茶の作法も大変なのかもしれないが、日本の茶道と比べれば『一期一会』等の厳しさよりも、色々な茶葉の香りや味を楽しみ、気軽に茶卓を囲んで、健康談議が出来る実用性が好いなと感じた。
数日後にはガラス製の茶壷や杯、色々なドライフルーツ等の茶菓子も買ってきてジャスミン茶を楽しんでも見た。二男は、「まもなく我が家のブームは去るでしょう。」等と笑っているが、まんざらでもないのかテイータイムには結構、機嫌良く付き合っている。
さらに数日後には、茶器を置く棚が有れば良いと女房が言い出して、骨董屋の店、家具を記憶の中で確かめる。中国茶器を入れられるようなものは今まであまり気に掛けていなかったので、思いは空を切る。
先日、出先から帰ると、二男がガレージで電動工具を音立てていた。何の事はない女房に言われ食卓脇のカウンターの棚を改造しているのだ。休日等には、二男はおもむろに中国茶を入れている。まだなれない手付きを冷やかしながら、私と女房も茶菓子を口にする。
テイータイムは住いを彩って余りあると思う。
012. 眼科病院にて
何十年ぶりというほど久し振りに『め』にものもらいが出来て眼科に出向いた。
東寺の近くにある眼科専門病院である。ここは一体何処かと思うほど老人、中年,そしてOL嬢らしき女性があふれかえる。察するに、加齢に伴う視覚障害と、コンピュータ業務などによる視力障害の増加であろうか。待合室は、学童時の集団検診を想い起させるほど不思議な賑わいが漂っている。
どういうわけか、受付でちゃんと『ものもらいのようです』と申告したにもかかわらず、とにかく視力検査のところに並ぶことを指示される。3列に配置された検査椅子に次々に患者が呼ばれ、視力検査を受けるのだが、順番が来るまでに、後続の患者が絶え間なくあとを埋める。
『何を患うよりも、目が見えなくなるのは怖いです』と呟きながら、ほとんど検査医の指し示す視力検眼表の記号が読み取れず、情けなそうなお婆さん。
『今日はよく見えていますね』とほめられている常連患者らしいおじいさん。
何か、指し示される記号に正解が答えられないのは、私自身プレッシャーを感じる。
やっと巡ってきた検査。色々レンズをハメ変えて、現状のめがねの度数が問題のないことを調べてくれるのだ。眼圧検査のあとで、やっと眼科医の診断である。
『要するに、ものもらいですね』と言いながら眼球の断面イラストを示しながら病状の原因、経過、今後の対応を説明してもらう。
なかなか優しい青年医である。『有難うございます。』と心から礼を言いたくなるタイプ。
看護婦さんが発給する目薬2種類と軟膏の説明をした後、受付で待つことになる。
やがて、名前を呼ばれて、再び目薬の説明を受けたのだが、先ほどはピンク色のキャップの目薬であったのに、今度は黄色である。『先ほどの説明のものと色が違うのでは。』と質問をすると、係りの人はカルテを持って内線電話で診察室に問い合わせをした。
『先ほどはピンクの目薬でご説明しましたが、どちらも殺菌薬で、今、確認しましたが、この黄色のもので間違いありません。ご安心ください』とのこと。
処方薬の説明が、診察室と医局(受付)で二度行われたのはチェックシステムとして有効なのかも知れないが、お年寄り患者の多い医療現場では些細な手違いは発見されにくいだろうから、不安が残る。
眼科専門病院というのは、建築計画的に見てまだまだ診療所レベルで、これだけの患者数を診察するには改良の余地がありすぎると思った。診察、受付など動線計画があまりにも無計画で、スタッフや患者が入り乱れてワンルーム的空間にうごめいているのが、入った途端の不思議な賑わいを感じさせたのだろうか。
ほとんどの生活が視覚に頼ることが多い人間にとって、視力の衰え・障害は結構重大問題であると考えさせられるひと時であった。
013. 食事のスタイル
近頃の日本の一般家庭での食事スタイルは、共働き家庭が増え、食事時間がまちまちになったり、健康管理のためそれぞれの食事メニューが異なるなど,多様化した食生活のため,食事時間に全員がそろうことが少なかったり、個別に盛られた料理を其々が食べる会席風個別スタイルなど多様である。
山賊飯などと揶揄していた、食卓の中央に幾つかに盛られた料理を、家族がおもいおもいにとって食べるスタイルは鍋料理の時は別として大変少ない。
個別スタイルであれば、自分のものは残さずきれいに食べるというような行儀作法もたちまちチェックされてしまうが、山賊スタイルのように誰が何をどれくらい食べたのかも解からなければ行儀作法など堅苦しいことは問題にならない。 理知的なスタイルと野蛮なスタイルと云えるかも知れない。
同じ釜の飯を食うということがあるが、山賊スタイルの食事は、家族(メンバー)の親密度、和やかさなど人情の暖かさを自然に育んでくれる。
色々な会話もはずみ家族が知らず知らずのうちに連帯していくチャンスがある。
どうして食事スタイルが改めて気になったかというと、先年、韓国を旅行して韓国の料理の形態が(多品種メニュー、まとめ盛り付け、多様な鍋料理等)どちらかといえば山賊スタイルであったこと。そして皆が大変食事を自然に楽しく、和やかに行い、しかも振る舞いの中に自然と目上のもの、年長者を敬う所作が随所に見られたことに感じるところ、心うれしさがあったからだ。
思い出せば、遊牧民にしろ、少数民族にしろ、自然や社会の生存競争の厳しさと戦う民族には、今だこうした山賊スタイルの食事空間が流れている。
食事という人間にとって基本的な行為を共有、連帯のうちに出来ればこそ、家族、社会の自然な人間らしい姿を身に付けることが出来ると実感、直感するのだ。
アウトドァにおけるバーベキュー、鍋料理パーテイなど人間関係を補完する為の食事スタイルがあるが、もっと家族の絆を、人間の熱き心を実感できる山賊スタイルで食べる料理メニューを日々の家庭料理の中に増やせば良いのではないかと思う。
核家族、個人主義、男女平等など、戦後、我々が進歩として獲得してきた欧米風価値観が、生活スタイルに反映される時、家族が食事行為と団欒を通して育んでいた連帯観、人格形成、生活の智慧や文化、風習の継承と言った大切な面を希薄にしてしまったと思う。
今、「食育」として小学校でも、食生活に関する教育が行われているが、食と健康など実利的側面が前面にあって、食生活の奥底にある人間と自然、人と人の互恵の関係などをを感学させる場にはなっていないのではないか。
旅における韓国料理は、健康メニューで実に人情豊かな空間を感じさせてくれた。
014. 姓名とイメージ
知人から自分の名前からゲーム感覚で、「脳内イメージ」が判別できる超人気サイトがあると教わった。
ちょうど、今、私にとってやがて2人目の孫が生まれることになって、一体どんな名前が良いかと次男夫婦が楽しみながら思案している。昔のように家長たるお祖父さんが名付け親に名乗りを上げることは、今では、叶わぬ願いで、私たち夫婦して『こんな名前はどうかな?』と話題に首を突っ込んで拒否されている。
それにしても生まれる赤ちゃんは自分の名前を選ぶことが出来ないのだが、大抵、色々な親の願いや希望が込められ、運命も左右されかねないという真剣な想いが、日常気にも留めていなかった「姓名判断」という篩にかける行動をとらせたりする。
漢字の画数がこれほど脚光を浴びるダイニングまわりはなぜか眩しい気配ですらある。
人は、芸能人や作家が芸名を持つ場合を除けば生涯ひとつの名前ですごし、死して戒名を持つのが一般的である。私の母は、何時の頃からか『易』や姓名判断が好きで、私が社会人になると同時に、「これからは周りとの協調も大切、親の面倒もちゃんと見てくれる人間に成ってもらわないと困るから」とまったく突然に、一存で私に本名以外の名前を姓名判断の先生に決めてもらったと言うのだ。
高校生になる直前に父親がなくなったのをいいことに結構やりたい放題で、母に苦労や心配をかけたこともあったのか、自分でも驚くくらい抵抗なく母の申し出に従った。
今から思えば如何なる心境であったのか思い出せないが、以来、母が亡くなるまで20年近く俗称を使うことになった。自営業として色々な取引先からいただく報酬や、講師などの給料扱いのものなど税務申告時には混乱をきたし、ある年は、本名と、俗称2つの名前宛に申告書が送付されてくることもあった。
また、旧来の知人、親戚のおばさんですら本名で呼び続ける人もいて、ジキルとハイドではないが、2つの人間、人格を生きるのは「ひょっとして、こんな感じかな」と思うこともあった。
母がなくなり、親孝行という口実もなくなれば、銀行取引や色々の実生活での不便は煩わしく、本名で再び生活することにした。こうした体験を持つ故に「脳内イメージ」とやらで、俗称と本名を比較してみると、過ぎ去った日々のあり様を結構反映しているイメージ図が浮かび上がり、面白いと思った。どうしてこんなソフトが開発されたのか興味深い。
それにしても、未熟児で生まれた私が無事に生育するようにと想いを込めて父が名付けてくれた本名は、俗称で生活した20年余り、やはり運命的に私の深奥に寄り添っていたように感じる。もし、生まれて来る時、自分で名前を選べるとしたら、人はどの様な「運命」をゆだねてオギャーと一声をあげたいだろうか。
親の専権とはいえ「名付け」は結構意味深いと思った。
015. 私と携帯電話
いまや携帯電話は社会生活には欠かせぬモノとなっている。
私も時代に後れることなく、PHSの出はじめから使いはじめ、まだ地下街などで携帯電話が通信出来なかった時にはPHSと携帯電話の2台を持ち歩いていたこともある。しかし、第一世代の携帯電話では事務所に居るか、仕事で出掛ける時も比較的行き先の明らかなことが多い私にはほとんど自宅への「帰るコール」しか利便がなく、充電や携帯のわずらわしさのため携帯を持たないことにした。
その後、携帯電話は進化し続け、カメラ機能も備えるまでになった。ちょっと建築現場写真も取ることが出来そうで少しは自分のライフスタイルにも役立ちそうだと思い始めていた3年前、息子夫婦と旅行をすることがあり、出先でのバラバラ行動と集合連絡のためトランシーバの役割かわりに持って便利という理由が動機となり再び携帯電話を持つことになった。
しかし、その後も仕事関連を始めほとんどが従来の固定電話で通話するため、多様な機能を搭載する携帯電話もしばしば身につけることを忘れる有様である。
先般、東京出張の折、会議が終わってコートのポケットに入れておいた携帯電話が無いことに気が付いた。何箇所か会議、面談で移動したため、コートを着脱、どこで落としたのか定かではない。同行のM氏が私の携帯に通話しても「電源が入っていないか、電波の届かない所云々」の応答しかなく、訪問先の方にも捜索をお願いして一区切りをつけた。
けれど、何かとても不安で落ち着かない気分である。普段はさほど重要とも思っていない携帯電話なのに、無くなったとなると自分の体の一部が亡くなったような不思議な感じがする。
同行のM氏は3台の携帯電話を所持、使い分ける達人。「とにかく、通話停止手続きをしましょう」という。ちょっと見渡すとちょうどNTTドコモ虎ノ門店があった。ずらり並んだカウンター。整理番号をもらって待つ。手続きは思いのほか簡単。生年月日、住所、携帯電話番号、機種を確認され本人とわかるとパソコンであっという間に利用中断手続きが完了。
再通話のための解除暗号番号を決め、手続き書の控えをもらって外に出た。他人が成り代わって通話することが無いということで少しほっとした。
「本当にどこで落としたのか」「ひょっとして、朝の新幹線かも知れない。荷物棚にコートを置いた。」つぶやく間もなくM氏は東京駅忘れ物センターに電話を入れ問い合わせてくれている。結果のわかるのは明日の11時以降とのこと。帰京。
ほとんどあきらめ、機種変更もやむなしと思ったが、最後にもう一度と翌々日忘れ物センターに電話した。確認質問の後しばらくあって、「届いておりますよぉー」と私のうれしさを見透かすように芝居掛かった係りの男性の声がした。「ありがとうございます」さらに翌日、ペリカン便で携帯電話は帰ってきた。
016. 相撲の世界
時津風部屋での新弟子のしごき、死亡事件がマスコミをにぎわしている。
30年近く前に叔父の知人で相撲のタニマチと呼ばれる施主の住宅を設計することがあって、その竣工祝いに叔父と私が招かれた時、その方の親交のある親方と2人の弟子が呼ばれ、チャンコなべを作ってくれ、ご家族と一緒に楽しいひと時を過ごした思い出がある。
その時何より感心したのは、お酒が強いとか、スポーツマンの叔父のウエストが現役を引退した親方の太もものサイズでしかないというような事ではなく、あまりの博識というのか、大抵の話題に臆することなく、フランス語も操る親方のまれに見るホストぶりであつた。
その時、聞くところでは、お相撲さんは色々なタニマチのところに出かけ交流を深めていくうちに、知らずしらず、ものすごく色々なことを学ぶという。
日本相撲協会はだからお相撲さんだけで運営することができる人材が育つのだとも聞いた。以来、本当に相撲の世界は特別のものと感心していたのだが、先般の朝青龍のゴタゴタ以来どうも組織として機能していないと思い始めていたところ、今回の事件が発覚。
世の中、あらゆるところでモラルというのか、人間としての基本的所作が失われ、今まで考えられない事件、犯罪が多発し始めている。
相撲の世界でも指導する親方も外国人の弟子や現代っ子との価値観の隔たりに、いささか、とち狂ったのだろうか。
相撲取りは勿論のことスポーツ選手は厳しい勝ち負けの体験を通して早くに人生の奥義を味わう機会が多いので、同じ年齢の一般人よりは、はるかに達観している人が多く尊敬していたが、指導者として次世代を育てる段階で、この様な事ではいささか残念といわざるを得ない。
勝負事であり、型を守ればよい、勝てばよいというものでもない相撲において、いわゆる「相撲道」の今後の在り方は何かと曲がり角にある日本人の「今」を考える上でも、一考に値するテーマではないだろうか。
何事も「道」と名のつくプロフェッショナルな世界は、単に技や流儀を覚え、型どおりにこなすという世界ではなく、当事者の精神性、個別の文化資本が折り重なって表現されるところに美しさを伴い、観るもの、他者に感動を与えるのであるから、これと言った正解があるわけでないところに、奥深さが感じられる。
春の大阪本場所を桝席で観戦した時、勝負が展開される土俵に観客の「気」が集中する、その熱気が、自分がその場に居合わせることの充実感、幸せな時を感じさせてくれた記憶が、今も鮮明によみがえる。それは、相撲道に生きる関取の一瞬の対決の火花が、わけなく一直線で心に届けられるからだろうか。相撲は日本の国技、さもありなんと思う。
017. パン食雑感
明治、文明開化といわれる時代から日本におけるパン食は肉食の解禁、製粉技術の向上、米の不作時の代替食、在留外国人や海外移民の帰国、キリスト教の発展、外国人向けホテルなど、様々な要因、影響を受けながら、生活の欧米化の流れの中で大いに発展してきた。
アンパンの考案のような和洋折衷の巧みさは日本におけるパン食を今日、日本の食文化、食生活の中心にまで押し上げたといわれている。 確かに、昨今、街の中に製法や味わいに特徴のあるパン屋さんが続々出店、メデイアにも取り上げられ、少々辺鄙なところでも行列が出来るパン屋さんさえある。
ヨーロッパを旅して、ホテルでの朝食バイキングではパンの種類の多さはむろんのこと、周りに並べられた単品料理やデザート類、関連の飲み物類の多様さにわくわくさせられる。
米食のように主食と副食〈おかず〉という関係ではなく、パンは並べられた食品の一つで、むしろ御添えものの様にさえ思える。日本における主食である「米」の位置付けとは何か違うように感じる。しかし、西欧で、「パンのみにあらず」の様に生き方を示す程のキーワードになるくらい西欧人にとってはパンは食生活における概念として主食なのかなとも思う。
それにしても、近年の日本人の「米」離れは、グローバル化の潮流とともに、日本の農業を根底から壊死させてしまいそうです。食の自給率が40%を割る。もしもの時、日本人はどうして生きていくのか。最近こうしたニュースやドキュメンタリーがテレビ番組にも採り上げられている。
はなやかな欧米文化とともにパン食を享受してきた我々が、一方で、知らず知らずの間に、米食文化=日本文化という図式をはるかに超えて、経済至上主義、進歩礼賛風潮の流れの中で、色々な日本人の文化、美徳を失いつつあること、食文化の変化が日本の根底を揺さぶりつつあることを知らされる。
自身、朝食はパン食で、昼は、麺類やサイリュウム、米食など色々、夕食は米食、おやつなどにケーキ、菓子類と結構小麦を取り入れた多様な食生活を送っている。
日本の「米農家」を死滅させないために適正なコメ価格を政治的に守ることと併せて、日本におけるパン食と米食のバランスというか、食生活のあり様を、多くの日本人が、文化レベルとの関連において考えあわせ、日本文化の基盤でもある「米食」を、今後どのように考えていくのか、とても大切な時期に来ているのではないかと思う。
018. 東寺の弘法市
毎月21日は東寺の弘法市の日です。
10月21日は日曜日で天気もよく、散歩をかねて出かけました。
私宅からは徒歩15分くらいで北門に着きます。
秋の観光シーズンは弘法市を訪れる人が一段と多く、人出を当て込んで、最近では東寺の境内からはみ出た道路際にも、その日限りのお店構えで、色々なものを並べています。
弘法市は骨董品を扱う出店が多かったことで有名でしたが、今では、和服の古着、京都近郷の特産食品、フリーマーケットでも見られる手づくりの工芸作品、植木、縁日につきものの屋台など、何でもかんでも、てんこ盛りの賑わい市です。
雑然と並ぶ出店も大体は位置取りが決まっていて、何度も来ていると結構冷静に巡回できます。それでも、同じ店で先に「なかなか味のある品」と目をつけておいた物が、まだあったり、なかったりというのは、なんとなく、「心」コロコロの楽しさです。
また、一体何に使うものだろうかと、さっぱり得体の分からない骨董品に人間の生活の歴史を感じることも、同じ道具でも色々な造形の趣があって、思わず感動することもあります。弘法市、ブラブラ歩きの醍醐味です。
時々、買い手と売り手の値交渉のやり取りが、周りの人をどっと笑わせるのもご愛嬌でしょう。
今回は、たと紙に入った新品同様の銘仙の古着を買いました。またシャツに仕立て直してもらうつもりです。
それにいつも出ている韓国オムニのスルメキムチを買い、南門から出ましたが、門を出ても、まだ弘法市の熱気の中でした。
12月21日は今年最後の終い弘法です。毎年、年末のあわただしさと「市」の活気があいまって、日頃の東寺の静かな境内を知る者にとっては、別世界。のんびり、まこと品定めの楽しさなどは無理な人ごみと熱気。
同じ東寺での毎月第一日曜日の「がらくた市」は知る人ぞ知る、骨董市の風情の残る縁日です。生活の智慧やいろいろな想いが道具や家具、工芸品に歴史と文化の香りを載せて魅力的なかたちに展開され、無造作に並べられています。
今は、元の持ち主を離れて、次に心かよわせる人を待っているという空気感はなんとしよう。これもまた、以外に「ちょっと京都」の味かも知れません。
019. 慰めの楓
我が家から南側の通りをはさんで向かいの屋敷跡、ながらく駐車場になっている敷地の奥に大きな「楓の木」がある。
先週あたりから真っ赤に色づき、居ながらにして晩秋の気配を満喫しながらテイータイムなど過ごせるのは、ここに引っ越してきて以来の自然の恵みである。
一軒東隣のT家の80歳のおばあさんは、3ケ月の病院生活から戻られ、介護の必要な身になられたので、急きょ、浴室を改装することになり、身近な設計士として、そのお手伝いをすることになった。
数年前、配水管が壊れた時、業者を紹介した縁で、はじめて少し話す間柄になったのだが、おばあさんは、趣味で木彫をたしなんでおられ、その作品の見事さに感心したものである。今度の改装工事中は色々話しかける機会があったが、おばあさんにとっても寝室から見える紅葉の移ろいは、ふさぎ勝ちな気分を、ことのほか慰めてくれるとのこと。二人して窓から「楓の木」を眺め、とてもうれしい気分になった。
この「楓の木」は、冬には枝振りがそれなりの語りかけをしてくれるし、春の芽を吹く一瞬から、夏に向ってむくむくと翼が広がるように緑いっぱいに堂々とする様は、本当に感謝状を差し上げたい都会の中の宝である。
いつもは我が家でありがたい借景と喜んでいたが、おばあさんにとっても長年うれしい「大木」だったことを知って、ぐるりと見渡せば、きっと多くの隣人が、この木からやすらぎや慰めをもらっているのだと、おおいに気が付いて、本当に感謝である。
気丈に振舞って居られるけれど、すっかり抗がん剤で容貌が変わられたおばあさんが、なお、自然の美しさを共に語ろうとされるとき、なぜか胸迫るものを感じた。
改装工事後、数ケ月後、おばあさんは亡くなられた。おばさんの木彫された姿見鏡を形見のごとくいただいたが、事務所に掲げて、ちらり姿を見るたびに、あの語らいの一瞬が思い出される。心の中で、「楓の木」と命名しておばあさんと僕の感謝の想いを記憶にとどめようと思った。
020. 手編みのセータ
わが女房殿は編み物が達者である。子供や私のセータ、カーデイガン、ベスト、マフラー、帽子など数十点を、その時その季節に編んでくれた。勿論、愛用してきた。
いまや、孫のために次々と作品が出来ていく。
ほんの1年前の孫のセータも、もう小さくなって又せっせと楽しみを紡いでいる。
孫のものはサイズが小さいのであっという間に仕上げていく。近年私のセータは3年がかりでいまだ袖が出来ない。
多分、孫には手編みのセータを着ている可愛いさがあふれているのに、爺さんには着せ甲斐がないらしい。
先日、嫁が産後の養生に実家に帰っている間に、次男が孫の最新のアンゴラの手編みセータ、(ちょっと編みづらい苦労作)を、こともあろうに、他の洗濯物と一緒にばっさり掘り込んで洗ってしまったとのこと。すっかり縮んで、着られなくなったと、誠に申し訳なさそうに報告したとか。 女房殿の落胆振りは、はた目にも気の毒であったが、そこは達人の偉いところ、次の作品を編んでいる。
3日前に来た孫が、毛糸の玉を見て、「これ、セータにして」といった一言が俄然やる気を起こさせてしまったらしい。
手編みのセータはちょっと編み物の経験のある人には、すぐそれとわかるらしく、私がセータを着ていると大抵、「手編みですね」と声をかけられることが多い。そして、きちと正確な編み目や、ディテールの仕上がりにとても上手に出来ているとお褒めの言葉をいただく。「女房が編みました」と作り手を告げるのは、その労に感謝して、思わず出る一言。
ときには、デザインや色合いに私のアイデアを入れてもらうこともあるので、既製品にない思い入れがあって、二十数年、愛用のものも多々ある。うっかり、「ちょっとここが」と云おうものなら、アッという間にほどかれてしまって、カーデイガンが一着消えてなくなる。
編み物を見ていると大変な手作業の繰り返しで、そんなに簡単に毛糸の玉に戻すなど思いもよらないが、手編みの達人にとっては、文句を言われた作品が、そのまま形に残るのが許せないらしい。二、三度そんなことがあってからは、めったなことは言わず、ありがたくマイシーズン愛用することにしている。
私や息子のものから孫のものまで、温もり一杯の手編みセータ、チョッキなどに包まれて、家族、皆がうれしい日々は、色々なスナップ写真に残されている。いつの頃からは、出来上がる度に記念写真を撮って、思い出の作品集と称してアルバムに残すようにしているが、孫の来ていたセータなど、ママ友の幼児に払い下げられて、行方知れずのセータもある。一目一目に思いのこもる手編みの心が何処かを巡るのも楽しからずやである。
廣瀬 滋著