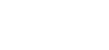031. 検査疲れに負けるな
先日、「老いの発見」の出来事のあと、頭のCT検査は問題がなかったが、突然倒れるのは糖尿病のこともありますから、日を改めてきちんと検査を受けられてはどうですかと言うことで、検査日を予約することになった。
久々に検査前日午後の10時以降は飲食をせず、神妙な気分で検査日の朝を迎えた。血糖値を調べる検査は、何しろ退屈な検査である。2時間後に、病院を出て秋晴れの街に開放されたとき、60歳をすぎれば人間ドックなど検査は受けず、成り行きのまま寿命をまっとうしようと考えていた自分が、何でこんなことをしてるのか、「ええかげんなやっちゃな」と自分を笑った。
1週間後、結果と診断の予約日。担当の女医さんは、ちょっと数値が高いです。インスリンはでていますが、機能が落ちている。今すぐ薬を飲む必要はないと思いますが、食事内容に気をつけてください。それに、肝機能が弱っているようです。腹部のエコー検査、CT検査を受けてみてください。そこで又検査の予約。
それに、眼科でも糖尿の影響が出ていないか検査してもらってはどうですか。眼科は以前に行ったことがある眼科専門病院に行きたいというと、紹介状を書きましょうとの事。
続いて、栄養指導士から日々の食事について色々と指導を受ける。どうも、毎食、繊維質をとることがすい臓などに負担をかけず良いというのがポイントで、ヒヤリングでは私の昼食、朝食に繊維質の摂取が少ないとの事。又、間食は厳禁との事。
3日後、またまた前日から飲食を控えて、腹部エコー検査とCT撮影を受ける。とにかく検査だけのため、病院側の流れに乗って身をゆだねるだけのこと。翌日は、眼科専門病院へ行く。これが又、すごい患者さんだらけ。大はやり。視力検査の後、瞳孔を開いて検査するとの事で、麻酔薬のようなものを時間を置いて点眼。初めて受ける眼科の本格的な検査にちょっとビビリ気味の我を知る。「糖尿の影響は何もありません。ちょっと白内障のケがでています。」「今、どうこうはないので、半年後に来て見て下さい。」看護婦さんが、「今日はどうしてこられました。」と聞く。「自転車できました。」「瞳孔が開いて眩しいですから、気をつけて帰ってください。」 病院の外に出ると、ほんと、眩しくて、周りがハレーションを起こして帰り道が白い。ここ2週間ばかりの検査で、久々に自分の体の状態に向き合ったが、何か疲れたなぁ「やれやれ、それでもまだ寝たきりにならなくて良しとするか。」老いの発見、老いの検証。人生、最後まで気合をいれて元気でいこうと思った。
032. 「瞑想するマネキン」
京都駅から家路に向かう時、伊勢丹のショウウインドウをふと見ると,なんと目を閉じてはるか彼方を見ているマネキンが初春のファッションを身にまとい、ぽっねんと並んでいる。見なれた目に表情を込めたマネキンがおおきなガラス越しに、こちらをながめているのではない。
かって,ブテイックを設計した時,このマネキンに服を着せると売れる確立が高いというのがあって,マネキンの展示会などもオーナと真剣に見に行く機会があったが、それは、殆ど顔立ち、目などに表情があって、しかもポーズにいろいろと工夫がされていた。
最近はマネキンの展示会に行くこともなかったので情報不足で「何を今ごろ言ってるの」と言われるかもしれないが、「め」を伏せ、瞑想するようなマネキンが、ぽっねんと静かに、しかも華やかなファッションを身に纏い立ちつくす様を見た瞬間、現代人の孤独感が実に良く表現されていると思った。
街を行く人々に漂うものを、このガラスケースの中に閉じこめ、共感と連帯を求め、訴えたのだ。この正直なアピールは消費に結びつくものになるのか興味があるが、感性マーケティングなどといわれるものの一つなのかとも思う。
情報化社会と言われて久しいが、個人が携帯電話やインターネット等によって現実に情報のネットワークに包まれると、殊更に一人一人が孤独であることがあぶりだされてしまったのだ。
何となく気付かずに気軽にやりすごしたかった人間の存在根源の重さを、多くの人々が感じざるを得ない現代こそ、その奥深い不安に打ち勝てる生命力を持たねばならないと『天』は迫っているのだろうか。
今日よく云われる「癒しの時」と言うのは、迫り来る人類の根源的変貌を予感して猶予を願う時なのかも知れない。住宅設計においても、個人の、家族の孤独のあり様が考えられなければならなくなるのではないか。
シェルターとしての機能性は留保されるとしても、日々の家事の利便性は優先されるとしても、個々の孤独に打ち勝つための生命力を磨く道場として、より消極的に捕えるとしても、癒しの『場』としての住空間のあり方がもっと重要視されるべきではないか。
住まい手とのコラボレーションを通じて共に考えていきたいことであり、過去の空間設計のディテールが具体的にどの程度有効なのかも探らなければならない。
IT革命と云われる今こそ、人類ドラマの渦の中心に在って変わらぬものを見据ヘ、瞑想するマネキンを意識していたい。
033. 「夢」
夢というのは、なかなかに深く面白みを含む言葉である。
将来の「夢」というときの「夢」は将来、何になりたいとか、自ら目指す目標に到達したいとか、意識上での願望でもある。
「夢」のない人生などというと、とても悲しく哀れですらある。
「夢」を持つことは努力してその夢に向うエネルギーを自らにうながし、日々の活動に目的意識が生まれ、生活を活性化することにもつながる。
しかし、「夢」の大きさ、実現度によっては、夢破れ、挫折感を味わうということもあり、時には一瞬の「夢」に終わることすらある。
その点、無意識中というのか睡眠時に見る夢は、実にリアルな日々の出来事をビデオを見るがごとく見ることもあれば、荒唐無稽、はっと目覚めて思わず笑ってしまう「夢」や、なかなかに恐ろしい夢や、とても幸せ感に浸れる夢など色々である。
正夢、白日夢、逆夢、夢騒がし、夢の夢など多くの人が、実に色々な夢を見ていることだろう。
夢の中では、亡くなった両親とも会えることがあるし、大学生の頃、トリュフォー監督の「突然炎のごとく」という映画を見たことがあったが、後日、主演のジャンヌ・モローと僕が小船に乗って夜の川を流れ行くシーンは「夢」とはいえ、いまだ思い出す印象深い夢である。
せめて、夢の中ででも、想いを寄せるマドンナと語り合う夢を見たいものだと思うのに、まったく夢にも現れず、ため息で目覚める青春の日々。本当に「夢」はゆめだからこそ、空想の世界に残り香のごとく楽しさを漂わせる。
いずれの夢にしても、夢を持つこと、追うことは、明日を生きる指標を意識することであり、その実現までは、たとえよこしまな欲望と紙一重でも、どこか許される美しさを感じさせるのは不思議である。
この世の現実に「夢」を追うことも、人にとっては空想のごとき人生のはかなさを感じるがゆえであろうか。
「夢」は深く透明感のある言葉であると思う。
034. からだのリセット(断食)
先日、「病気がイヤなら油を変えなさい」の著者、杏林予防医学研究所の山田豊文氏の講演を聞く機会があった。
マーガリンはプラスチックです。牛乳を飲んでいると骨代謝のバランスをかえって損ね、アタマの切れる子になったり、色々な病気のもとになる。
最近の無差別殺人事件も、社会環境などよりも戦後からの食生活の間違いが脳に悪影響を及ぼして人を殺したいという衝動をおさえられないからです。
メタボリックシンドローム、アトピーなど昔は日本で余り問題にならなかった健康障害がなぜ出てきたか。
分子生物学を研究されてきた立場からの説得力のある話に会場は静まり返っていた。
チーズや乳製品を摂取すれば、立派なからだになると思っていた人は、私だけではないだろうが、ことごとくそれが誤っていることを、研究データを示しながら話されてみると、戦後の食の欧米化を今更ながら真剣に振り返って見る必要がある。
今の医学は、崖っぷちに立たされた人が落ちないようにするのではなく、落ちてくるのを待ってあれこれいじくっている。
医療行政の仕組みもおかしい。ぽんぽんと威勢良く講演ははじける。
人間を構成している60兆個の細胞が元気になることを考えるのが基本である。
その細胞に直接関与するのが油(脂質)ということで、良い脂肪酸をとること、骨代謝が正常であること、骨の健康が長寿のカギということで、カルシュムの脱灰の仕組みを知ることの大切さ、生の食材から食物酵素を補給すること、肝機能を高め有害物質を解毒すること、腸をきれいにすることを力説された。
自動車を車検に出すことはごく当たり前に行なわれている。どうして人間のからだをリセットしないのか。断食という手法。研究の結果、必要な養分をとりながらの断食法は有名なプロ野球選手や芸能人などが山田氏に師事、健康的にその成果を挙げているという。
リセット。人は、日々のストレスから開放されるために色々な工夫を行なっているが、自分の体をリセットすることが「断食」ということでもあることに意外と気付いていないのではないか。リセットはある意味ポジテイブな生き方でもあるとの説である。
断食というと3日、7日、21日と期間もあるそうだが、ちょっと覚悟もいるかと思いながら、挑戦、いや、リセットをしてみたいと思った。
しかし、結果的に断食に必要な栄養分と言う高価な液体を販売するセールストークにつながっていたので、食生活の健康に影響大なることやリセットの意味合いは理解しながらも、どうせ人間は死ぬ。寿命は定めという諦観も持ち合わせる身には、その液体をその場で買い求める仲間にはなれなかった。
035. 困った隣人
いっぱいゴミガラクタを溜め込んでゴミ屋敷になって近隣住民を困らせたり、野良ネコや犬などに無分別にエサをやり、結果として悪臭や騒音、環境汚染などで近隣住民に迷惑をかけても一向に意に介さない人がいることが度々テレビ番組でも取り上げられているが、国家レベルでの困った隣人と呼べるのが北朝鮮である。
話し合い(6カ国協議)にものらりくらりとその場を交わし、都合が悪くなればだんまりを決め込む。そして開き直って隣人を威嚇する。 全ての朝鮮人の品性がこれほどひどいと思いたくないが、今の指導者や支配階級の自得一辺倒の生き様は本当に反吐が出そうである。
中国やロシアも国連の理事会では決まって北朝鮮の肩を持ち、何が国益なのか良くわからないが、貧相な国民性を世界にさらしている。歴史上、中国支配民族・権力者のすさまじい強欲地獄を反面として、孔子や孟子などの賢人が出たのかとさえ思わせる。
近年の地財権に関する対処にしても、一般庶民を無視した都市開発にしても、一党独裁の政治システムだけでは語れない中国人権力者のバランスを欠いた中華思想が大いに影響していると思われる。困った隣人が持ち合わせている性格、品性である。
見渡せば、アフリカでも中東でも困った隣人同士が果てしない強欲の突っ張りあいをしている。
この性格、焼きなおさなければ直らないなどと言うが、人間とはそもそも困った存在なのだろうか。こうした混乱の世界情勢の中で、元来、日本人は比較してみれば結構バランス感覚に優れた民族であり、助け合い「結」の精神性などが、社会システムとしても暗黙裡に機能する姿は、震災復興活動などにも垣間見えて、世界から注目されている。
東洋の島国、日本は今まで情報発信力が弱いというか、自己主張をあまり得意としない国柄であったため、商人道に於ける「三方よし」のような精神が生活の根底にあることがあまり世界に知られていなかったのではないか。困った隣人には皆が和やかに生きられることこそ幸せな社会であることを、理屈抜きで承知してほしい。
昨今、中国でも共産主義の破たん傾向から仏教信者が3億人にも達するという。前を向いて生きようなどと、自身、叱咤激励しているが、困った隣人、北朝鮮の核実験、ミサイル発射のニュースは人間存在に疑問を抱かせて怖いものがある。
036. 生活美人について
いろいろな人間活動、その「道」のプロフェッショナル、達人はよく知られています。
しかし、身近な日々の生活の中で自分の生活を活性化できる感性と才覚を持つている人。日常性と非日常性の自分なりのバランス感覚を持っている人。
生活の中で、快適、美しい、落ち着く、便利など生活を左右する感性を空間(環境、現実の住居などを含めて)、もの(家具や道具など)、システム(手順、作法、所作なども含めて)として演出、表現、展開できる人。別な言い方をすれば、生活シナリオを想い描き(ストーリ化)、その実現・演出のために必要なものや手段を工夫、考案できる人。そのような人のことを私は「生活美人」と名付けています。
生活美人と「片付けの上手な人」、「お掃除の上手な人」、「お料理の上手な人」など家事の達人とは異なります。
生活美人はある意味、生活シーンの多様な状況の中から新しい発見、気付きに鋭敏で、その時々の最適な方向性や問題解決にバランスの取れた才覚を発揮できる生活ジェネラリストといえます。その道の業師としてのプロと言うのではなく、老若男女、誰でも生活美人になれ、かつ生涯生活美人としての資質を磨き続けることが求められます。生活美人にはゴールはありません。人間国宝とか、技能士といった資格検定もありません。
しかし、生活美人として生きるという自覚を持つことが出来れば、そこからいろいろな展開に可能性が生まれるでしょう。
自分の日々の生活、行動の中に、絶えず新鮮な感性情報を取り込み、又確認する習性をつけることから、新しい生活スタイルをイメージする、生活のシナリオ化を試みることを楽しみましょう。
体験的に、生活美人への道は、家庭生活においても、職場や学校生活においても、その場、その時の場景や事象の中に何かを気付き、新しい問題意識を持ち、その解決に向けて知恵、アイデアを創出することを心掛けることに見出せると思います。このプロセスは、プロデユーサやデザイナーの研修、職能体験に近いものがあると感じています。
あなたの中に生活美人としての資質、感性、才覚がどれだけ隠れていますか。
気付いていない、意識していなかった、あなたの生活美人度を覚醒しましょう。
おしゃれに生きる力が実感できるようになり、幸せ感が身近にイメージできるようになると思います。
037. 「仏教の来た道」展を見て
自宅のすぐ傍、西本願寺の前に龍谷ミュージアムがある。
まだ開設されて2年にもならないのだが、展示会が不定期なため開館しているときが読めず、散歩がてらにのぞいて見ようと思って行くと、何も催しの無い時だったりして、気になる施設でありながら外から眺めるだけであった。
4月の終わりから、特別展「仏教の来た道」が開催されていて、これは見逃せないと思いつつ、6月になって仕事の気分転換を兼ねて昼下がり出かけてみた。
20世紀初頭に西本願寺代22世門主、大谷光瑞師によって組織された「大谷探検隊」のもたらした資料を中心にシルクロードにおける様々な民族・言語・文化の交流の有様を多角的に紹介している展示会である。
仏教の源流を感じさせてくれるガンダーラの仏立像等の石像や仏伝浮彫にあらわされたその教えや説話の数々は、なぜか心を吸い取られるようで心地よかった。
又、西域の仏教文化と多様な宗教の関係も丁寧に解説展示されていて、ゾロアスター教やマニ教など日頃区別もつかない無知な世界にいる自分だが、とにかく、人類が何か心頼りに「命」のありかを求めて、祈りの気持ちをかくも美しい仏像や壁画に表すエネルギーを持ち合わせていたという歴史に感激した。
インドで誕生した仏教がガンダーラ、西域を経て中国へ、そして日本にまで伝播してきた人類の血の流れのようなものが見て取れて大谷探検隊の活動の意味が、今のこの時代にこそ、その価値を輝やかさせていると思えた。
ウイグル語の経典など、なんとも読むことすら出来ないが、一生懸命書き写された様子はひしひしと伝わる。
仏教の経典にも阿含経、般若経、妙法蓮華狂、維摩経,無量寿経、阿弥陀経、金光明経などいろいろあって,その特徴的な教えがシンプルに書かれた解説もいっぺんに賢者になれるような気にさせてくれる。
音声ガイドを聞きながらとても充実した時間が過ごせた。
NHKと龍谷大学共同のCGによるペゼクリク石窟の再現映像もとてもすばらしかった。
038. 新年散歩
正月3日、運動不足を解消と女房と二人で散歩。
年の暮れに人から「神様は怠け者、いつも寝ていることが多いので、余りいろいろ頼んでも、ご利益をかなえてもらえることはない。」と聞かされた。
本人の努力や研鑽がなくて、神頼みなんて言うのはそりゃ無理なことだろうと思うが、ズバリ言われると新年の初参りも、込み合う神社へ出向く気が薄くなる。
近場の東寺界隈にでもとブラリ。東寺へはガラクタ市や21日の弘法さんなど比較的散歩がてらに出かける定番コースでもある。いつものように北門から境内に入ると石畳みの道。弘法さんの日にはこのあたりも出店でいっぱいの通り道であるが、さすが正月3日。ほとんど人通りもない。
やや行くと掘割があるが、橋の脇すぐ、堀の中、いつもは亀が甲羅干しなどしているわずかな平場を持った石台の上に、なんと「サギ」が1羽身じろぎもせず佇んでいる。冬の風に胸元の長い毛のみがそよいでいる。「珍しい。鷺や」「ゴイサギとは違うな」となんとなく高揚した気分で私が言うと、女房はすかさず「あんた、お正月から詐欺に会うてどうしますね。はよ通り過ぎんと」と腕を引っ張る。ああ、なるほど、サギと「詐欺」ね。女房はいつもこうしたことに頭が回るので、「吉本興業に就職したらよかったのに」と冷やかしながら境内の奥に行く。
いつもの様に弘法さんにお参りして、南門を出ると、通りの向かいにまっすぐ南に向かう道があるのに気が付いた。きっと昔は南門に向かっている何か由緒ある道かも知れないと初めてその道を南下することにした。京都に住んでいても、この辺りは初めてくる。
二人で街並みのどこか京都らしくない、密度のないことをあれこれ評しながら10条通りまで下る。城南宮まで行ってみるかと東に向かうが、結構、寒風が厳しく、油小路通りでは阿吽の呼吸で北に向かう。この通りも拡張工事が長い間続いたが数年前、大阪方面への連携道路として完成、今や幹線道路の感がある。
こうした街並みの切り口には京都らしさよりも今の文明がいたるところに顔を見せているので、こうして散歩する視線には煩雑すぎて疲れる。ほんのわずかな距離ではあるが、自宅の近辺を歩いてみると、あらためて今の京都の歴史・文化と現代の文明との混在を知らされる。ヨーロッパの都市計画と日本の街並み計画の出発点、焦点のあてどころの違いを感じざるを得ない散歩でもあった。
039. 究極のコモンセンス
辞書にはCommonsense(コモンセンス)とは常識的な、常識でわかる、明白ななどの意味づけがされているが、元々、Commonには普通の、共同の、公衆の、などの意味があり、Senseには感覚、観念、思慮、意味、多数の意見などの意味合いが込められている。日本語の「常識」には、普通一般人の有す、又有すべき標準知力。専門知識でない一般知識と共に、理解力、判断力、思慮分別を含むとある。
何が一般的なのか、世間の常識に照らし合わせて如何なる言動を振舞うか、日々の生活の中で人々は刻々とコモンセンスという規範袋の中から生活観念、判断指標などを選択しながら生活を営んでいる。常識を超えた判断力が時と場合によって色々な窮地を救うこともあれば、常識に従ったお蔭で災難から逃れることもある。
つまり、一般に、生活シナリオは、いわゆるコモンセンスを基軸に成り立っているのだが、それぞれ個人が自分なりの生活シナリオを描こうとすれば、ストーリの展開される場所(空間)や、時、意味合いなどによって異なった表現、演出を巧みに選別しながら行動をしなければならない。
異なったストーリ展開、演出であればこそ個性が感じられ、人々は自らも、又、他人にもその存在を確認させることが出来るからである。
しかし、ここで大切なことは、よく言う「相手の立場に立つ」などコミュニケーションの原則のように、自らのシナリオが相手に理解されることが必要になるので、コモンセンスの許容範囲、容量を如何に捕らえておくかという問題が生じる。
究極のコモンセンスとはまさにこうした変幻自在の状況変化の中で、如何にバランスを取りながら、自らの感性、才覚を発揮させうるかという極意の「もと」のようなものである。究極のエゴイストとして生きるなどと、わけなく粋がっていた若い頃の自分の思考回路と、どこか似通っているように思える。
わかった様な分からぬ「究極」という見解であるが、ある意味、決め付けてとらわれた感覚、思慮、意味などをもたず、自由に生活シナリオを展開するという心意気を持って、かつ、天下に、人々に迷惑をかけない、どこか「美」という価値尺度を掲げた道理、それを究極のコモンセンスと呼んでみたいと考える。 共感が得られるか定かでなないが。
040. 理想への狂気
世界の至るところでの争いはその根底に人間の理想や夢に対するあこがれ、あるいは願望への執着がもたらす狂気ではないか。
日本における終戦記念日8月15日前後には、いろいろな報道特集やテレビ番組で、日本が第2次世界大戦に突入、特攻隊、最後は原爆投下に至る敗戦のあらゆる局面を改めて知らされる機会が多いが、その背景には「大東亜共栄圏」を築くという願望・命題がいつの間にか多くの国民を巻き込み、学徒出陣をした若き精鋭たちにも戦争という現実の暴挙を、壮大な国家命題に志向する、理想への参画という幻影に重ねて、狂気への麻痺を受容したと思える。
今、ヨーロッパ共同体(EU)も積年のドイツ、フランスの戦闘をはじめとする戦乱の歴史を清算して、共存共栄の欧州圏を築こうとする理想、願望が発端である。
その提唱が「大東亜共栄圏」のように日本一国ではなく、複数国家の協議、外交力によって進められたこと、多分に第2次世界大戦の教訓も含めて狂気に至ることなく進行しているが、個々の国がひとたびその願望や理想の方向に独自の利得を抱けば、たちまち狂気が頭をもたげ、理想そのものの崩壊につながる危険をはらんでいることも先のギリシャやスペインの経済破たん問題の処世に感じ取れる。
また、「アラブの春」以来、イスラム教と政治とのかかわりもそれぞれの集団や民族がいかに自分たちの理想や願望に忠実であろうとするか、狂気の戦いである。
聖戦という発想は「狂気」以外の何物でもないと思える。
もし人々が、日々の生活を穏やかに過ごすこと、お互いが思いやり助け合って暮らすこと、現実のあり様を基本として大切に生きることをモットーとするなら、至るところの紛争はかくも過激になることはないであろう。
しかし、人間は夢や理想を持つこと、創造的に環境を生きる特性を持ち合わせ、そのことが生み出すいろいろな利得をも享受してきた。「少年よ大志を抱け」をはじめ、人は成長の過程で絶えず理想や夢を持って生きることを教育され、確かに日々の生活はその価値観によって緊張を保ち、進歩、達成感によって活動のエネルギーは代謝しているといえる。
宗教と科学の究極の対決もまた、それぞれの理想の極みへの狂気の思い入れであり、過去には宗教裁判などで多くの血を流しているという史実がある。
つまり、人間にとって理想や夢を抱くことは大いに活動の原動力になるが、その理想や夢が独善的、独りよがりのものとなり、その達成のためにはいかなる犠牲も払うという狂気に達した時、その理想は意義を失った無意味なものとなり、破壊と、混乱、滅亡を現実化させる。狂気の熱情。そして究極のコモンセンス。岐路に立った時、いかに生きるか。終戦記念日のころはことさらこのことが気になって重い。
廣瀬 滋著