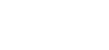061. 教会の献堂式
昨年来、設計監理をしてきた教会が2月に完成し、4月3日に献堂式が行われた。
東日本大震災のため、献堂式も延期するかどうか牧師さんも色々考えられたが予定どうり各地から関係者の方も参加され厳粛に行われた。
最初に被災者の方への黙祷からはじまり、賛美、聖書朗読、祈祷、経過報告、賛美、献堂の辞、説教、祈祷と式典は進み、建築関係者への感謝状贈呈が行われた。
私も設計監理者として感謝状をいただき、お祝いと謝辞を述べた。
関係者の祝辞、祝電披露、賛美、感謝祈祷、頌栄、祝祷、牧師挨拶と無事式典は終了。
賛美歌が会堂に良く響きわたり、教会らしさを感じさせることが出来たのは当初から気にかけていたのでほっとするところであった。
式典の後、教会メンバー手作りのケーキやお料理でのパーテイがあり、参加された皆さんが思い思いに建物の中を見学された。
今回、設計に当たって教会関係者からの要望、設計条件を集約すると、そのイメージ、空間構成は長年携わってきた住まいづくりと結構近いことを私は直感した。つまり、祈りの場であると同時に、人々が集い、共に愛を育み、神に感謝、無条件に愛されていることの実感できる場、それは基本的に家族の住まいが目指すものをも含むものであることを。
敷地や法規的制約の中で色々多様な使用条件をまとめると、外観はそれほどシンボリックな形態にはならなかったのだが、信者の方が、「いろいろ教会を見てきたが、この教会は新しい形ですね。」といわれた。
よく聞くと、メインの礼拝堂以外に、皆でお料理を作って色々コミュニケーションを取れるダイニング・リビングもあり、宿泊室、祈祷室、シャワー室、母子室、事務室、パントリー、多目的に使えるロビーなど、とにかく便利に、閉鎖的でなく連続した動線で空間が繋がっているのに感心しましたとのこと。
まさに私の思い通り、信者の皆さんの共有する住まい感覚にまとめられたことを評価してくださったとうれしく思った。
信者の方が、教会で時を過ごしていると、「ついつい時間を忘れ家に帰りたくないのです。」と言われたのは本当にこの計画に参加してよかったと心温かくなった。
無事、献堂式も終え、これからこの拠点から、信者の方の色々な活動が豊かに確かに発展していくことを祈りたい。個人の住宅設計のとき以上に、自分がお役に立ったのかなという思いがして、ほっとする気分を久々に味わった。
062. 人それぞれの「昔」
先日5歳の孫が「昔はエビフライが好きやったけど、今は嫌い」とさらりと言って、おばあちゃんの折角作った食事に好き嫌い。
たった5年しか生きていないのに「何が昔やねん。」と思わず胸の内で叫んでしまった。
そういえば、結構2,3才の頃、遊んでいたこと、出かけた思い出などを昔という表現で話すことがあるなと気付いた。
10年一昔などとも言うが、人にはその時々の流れや出来事の思い出が、昔という何ともあいまいな一塊になって不意に、ふっと蘇ってくるのだろうか。
小さな子供でも、「日本昔ばなし」ではないが、知らないうちに絵本やお話を聞かされたりする中で、昔という意味合いが理解されているのだろうか。
「昔は良かった。」「昔は苦労したもんだ。」等と今と比べて異なる感慨に触れる時、日常的に個人的に「昔は、、、」なんて口走っているのだが、世の中には歴史というより人それぞれの「昔」がいっぱいあって、小説やドラマの中でも自分の知らない昔、共感できる昔など、様々な昔が渦巻いていて、単に史実というよりも、やっぱり「昔」と受け止めたい喜怒哀楽を含めた一瞬間に、笑いや涙を誘うのである。
昔の自分と言うセリフの中には、自身で成長したというか、今まで気付かなかったものに感動したり、初めての行動をとれるようになったという実感への感慨もあるだろう。
勿論、まわりの環境や社会の変化につれて、知らず知らずのうちに以前とは異なる状況体験することになった、その移り変わり、蓄積がふっと感じられるとき、「昔はな」と思わずつぶやきたくなるのかも知れない。
二十世紀以来、十年ひと昔と言われるくらい、時代の変化は激しいが、一人の人間の寿命というスパンから思えば1000年の歴史などというより、今は昔という概念は、すこぶる身近な尺度として温かいものなのかもしれないと思う。
そう思えば、5歳の孫の「昔」もうなずけるのだ。
063. 私の英会話つれづれ
今や世の中のグローバル化の流れの中で、英語が話せると言うことは必須のようで、企業でも社内の会話を英語で行うところも出ている。
我々の世代でも、どこかにこれからは外国語の一つや二つは話せないといけないという潜在意識があって、大学時代は英国からの留学生に英会話を習ったり、社会人になってからも何度か学習教材を買い込んで英会話にチャレンジ。
時にはマドモァゼルと話してみたいと欲深くフランス語スクールに通ったこともあった。
しかし、日常仕事で英語を使う環境でもなく、海外旅行でささやかな日常会話を使う程度では結局継続性もなく、上達したと言う実感もないまま年老いてしまった。
TVの英会話教材のコマーシャルを見ていて「何とか英会話がマスターしたかったなぁ」とつぶやくと、「死んでからあの世で幽霊になってアメリカ留学したら」と女房がぴしゃりと助言。
数十万円の語学教材を買い込んでは、ほったらかしの前科者には返す言葉もない一言ではあるが、心の奥底にあるこちらの無念さを、ぐさりと掘り起こす一言でもある。
長男を2年間アメリカに留学させたのも自分の気休めの一つだったのかもと述懐する始末。伯父の会社のアメリカ駐在員にならないかと言う話も、若気の至りで「帝国主義の国には行きたくない」と蹴ってしまった事も、振り返れば英語には縁がなかったのかと、自らを慰めても見る。
翻訳ソフトや小型の会話機が、いずれ個人レベルで購入できると言うニュースにも期待したこともある。何が何でもと言う必要性がないところでの自分の努力不足の思い違いを一事が万事垂れ流してきたのではないかと反省もする。
本当にあの世で流暢に世界中の人々と楽しく語り合えるなら、あの世も大いに期待感を抱かせるぜ。
最後は小学校から英会話を学ぶ孫が国際人になってくれればいいなぁと思いつつ、これからの日本の若者にグローバル化の流れの中でも、逞しく生き抜けるよう、外国語会話熟達へのエールを送りたいと言う達観の極みをよそおいつつ、[Nice meet you.]などいくつかの日常会話のフレーズを呟いてみるのである。
064. 変化・変貌
先日久しぶりに東京・新橋駅に降り立った。
駅前広場には蒸気機関車が据えられテーマパークの一角のような賑わいである。霞ケ関の方に向けて歩き出してまもなく、同行のK氏が「あれが、かの超高層ですよ」と話しかけられた。一瞬どこにも超高層ビルなど見当たらないと思った瞬間、よみがえった。40年前、日本で始めての超高層ビル36階建て霞ヶ関ビルを見学したことを。
いまや、周りのビル群に溶け込んで、およそ超高層建築の風情は感じられない。子供時代に訪れた場所や見たものが、大人になって訪ねて見れば、「なんだ、こんなに小さかったかな」と驚くに似た気持ちが流れ、急に街並みが気になった。
振り返れば、東京に住んだ昭和40年から6年間は、東京のエネルギシュな発展振りを身をもって受け止め、20代の青春と歩調をあわせ実に思い出深いものであった。
京都に帰ってからも何度も仕事や所用で東京に出かけ、その度に新しい都市環境があわただしく蓄積と変貌、変化・展開する様を知った。
しかし、とりわけ住み慣れた渋谷や仲間とうろついた新宿界隈の変化・変貌は、飲食や遊び、買い物といった生活レベルでの体験とつながりがあって、別段違和感はなく、むしろ変化の様を知っている余裕があった。
やがて、地下鉄網が複雑に発展して、乗り継ぎなどに戸惑どったり、あるべき街角の喫茶店が見つからなかった頃、もはや自分はこの都市から異郷人になったと思ったが、それは日本経済の発展のなせるところという認識で受け止めていた。
今、かっての超高層ビルの光り輝くデビューを知る自分が、この都市に埋没したビルと共に佇む光景は、どこか遠い夢の世界のような感じがする。40年の歳月の流れが一瞬に静止。
首都、東京のダイナミックな変化・変貌の事実を背景に、さして変わらぬ一点の自分が影を共にしている昼下がりは不思議なものだ。
何かが違う。変化・変貌を連続して感じてきたという安心感というのか、共有感が無く、東京は日本人としての連帯感を抱かせることの無い都市になったと思った。
国会議事堂周辺はテロ対策の警備が敷かれ、よそよそしい空気は、戦後の日本の変化・変貌を心なしか寂しいものにしている。東京はもとより、日本中、1000兆円の借金をしてまでこれほどの変化・変貌をしなければならなかったのか、政治の根本姿勢も気になるところである。
065. 東本願寺御影堂改修工事を見て
私の住まいは東西本願寺門前町のすぐ近くにある。先日、東本願寺御影堂の屋根瓦葺き替え工事現場を見学した。
概ね、社寺の屋根瓦の葺き替えは100年に一度、構造体の修復を含めた改修工事は300年に一度おこなわれる。明治時代に再建された東本願寺御影堂は100年目の工事。
現在近くで10年がかりで行われている西本願寺の改修工事は300年に一度のものである。一生のうちに100年に一度、300年に一度といった改修工事現場に同時に出会うのもラッキーなことである。
日本の建築の様式の大きな流れが400年くらいのスパンで変化しているといわれているが、1600年代(江戸時代)頃に建立、再建された社寺・仏閣群が、また西欧の影響を受けた近代日本・明治時代の建築群が今、改修の時期を迎えている。改修工事で技術的なすばらしい工夫や、当時の人々が大切にしていた文化の匂いが立ち返ってくるのに接することが出来るのはうれしく、幸せを感じることである。
東本願寺は明治の近代建築技術を取り入れ再建されているため、屋根の荷重を減らす工夫が色々されていたので、瓦を取り除いた時、西本願寺などの事例から多分30~40センチくらいは木組の復元があるのではという想定を覆し、わずか10センチくらいしか高さが変化しなかったという。
明治の土木技術を駆使、自然の高低差を利用した琵琶湖疎水から引かれた水を利用して火災時の消火に備えたスプリンクラー様の消火栓が屋根に設置されているなどは驚きである。
今回の東本願寺改修工事では、従来の土を使用した土居葺きをやめ、桟葺きに変更して屋根荷重を減らし地震に備えるという。今回発見された烏丸通りから巨大な木組みの斜路を作り、直径2メートルもあるかという梁・丸太材を30メートルを超える高さまで人力で引き上げている当時の建設工事現場の写真は、かのピラミッドの建築想像図を思い起こさせる。
引き綱には全国から寄進された信者の女性の髪の毛を編んだ綱が使われ、その一部は今も記念展示されている。今の巨大クレーンが軽々と資材を操り建設する現場とはかけ離れ凄いものを感じさせる。
人力、智恵の結集が巨大な構築物を作り上げる時空は、多くの人々を感動の世界に導いたと思う。先年、この改修工事に備えて小屋裏を見学する機会にも恵まれたが、巨木が縦横に組まれた大空間に言葉に言い尽くせない圧倒的な「力」を感じたのはこうした血と汗のプロセスが埋め込まれていたせいなのだと改めて感心した。
066. 東海道五十三次「関宿」を訪ねて
幸いなことに大変気持ちの良い快晴日。住まいやインテリア、生活に興味のある私的な倶楽部活動を続けて13年目になる仲間と東海道五十三次の内の「関宿」を散策した。
京都から草津へ、草津で乗り換え柘植、さらに関西線に乗り換えて関に着く。京都に住んでいると、三重県といえば南の方角にあると感じているので、まず、滋賀県・草津に(北の方角)に向うことからしてすでに方向感覚が乱されるうえ、初めて訪ねる関は到着するまで、自分の中でこれと定めるもののない不思議な土地と感じていた。
一見して宿場町という街並みに接して、安心感と同時に、観光客に早代わりの自分を知る。
過って、奈良井宿や妻籠など宿場町を観光したことはあるが、関はお伊勢さん参りの人達や参勤交代で賑った交通要衝の地で「鈴鹿関」が置かれていたところと聞くと、いっぺんに親しみがわいてくる。
東西1,8kmに及ぶ町並みの保存は昭和59年、国の重要伝統的建築物群保存地区に選定されている。環境問題が話題の最近こそ、町屋保存などを初め、町並みの保存はあちらこちらで叫ばれるが、すでに手遅れのところも多い中、関の住民の意識の確かさに感心する。本陣跡や、旅籠、町屋、山車倉など建築と当時の生活空間をほどよく見学できるのはうれしい。関の特産火縄屋さんがあったのを知って、こんな商売も昔はあったのだと遠い時間を感じた。
皆で休息した茶房も昔は薬屋さんで、茶房は奥の座敷などを利用してしつらえてあるが、表の間には、色々な骨董と言うか、昭和初期から戦後しばらくの間に使われていた道具などが所狭しと陳列されている。京都にもこうしたところは多々あるが、やっぱりちょっと鄙びているところが宿場町らしい。
往時、旅姿の老若男女がにぎやかに行き来していたこの街、看板のひらがなで書かれた面は京都方面を、漢字で書かれた面は江戸に向う方角を示しているなんぞは、なかなかのアイデアであろう。今、観光としてみると実にほのぼのと楽しい街並みである。
みやげに和菓子「関の戸」と伊勢茶を買った。
時々こうした昔の町なみを散策すると、一気に古の生活も偲ばれて、脈々と流れる日本人の心意気が、自然に身に染みて、とても落ち着いた気持で満たされる。歴史の中に生きてきたもの、目には見えないが、何かが、自分の中にも今なお瞬いているのを覚える。
満足感を背負って帰路は思わず微笑みでいっぱいであった。
067. 生き方の曲がり角
今年こそは、地球温暖化に世界が力をあわせて具体的対策を実行しなければ、本当に地球環境は取り返しがつかないと言われている。日本の将来は、大局的に、技術立国を目指すほかないとしても、政治、経済におけるグローバルスタンダードに飲み込まれてしまっては、その大義も国民のためというより国際資本家を巨大化させ、貧困層の増大を促すだけになってしまう。
ほとんどの団塊の世代は定年後の余生の過ごし方、選択を迫られる。地球世界、日本、個人、どのレベルに於いても流れの変節を迎えているといえる。
2005年を境に、日本人口が減少し始めたという事実は、日本の将来に何か言い知れぬ世界が訪れることをイメージさせ、自分の死後のことと割り切ってしまえばそれまでであるが、「孫」の顔を見てしまった上は、無関心ではいられない。
年末から年頭にかけてのテレビの色々な討論やドキュメンタリー番組を見ても、本当に色々と考えさせられるが、国家として、政治において日本人のあり方を世界に示す必要性は大いにあるのに、国政選挙の投票率は低く、国民の真意は姿を示すことがない。
政治がどうのこうのといっても、政治家を選ぶのは結局、国民なんですから。」と日本人の生き様への真剣な対峙のなさを、捨て台詞のように締めくくる評論家の一言は、日本人の生活・文化、職人気質を育んだ優しさという自然観、美徳を思えば、ジレンマを感じざるを得ない。
アメリカのように弁護士だらけの訴訟、権利主張社会になってうれしいか。
バランス感覚に優れたコモンセンスのある政治家を選びたい。
いつも煮え切らない国民と捕らえられがちな日本、外交ではあるが、シロ、クロを即決することが必ずしも優れているばかりでないことを、時間がかかっても順序だてて諸外国に話し続ける忍耐と勇気を持ちたい。
アメリカも今なら、イラク戦争のつまずきからこうした日本人の原理・原則も理解できるのではないかと思える。いずれにしても、日本人を取り囲むあらゆる潮流はその潮目を迎え且つ混沌としている。
今まで何度も問い直しては来たが、プラネット・アースに生かされているという実感をやっと身近に感じるような気がする「今」、明日の一歩は、ささやかでも死後の道につながってほしいと思う。
068. 上棟式
地鎮祭も執り行われ、やがて住まいが形として姿をあらわす棟上の日は、何時も最もわくわくする。図面や模型の段階で思い描いていたものがその輪郭をあらわす。柱や梁の部材がクレーンに吊り上げられて組み立てられていくのを眺めている時は、プランニングのときに住まい手とやり取りしたこと、あれこれ考えたデザインへの想いが青空を背景に次々と紡ぎ出されていくようである。
私は、ぼんやりと棟梁をはじめ職方のきびきびとした動きを見ているのがとても好きだ。段々と高場の作業になり緊張が高まっていく中で大工さん同士の軽妙なダジャレのやり取りも楽しく、協同作業の中で一つの何かが生まれかかっている、その時の高まりが心をうれしくさせてしまう。
日暮れなずむ頃、ようやくにして棟が上がり作業が仕舞い支度になる。そして、組み上がつた骨組だけの家の中に簡単な祝宴の場が設けられる。棟に挙げた御幣に向かって、居合わせる全員の礼と拍手、建物の四隅の柱に米と、塩、清酒での清めによって無事棟上式を終える。
ここからは祝宴となる。住まい手の施主としての挨拶、設計者、施工者のお祝いの一言、乾杯が行われ皆の歓談が始まる。この十月三日、新宿Y邸の上棟式では十三夜の月を眺めながら一献を傾けることになったが、その場は大東京にありながら佐渡島出身の大工さんの秋刀魚の手づかみ漁の話等ですっかり昔の日本、秋の風情を語りつつ別世界であつた。
昭和40年代の頃には酒豪の職人さんも多く、木遣り節等自慢ののどを聞かせる大工さんもいて盛りあがったが、職方のほとんどが自動車で現場に来るようになって、アルコール類を控えるため、今では結構わきまえた宴である。
それでも時々酒好きな職人さんがいて、どっと愉快なパーテイになる。やっぱり私は職人さんのおおらかさいっぱいの棟上が好きだ。どんな施主が、設計者が、そしてどんな職方が関わりあつて住まいを造ろうとしているのか、きっと昔は本音の姿で語り合い、より良い完成に向けての気脈を通じるための大切な場であつたのだろう。
都会では地鎮祭、上棟式をすることも少なくなったと聴くが、形式というよりセレモニーが持っていた形を通しての人と人との有り様や、自然、環境に対する心構えを問い直す機会として大切なけじめかと考える。もし、上棟式がなかったら、私は十三夜の月をこれほど感慨深く眺めただろうか..。
069. 松茸狩り
地球温暖化といえど、さすがに10月も中旬に向うと秋らしさが色濃く感じられる。
秋は味覚の季節、市場にも色々な旬の食材が並び美味い料理を思い浮かべながら心楽しくなる。中でも松茸は子供の頃は今の様に希少なものではなく、ごく身近に食することが出来た。
私が松茸狩に最後に能勢の山に行ったのはもう20数年前である。その頃でもそれほど豊作という状況ではなくなりつつあったので、山の斜面に沿って目を凝らし、落ち葉を掻き分け、1本の松茸を見つけると不思議なくらいうれしかったのを思い出す。
1本見つけると近くに数本が見つかりやすく、香りを嗅ぎながら「見つけたよー。」と思わず叫んだものだ。
山すそにござを敷いて松茸スキヤキをみんなでわいわい語りながら食べた。
勿論、牛肉よりなにより、松茸がなべから溢れるくらいで、皆が贅沢感に浸って幸せいっぱいだった。
今、日本では環境の変化で、松茸の収穫量は激少、松茸狩りを楽しめる機会は少ない。
そんな時、南北朝鮮の首脳会談が行なわれ、北朝鮮から韓国のお土産に4tもの松茸が送られたとの報道。内の奥さん曰く、「そんなにいっぱい、どうするのかしら。」「誰に分けてあげるのかしら」国家がもらったお土産は一体誰に、どうなるのか行く末を知りたいという。「大統領府や官邸の料理にでも使われるのでは」と答えてみたものの、秋の味覚を多くの人々におすそ分けする仕組みがあれば最高だろう。あの日本の福島だったかで毎年振舞われるサトイモ鍋の催事ように。
時々、遠方の知人達から産地の特産物を送られることがあるが、その新鮮さと同時に、季節感が心身に届くのが何よりうれしい。もう1度松茸狩がしてみたいな。
秋に想う。
070. 着物(和服の生活)
年末からの雪不足のため、今年の正月は久しぶりに京都で過ごすことになった。
京都の家で過ごすとなると思い出したように着物を着て、くつろぎたくなるのは不思議な習性ではあるが、元旦からずっと着物を着て過ごしてみると、改めて和服のなんとも云えぬ温かさとゆったり感がうれしくて『これぞ日本の心だ』と確信してしまう。
我が家の居間はフチナシタタミ敷き床ではあるが、ソファも置いてあるので、着物でソファに腰掛け新聞を読んだり、TVを見たり、お茶を飲んだり、トイレに行っても、段々と着崩れを直す要領が解かって来ると、着こなしの充実感のほうが楽しくなってくる。
「ちょっと角帯の締め具合を緩めのほうが具合がいいな」等着物にかけては達人である女房に意見を求める。それにしても、体と着物の間にふんわりとした空気層があって、その暖かさがこれほど気分をリラックスさせてくれるものだったとは、今まで実感することがなかった。
何度か和服を着てやっと少し本来の良さを感じることが出来るようになったのだろう。
言い古されたことではあるが、日本文化の持っているフレキシビリテイ、『間』の奥深いすばらしさを本当に大切にしたいと思う。
おせち料理のバランスの取れた味と栄養のくみ合わせ、色とりどりの美しさ、味わって飲む日本酒、日本間(和室)の穏やかさ、どれもこれも調和ということにおいて人間的だ。
スキーは出来なかったが、今年のお正月は久しぶりに日本人であつた。
それにしても初詣、昔に比べてあまりにも「普段着」の人が多すぎるのはどうか、せめて新年「ハレ」の精神、けじめも必要ではないか。
廣瀬 滋著