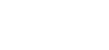071. 職人でありたい
20年近く高校時代からの友達が経営するセンサー関連の会社に関わりがあるのだが、3年前、その会社の集まりで、新たに入社した30歳前後の中国人の営業担当者と話す機会があったが、「あなたは日本人についてどう思いますか。」と尋ねたら、すかさず「日本人は基本的に皆、職人ですね。」という予期せぬ答えが返ってきた。
中国人の彼は、親の仕事を受け継ごうとも考えないし、その時々に一番合理的、経済的な仕事を選択し努力する。ひとつのことにこだわらない。日本人は、何かとプライドやしがらみに縛られ、細部にこだわり、まさに「職人」ですね。という意味の補足説明があった。「日本人は職人か。」と彼の仕事に関する経験談も聞きながら、その時、何かユダヤ人や中国人との違いを生々しく教えられた気がしていた。
時は流れ、最近、韓国の知人と建築の共同プロジェクトについて話をしたが、言語の壁はともかく、大局的イメージに於いては大いにこちらの考えに賛同し、協力し合いましょうということになるのだが、ことの運び方になると何となくかみ合わないものを感じさせられる。
韓国でも40才台以下のハングル世代はアメリカナイズした合理的、論理的ものの考え方を備えているとのことで、日本人が今グローバルスタンダードなどと、うろたえているが、中国人も韓国人もはるかに先行して国際人である。過酷な競争原理にも精神的に対応出きる強さを備えている。
しかし、私は、あること、あるものを、より経済的、合理的に生産したり対処して、競争に打ち勝つことが出きるとしても、創造的なものは、長い作業や技術の積み重ねの中から涌き出るもので、今日の日本を支える多くの先進的技術、ビジネスメニューは、いずれも職人的粘り強さ、一途な積み重ねから生まれてきた事実があり、日本が小さな島国でありながら、今日経済大国として存在できているのも、創造的具体化の能力、つまり「職人魂」のお蔭ではないかと思う。
新しい発見や技術が職人的日常作業の中から生まれるので、とかく華々しさがなく、日本人は創造的でないというような誤解があるが、日本人は創造的民族である。日本人から「職人魂」がなくなれば日本人の「心」は消滅すると思う。
構造改革の掛け声のもと、過激な競争社会を築き、経済的に勝ち残れても、日本人の未来の楽しさはない。誇れる文化を創り出すのは「職人魂」あふれた日本人である。やみくもにグローバルスタンダードに合わせるのではなく、なんとか本来の日本人が生き残れるバランスの取れた舵取りを日本の政治に期待する。
そのために、一人一人がそれぞれの生活の中で「職人魂」を失わなければ、日本人は日本人として輝くことが出来る。「日本人は職人」で大いに結構。私は日々の仕事を通じて住まいづくりの「職人」でありたいと思う。
072. 小さな庭(生活と緑)
小さな北の裏庭に植えた金木犀が、今年も申し訳程度の花をつけた。日当たりが悪いのを承知ではあったが、冬でも窓からミドリが見えてほしいと常緑樹で、しかも花の匂いが季節を知らせてくれると金木犀を選んだのだが、毎年、かすかな香りしかない。
二年の間に50センチ位は大きくなって2.5メートルくらいにはなったが、西陽がやっと上の部分1メートル位にあたるだけの気の毒な環境である。
ほとんど毎日仕事をしながら眺めているので、ことのほか葉っぱの色艶も気になる。脇に植えたアオキは北の庭向きなだけに、勢いもあってなんとなく安心であるが、もっと花を咲かせて良い金木犀には僕の勝手な選択で「ごめんな」と何時も謝っている。
それでも、もう少し高くなったら、急に日射量が多くなって、ぐんぐんパワーアップ、いっぱいの花をつけてくれるのではないかと金木犀と僕のハッピーエンドを願っている。 京都の町屋で育つた僕は、ことの他中庭、坪庭、裏庭には色々な思い出がある。一時期、住んだ桂坂の郊外住宅では、一日中、陽のあたる南の庭で芝刈りをしたり、色々な草花を育てたり、勝手に鳥が運んできたグミの種から、苗木が出現して驚いたり、花ミズキの種を冷蔵庫に保管して翌春それを栽培したり、拾ってきたドングリから苗木を多数栽培したりと、もっぱらアクテイブなかかわりであつた。
中庭、坪庭、裏庭は違う。それも小さな庭ほど生活の中で静かな対話、心の流れを受け止めてくれる。ベランダや室内では観葉植物への程よい水遣りに心配りながら都会生活の言い訳をしている。
夏の信州の別荘では自然の勢いを雑草に感じながら緑の照り返しに包まれて心安らぐ。植物は僕の生活になくてはならないものである。住まいと自然等と振りかぶらなくても、生活の中での植物、「緑」との関係を楽しむシナリオを描くだけでも住まいはもっと豊かになるのではないか。
後年,金木犀は、5メータ余りの高さになって、西日を浴びることができるせいか、花をいっぱいつけて、何とも季節の香りを届けてくれている。
073. 応援
テレビでプロ野球、阪神タイガースの野球中継を見ていると、試合の合間にカメラが観客席を捕らえ、ファンの熱い応援の姿がクローズアップされる。
お父さんの膝の上で、同じように虎フアン、アイテムの縦縞シャツを着て小さなメガホンを訳けなく振っている幼子の姿や少年が、贔屓の選手に夢を託して大声で応援している姿は微笑ましい。
まるこい中年の小父さんが本当にうれしそうに拳を突き上げ、応援の王道を貫く姿、茶髪の生きのいい若者男女が色々なプラカードを掲げたり、パフォーマンスをお祭り気分で繰り広げる様は、活気にあふれている。
そばで老夫婦がこの熱気を楽しみつつ、静かにグランドに目線を向けている。もし、街中で会ったとして、きっと澄まし顔で闊歩しているであろう美人が、お目当ての選手名を書いたカードを両手で掲げ、左右にリズミカルに振っているのも昔の球場風景を知るものにとっては新鮮である。
甲子園にはこうした応援気分に膨れ上がる5万人近い老若男女が、それぞれの想いを託しつつ、タイガースというチーム応援に集っている。
この応援の姿は、近頃、経済活性や事業創出に関して言われる「連携」という概念を具現しているのではないかと思わせる。ファンにはタイガースの活躍、優勝という目標、希望が明確にあって、その為に一人一人がチケットを買って経営支援をし、現場に駆けつけそれぞれの出来る事で応援する。ストレス解消の人もあれば、プロの技を学ぶ・楽しむなど、それぞれの目先の利得はあるだろうが、とにかくも大勢の人々がタイガースの応援に集まることが周りの経済効果を高め、タイガースの優勝ということになれば何百億円の経済波及効果があるといわれる。
現実社会では、産学官の連携、地域の連携、企業の連携などが盛んに喧伝されるが、いずれもそれぞれの立場に固執、飛翔できず失敗に終わるケースが多い。
タイガースファンの様な透明な情熱の集積が、もし、地域コミュニテイや町おこしにおいても結集することが出来れば、大抵のことは成功するだろう。
わかりやすい「夢」、夢に向っての楽しい共同体験と学習が程よく出来るコラボレーションシステムの創造は、タイガースファンのラッキーセブンに宙を舞うカラー風船の中に隠されているのだろうか。
これからのデザイナーはその秘密を明確にする役割を担っているのかもしれない。
074. 「やってみなければ判らない」
私達の生活の中では「やってみなければ判らない」ということがしばしばある。
しかし、科学的,合理的考え方が多くの文明を築いてきた、進歩をもたらしたと結果的に信じ込ませられている人々に、そんなことを言ったら、無責任と評価されない。
人類が「火星」に行くというような場合は『やってみなければ判らない』では済まされない。人命にかかわる事、目的の明解なものは、科学的に実験、検証などが行われ、その安全、効果を充分に確認してからものごとが行われるが、それでも、失敗と言う結果が生じることがある。
たとえ成功したものでも、そのプロセスにおいて『やってみなければ判らない』をひそかに幾つも繰り返している。日々の生活レベルの範囲では、厳密な目的や結果を設定されない、あいまいなことがいっぱい有り、そのファジーさに対応することが目的であったりするものが多い。
住宅における構造体は人命を守るシェルターとして十分耐力を有する科学的数値根拠を持つものでなければならないが、木構造などは今だ謎の部分を秘めている。
インテリア《室内環境》デザイン等はその基準設定の有り方、運用の仕方などは、住まい手との個別関係において意味をなすため、『やってみなければ判らない』部分が多い世界になる。
人と環境、人と人のより良い関係を築くという行為は、始めに固定された目的や到達点があるわけではなく、相互の交流によって変動しながら快適値を求めつづける事が重要だ。
昨年施行された『住宅の品質確保の促進に関する法律』は、住まいづくりのずさんさを考え直す上で有効ではあるが、住まい手も作り手もが保証問題や、性能の等級などに拘泥すると、本来の可能性、創造性を見失うことになる。
住宅の10年保証などは基本的に考えれば当然であり、同じなら25年、30年、建築主が住む限り保証するものであっても良い。
悪徳業者の建てた住宅は、新築時より問題があり、単純な10年保証制度でユーザを保護できるものではない。結果を受け取るだけで満足するのではなく,『やってみなければ判らない』世界に、住まい手も作り手もが楽しくチャレンジできるように、その根底に互いを信頼する心、互いを裏切らないモラルを持ちたい。
075. 在住外国人問題
近年、日本に仕事を求めてやってくる外国人の増加と、その在住外国人とのトラブルや関連犯罪の増加が気になるところである。先日も広島でのペルー人による少女殺人事件が心を痛めるが、その背景に、日本の少子化、高齢化社会という社会構造の変化が労働市場、特に過酷な労働条件の場においての人材確保の問題がある。
積極的に日系人などを受け入れざるを得ないという状況である。TV番組などで出稼ぎ外国人コミュニテイと近隣日本人住民との交流、親睦のためのイベントなどが紹介され、かすかに日本人が日常生活レベルで外国人・他民族との接触、対応の仕方を学びつつあるのを知らされるが、長い歴史の中、単一民族国家で来た日本人にとって、他民族との共存のすべは、まだまだ不明である。
国内における外国人の凶悪犯罪が報道されるたびに、日本人は共存の根本的なありようを考えるより、自己防衛に身をすくめてしまいかねない様な気がする。
10年近く前の夏の暑い日、私は仕事で名古屋に出かけた。打ち合わせ前にランチを摂ろうと駅構内の食堂に入り、セルフサービスでメニューを選択、テーブルに着いたのだが、すかさず、「ここはあいてるか」とやや酔っ払った風情の初老の男が私に相席を求めた。ほかにもいくらも空席があるのに、私はいやな感じがしたが、黙ってうなずいた。
私の食事中、その男は私の顔をしげしげと見ながら、ずっと独り言のような、話しかけるような口調で、政治ぽい愚痴を繰り出していた。内心、拘わりたくない、早く食事を済ませて立ち去ろうと思っていたとき、「お前はペールー人か。」と正面から私に向って訊ねてきた。一瞬、何を訊ねられたのか。「お前はペルー人か。」、繰り返し聞かれた問いに想定外の困惑の中で「日本人です」と答えた。
とたんに男が安心したように、「いやぁ、お前が何も言わんので、日本語がしゃべれんのかと思った。」時は夏、工事現場監理もあって日焼けした私の顔色、おまけに髭を生やしている顔つきはすっかり日系ペルー人に思えたという。
男の住む愛知県の地方都市では自動車関連産業の働き手として、めっきりペルー人が多くなって、興味半分、ペルー人と近づきになりたかったらしい。
あの日の体験を思い出しながら、観光旅行などでは軽く流すことも出来る言葉の壁、文化の違いを、日常生活を共有するもの同士として如何に平和に混在・融和させればいいのか、今後ますます多民族化する日本社会を思うと気が重い。「国際結婚に報奨制度」などが手始めとして早道か、なんて思ってしまう軽率さを自戒しながら。
076. 環境は命の基本
戦後の食糧難時代に、日本の農業は色々な研究も生産方法も、増産、生産効率アップという目標に向かって進められた。化学肥料、農薬、農機具の投入、品種改良など、そのための多大な投資が必要となり、結果的に生活を支える基本食の米価は政府が補助金を投入しなければ市場性を失う状態になる。農業の合理化、改革の推進を担う農協は、いつの間にか農家の活動を資金面で支援する金融機関となり、農作物づくりの根本や環境への配慮などにおいて指導力を発揮するどころか、単なる金儲け組織になってしまった。
近年、中国からの輸入食品問題をきっかけに、食の安全、食の流通などが食料自給率低下の流れの中で問題視されるようになったが、日本の農業も技術力は高いものの、安全やコストを含めた消費者の満足度には程遠い状況である。
色々な農業関連の法律に縛られて、今日の国民の要求にこたえられる農業の展開は困難を極めている。心血を注いでプロの専業農家が作った安心、安全な作物を如何に消費者に届けるかという、生産と流通の有効な相互関係を構築するためには、従前の法律や流通慣習に縛られていたのでは不可能である。
近年、産地直販、地産地消、有機農法など、作る側と販売側、消費者がヴァリューチェーンを形成して色々な取り組みがなされている。
その多くは、今までの反省も含め、農業はまさに生き物、環境の循環を大切にするという指標を持っている。良く考えてみれば、食物はわれわれ生命の源であり、その食物は全て命の連鎖、自然環境の循環システムの上で成り立っている。
日本では年間約3万人の自殺者がいるというのも大きな問題になっているが、世界には年間5000万人を越える餓死者がいるという。
種の取れない遺伝子改良された作物は、短期的には食糧増産につながるかも知れないが、
長い目で見たとき、その地域、気候に合った子孫を残すかというと疑問が残るそうだ。
先日もイチゴの苗を親の株からヘソの緒をつなぐようにしたままで育て、最適な遺伝子が伝わっていく育成法をしている武山農園を見学したが、有機栽培、無農薬、加温なしという条件で育つイチゴにチャレンジしている青年の心意気は、まさに命の原点と如何に一体化できるかの勝負を見る思いであった。
われわれを取り巻く自然環境はそれこそ神がお造りになったと思って初めて合点できるほど複雑、多様、膨大であるが、人類が何をするにもその基本指標として忘れてはならないものである。農業(agriculture)は教養・文化(culture)の語源でもあり,身近に、農業はまさに人間に環境の何たるかを教えてくれる。環境問題には地球温暖化対策を筆頭に、省エネ、リサイクル、生物多様性、エコカーなど多くの切り口があるが、いずれも経済問題として展開される。勿論、今日の社会、人間の営みのあり様はそうしたものでもあるが、なんとか、環境は「命」の基本であるということを疎かにしないでいたいものだ。
077. 環境についてもっと考えよう
地球温暖化による色々な気象現象の変化が身近に感じられる昨今、CO2の削減のための技術開発や省エネに対する行動・努力は国家、企業レベルから一般大衆のライフスタイルの検証をも求めるところまで来ている。
大阪ガス主催のエネルギー・環境フェア2008を見学したが、CO2排出量として結構大きなパーセンテージをしめる発電のためのエネルギー消費を如何に抑えるかという問題は、一般家庭に燃料電池が実使用されるときには、時々にガスのまま、あるいは電気に換えて使いこなせる天然ガスをエネルギー源として利用するほうが、オール電化よりはるかに、熱効率の良いシステムになる。
今は安全面やシステムのシンプルさがオール電化住宅にも得点を与えているが、太陽光発電システムとの併用など、仕組みとしては複雑でも、それらを適時、的確にコントロールできるなら、おそらくエネルギー供給は天然ガス主体のものとなろう。
原子力発電や水力発電などCO2を発生しない電力装置は、効率のためにコンスタントに稼動させる必要があるため、基本電源量生産としては有効でも、電力需要の変動に対処する部分においてはオールマイテイでないのと、放射能問題など他の環境問題が懸念されるため、拡大設置には限度がある。
それにしても、超小型オンサイト水素発生装置や生ゴミ真空乾燥装置など地球環境改善のために、色々な技術や装置開発が行なわれていて、会場の賑わいは大勢の人が環境ビジネスに携わっていることを実感させる。
一方、別の話しだが、365日24時間、山地に放し飼いの酪農は、牛が山間の下草を食べるため、今問題になっているトウモロコシ、ダイズ、等の配合飼料に頼らない、人間の食料と競合しない酪農が可能である。山地の下草狩を牛がやってくれることになり,里山は健康を取り戻し、林業家にとっても経費節減になる等のメリットがある。自然な草で育つ牛の牛乳は、乳脂肪分が3.2~3.5%だそうだが、何時の頃か5%以上のものを規格として国が決めたため、勢い配合飼料をえさに、過密な牛舎で育てる酪農が主流となって、この環境問題の中で、飼料高騰(エタノールへの転用のためなど)、牛の糞尿やゲップによるメタンガスの排出などマイナス条件を抱え込んでいる。
メタボが問題になるご時世、そんなに濃い牛乳を飲む必要があるのか、一生懸命、牛の健康も考えて生産する牛乳が、コーラやジュースのように量産されるものより安い価格でよいのかと、訴える酪農家の信念に燃えた声は、環境問題をもっと奥深く考えなければならないことを教えていると思う。
日本の環境対策・改善技術は大いに先端を目指すがよいが、進歩という概念ばかりでなく、江戸時代の環境循環型の人間の、生活の智恵を生かす努力、振り返ってみてもよいのではないかと思った。
078. 「おしゃれ」とは
誰でも、おしゃれな人と言われるのは結構、気分のよいものであろう。そこにはその人なりの独自性や感性が表現されていて、それなりの美しさや秩序を持ち合わせていることを認めてもらえたのと同義であると思うからである。
「歌舞伎」の語源は、飛び切り長い刀を差して派手な格好をして街を闊歩した江戸時代の若者たち「かぶく」もの、時代の先端を行く前衛者からきているという話を聞いたことがあるが、人々は、とにかく、まだ人のやっていないことをやる人を、その生き方の勇気をも含めてそれなりの賞賛の意を込め、「おしゃれな人」と呼称したのだと思う。
戦後、欧米の影響を受けて、民主主義が台頭する中で、平等精神、個人の尊重という風潮は、ファッションデザインの中にその表現を求めて、人々はだんだんと自分らしさを生活するようになった。しかしまだ、自己表現になれない日本人は、「流行」という与えられたスタイルに身を委ねていた。
戦後40年を過ぎた頃からは、何をやっても「私の勝手でしょ」と履き違えたおしゃれも見境なく巷にはびこるようになった。「おしゃれ」とは何か。
他人真似でない「おしゃれ」な生き方は、かっこいいが、その人の生き様を根底に表現しているものでなければならず、それほど容易く簡単なものではない。
自分なりのものの見方や考え方、感じ方を生活において心掛けることを「おしゃれ」というキーワードで捉えてみれば、その原点は自分が、
・他人が未だしていないこと、・他人が未だ感じていないこと、・他人が言わないこと(気に留めなかったこと)、・他人が未だ表現しなかった方法などに全感覚をセンサーにして気付き、発見を行い、ものの見方を磨き、考え方を模索することにつながる。
また同時に、新しい意味や表現の追求は、おしゃれの具体化につながるが、そのために
・新しい素材のコーデイネーション。・新しい色使い、カタチ、テクスチュアー、スケールの提案。・新しい使い方の発見、・新しい機能の提案。・新しいシナリオ(生き方、可能性)。・新しい心理の発見などにつながって、「おしゃれ」をすることの意味合いは自分自身の存在を問い続けることにもなるのではないだろうか。
男女を問わず、街にはトレンデイな流行に身を飾り、ジムに通って健康を願い、おしゃれなレストランで食文化を消化し、文化センターで教養を身につけ、時にはボランテイア活動をするといった流行のライフスタイルを実行している人々は多勢いる。
一見、今時のおしゃれな人と見えるが、本当のところはどうなんだろう。良い意味でおしゃれな心、日本人の心を磨く努力をし、平和なおしゃれを発信できる「おしゃれ人」になりたいと願うが、その一歩一歩はもっと実在感のある生活と、そこに感じる反省と感謝の念を繰り返し自問自答することなのかと思う。
079. 歴史を学ぶことの大切さ
近年、日本のアジア外交、特に中国、韓国、北朝鮮との関係は、政治、経済、文化、人権問題などあらゆる面において解決しなければならない局面を抱え込んでいる。
現実問題としては、中国の急速な経済活動に引きずられて起こる連鎖反応的な諸問題、
北朝鮮の核実験や拉致問題に代表される国家としての非常識な振る舞いに悩まされ続けている。しかも、ことあるごとに、歴史問題、過去の歴史の認識に関して、一方的に日本が悪者という勝手な論拠を振りかざし、自国内における諸問題の民衆への不満・圧力をかわすことに利用している。
しかし、多くの日本人は、近代・現代史はむろんのこと、アジアの近隣諸国との関係をどれだけ学ぶ機会があっただろうか。学校における歴史教育は、たいてい時間切れで、近代・現代史は私も含めて、詳しく学ばなかった人が多いと思う。
だから、勝手な中華思想を振りかざされても、反論する力をもてないでいるのが多くの日本人の現状である。確かに満州国建国から第二次大戦にいたる歴史の中で、日本の行動も問題なしというのではないが、「南京大虐殺事件」にしても、近年の調査では、中国共産党が蒋介石率いる国民党を打ち倒すために、巧みに仕掛けたことが事実だったことが明白になってきている。にもかかわらず、先の中国首相・江沢民は、日本訪問のときには、早稲田大学での講演で「3500万人の中国民同胞を殺戮した日本人は未来永劫断罪されるべきだ」と南京事件の10万人とも30万人とも言われていた被害規模を、何百倍にも誇張してまくし立て、それを聞いていた学生諸氏は、歴史勉強不足のため、誰も反論することがなかったという。
このことを、先日桜井よしこさんの講演で聞かされ、あまりの悔しさに涙が出た。日本人の優しい気質が利用されている。対アメリカ外交にしても、脅せば引くと見くびられているのは残念だ。
日本のよき国民性が今日のグロバーリゼーションの流れの中でどんどん変質させられるのは悲しいことである。
何とか、しっかりと歴史を学び、ことの真実を把握して、日本人としての考え、意見を言えるようにするべきだと思う。
小学校における歴史教育はなきに等しい状況と聞くにつけても心配である。我々大人も、日本の行く末を誤ることのないよう、努めて歴史を学び、国民の一人として確かな指標を持ちたいものだ。
080. 100分の1秒
トリノ冬季オリンピックの競技をテレビで見ていると、スピード、技の正確さ・美しさ、チームワークの巧みさなどが色々な競技種目の中で綾なされ競われているが、とりわけスピード〈タイム〉の争いは運命的でもある。
100分の1秒差に7,8人の選手がひしめいているスピードスケート(500m)競技では、誰が金メダルに輝いてもおかしくない世界であり、選手の一瞬のミス、私には「神」のいたずらかと思えるようなコーナワークの所作が、勝者・敗者の天と地を決めている。
日常生活で100分の1秒という瞬間がこれほど格別に意識されることはない。意識されるとすれば、「あの時立ち止まらなければ」,一瞬の出会い頭で交通事故にあって命を落とすなど、大なり小なり何かの事故・事件とのかかわりが多い。
選手たちは、その一瞬の記録のために、計り知れない努力を、トレーニングを積み重ねてくる。絶えず一瞬を意識しながら生活する日々は一体どのようなものだろう。
こんなことを考えている間に、何人ものスケータが目の前を風のごとく流れ飛んでしまうのだ。
瞬間を生きているときは何も意識がないのか。多分、余分なことを考えたり、感じたりすることは重圧となって、スピードを鈍らせ、結果、敗者となるのだろう。
よく「一瞬を大切に生きよう」などと言うが、我々の人生や生活においても、やはりそれなりの相当の修行がなければ、一瞬という「時」の存在すらありえないのかも知れない。
ひとつの競技のようにルール化され、絞り込めない我々、それぞれの生活の最適のゴールは、自らの人生のフレームを描くことがなければ想定することも定まることもない。ゴールへの一瞬を極める努力目標も立たない。若い頃に大志を抱くこと、希望を掲げることがいかに大切なことかをあらためて感知する。
最近のゆとり教育と言われる小学校教育においても,はたして大志を抱く原動力になる「生命力」を芽吹かせる配慮がなされているのか。従来のように、家庭教育、「親の背中を見て子は育つ」を再認識しなければならないのか。小学生対象の「トレーダ教室」が開かれ、子供が株の売買を早くから訓練すると言う現実は、人生を金銭獲得競技のみに絞り込み、その一瞬の大切さを教えると言うのだろうか。
人生はなかなか絞り込めないものだからこそ、100分の1秒はなかなか見えてこない。
廣瀬 滋著