月別アーカイブ: 2024年12月
私の思考散歩・生活雑感 ぽつり草々 091〜100
2024/12/10
091. 輝きの一歩
宮里藍選手をはじめ諸味里しのぶ,横峯さくらなどの台頭で女子ゴルフプロのトーナメントはテレビ中継を見ているだけでもなかなか楽しい。私は、もう自らのゴルフの才のなさに見切りを付けて久しいが、選手がコースマネジメントを巧みに、しかも技とパワーを発揮するとき、過って克服できなかった前下がりなど傾斜面からのショットやアプローチ、グリーン上の芝目の読みなど懐かしく思い出される。
それにしても、8000人を越えるギャラリーを従えての宮里藍の勝利のパットの瞬間、その野外劇場のような有様は、なかなか感動のシーンである。
最近は、ゴルフをする人だけでなく、子供をはじめ、ゴルフをしない人もギャラリーとして多く参加しているとのこと。緑いっぱいの自然の中で繰り広げられるスター選手の活躍を、ピクニックのように、そぞろ歩きで追っかけるひと時は、ゴルフ場の爽快感を知るだけにうなずける。
何よりも、女子ゴルフプロトーナメントにこれだけのギャラリーを集め、テレビ中継視聴率をアップさせるのは宮里藍人気であろう。今までの女子プロ選手にはなかった爽やかさと可愛さに加えて、安定した確実な技術の向上、キャリアを重ねるにつれ、精神面での強さが色々な発言やしぐさに感じ取れ、とても20歳になったばかりとは思えない奥行きを感じさせる人間性も、多くの人々をファンにさせるのだろう。
宮里選手のように、自らがマネジメントした通り、ことが運ぶ技術、パワーは一体どれほどの練習、努力、研鑽の継続の上に築かれているのだろう。
私のゴルフは、たしなみ、所詮遊び程度のものに過ぎなかったのだが、取り組む姿勢によって、何事も人生を豊かにさせるものであることを、つくづくと感じさせる。スポーツの世界はこのことを単純明快に勝者と敗者という結果の積み重ねによって示唆する。
勝ち負けにこだわらないで最善を尽くそう等と言うが、勝ち負けが身にしみて分かるからこそ人は深まりを知る機会を得られるのだ。日常生活では勝ち負けを言うと角が立つことが多いが、時には潔く勝ち負けを感得することが、明日への一歩を確かなものにしてくれる。
西陽を浴びて18番グリーンに上がってくる宮里選手の姿は、その一歩一歩が輝くための戦いの大変さを引き連れている。しかし、それが美しく、彼女の笑顔に包まれているため、私たちは一瞬、我を忘れて拍手喝さいを送るのである。
だが、感動し、浮かれてばかりは居られない。人それぞれの輝きの一歩はどんな時からでも、自身の決意と勝敗に怯まぬ継続した行動からはじまると思うから。わが道なりの輝ける日をめざし、一歩前進の努力をし続けようと静かに思う。
092. ゴールデンウィーク
日本の社会人にとって、ゴールデンウィークはお盆や正月休みと比べて時候の良さとあいまって唯一、行楽や気休めに自由に過ごせる休暇期間といえる。
勤勉な日本人には1ケ月をこえる長期休暇を生活設計の中に取り込むことは不得手だが、近年、欧米と比べ、ささやかながら10連休くらいのゴールデンウィーク休暇は、こなしきれるライフスタイルは一般化してきた。
今年は約6400万人(昨年を1000万人上回る)の人々が日本各地の行楽に出かけたと言う。海外旅行も含めると、多くの日本人が余暇の取り方、過ごし方に多様な自分なりのスタイルを発揮しているといえる。
30年ほど前、アメリカのフェニックスでキャンピングカーを借りてグランドキャニオンに行こうとした時、3日間のレンタルを申し込んで断られたことを思い出す。そんなに短いレンタルは無かったからである。その時、休暇というものに対する考え方の日米の違いを体験した。
帰国後、自分の生活の中に緩急を取り入れようと、ささやかながら別荘を白馬乗鞍スキー場に持った。当初数年は、自然とのふれあいの楽しさもあり、年間、約50日間くらい利用していたように記憶している。やがては、遊びや周辺観光よりも、敷地の整備、別荘のメンテナンスなど都会では出来ない労働作業に汗することが楽しくなり、その為の道具や資材の販売店などを地域で探すうちに、色々と周りの地理や人々との関係が織りなされ、自分の中に山荘での生活というものが実感できるものになった。
何しろ、地下室にはスキー関連のもの以外に、雪かき用具、鍬、鋤、斧、スコップ、草刈り機、電動工具,セメントを煉る船、長い折りたたみ梯子、塗装用具など色々ものがあり、その上、30年間、時代の進化の中で使い捨てた暖房機器や家電品、住宅機器の残骸もあって、地下室はまさに山荘での私の休暇生活の歴史館の感がある。
一方、建設時、小さな山村部落の18軒目として参加させてもらったのだが、いまや150軒以上のペンションや別荘が建ち並び、10数年前に開通した栂池高原への谷超えの道路や、新しいホテルの完成、温泉の試掘成功など、周辺環境も大きく変化。早くからの有線によるテレビ視聴、湧き水の上水道化、一昨年の下水道整備などインフラの向上は利便性の有難さを感じさせてくれるものの、折角のミネラルウォーターでのコーヒーの味を減滅させてもいる。
今年のゴールデンウィークは好転に恵まれ、山菜採り、ブシュ刈りや周辺整備に汗することが出来た。「山荘の 庭にぽつぽつ フキノトウ」、「水芭蕉 群れて際立つ 岩清水」なんて俳句を詠んでハンモックで一休み。女房殿は「うぐいすと 共に目覚める 山の春」と詠んでご満悦。ゴールデンウィークは「非日常」という「時」の断片でもある。
093. 新年に想うこと (初孫誕生)
あわただしくも、昨12月31日夕方、孫が誕生。カンガルー何とか方式とやらで臍の「緒」が繋がったままで30分余り赤子は嫁の胸の上に素肌のままで抱かれていたそうだが、病室を見舞ったときは、産衣にくるまれ、この世に小さな一人の顔を輝かせていた。
その時、私は、父方の祖父母、父・母、私、息子、孫と、母方の曾祖母、祖父母と実際に出会った家族5代(6代)の顔を一瞬に思い出していた。一般的に普通は夫々5世代のつながりを実体験できるが、祖父母、両親、子供達との色々な思い出とともに「命」の繋がりが「時」の連続として存在することをあらためて思い知る。
墓参りの時などは、遠い先祖をも漠然とイメージしながら自分の存在の今日あるのはあなた方の存在あればこそと感謝して「手」を合わせ、不思議な「命」、「時」の脈絡を静かに追想している。
子孫存続という「命」の連続は、生々しい生活事象の中では、繁栄、衰退というような「命」・「時」を力の世界で征する為の悲喜劇を繰り広げさせて来たが、一人一人の「命」は二度とない人生、大切に生きることを目指し、その本懐を願っていよう。
このことは、ただ自分の「命」が時の連続、時をつなぐだけの存在ではなく、他の「命」とのかかわりにおいて、命そのものの生きる背景、「時代」をどのように築くか、新たに生誕する担い手のための「時代」の美しき連続のために何が出来るか、少しでも尽くすことがないのかを考え、ささやかなことであれ実行することである。
自らの「命」は生まれ出でた時代、家庭・家族環境等により、出自、「運命」と言う束縛を受け、誰もがその「命」を平等に羽ばたかせることは出来ないのかも知れないが、自らの「時」の使い方、生かし方は、ちょっとした心掛けで大いに多くの命との交流・交感、共鳴から命の存続そのものに意味を、輝きを与えることになるだろう。
今、日本は少子化時代ということで、日本民族、社会の衰退が懸念され始めているが、子育てに関ることで「命」、「時」のあり方を自然に学習できる体験の場を逃してしまう世代が、自らの個としての「命」を思いやることに気付くだろうかと心配する。
「命」は「時」が省みられず、「時」は金なりが「時」の大切さを戒めることから逸脱して強欲に走る人たちの旗印になってしまっては大変だ。
孫がどんな「命」の使い方をしてくれるか、私の人差し指をぎゅっと握り締める小さな手に「時」がバトンタッチされて行く。
094. 食初め
孫の生後100日にあたり、「食初め」を行った。
父親方の祖父、つまり私が食べさせるのが丈夫な子に育つという「ことの慣わし」と云う嫁の調べによって、その役を仰せつかる事になった。
本当はどうなのか,私に華を持たせてくれる心遣いかも知れないが、素直にうれしく息子の家に出向いた。息子のときにも使った朱塗りのお膳の上に睨み鯛、吸いもの、野菜の煮物、かまぼこ、だし巻、お赤飯、香の物、それにそら豆大の小石が2個塗りの器に盛り付けられている。
ちょっとあらたまった気分である。鯛の身をほぐして、おもむろに孫の口元に運んでやる。次々に食べさせる真似事をして、最後に小石を鋏んだあと、箸を歯茎に当ててやると、丈夫な歯性の子になるとかで、そのことを執り行う。
いたずら心で、梅干を口もとに持っていったときは、孫君は身震いをして今にも泣き出しそうであった。息子は「もうこれでトラウマになって梅干は食べなくなるかも」と爺の子供じみた振る舞いを静かにたしなめた。
振り返って思うに、自分の子供の時の「食初め」の記録写真はあるのだが、まったく細やかな記憶がない。30数年前のことであれば、当たり前かも知れないが、そのとき親として、何を願っていたのか。幸い息子たちも健康に今日まで来たのは、結構、願い事が天に通じていたのであろうか。もし、孫と話し合う時が来たら、「お前の元気な成長を願って、お父さん、お母さんは気合を入れてビデオも写真も撮っていたよ」と教えてやろうと思った。
親は案外照れくさくて、そんな当たり前のことは伝えないかも知れない。赤子が母乳だけで、あっという間に7kgにも成長し、子供らしい表情を振りまくことも楽しい驚きであるが、やがては少しずつ離乳食に始まり、色々なものを食べ、母親以外との関係を紡ぎ出すのだろう。
毎日眺めているわけではなく、1週間に一度くらい観察するというスタイルでの孫との出会いは、自分の子供の育児よりも、かえって確かな実感がある不思議な気分だ。
抱いてあやした孫の、ほのかにセータに残る体臭は、DNAを引き継ぐ生命の営み、役目を、まさに遂行した安堵感を知らせている。ときの流れ、命のつながりを爺として感じさせる「食初め」であった。
095. 健康のレベル
経済成長の後、高齢化の進む日本社会にあって、多くの人々の関心は「健康」に向けられている。如何に健康に美しく、楽しく余生を生き抜くか。古来からの人類の願望でもある。
昨年来、東西医学の補完・統合型医療を基軸に如何なる健康サービスが創出、提供出来るかというプロジェクトにかかわる機会があったが、「健康」と言う概念が実に微妙で奥深いものであるかを知らされた。
従来の西洋医学における検査では、血液のある成分の数値が通常より少し異常であれば、自覚症状もなく、本人は健康という認識であるにもかかわらず、たちまち病名がつけられたりする。
また、逆に、検査の結果、数値に異常はないにもかかわらず不快感がぬぐえず、本人にとって不健康と思える状態(未病)もある。
試みに、プロジェクト調査事業の一環として、東西医学統合型「人間ドック」が実施された。従来の人間ドック受検者に、同時に東洋医学による検診(問診、脈診、舌診等)を行い、その診断評価と合わせてトータルに見直すと、健康に対する個人の認識と症状のずれが、比較的合点が行くものになると言う傾向がつかめてきた。
学術的にこうした「健康」のレベルを明確に把握するためには、東洋医学における診断と評価の因果関係を証明するバイオマーカーの検索がぜひ必要なことになるが、とても高価な分析検査機械が必要なこと、分析手法充実、さらに、唾液や血液の分析は、昨今の個人情報保護の立場から慎重を期すことが求められ、有効データとして蓄積されるにはハードルは高い。
しかし、やがて東西統合型診断が一定の成果を挙げるようになれば、「健康」のレベルは連続的に評価・認識できるようになり、そのことは個人の許容範囲・偏差を踏まえた治療方法や健康維持・増進への対応が出来ることにつながると思われる。
ホームヘルスケァの観点に於いても、血圧計、心電計、体温計など検査機器がユニバーサルデザイン化の流れの中で、家庭での測定・検査値が信頼できるものとなり、データが即、医療機関に電送され、迅速に健康管理などが行われる時代となった。我々の「健康」レベルは色々な段階、生活局面でサポートされるようになって来ている。
とはいえ、究極、病は「気」からとも言う。ストレスのない生活の過ごし方は本人の「生きかた」心構えにもあると思えば、どのレベルの「健康」を望むのかを自身に問いかけねばならないのかも知れない。
096. 規則のきわどさ
先日、地域の交通安全対策活動のひとつとして、朝の通学時間帯に、婦警さん、ボランテイア達と中・高校生の交差点での交通指導を行うことに立ち会った。
横断歩道での自転車と歩行者の分離ゾーンの通行という指導を担当したが、これがまったく大変である。
確かに、路面には自転車マークまで印されているが、信号が「青」に変われば、歩行者も、自転車も少しでも近道しようと気忙しく、斜めに突っ切って、入り乱れて思い思いの方向に進む有様である。
指導をして、殆んどの学生も一般人も、「分かりました」という顔つきをするが、「この急ぐ時にそこまで言うなよ」という気配が態度に隠されている。
イヤーホーンで音楽を聴きながら通学してくる学生は、こちらが何を訴えているのかもお構いなく、自転車のスピードを緩めることなくさっと通り抜けるのだ。
私自身、自転車通行ゾーンのあることはよく承知しているが、いつも規則どおり走行しているかと言われれば「ゴメンナサイ」と言わなければならない。
ちょうどその日、歯医者に行くのに自転車に乗ったが、努めてゾーンを守る走行を試みたが、みんなが規則を守っているわけではないので、状況によってはかえって危険なこともあると感じた。
世の中には、憲法に始まり、色々な規則までが定められるが、全ての人がそれぞれの法律・規則を知っているわけでもなく、理解していることも少ないので、法・規則に基づく行動が決まってとられることがない。
法・規則を悪用して抜け駆けで得する人達がいることをニュースで知れば、人は決め事を軽んじてしまいかねない。生活における規則、慣習レベルなどは、まず「私の勝手でしょ」と言う戦後の個人主義、自由主義の誤用の下に吹き飛んでしまうのだろう。
色々な時代、人は色々な規則を作り、そのためにかえって不都合を感じざるを得ないことも多かった。規制緩和は今の政治テーマでもあるが、自転車ゾーンの通行と言うちょっとしたことでさえ、問題ありで、人間が穏やかに安全に暮らすための智恵は、出し合わねばならないが、安易な規則化は守れないことによる苛立ちを喚起し、ことの判断基準から慈愛を失わせ、人間の持つ「業」に押し切られてしまう。
決め事をしなければ生きられず、その呪縛から逃れたい願望も永遠であるのか。
まあ、交通規則は守らねば、事故死につながると言う分かり易さがあるので、努めて遵守する人達が街中を闊歩することを祈りたい。
097. 気さくな人、気難しい人
世の中には気さくな人、気難しい人がいる。
しかし、はじめから天性気さくな人なのか、その老婦人は、電車に乗り込んで、ぽんと座席に座るや否や隣の夫人に「今日は暖かね。」と声を掛け、相手がうなずく間もなく「出かけにシャツを一枚脱いできたの。夕方には寒くなるかも知れないけど。」というと昼下がりの比較的ガランとした電車の中で、今乗り込んできた駅周辺に住まいがあるのだろう。そこに移り住んだ事情や、不動産の値段の話。
山陰の香住にカニを食べに行く旅行の話。主人に死なれ、一人息子の嫁もなくなったため、孫も居ないという身の上話。御主人のガンの発見が遅かったこと。
話し相手に選ばれた婦人も、時々相槌をうまい具合に打ってあげているのか話は途切れることなく、周りのちらほら乗客も老婦人の人生物語を走行車音の中で、途切れ途切れに聞かされている。黒の帽子、黒のパンタロンスーツ、黒のコート、指に真珠とダイヤの指輪、もう片方に金の印鑑タイプの指輪。小さめのキャスター付きバッグをもって手振り身振り、めがねの奥で光る目が、「人生色々あるのよ。」と隣の婦人に力強く迫っている。
終着の京都駅に着くまでの僅か15分ばかりの間に、老婦人は自分の心の中にあった思いも込めてどっと何かを吐き出したような気がする。なぜかその時、気さくな人は愛情いっぱいを知った寂しがりなのかなとふっと思った。
私の孫も、私の母も気さくな人タイプである。先日も孫は、信号待ちの間に中年のおばさんに何か話しかけたらしく、後から小さいほうの孫と追いついたときに、「気さくなお子さんですね」といわれた。 自販機の飲料交換の青年にも話しかけ、気に入られたのかカルピスをただでもらった事もある。
誰もが自分のことを受け止めてくれると信じきっているのだろうか。
大人になっても気さくな性格を持ち続けられるだろうか。
孫に思いがけず話しかけられた人が、なんとなく和やかな笑顔になる様を何度となく見てきたが、電車の老婦人もまた現代失われてしまった人の絆の結び方をあっけらかんと示していたのかとも思うのだ。
外国人のようにハグすることも、挨拶代わりに抱き合うこと、キスすることも少ない日本人にとって、気さくな人柄の表現は気軽な挨拶、共感できることの瞬時の発見とメッセージの伝達能力を身につけることから始まるのではないかとおもう。
共感できることの瞬時の発見は、愛情に満ちた世界で育まれるとも考える。子供の時にこそ、その感性の基盤が芽生えるのだから、子育ては実に重要な瞬間、瞬間である。
気さくな人と気難しい人は対極にあるのではなく、気難しい人は後天的な環境、学習によって共感できることの発見が論理的になりすぎるため表現の機会を失いやすい人とも言える。
気さくさを失わずまわりを眺め感じてみよう。今まで見知らぬ人が身近な人になるかも知れない。一期一会の連鎖の世界平和さえイメージできるかもしれない。
098. 生活の先を読む
今の日本、いや世界中で明日を、これからの生活の先を読むには難しい状況がいたるところで垣間見える。そんなに振りかぶらなくても一寸先は闇、いつの時代も人の行く末は分からないのだが、こと、住まいづくりにおいて、生活シナリオを描き、出来るだけ長きに渡って快適に対応してくれる住まいづくりを心掛けましょうと提唱してきたが、30代、結婚間もない若い施主の方と住まいづくりコラボをしていると、果たして自分もあの頃、それほど生活の先を読めていたのかと、同じ迷い道に共感してしまう。
子供だって果たして希望通り一姫二太郎なんて具合に生まれてくれるものやら、夫婦の仕事、社会との関わり方もどの様に変転するのか。時代の変化がすさまじく早く、大きなうねりと言うより日常の文明生活にも振り回される現代人にとって生活の先を具体的にイメージすることは本当に困難なことと言える。
思わず、テレビや雑誌などメデイアのトレンド特集に思いを重ねてしまうのも一つの割り切り方でもあろう。しかし、メデイアとて、これからの日本人の生活をどれほど先読みできるのだろうか。
先日、テレビ放映された映画「やさしい刺繍」の主人公は80歳になってスイスの小さな山村で主人に先立たれた落胆の日々、ちょっとしたキッカケから若い頃に夢に描いていた下着制作を始め、主人と共にやってきた雑貨店をランジェリーショップに変えてしまう。
保守的な村人からはひんしゅくを買い、牧師の息子からも妨害を受けるが、その地域の伝統的刺繍を下着にくわえることでインターネットでも売れ始め、大成功。80歳の老婆の生活は仲間の人たちと共に輝くものになると言うストーリ。夢を持ち、諦めなければ、自分の願う生活空間が手に入ると言うストーリにはおおいに心うれしくさせられた。
現実ばかりにとらわれていると、本当に先を読むことは難しいが、自らが主体的に夢を描き、その実現のための手立てを少しでも住いの中に取り入れておけば、それなりに悔いのない納得の住まいづくりが出来るのではないか。
生活シナリオには想像たくましい虚構の企て、虚像の自分を何パーセントか閉じ込めることが必要である。現実には先の読めない時代であればこそ、住まいづくりにおいては、先の夢を読まなければならない。建築家はコラボの作業の中で、大いに夢を虚構を語る役割を担う事になるのだろうか。
099. 晴れとケのけじめ
近年は年末の慌ただしい日常生活から、元旦に一転して晴れやかな改まった時を実感するということが希薄になった。以前のように、元旦はお店も閉まっている。ほとんどの人は盆と正月というくらい、休みの人が多く、国中の人たちが日常活動をとめて、けじめの時を迎えるという風潮がすたれてきた。
わざわざおせち料理を作るまでもなく、元旦から色々なお店が開いているのだから特別に構えることもないのだろう。
初参りに出かけても、デートのカップル。女性は多分、親御さんが思い入れをしたのだろう、着物姿の晴れ着であるのに、相方の男性は、ヨレヨレのジャンパーにジーンズ、髪の毛もぼさぼさ。常着と晴れ着の道行はまさに今の日本文化の混沌さを感じさせる。
わきまえたカジュアルさではなく、知性を放棄したルーズさは気分が悪い。
今年も我が家では元旦の朝は、二人の息子夫婦、二人の孫が一同に会して女房殿手作りのおせち、二人の嫁が其々一品の料理を持ち寄って新年を祝った。長男が三脚をたて、自動シャッターで記念撮影。小梅と昆布の入った福茶のあと屠蘇で献杯。
孫もわけなく神妙に「おめでとうございます」と言って、白味噌じたての雑煮を「茶色じゃないよ、ちょっと甘い。」などといいながら味わっている。
女房が、ゴマメや数の子、黒豆、たたきごぼう、蓮根などを食べる意味を孫に説明しているが、どこまで通じたことやら。
殊更、何がどうと言わないまでも、いつもと違う食生活、作法を経験することで、孫にも生活のあり様を考える気風を身に付けさせたいと思う。
息子たちが結婚した当時数年は、そろって信州の別荘で正月を迎えたのが習慣化して、こうして元旦は朝から皆が出向いてきて共に新年を祝うのが我が家の習いになったが、そろそろ各自の家庭の正月料理も手作りしてはどうかと女房は提案して、嫁たちに手始めに一品を持ってきてもらったのだが、ローストビーフと胡麻団子が加わって、いつものおせちに変化のきざし。 新しい我が家のハレとケの生活習慣がどの様に展開するかは分からないが、次世代にも、こうした生活習慣の原点を忘れないでほしいと思う。
厳しい日本経済事情の中で、サービス業の方々などの祝祭日関係なしの就労はやむをえないのかもいのかもしれないが、其々の家庭の晴れの生活空間がなし崩しに消滅していくのは寂しい限りでもある。
100. 景観・街並との調和
日本において、建築のシステム、資材がさほど多様でなかった戦前までは、たとえ成り行きで個々の建築が集積した結果の街並も、それはそれなりに美しさを持っていた。
江戸時代からの木割り術なども木造建築に秘められた規律感をもたらしていたと言える。
戦後、都市化の流れの中で人々の活動が都市に集中し始めると、経済活動の発展は時間や空間の多様な使い方を追い求め、いつか都市におけるインフラ、住宅や一般建築をはじめとする文明・文化の構築物は景観という概念ではコントロールを失ってしまった。
ゴミゴミした街、都市などは人々の営みの発展途上の証のように受け止められていた。しかし、無節操な都市化、建築行為は日々の生活の利便性や、安全・安心、健康、地域コミュニテイなど本来求められるべき生活基盤の根源を脅かし始め、結果として犯罪などマイナス事象も多発することとなった。
先進国としてこれではいけないと言うのか、景観法も定められ、環境・景観に対して気配りが必要であるという社会的コンセンサスがたちあがった。
ヨーロッパの都市を旅すると、新市街、旧市街と言うように歴史的な景観を持つ町並みとが対極的に計画された例を多く見るが、日本ではせいぜい歴史的保存地区程度の空間構成規制くらいしかないので、景観破壊のエネルギーの方が大きいといえる。又、開発や建築行為には経済活動が伴うため利害関係の対立もあり、建築協定などもなかなかスムーズにまとまりにくいのが現状である。
個人住宅においても、施主の方が計画当初から近隣環境、景観の配慮を第1に上げられることはまずありえず、住まい手の趣味や希望をむしろ法規制に如何に対応させるか苦労することが多い。
個々の建物が仮に景観を意識してデザインしても、隣地の建物が同時に同様の条件で建築されるわけではないので、周りとの調和を考えることの努力や配慮はその評価を未来にしか確認できない。
つまり、未来の街並をイメージできる「力」を身につける、あるいは了解しやすい景観コンセプトの一般化を行うことが必要であろう。
最近の京都の町屋再生プロジェクトや開発行為も見ても時流に乗った経済活動に過ぎないものが多い。
「京都の土地は京都人以外に売るな。」「地上権、空中権だけ売ればよい。」と痛烈発言が出るくらい、平安京の心をトータルに長い目で見据えた景観デザインが望まれる。
東京資本、中国資本といわれる魔の手が率先して日本の文化遺産・京都の平和・安寧の「美」を理解して日本人共有の調和の精神を京都人と共に再構築することも現実的な方法、めざす一歩であるかもしれない。
廣瀬 滋著
私の思考散歩・生活雑感 ぽつり草々 081〜090
081. ゲレンデにて
暖冬で雪が降るのかと心配していたが、年末列島に雪が降り、今年も雪景色の白馬乗鞍の山荘で正月を迎えることが出来た。
元旦から小雪ちらつくゲレンデに、新年、初すべりを楽しんだ。なんと、初めてマスター用のリフト券が発売されている。マスター券といえば技を極めた人という意味ではなく、50歳以上のスキーヤのための約37%割引リフト券である。
スポーツにシニヤーやシルバーはなじまないとの気配りも感じ取れる。スキー人口は下降の一途をたどり、ゲレンデも往年の賑わいが無い。此処にも高齢化が急速に進む日本の現状が感じられる。割引券を発行して、かってスキーを楽しんだ人々を呼び戻したいのだろうか。60歳を超えた私にしてみれば、同じ発行するならもっと早く発行してくれれば良かったのにとケチな想いに一瞬とらわれたが、割安な一日リフト券で存分に滑れるという満足感はなかなかうれしい。
リフトで相乗りになった男性が、「ボードが増えましたね。私は7年ぶりのスキーで、すっかり体力が落ちて、息切れがして大変です。」と話しかけてきた。聞けばかろうじてまだ40代にしがみついているという。「私は60歳を超えました。シーズンはじめはやっぱり一気にゲレンデを下りきれませんね。」「いや、60代になってもスキーが出来るなんて、憧れですよ。そうなりたいと願ってるんですが。」山頂に着くまでマスター同志の会話をしながら、眼下に広がる雪山を眺めると、若かりし頃、子供とその友達数人を引き連れて、あちこちゲレンデをツァーした日々も懐かしくオーバラップ。
同じゲレンデに30年以上来ていると、周りの施設の変化は勿論のこと、営業をやめてしまった喫茶店のマスターの行方、長い間顔見知りだったリフト会社の経営者の息子、色々世話になった村人・友人とのたくさんの思い出が雪をかぶった木立の間に幾重にもよみがえってくる。「やっぱり年を重ねたな。」という実感がとても深い。さぁ、いくぞ。一気に斜面を滑降すれば、何もかも考えなしの爽快感。
転びまくった初心者時代の充満感から、ボーゲン、クリスチャニア、パラレル、ウエーデルなど技術の習得に一喜一憂した感慨も今は無く、雪面に我を問うという、ほとんど答えの解らない時空の中で、今年もスキーが楽しめたという「ほっと」したひと時が静かにゲレンデに溶けて流れる。
長い間、ほとんど新年をゲレンデでのひと滑りで重ねてきたが、真っ白な雪景色は、「いつも原点に戻る勇気を持とう」という私の信条のひとつを確認するのにふさわしい背景でもある。
082. 花いっぱい運動
私の住んでいる京都・下京区内でも、街づくりの基本計画の中に「みんなで支え合うやすらぎのまち構想」というテーマがあり、その中で区民による花いっぱい運動やまちの美化運動に取り組もうという課題が提示されている。
ここ2,3年、行政の少ない予算をもとに一時的、ごく一部の地域にフラワーポットを並べると言う表面的な活動が、町衆フォーラムのメンバーによって展開されたが、コミュニテイの育成と言う点からも効果をあげているとはいえない。
このたび、町会長、役員の賛同の下、身近な私の住む町内(23世帯)の方になんとなく薄れてしまった近隣のコミュニテイを再生することもかねて、「みんなで企画した花いっぱい活動をしませんか。」と言う呼びかけをしてみた。
ただ花をそれぞれの家の前に植栽すると言うのではなく、たとえば、今年の秋は選別した色の組み合わせの花を咲かせると言う方法で、皆のメッセージを表現できること、花を咲かせることや飾ることの過程を通じて、近隣のお年より世帯も含め、お互いのコミュニケーションの機会をより自然に多く持てるようにする事など,そして、もし私たちの町内が、花いっぱい活動でより美しくなれば、やがて、お隣の町内もより意識されたかたちで家の前の植栽などが整備され、皆で町の美化に取り組もうという共有意識が芽生えるのではないかというような趣旨書を回覧した。
その後、参加の意向や、方法について簡単なアンケートを実施した結果、1世帯以外は賛成と言う結果で前向きに取り組む方向になった。
しかし、よく説明を聞きたいという方、園芸には知識が無いので心配という方もあり、継続性や成果を考えると活動開始前に充分話し合う場を持たなければならない。事のはじめを慎重にしなければならないと云う思いに駆られる。
幸い町会費に少しゆとりのあることと、町内に古くからの花屋さんがあり、今年の町会長の奥さんが花屋さんの娘さんであることが、この提案をしたキッカケでもあるが、2,3人の園芸愛好家の奥さんが居られることがわかった事も、計画を実行するのには好条件。
都会の道端での園芸がどの様な町の美化に役立ち、また花いっぱい活動がどんなコミュニテイの創出に繋がるのか、身近な、ささやかな試みではあるが、人々の連携の原点を確かめてみたいと思う。
また、楽しみながら、色々な花のありようを学ぶことで「花」の持つ美しき可能性を味わい知る機会にしたい。勝手に「多忙」を作り出していると家人に笑われながら、町内会の皆さんとの地縁を実感できることを願っている。
083. コミュニケーションデザイン
私が高校生のころ、これからはデザインの時代だと美術部の先輩が言うのをなんとなく直感的に信じて、自分の好きなことを生かしながら社会に役立つことをしたいと今日に至る人生の道を歩むことになった。
この40年余り、デザインの領域は拡大し続けてきた。はじめは最も理解しやすいかたちで、ファッションデザインとともにデザインは流行というような軽い受け止め方をされ、やがて、ビジュアルデザインやプロダクトデザインが成長する資本主義経済活動の一翼を担うことになった。
色や形、質感、それらのプロポーション、バランスのセンスがデザイン性と同義に捉えられていたが、日本の経済成長とともに、建築、インテリアの分野にもデザイン性が意識され出すと、単なる美意識上の問題より、生活、時系列を踏まえた人間との関係、環境との関係が重視されるようになった。
実務においても、デザインはハンドワークの時代からヘッドワークの時代へと変転した。パソコンとデザイン関連ソフトの普及によってさらに一段と拍車がかかり、いまやWebデザインも花盛りである。アナログデザインワークからデジタルデザインワークと捕らえたほうがわかり易いかもしれない。
そして,今、最も求められるデザイン領域は人類の平穏のため、平和のため、のぞましい人間性の再構築のためのコミュニケーションデザインではないだろうか。
身近なところでは、家族の関係デザイン、地域コミュニテイのデザイン。
ユニバーサルデザインやサステイナブルデザインというような技術解決型思考ではない、もっと感性の交流が図られ、知らず知らずのうちに倫理的ルールが育まれ、生活習慣行為や文化が生まれる仕組み、システムのデザイン回路が望まれる。
人と人の間に、あらゆるチャンネル、メデイアを通して出会い、接触のチャンスを生み出すことが求められる。具体的な「場」、「時」の設定、その演出、コミュニケーションデザインが必要となる。
考えるに、過去から、「祭り」や宗教、農漁業などの生業の共同作業などが、コミュニケーションデザインを立派に成育してきたと思うが、グローバル、情報ネット社会・時代においては、あまりに複雑に個別のコミュニケーションデザインが複層・混合したために、もともとの美しい人間の知恵のデザイン結晶は輝きを失なってしまった。
一方、もはや後戻りのできないデジタル時代のコミュニケーションデザインは、すべての人類が共通のOSで動くロボットのようになった時、初めて究極の姿を現すのだろうか。そんなこんなに思いをめぐらせながら、アナログデザインの極上の住宅設計手法を模索している。
084. 継続と転換(改革)
「継続は力なり」と言われるように、物事を継続して積み重ねることは、結果として大きな成果をもたらすことは誰しも知見したことがあろう。
継続の評価は、継続がそれなりのエネルギーを注ぐ努力行為が伴うので、大概は諦めたり、挫折して成果を残すことがないことへの戒めを含むといえる。
一人の人生に於いても、企業、サークル活動にも何かを継続することの大切さは自明の体験としてそれぞれ意識される。「三日坊主」は継続に対する自嘲の念と言える。
そんなに短期間に成果が上がらなくても、我慢強く、時には意地になってひとつの行為を、信念を持って貫くことは、やがてそのことに喜びを感じたり、その流れの中で起こりうる色々な事象を体感・体得することによって、自身の、企業やサークルの歴史を刻む安らぎを知ることが出来る。
それは自己存在の確認でもある。継続行為・活動の中で、色々な人に出会うことによって、定点観測にも似て、多くのことが客観的に見えてくるのもなかなかのメリットである。
中でも他に対する奉仕の精神の継続は、時にはお節介になったり、誤解を生むこともあるが、私の継続ごとの原動力である。
これは自己のパワーアップ、自らの成果に集中力を持たない相対的なもので、「継続は力なり」と言うものの、目覚しい評価を得られないことも多い。奉仕精神、活動の継続は、生きていることへの自己確認と死に至る瞬間へのイメージが描ける時、初めて納得出来るものかもしれない。
気づかずに悪癖や悪行を継続してはいないか。転換を図り、新しい局面を切り開くことも人生における「力」である。「原点に返る勇気を」を座右の銘に生活を駆け抜けているが、これはプラス思考のひとつであり、結構、ズブトイ楽天家でもある自覚がなせる処世の継続かもしれない。
2009年雇用問題も深刻な時節、本当の意味でサラリーマン経験もなく、基本的に転職経験のない私は、家族を養い生き抜くために、多様な継続、多様な転換をいつもパラレルに行ってきたと言える。ゲリラ的生き方。「怖いもんて、ないよ。」
いやぁーほんと、毎日が継続と転換。「鬼は外、福は内。」
085. 出会い川と心の旅路
人生、今まで多くの人々と出会ってきた。出会いを思い出せる人とは、出会いが一瞬であったとしても印象に残る人、色々な出来事も含めて記憶に残る人、心深く私情に漂い続ける人である。
その時々には思いもしなかったが、振り返れば、「心の旅路」といえば大袈裟かもしれないが、自分の感受性や考え方、生き方・生活のあり様に大きな影響を受けたのは、川の流れのような多くの人々との出会いであったと思える。
激流であり、清流であり、それぞれの人が年齢や職業、性別、などに関係なく、私の知らなかったいろいろな世界を感じさせ、考えさせてくれた。
時に、1対1の密度の高い出会いは、自身の未熟さを思い知る修練の場でもあった。ガキ大将で自分中心だった幼少の頃を思い出すと恥ずかしが、初めて恋をして、自分以外の他人・相手の存在、心を実感したときの大人への入り口から、出会い川は身近に意識されるようになった。
なるべく身構えることなく、自身を白紙状態にして、いろいろな人と出会うことで、その出会いの香さえも大切にしたいと心掛けるが、そうした姿勢を持とうとすること自体が心の旅路を曇らせる時もある。
住宅設計において、住まい手の生活シナリオを共に思い描く作業をしながら、クライアントの出会い川と心の旅路を垣間見るとき、求める生活空間がフラッシュする。
十人十色のこだわり、自分流暮らし、心の旅路が見えてこそ、住空間の具体化が図れるのだが、実際にはなかなか心の旅路のコラボレーションは、それが「今」という生々しい時間の中では正体をつかみかねる。
しかも、最近の携帯電話社会に育つ人々には、きっと今までとは別の出会い川が流れ始めているので、自ら傷つき、葛藤しながら味わい深い旅路が思い出として残ることもないのではないだろうか。
そんな時、人々は住空間に何を求めるのだろうか。地球環境の保全も重要課題だが、人々の出会い川が血も涙も笑いも忘れ去ってしまうことのない様にと願う。
住宅設計の楽しさのためにも。
086. 深夜のラジオ便
3年ほど前の、なかなか寝付けなかった夜、明け方の4時前、枕元においておいたポケットラジオにスイッチを入れた時、「NHK深夜のラジオ便」なる番組に出会った。
丁度、ニュースに続いて、「こころのたより」というコーナがはじまり、どこのお寺の僧侶かは忘れてしまったが、人間の生きる道について、いたく感心させられるお話が聞けた。
以来、なんとなく気になって、「日付が変わって午前0時のニュース」というくだりから、世界各地に居住している日本人のホットな話題や、色々な分野の方のナイトエッセー、朗読、演芸、テーマを絞った音楽、日本の歌謡、そして始めに感心した「心の便り」ではその道で色々と研鑽努力された人の体験談が語られるのを聞いている。
時々、イヤーホーンをつけたまま、うとうとと寝込んでしまうことも、(90分のタイマーセット付きラジオ)ふっと気が付いて又、耳を傾けている。
とにかく、あらゆる意味で世界は広い、色々な人生があること、ひたすらに信念を持って努力して生き続けた人が、実に美しいと感動させる人生の軌跡を残されていることを知らされる。
又、南半球ブラジルからの便りをきいていると、寒い寒いと震えている日本と反対に、真夏のクリスマスやカーニバルの様子が伝えられ、灼熱の砂浜、波の音などは想像するだけで暖まる。
時々リスナーからの便りが紹介されるが、日本の北から南、高齢者時代、全国には夜に眠れぬ人が多いのか、この番組を聴いている人が結構多いのに驚かされる。
日々交代でアンカーを務める方々も、すでにNHKの一線を退いたベテランアナたちで、そのリーデイングは安心感が漂い、人気がある。
書店に行って、深夜便の冊子をパラパラとめくってみると、ああ、あの人、こんな顔してるんだとか、この人なら以前テレビでも見たぞ等ラジオの音声の印象が新しい。
週に一度ある浜田さんと云う料理の先生は身近な材料を生かしたシンプルなメニューを大変可愛い声で指導される。音声だけではあるが、その語り口に引き込まれ、翌日には女房にかわって、その一品を私が手作りすることも2度、3度。
もし、眠れぬ夜があったら、0時前後の海外からのたより、ナイトエッセー、4時からの心のたよりがお薦め。
歌謡番組や、音楽、演芸は、人によっては好き嫌いがある上、他のラジオ局でも類似内容がある。多分NHKでは深夜トラック便を走らせている方や、多様なリスナーにも配慮しているのだろう。すっかり、うとうと寝が習慣化してしまった。
087. 運命の一瞬
人生を振り返ってみると、もし、あの時こうしていたらという決断、決心の一瞬は誰にでもあるだろう。それほど自己の意思に因らないまでも、たまたま居合わせた、偶然の出会い、ちょっとした思いつき等も運命というのか、人の人生の流れを大きく変える。
また、自らでは本当にどうすることもできない運命の一瞬。ニュースで知る事故や事件のように、ほんとうにもし数秒、そこを早く通り過ぎていたら災難に巻き込まれなかったであろうにと、なんとも不思議な一瞬、運命という閃光を感じさせられる。
日々の平凡な生活の流れにおいては、運命はこれといって音を立てるでもなく、姿を潜めているが、(社会の常識に合わせて)幸せなこと、おめでたいことが起こった時や、逆に病魔に倒れたり災難にあったりすると、途端に運命は巨大な力で「運命、ここにあり」と躍り出てくる。
その一瞬に至り、その因縁を振り返って反省したり、さらに乗り越えて自らの運命に立ち向かおうと自身を鼓舞したりする。
運命に翻弄されて、波乱万丈の人生を送る人や、数奇な運命といわれる稀なる一瞬を積み重ねて生命を終える人など、様々である。
しかし、考えてみるに、平凡と思える日々の流れの中では、自動的「運命の一瞬」がぐさりと我が身に突き刺さることがないとするなら、お金持ちになりたいとか、有名になりたいとか、出世をしたいとか、我欲を出さなければよいとも思えるが、あまりにも刺激のない人生に我慢できないのが文明人である。
太平洋の孤島で一生同じような生活を自然と共に暮らす人たちのドキュメンタリーを見ると、運命はやすらぎそのものだと思える。
しかし、人類がどうしょうもない天災のごとき他動的「運命の一瞬」に遭遇すると、もはや「神」「仏」に祈ることで「運命の一瞬」にさらされた傷を癒そうとする。
日頃から、「運命の一瞬」の力の凄みを知る人たちは、心に「神」を棲まわせて、その閃光に耐える身支度をしている。
私は今日まで、幾たびか楽天的に「運命の一瞬」をやり過ごしてきたように思うが、早くに、弟、父親、祖母(母方)の死に出会いその後も祖父母、祖父、叔母と母親、身近な家族との別れの無常、厳しさ、「運命の一瞬」に立ち会ったことと、小学校から大学まで、その時々に恩師に出会えた有り難さが、大いに運命に耐える力を支えてくれたと思う。
ここまで生きてきて、「何とかなるものだ」と運命の一瞬を振り返りながら、わけなく、誰にともなく感謝の献杯。無事の一瞬。
088. 春の息吹
日本の春は、庭木も山々の木々もいっせいに芽吹く。「サクラ咲いたか、まだかいな。」
私宅のムクゲの新芽が葉っぱに姿を整えるのをみていると、春はことさらに生きていることが実感される時である。
先日、清水寺、成就院で森清範貫主の法話を聞く機会に恵まれたが、先祖代々、脈々と流れる「縦の流れの命」を心することの大切さを話された。
35億年前、地球上に生物が誕生して以来、花や草木、動物、虫、魚、ありとあらゆる生物が、全てひとつの生命から生まれてきたことをイメージすると、確かに生きているというより生かされているという捉え方のほうが適切だと思われる。
十数年前、人間の中には、ゴキブリの持つ遺伝子さえも含む、多種の遺伝子が組み込まれていて、しかも単純な遺伝子しか持たない大腸菌のような生き物と共生することで生命が維持されているという話しを聞いた時以来、なるべく謙虚に感謝して生きることを心がけてきたつもりではあるが、命の営みを顕著に感じる春は、本当に生きることの意味をより考えさせられる。
人生の結果=能力×熱意(努力)×考え方(生き方)という人もいるが、授かった「命」を大切に生きるかという点では、生き方はその決め手になるのではないだろうか。
生き方というのは、人生において色々な局面、特に艱難辛苦に出くわした時、どのような判断を下し、どんな行動・言動をとるかということで示される。
うろたえることなく、適切な決断、行動が取れるためには、自己中心ではなく、自らは生かされていると言う観点にどれだけ身をおけるかということなのだろうか。20代の頃、究極のエゴイストに憧れていたが、今やっとその本当の姿が理解できるような気がしている。日々の設計やデザインの仕事の中では、やはりクライアント、オーナとの出会い、コミュニケーション、コラボレーションの流れの中に、どれだけ互いの存在、家族、「命」のあり様を感じ取りながら、もの造りが出来るかということかと思うが、地域社会活動も含め、より多くの人々との出会いの中で、「命」のすばらしさを確かめ合えれば良い。
そんなことを、切に思わせる春の息吹である。
089. 京都新光悦村
江戸時代初期、本阿弥光悦によって京都洛北・鷹ケ峰の地に形成された「光悦村」には、様々な分野の工人が移り住み、交流機会が創出され、次々と新しい技や表現が生み出されて行ったと言われています。
日本の美術や工芸の発展に大きく貢献した、この「光悦村」の精神を継承し、これからの産業やものづくりのあり方を示す新しいスタイルの産業拠点が「京都新光悦村」です。(京都新光悦村パンフレットから)
先日、この事業の拠点の造成工事がほぼ完成したということで、現地見学会に参加した。
21世紀の京都の新たな生活文化の創造と産業の活性化を目指す新産業拠点というコンセプトは従来の産業団地造りと比べ、最大で約1ha,最小は300㎡と言う区画割の小ささ、里山をイメージさせる景観作りなどにその基本姿勢がうかがわれた。
近くにある京都伝統工芸専門学校が、卒業生を中心とした人材の更なる産業への貢献を目指してインキュベーション的な施設を建設することが決まっているそうだが、他の参加企業の実質的な選定基準、その連携・全体運営のさせ方などは明確ではなく、光悦というすばらしいリーダによって推進された光悦村のように成果を出すためには、何か近代産業と伝統産業のコラボレーション、異業種の技術的コラボレーションなどを創造的に運営したり、調整しながら成果に結びつけるためのプロジューサ的人材・組織を考案し、運用しなければ、せっかくの新しい産業拠点も形骸化してしまうのではないかと心配がよぎる。
行政は拠点の造成工事を行い、分譲してしまえば、取りあえずこの事業にけりをつけられるのだろうが、税金の無駄使いに終わらないためには、むしろこれからの「京都新光悦村」の実行にこそ、何かの形で積極的に力添えをするべきである。
私が現地見学会に参加したのも、関西デザインオフィスユニオン京都本部のメンバーとして、何か役立つことが出来るかを見極めるためである。あるNPOが、今後の運営をリードしようとされているとも聞くが、新しいビジネス創造と光悦ブランドの産業化という現実の命題を考えると、よりダイナミックな開かれた新光悦村コミュニテイ育成のプログラム、タイムスケジュールの作成、総括するブランド戦略の創造が求められる。
長年、デザイン活動を通じてこうしたことに経験をつんできたデザインオフィスユニオンのメンバーが助力できることは少なくないと感じた。また、その活動プロセスに観光・集客、教育・学習など南丹市の地域振興に結びつけるというコンセプトが並存されることで、光悦の根本精神が今の時代に、よりよく理解され、少しでも実業として芽吹くことが期待される。世界に発信できる新・光悦ブランドの誕生を夢見よう。
090. 通勤電車
時々大阪で会議があったりすると、いわゆる通勤時間、ラッシュ時にJR新快速列車を利用することがある。つい最近、確かに座席に坐ることが出来ない状況であるが、ぼんやりと立って運ばれていると、昔のラッシュ時とはずいぶん様相が違うことに気が付いた。
昭和40年代、私が小田急線を利用していたときの身動きも出来ず、斜めになったら、次のゆれ戻しでもない限り、そのままの姿で荷物のごとく運ばれていた苦痛のラッシュ時間。
あるときは、中央線新宿から御茶ノ水の途中で、ドァに押し付けられていた肩に一瞬凄い圧力がかかり、強化ガラスのはずのドァのガラスが、びしっと言う音と共にひび割れた思い出は忘れることが出来ない。
今は、冷房もよく利いて、少し隙間もあり、たいてい携帯電話でメールを無線機を打電するように打ち続けている人や、社内テストでもあるのかパソコンのマニュアルを受験勉強風に読み込んでいる人や、I-potやミニデイスクで音楽の世界に嵌っている人たち、マンガを読んでいる人たち、疲れきった人達がわずかな仮眠?の息使いをしていたりする。
勤務時間帯も多様になり、以前のように誰も彼もが同じ流れにがむしゃらに乗っかっているというイメージはない。たまたま乗り合わせ、それぞれが自分の生活をしている瞬間の集まりである。
これからは少子化で、日本の人口は減り続け、乗客数も斬減すると鉄道会社幹部の心配顔がTVに映し出されていたのも最近のことだ。
あの凄いラッシュ時が昔のことと思えるのに、ここ数年、痴漢対策として女性専用車両が運行されるのは、今の通勤電車にかえって痴漢をする余裕や隙間が出来たからか、運輸サービスの質的改善がやっとここまで気配りをするようになったのだろうか。
外国のビュフェ付き通勤電車と、そこで和みながら家路に着く乗客を知ると、生活が途切れなく人間らしさで輝いているようでうれしくなる。
やがて、通勤電車、ラッシュはどの様な有様になるのだろう。駅のホームに吐き出される時、今も昔もまだまだ荷物扱い、単に運ばれた「一人という荷物」を感じさせられるのは寂しい。
廣瀬 滋著
私の思考散歩・生活雑感 ぽつり草々 071〜080
071. 職人でありたい
20年近く高校時代からの友達が経営するセンサー関連の会社に関わりがあるのだが、3年前、その会社の集まりで、新たに入社した30歳前後の中国人の営業担当者と話す機会があったが、「あなたは日本人についてどう思いますか。」と尋ねたら、すかさず「日本人は基本的に皆、職人ですね。」という予期せぬ答えが返ってきた。
中国人の彼は、親の仕事を受け継ごうとも考えないし、その時々に一番合理的、経済的な仕事を選択し努力する。ひとつのことにこだわらない。日本人は、何かとプライドやしがらみに縛られ、細部にこだわり、まさに「職人」ですね。という意味の補足説明があった。「日本人は職人か。」と彼の仕事に関する経験談も聞きながら、その時、何かユダヤ人や中国人との違いを生々しく教えられた気がしていた。
時は流れ、最近、韓国の知人と建築の共同プロジェクトについて話をしたが、言語の壁はともかく、大局的イメージに於いては大いにこちらの考えに賛同し、協力し合いましょうということになるのだが、ことの運び方になると何となくかみ合わないものを感じさせられる。
韓国でも40才台以下のハングル世代はアメリカナイズした合理的、論理的ものの考え方を備えているとのことで、日本人が今グローバルスタンダードなどと、うろたえているが、中国人も韓国人もはるかに先行して国際人である。過酷な競争原理にも精神的に対応出きる強さを備えている。
しかし、私は、あること、あるものを、より経済的、合理的に生産したり対処して、競争に打ち勝つことが出きるとしても、創造的なものは、長い作業や技術の積み重ねの中から涌き出るもので、今日の日本を支える多くの先進的技術、ビジネスメニューは、いずれも職人的粘り強さ、一途な積み重ねから生まれてきた事実があり、日本が小さな島国でありながら、今日経済大国として存在できているのも、創造的具体化の能力、つまり「職人魂」のお蔭ではないかと思う。
新しい発見や技術が職人的日常作業の中から生まれるので、とかく華々しさがなく、日本人は創造的でないというような誤解があるが、日本人は創造的民族である。日本人から「職人魂」がなくなれば日本人の「心」は消滅すると思う。
構造改革の掛け声のもと、過激な競争社会を築き、経済的に勝ち残れても、日本人の未来の楽しさはない。誇れる文化を創り出すのは「職人魂」あふれた日本人である。やみくもにグローバルスタンダードに合わせるのではなく、なんとか本来の日本人が生き残れるバランスの取れた舵取りを日本の政治に期待する。
そのために、一人一人がそれぞれの生活の中で「職人魂」を失わなければ、日本人は日本人として輝くことが出来る。「日本人は職人」で大いに結構。私は日々の仕事を通じて住まいづくりの「職人」でありたいと思う。
072. 小さな庭(生活と緑)
小さな北の裏庭に植えた金木犀が、今年も申し訳程度の花をつけた。日当たりが悪いのを承知ではあったが、冬でも窓からミドリが見えてほしいと常緑樹で、しかも花の匂いが季節を知らせてくれると金木犀を選んだのだが、毎年、かすかな香りしかない。
二年の間に50センチ位は大きくなって2.5メートルくらいにはなったが、西陽がやっと上の部分1メートル位にあたるだけの気の毒な環境である。
ほとんど毎日仕事をしながら眺めているので、ことのほか葉っぱの色艶も気になる。脇に植えたアオキは北の庭向きなだけに、勢いもあってなんとなく安心であるが、もっと花を咲かせて良い金木犀には僕の勝手な選択で「ごめんな」と何時も謝っている。
それでも、もう少し高くなったら、急に日射量が多くなって、ぐんぐんパワーアップ、いっぱいの花をつけてくれるのではないかと金木犀と僕のハッピーエンドを願っている。 京都の町屋で育つた僕は、ことの他中庭、坪庭、裏庭には色々な思い出がある。一時期、住んだ桂坂の郊外住宅では、一日中、陽のあたる南の庭で芝刈りをしたり、色々な草花を育てたり、勝手に鳥が運んできたグミの種から、苗木が出現して驚いたり、花ミズキの種を冷蔵庫に保管して翌春それを栽培したり、拾ってきたドングリから苗木を多数栽培したりと、もっぱらアクテイブなかかわりであつた。
中庭、坪庭、裏庭は違う。それも小さな庭ほど生活の中で静かな対話、心の流れを受け止めてくれる。ベランダや室内では観葉植物への程よい水遣りに心配りながら都会生活の言い訳をしている。
夏の信州の別荘では自然の勢いを雑草に感じながら緑の照り返しに包まれて心安らぐ。植物は僕の生活になくてはならないものである。住まいと自然等と振りかぶらなくても、生活の中での植物、「緑」との関係を楽しむシナリオを描くだけでも住まいはもっと豊かになるのではないか。
後年,金木犀は、5メータ余りの高さになって、西日を浴びることができるせいか、花をいっぱいつけて、何とも季節の香りを届けてくれている。
073. 応援
テレビでプロ野球、阪神タイガースの野球中継を見ていると、試合の合間にカメラが観客席を捕らえ、ファンの熱い応援の姿がクローズアップされる。
お父さんの膝の上で、同じように虎フアン、アイテムの縦縞シャツを着て小さなメガホンを訳けなく振っている幼子の姿や少年が、贔屓の選手に夢を託して大声で応援している姿は微笑ましい。
まるこい中年の小父さんが本当にうれしそうに拳を突き上げ、応援の王道を貫く姿、茶髪の生きのいい若者男女が色々なプラカードを掲げたり、パフォーマンスをお祭り気分で繰り広げる様は、活気にあふれている。
そばで老夫婦がこの熱気を楽しみつつ、静かにグランドに目線を向けている。もし、街中で会ったとして、きっと澄まし顔で闊歩しているであろう美人が、お目当ての選手名を書いたカードを両手で掲げ、左右にリズミカルに振っているのも昔の球場風景を知るものにとっては新鮮である。
甲子園にはこうした応援気分に膨れ上がる5万人近い老若男女が、それぞれの想いを託しつつ、タイガースというチーム応援に集っている。
この応援の姿は、近頃、経済活性や事業創出に関して言われる「連携」という概念を具現しているのではないかと思わせる。ファンにはタイガースの活躍、優勝という目標、希望が明確にあって、その為に一人一人がチケットを買って経営支援をし、現場に駆けつけそれぞれの出来る事で応援する。ストレス解消の人もあれば、プロの技を学ぶ・楽しむなど、それぞれの目先の利得はあるだろうが、とにかくも大勢の人々がタイガースの応援に集まることが周りの経済効果を高め、タイガースの優勝ということになれば何百億円の経済波及効果があるといわれる。
現実社会では、産学官の連携、地域の連携、企業の連携などが盛んに喧伝されるが、いずれもそれぞれの立場に固執、飛翔できず失敗に終わるケースが多い。
タイガースファンの様な透明な情熱の集積が、もし、地域コミュニテイや町おこしにおいても結集することが出来れば、大抵のことは成功するだろう。
わかりやすい「夢」、夢に向っての楽しい共同体験と学習が程よく出来るコラボレーションシステムの創造は、タイガースファンのラッキーセブンに宙を舞うカラー風船の中に隠されているのだろうか。
これからのデザイナーはその秘密を明確にする役割を担っているのかもしれない。
074. 「やってみなければ判らない」
私達の生活の中では「やってみなければ判らない」ということがしばしばある。
しかし、科学的,合理的考え方が多くの文明を築いてきた、進歩をもたらしたと結果的に信じ込ませられている人々に、そんなことを言ったら、無責任と評価されない。
人類が「火星」に行くというような場合は『やってみなければ判らない』では済まされない。人命にかかわる事、目的の明解なものは、科学的に実験、検証などが行われ、その安全、効果を充分に確認してからものごとが行われるが、それでも、失敗と言う結果が生じることがある。
たとえ成功したものでも、そのプロセスにおいて『やってみなければ判らない』をひそかに幾つも繰り返している。日々の生活レベルの範囲では、厳密な目的や結果を設定されない、あいまいなことがいっぱい有り、そのファジーさに対応することが目的であったりするものが多い。
住宅における構造体は人命を守るシェルターとして十分耐力を有する科学的数値根拠を持つものでなければならないが、木構造などは今だ謎の部分を秘めている。
インテリア《室内環境》デザイン等はその基準設定の有り方、運用の仕方などは、住まい手との個別関係において意味をなすため、『やってみなければ判らない』部分が多い世界になる。
人と環境、人と人のより良い関係を築くという行為は、始めに固定された目的や到達点があるわけではなく、相互の交流によって変動しながら快適値を求めつづける事が重要だ。
昨年施行された『住宅の品質確保の促進に関する法律』は、住まいづくりのずさんさを考え直す上で有効ではあるが、住まい手も作り手もが保証問題や、性能の等級などに拘泥すると、本来の可能性、創造性を見失うことになる。
住宅の10年保証などは基本的に考えれば当然であり、同じなら25年、30年、建築主が住む限り保証するものであっても良い。
悪徳業者の建てた住宅は、新築時より問題があり、単純な10年保証制度でユーザを保護できるものではない。結果を受け取るだけで満足するのではなく,『やってみなければ判らない』世界に、住まい手も作り手もが楽しくチャレンジできるように、その根底に互いを信頼する心、互いを裏切らないモラルを持ちたい。
075. 在住外国人問題
近年、日本に仕事を求めてやってくる外国人の増加と、その在住外国人とのトラブルや関連犯罪の増加が気になるところである。先日も広島でのペルー人による少女殺人事件が心を痛めるが、その背景に、日本の少子化、高齢化社会という社会構造の変化が労働市場、特に過酷な労働条件の場においての人材確保の問題がある。
積極的に日系人などを受け入れざるを得ないという状況である。TV番組などで出稼ぎ外国人コミュニテイと近隣日本人住民との交流、親睦のためのイベントなどが紹介され、かすかに日本人が日常生活レベルで外国人・他民族との接触、対応の仕方を学びつつあるのを知らされるが、長い歴史の中、単一民族国家で来た日本人にとって、他民族との共存のすべは、まだまだ不明である。
国内における外国人の凶悪犯罪が報道されるたびに、日本人は共存の根本的なありようを考えるより、自己防衛に身をすくめてしまいかねない様な気がする。
10年近く前の夏の暑い日、私は仕事で名古屋に出かけた。打ち合わせ前にランチを摂ろうと駅構内の食堂に入り、セルフサービスでメニューを選択、テーブルに着いたのだが、すかさず、「ここはあいてるか」とやや酔っ払った風情の初老の男が私に相席を求めた。ほかにもいくらも空席があるのに、私はいやな感じがしたが、黙ってうなずいた。
私の食事中、その男は私の顔をしげしげと見ながら、ずっと独り言のような、話しかけるような口調で、政治ぽい愚痴を繰り出していた。内心、拘わりたくない、早く食事を済ませて立ち去ろうと思っていたとき、「お前はペールー人か。」と正面から私に向って訊ねてきた。一瞬、何を訊ねられたのか。「お前はペルー人か。」、繰り返し聞かれた問いに想定外の困惑の中で「日本人です」と答えた。
とたんに男が安心したように、「いやぁ、お前が何も言わんので、日本語がしゃべれんのかと思った。」時は夏、工事現場監理もあって日焼けした私の顔色、おまけに髭を生やしている顔つきはすっかり日系ペルー人に思えたという。
男の住む愛知県の地方都市では自動車関連産業の働き手として、めっきりペルー人が多くなって、興味半分、ペルー人と近づきになりたかったらしい。
あの日の体験を思い出しながら、観光旅行などでは軽く流すことも出来る言葉の壁、文化の違いを、日常生活を共有するもの同士として如何に平和に混在・融和させればいいのか、今後ますます多民族化する日本社会を思うと気が重い。「国際結婚に報奨制度」などが手始めとして早道か、なんて思ってしまう軽率さを自戒しながら。
076. 環境は命の基本
戦後の食糧難時代に、日本の農業は色々な研究も生産方法も、増産、生産効率アップという目標に向かって進められた。化学肥料、農薬、農機具の投入、品種改良など、そのための多大な投資が必要となり、結果的に生活を支える基本食の米価は政府が補助金を投入しなければ市場性を失う状態になる。農業の合理化、改革の推進を担う農協は、いつの間にか農家の活動を資金面で支援する金融機関となり、農作物づくりの根本や環境への配慮などにおいて指導力を発揮するどころか、単なる金儲け組織になってしまった。
近年、中国からの輸入食品問題をきっかけに、食の安全、食の流通などが食料自給率低下の流れの中で問題視されるようになったが、日本の農業も技術力は高いものの、安全やコストを含めた消費者の満足度には程遠い状況である。
色々な農業関連の法律に縛られて、今日の国民の要求にこたえられる農業の展開は困難を極めている。心血を注いでプロの専業農家が作った安心、安全な作物を如何に消費者に届けるかという、生産と流通の有効な相互関係を構築するためには、従前の法律や流通慣習に縛られていたのでは不可能である。
近年、産地直販、地産地消、有機農法など、作る側と販売側、消費者がヴァリューチェーンを形成して色々な取り組みがなされている。
その多くは、今までの反省も含め、農業はまさに生き物、環境の循環を大切にするという指標を持っている。良く考えてみれば、食物はわれわれ生命の源であり、その食物は全て命の連鎖、自然環境の循環システムの上で成り立っている。
日本では年間約3万人の自殺者がいるというのも大きな問題になっているが、世界には年間5000万人を越える餓死者がいるという。
種の取れない遺伝子改良された作物は、短期的には食糧増産につながるかも知れないが、
長い目で見たとき、その地域、気候に合った子孫を残すかというと疑問が残るそうだ。
先日もイチゴの苗を親の株からヘソの緒をつなぐようにしたままで育て、最適な遺伝子が伝わっていく育成法をしている武山農園を見学したが、有機栽培、無農薬、加温なしという条件で育つイチゴにチャレンジしている青年の心意気は、まさに命の原点と如何に一体化できるかの勝負を見る思いであった。
われわれを取り巻く自然環境はそれこそ神がお造りになったと思って初めて合点できるほど複雑、多様、膨大であるが、人類が何をするにもその基本指標として忘れてはならないものである。農業(agriculture)は教養・文化(culture)の語源でもあり,身近に、農業はまさに人間に環境の何たるかを教えてくれる。環境問題には地球温暖化対策を筆頭に、省エネ、リサイクル、生物多様性、エコカーなど多くの切り口があるが、いずれも経済問題として展開される。勿論、今日の社会、人間の営みのあり様はそうしたものでもあるが、なんとか、環境は「命」の基本であるということを疎かにしないでいたいものだ。
077. 環境についてもっと考えよう
地球温暖化による色々な気象現象の変化が身近に感じられる昨今、CO2の削減のための技術開発や省エネに対する行動・努力は国家、企業レベルから一般大衆のライフスタイルの検証をも求めるところまで来ている。
大阪ガス主催のエネルギー・環境フェア2008を見学したが、CO2排出量として結構大きなパーセンテージをしめる発電のためのエネルギー消費を如何に抑えるかという問題は、一般家庭に燃料電池が実使用されるときには、時々にガスのまま、あるいは電気に換えて使いこなせる天然ガスをエネルギー源として利用するほうが、オール電化よりはるかに、熱効率の良いシステムになる。
今は安全面やシステムのシンプルさがオール電化住宅にも得点を与えているが、太陽光発電システムとの併用など、仕組みとしては複雑でも、それらを適時、的確にコントロールできるなら、おそらくエネルギー供給は天然ガス主体のものとなろう。
原子力発電や水力発電などCO2を発生しない電力装置は、効率のためにコンスタントに稼動させる必要があるため、基本電源量生産としては有効でも、電力需要の変動に対処する部分においてはオールマイテイでないのと、放射能問題など他の環境問題が懸念されるため、拡大設置には限度がある。
それにしても、超小型オンサイト水素発生装置や生ゴミ真空乾燥装置など地球環境改善のために、色々な技術や装置開発が行なわれていて、会場の賑わいは大勢の人が環境ビジネスに携わっていることを実感させる。
一方、別の話しだが、365日24時間、山地に放し飼いの酪農は、牛が山間の下草を食べるため、今問題になっているトウモロコシ、ダイズ、等の配合飼料に頼らない、人間の食料と競合しない酪農が可能である。山地の下草狩を牛がやってくれることになり,里山は健康を取り戻し、林業家にとっても経費節減になる等のメリットがある。自然な草で育つ牛の牛乳は、乳脂肪分が3.2~3.5%だそうだが、何時の頃か5%以上のものを規格として国が決めたため、勢い配合飼料をえさに、過密な牛舎で育てる酪農が主流となって、この環境問題の中で、飼料高騰(エタノールへの転用のためなど)、牛の糞尿やゲップによるメタンガスの排出などマイナス条件を抱え込んでいる。
メタボが問題になるご時世、そんなに濃い牛乳を飲む必要があるのか、一生懸命、牛の健康も考えて生産する牛乳が、コーラやジュースのように量産されるものより安い価格でよいのかと、訴える酪農家の信念に燃えた声は、環境問題をもっと奥深く考えなければならないことを教えていると思う。
日本の環境対策・改善技術は大いに先端を目指すがよいが、進歩という概念ばかりでなく、江戸時代の環境循環型の人間の、生活の智恵を生かす努力、振り返ってみてもよいのではないかと思った。
078. 「おしゃれ」とは
誰でも、おしゃれな人と言われるのは結構、気分のよいものであろう。そこにはその人なりの独自性や感性が表現されていて、それなりの美しさや秩序を持ち合わせていることを認めてもらえたのと同義であると思うからである。
「歌舞伎」の語源は、飛び切り長い刀を差して派手な格好をして街を闊歩した江戸時代の若者たち「かぶく」もの、時代の先端を行く前衛者からきているという話を聞いたことがあるが、人々は、とにかく、まだ人のやっていないことをやる人を、その生き方の勇気をも含めてそれなりの賞賛の意を込め、「おしゃれな人」と呼称したのだと思う。
戦後、欧米の影響を受けて、民主主義が台頭する中で、平等精神、個人の尊重という風潮は、ファッションデザインの中にその表現を求めて、人々はだんだんと自分らしさを生活するようになった。しかしまだ、自己表現になれない日本人は、「流行」という与えられたスタイルに身を委ねていた。
戦後40年を過ぎた頃からは、何をやっても「私の勝手でしょ」と履き違えたおしゃれも見境なく巷にはびこるようになった。「おしゃれ」とは何か。
他人真似でない「おしゃれ」な生き方は、かっこいいが、その人の生き様を根底に表現しているものでなければならず、それほど容易く簡単なものではない。
自分なりのものの見方や考え方、感じ方を生活において心掛けることを「おしゃれ」というキーワードで捉えてみれば、その原点は自分が、
・他人が未だしていないこと、・他人が未だ感じていないこと、・他人が言わないこと(気に留めなかったこと)、・他人が未だ表現しなかった方法などに全感覚をセンサーにして気付き、発見を行い、ものの見方を磨き、考え方を模索することにつながる。
また同時に、新しい意味や表現の追求は、おしゃれの具体化につながるが、そのために
・新しい素材のコーデイネーション。・新しい色使い、カタチ、テクスチュアー、スケールの提案。・新しい使い方の発見、・新しい機能の提案。・新しいシナリオ(生き方、可能性)。・新しい心理の発見などにつながって、「おしゃれ」をすることの意味合いは自分自身の存在を問い続けることにもなるのではないだろうか。
男女を問わず、街にはトレンデイな流行に身を飾り、ジムに通って健康を願い、おしゃれなレストランで食文化を消化し、文化センターで教養を身につけ、時にはボランテイア活動をするといった流行のライフスタイルを実行している人々は多勢いる。
一見、今時のおしゃれな人と見えるが、本当のところはどうなんだろう。良い意味でおしゃれな心、日本人の心を磨く努力をし、平和なおしゃれを発信できる「おしゃれ人」になりたいと願うが、その一歩一歩はもっと実在感のある生活と、そこに感じる反省と感謝の念を繰り返し自問自答することなのかと思う。
079. 歴史を学ぶことの大切さ
近年、日本のアジア外交、特に中国、韓国、北朝鮮との関係は、政治、経済、文化、人権問題などあらゆる面において解決しなければならない局面を抱え込んでいる。
現実問題としては、中国の急速な経済活動に引きずられて起こる連鎖反応的な諸問題、
北朝鮮の核実験や拉致問題に代表される国家としての非常識な振る舞いに悩まされ続けている。しかも、ことあるごとに、歴史問題、過去の歴史の認識に関して、一方的に日本が悪者という勝手な論拠を振りかざし、自国内における諸問題の民衆への不満・圧力をかわすことに利用している。
しかし、多くの日本人は、近代・現代史はむろんのこと、アジアの近隣諸国との関係をどれだけ学ぶ機会があっただろうか。学校における歴史教育は、たいてい時間切れで、近代・現代史は私も含めて、詳しく学ばなかった人が多いと思う。
だから、勝手な中華思想を振りかざされても、反論する力をもてないでいるのが多くの日本人の現状である。確かに満州国建国から第二次大戦にいたる歴史の中で、日本の行動も問題なしというのではないが、「南京大虐殺事件」にしても、近年の調査では、中国共産党が蒋介石率いる国民党を打ち倒すために、巧みに仕掛けたことが事実だったことが明白になってきている。にもかかわらず、先の中国首相・江沢民は、日本訪問のときには、早稲田大学での講演で「3500万人の中国民同胞を殺戮した日本人は未来永劫断罪されるべきだ」と南京事件の10万人とも30万人とも言われていた被害規模を、何百倍にも誇張してまくし立て、それを聞いていた学生諸氏は、歴史勉強不足のため、誰も反論することがなかったという。
このことを、先日桜井よしこさんの講演で聞かされ、あまりの悔しさに涙が出た。日本人の優しい気質が利用されている。対アメリカ外交にしても、脅せば引くと見くびられているのは残念だ。
日本のよき国民性が今日のグロバーリゼーションの流れの中でどんどん変質させられるのは悲しいことである。
何とか、しっかりと歴史を学び、ことの真実を把握して、日本人としての考え、意見を言えるようにするべきだと思う。
小学校における歴史教育はなきに等しい状況と聞くにつけても心配である。我々大人も、日本の行く末を誤ることのないよう、努めて歴史を学び、国民の一人として確かな指標を持ちたいものだ。
080. 100分の1秒
トリノ冬季オリンピックの競技をテレビで見ていると、スピード、技の正確さ・美しさ、チームワークの巧みさなどが色々な競技種目の中で綾なされ競われているが、とりわけスピード〈タイム〉の争いは運命的でもある。
100分の1秒差に7,8人の選手がひしめいているスピードスケート(500m)競技では、誰が金メダルに輝いてもおかしくない世界であり、選手の一瞬のミス、私には「神」のいたずらかと思えるようなコーナワークの所作が、勝者・敗者の天と地を決めている。
日常生活で100分の1秒という瞬間がこれほど格別に意識されることはない。意識されるとすれば、「あの時立ち止まらなければ」,一瞬の出会い頭で交通事故にあって命を落とすなど、大なり小なり何かの事故・事件とのかかわりが多い。
選手たちは、その一瞬の記録のために、計り知れない努力を、トレーニングを積み重ねてくる。絶えず一瞬を意識しながら生活する日々は一体どのようなものだろう。
こんなことを考えている間に、何人ものスケータが目の前を風のごとく流れ飛んでしまうのだ。
瞬間を生きているときは何も意識がないのか。多分、余分なことを考えたり、感じたりすることは重圧となって、スピードを鈍らせ、結果、敗者となるのだろう。
よく「一瞬を大切に生きよう」などと言うが、我々の人生や生活においても、やはりそれなりの相当の修行がなければ、一瞬という「時」の存在すらありえないのかも知れない。
ひとつの競技のようにルール化され、絞り込めない我々、それぞれの生活の最適のゴールは、自らの人生のフレームを描くことがなければ想定することも定まることもない。ゴールへの一瞬を極める努力目標も立たない。若い頃に大志を抱くこと、希望を掲げることがいかに大切なことかをあらためて感知する。
最近のゆとり教育と言われる小学校教育においても,はたして大志を抱く原動力になる「生命力」を芽吹かせる配慮がなされているのか。従来のように、家庭教育、「親の背中を見て子は育つ」を再認識しなければならないのか。小学生対象の「トレーダ教室」が開かれ、子供が株の売買を早くから訓練すると言う現実は、人生を金銭獲得競技のみに絞り込み、その一瞬の大切さを教えると言うのだろうか。
人生はなかなか絞り込めないものだからこそ、100分の1秒はなかなか見えてこない。
廣瀬 滋著
私の思考散歩・生活雑感 ぽつり草々 061〜070
061. 教会の献堂式
昨年来、設計監理をしてきた教会が2月に完成し、4月3日に献堂式が行われた。
東日本大震災のため、献堂式も延期するかどうか牧師さんも色々考えられたが予定どうり各地から関係者の方も参加され厳粛に行われた。
最初に被災者の方への黙祷からはじまり、賛美、聖書朗読、祈祷、経過報告、賛美、献堂の辞、説教、祈祷と式典は進み、建築関係者への感謝状贈呈が行われた。
私も設計監理者として感謝状をいただき、お祝いと謝辞を述べた。
関係者の祝辞、祝電披露、賛美、感謝祈祷、頌栄、祝祷、牧師挨拶と無事式典は終了。
賛美歌が会堂に良く響きわたり、教会らしさを感じさせることが出来たのは当初から気にかけていたのでほっとするところであった。
式典の後、教会メンバー手作りのケーキやお料理でのパーテイがあり、参加された皆さんが思い思いに建物の中を見学された。
今回、設計に当たって教会関係者からの要望、設計条件を集約すると、そのイメージ、空間構成は長年携わってきた住まいづくりと結構近いことを私は直感した。つまり、祈りの場であると同時に、人々が集い、共に愛を育み、神に感謝、無条件に愛されていることの実感できる場、それは基本的に家族の住まいが目指すものをも含むものであることを。
敷地や法規的制約の中で色々多様な使用条件をまとめると、外観はそれほどシンボリックな形態にはならなかったのだが、信者の方が、「いろいろ教会を見てきたが、この教会は新しい形ですね。」といわれた。
よく聞くと、メインの礼拝堂以外に、皆でお料理を作って色々コミュニケーションを取れるダイニング・リビングもあり、宿泊室、祈祷室、シャワー室、母子室、事務室、パントリー、多目的に使えるロビーなど、とにかく便利に、閉鎖的でなく連続した動線で空間が繋がっているのに感心しましたとのこと。
まさに私の思い通り、信者の皆さんの共有する住まい感覚にまとめられたことを評価してくださったとうれしく思った。
信者の方が、教会で時を過ごしていると、「ついつい時間を忘れ家に帰りたくないのです。」と言われたのは本当にこの計画に参加してよかったと心温かくなった。
無事、献堂式も終え、これからこの拠点から、信者の方の色々な活動が豊かに確かに発展していくことを祈りたい。個人の住宅設計のとき以上に、自分がお役に立ったのかなという思いがして、ほっとする気分を久々に味わった。
062. 人それぞれの「昔」
先日5歳の孫が「昔はエビフライが好きやったけど、今は嫌い」とさらりと言って、おばあちゃんの折角作った食事に好き嫌い。
たった5年しか生きていないのに「何が昔やねん。」と思わず胸の内で叫んでしまった。
そういえば、結構2,3才の頃、遊んでいたこと、出かけた思い出などを昔という表現で話すことがあるなと気付いた。
10年一昔などとも言うが、人にはその時々の流れや出来事の思い出が、昔という何ともあいまいな一塊になって不意に、ふっと蘇ってくるのだろうか。
小さな子供でも、「日本昔ばなし」ではないが、知らないうちに絵本やお話を聞かされたりする中で、昔という意味合いが理解されているのだろうか。
「昔は良かった。」「昔は苦労したもんだ。」等と今と比べて異なる感慨に触れる時、日常的に個人的に「昔は、、、」なんて口走っているのだが、世の中には歴史というより人それぞれの「昔」がいっぱいあって、小説やドラマの中でも自分の知らない昔、共感できる昔など、様々な昔が渦巻いていて、単に史実というよりも、やっぱり「昔」と受け止めたい喜怒哀楽を含めた一瞬間に、笑いや涙を誘うのである。
昔の自分と言うセリフの中には、自身で成長したというか、今まで気付かなかったものに感動したり、初めての行動をとれるようになったという実感への感慨もあるだろう。
勿論、まわりの環境や社会の変化につれて、知らず知らずのうちに以前とは異なる状況体験することになった、その移り変わり、蓄積がふっと感じられるとき、「昔はな」と思わずつぶやきたくなるのかも知れない。
二十世紀以来、十年ひと昔と言われるくらい、時代の変化は激しいが、一人の人間の寿命というスパンから思えば1000年の歴史などというより、今は昔という概念は、すこぶる身近な尺度として温かいものなのかもしれないと思う。
そう思えば、5歳の孫の「昔」もうなずけるのだ。
063. 私の英会話つれづれ
今や世の中のグローバル化の流れの中で、英語が話せると言うことは必須のようで、企業でも社内の会話を英語で行うところも出ている。
我々の世代でも、どこかにこれからは外国語の一つや二つは話せないといけないという潜在意識があって、大学時代は英国からの留学生に英会話を習ったり、社会人になってからも何度か学習教材を買い込んで英会話にチャレンジ。
時にはマドモァゼルと話してみたいと欲深くフランス語スクールに通ったこともあった。
しかし、日常仕事で英語を使う環境でもなく、海外旅行でささやかな日常会話を使う程度では結局継続性もなく、上達したと言う実感もないまま年老いてしまった。
TVの英会話教材のコマーシャルを見ていて「何とか英会話がマスターしたかったなぁ」とつぶやくと、「死んでからあの世で幽霊になってアメリカ留学したら」と女房がぴしゃりと助言。
数十万円の語学教材を買い込んでは、ほったらかしの前科者には返す言葉もない一言ではあるが、心の奥底にあるこちらの無念さを、ぐさりと掘り起こす一言でもある。
長男を2年間アメリカに留学させたのも自分の気休めの一つだったのかもと述懐する始末。伯父の会社のアメリカ駐在員にならないかと言う話も、若気の至りで「帝国主義の国には行きたくない」と蹴ってしまった事も、振り返れば英語には縁がなかったのかと、自らを慰めても見る。
翻訳ソフトや小型の会話機が、いずれ個人レベルで購入できると言うニュースにも期待したこともある。何が何でもと言う必要性がないところでの自分の努力不足の思い違いを一事が万事垂れ流してきたのではないかと反省もする。
本当にあの世で流暢に世界中の人々と楽しく語り合えるなら、あの世も大いに期待感を抱かせるぜ。
最後は小学校から英会話を学ぶ孫が国際人になってくれればいいなぁと思いつつ、これからの日本の若者にグローバル化の流れの中でも、逞しく生き抜けるよう、外国語会話熟達へのエールを送りたいと言う達観の極みをよそおいつつ、[Nice meet you.]などいくつかの日常会話のフレーズを呟いてみるのである。
064. 変化・変貌
先日久しぶりに東京・新橋駅に降り立った。
駅前広場には蒸気機関車が据えられテーマパークの一角のような賑わいである。霞ケ関の方に向けて歩き出してまもなく、同行のK氏が「あれが、かの超高層ですよ」と話しかけられた。一瞬どこにも超高層ビルなど見当たらないと思った瞬間、よみがえった。40年前、日本で始めての超高層ビル36階建て霞ヶ関ビルを見学したことを。
いまや、周りのビル群に溶け込んで、およそ超高層建築の風情は感じられない。子供時代に訪れた場所や見たものが、大人になって訪ねて見れば、「なんだ、こんなに小さかったかな」と驚くに似た気持ちが流れ、急に街並みが気になった。
振り返れば、東京に住んだ昭和40年から6年間は、東京のエネルギシュな発展振りを身をもって受け止め、20代の青春と歩調をあわせ実に思い出深いものであった。
京都に帰ってからも何度も仕事や所用で東京に出かけ、その度に新しい都市環境があわただしく蓄積と変貌、変化・展開する様を知った。
しかし、とりわけ住み慣れた渋谷や仲間とうろついた新宿界隈の変化・変貌は、飲食や遊び、買い物といった生活レベルでの体験とつながりがあって、別段違和感はなく、むしろ変化の様を知っている余裕があった。
やがて、地下鉄網が複雑に発展して、乗り継ぎなどに戸惑どったり、あるべき街角の喫茶店が見つからなかった頃、もはや自分はこの都市から異郷人になったと思ったが、それは日本経済の発展のなせるところという認識で受け止めていた。
今、かっての超高層ビルの光り輝くデビューを知る自分が、この都市に埋没したビルと共に佇む光景は、どこか遠い夢の世界のような感じがする。40年の歳月の流れが一瞬に静止。
首都、東京のダイナミックな変化・変貌の事実を背景に、さして変わらぬ一点の自分が影を共にしている昼下がりは不思議なものだ。
何かが違う。変化・変貌を連続して感じてきたという安心感というのか、共有感が無く、東京は日本人としての連帯感を抱かせることの無い都市になったと思った。
国会議事堂周辺はテロ対策の警備が敷かれ、よそよそしい空気は、戦後の日本の変化・変貌を心なしか寂しいものにしている。東京はもとより、日本中、1000兆円の借金をしてまでこれほどの変化・変貌をしなければならなかったのか、政治の根本姿勢も気になるところである。
065. 東本願寺御影堂改修工事を見て
私の住まいは東西本願寺門前町のすぐ近くにある。先日、東本願寺御影堂の屋根瓦葺き替え工事現場を見学した。
概ね、社寺の屋根瓦の葺き替えは100年に一度、構造体の修復を含めた改修工事は300年に一度おこなわれる。明治時代に再建された東本願寺御影堂は100年目の工事。
現在近くで10年がかりで行われている西本願寺の改修工事は300年に一度のものである。一生のうちに100年に一度、300年に一度といった改修工事現場に同時に出会うのもラッキーなことである。
日本の建築の様式の大きな流れが400年くらいのスパンで変化しているといわれているが、1600年代(江戸時代)頃に建立、再建された社寺・仏閣群が、また西欧の影響を受けた近代日本・明治時代の建築群が今、改修の時期を迎えている。改修工事で技術的なすばらしい工夫や、当時の人々が大切にしていた文化の匂いが立ち返ってくるのに接することが出来るのはうれしく、幸せを感じることである。
東本願寺は明治の近代建築技術を取り入れ再建されているため、屋根の荷重を減らす工夫が色々されていたので、瓦を取り除いた時、西本願寺などの事例から多分30~40センチくらいは木組の復元があるのではという想定を覆し、わずか10センチくらいしか高さが変化しなかったという。
明治の土木技術を駆使、自然の高低差を利用した琵琶湖疎水から引かれた水を利用して火災時の消火に備えたスプリンクラー様の消火栓が屋根に設置されているなどは驚きである。
今回の東本願寺改修工事では、従来の土を使用した土居葺きをやめ、桟葺きに変更して屋根荷重を減らし地震に備えるという。今回発見された烏丸通りから巨大な木組みの斜路を作り、直径2メートルもあるかという梁・丸太材を30メートルを超える高さまで人力で引き上げている当時の建設工事現場の写真は、かのピラミッドの建築想像図を思い起こさせる。
引き綱には全国から寄進された信者の女性の髪の毛を編んだ綱が使われ、その一部は今も記念展示されている。今の巨大クレーンが軽々と資材を操り建設する現場とはかけ離れ凄いものを感じさせる。
人力、智恵の結集が巨大な構築物を作り上げる時空は、多くの人々を感動の世界に導いたと思う。先年、この改修工事に備えて小屋裏を見学する機会にも恵まれたが、巨木が縦横に組まれた大空間に言葉に言い尽くせない圧倒的な「力」を感じたのはこうした血と汗のプロセスが埋め込まれていたせいなのだと改めて感心した。
066. 東海道五十三次「関宿」を訪ねて
幸いなことに大変気持ちの良い快晴日。住まいやインテリア、生活に興味のある私的な倶楽部活動を続けて13年目になる仲間と東海道五十三次の内の「関宿」を散策した。
京都から草津へ、草津で乗り換え柘植、さらに関西線に乗り換えて関に着く。京都に住んでいると、三重県といえば南の方角にあると感じているので、まず、滋賀県・草津に(北の方角)に向うことからしてすでに方向感覚が乱されるうえ、初めて訪ねる関は到着するまで、自分の中でこれと定めるもののない不思議な土地と感じていた。
一見して宿場町という街並みに接して、安心感と同時に、観光客に早代わりの自分を知る。
過って、奈良井宿や妻籠など宿場町を観光したことはあるが、関はお伊勢さん参りの人達や参勤交代で賑った交通要衝の地で「鈴鹿関」が置かれていたところと聞くと、いっぺんに親しみがわいてくる。
東西1,8kmに及ぶ町並みの保存は昭和59年、国の重要伝統的建築物群保存地区に選定されている。環境問題が話題の最近こそ、町屋保存などを初め、町並みの保存はあちらこちらで叫ばれるが、すでに手遅れのところも多い中、関の住民の意識の確かさに感心する。本陣跡や、旅籠、町屋、山車倉など建築と当時の生活空間をほどよく見学できるのはうれしい。関の特産火縄屋さんがあったのを知って、こんな商売も昔はあったのだと遠い時間を感じた。
皆で休息した茶房も昔は薬屋さんで、茶房は奥の座敷などを利用してしつらえてあるが、表の間には、色々な骨董と言うか、昭和初期から戦後しばらくの間に使われていた道具などが所狭しと陳列されている。京都にもこうしたところは多々あるが、やっぱりちょっと鄙びているところが宿場町らしい。
往時、旅姿の老若男女がにぎやかに行き来していたこの街、看板のひらがなで書かれた面は京都方面を、漢字で書かれた面は江戸に向う方角を示しているなんぞは、なかなかのアイデアであろう。今、観光としてみると実にほのぼのと楽しい街並みである。
みやげに和菓子「関の戸」と伊勢茶を買った。
時々こうした昔の町なみを散策すると、一気に古の生活も偲ばれて、脈々と流れる日本人の心意気が、自然に身に染みて、とても落ち着いた気持で満たされる。歴史の中に生きてきたもの、目には見えないが、何かが、自分の中にも今なお瞬いているのを覚える。
満足感を背負って帰路は思わず微笑みでいっぱいであった。
067. 生き方の曲がり角
今年こそは、地球温暖化に世界が力をあわせて具体的対策を実行しなければ、本当に地球環境は取り返しがつかないと言われている。日本の将来は、大局的に、技術立国を目指すほかないとしても、政治、経済におけるグローバルスタンダードに飲み込まれてしまっては、その大義も国民のためというより国際資本家を巨大化させ、貧困層の増大を促すだけになってしまう。
ほとんどの団塊の世代は定年後の余生の過ごし方、選択を迫られる。地球世界、日本、個人、どのレベルに於いても流れの変節を迎えているといえる。
2005年を境に、日本人口が減少し始めたという事実は、日本の将来に何か言い知れぬ世界が訪れることをイメージさせ、自分の死後のことと割り切ってしまえばそれまでであるが、「孫」の顔を見てしまった上は、無関心ではいられない。
年末から年頭にかけてのテレビの色々な討論やドキュメンタリー番組を見ても、本当に色々と考えさせられるが、国家として、政治において日本人のあり方を世界に示す必要性は大いにあるのに、国政選挙の投票率は低く、国民の真意は姿を示すことがない。
政治がどうのこうのといっても、政治家を選ぶのは結局、国民なんですから。」と日本人の生き様への真剣な対峙のなさを、捨て台詞のように締めくくる評論家の一言は、日本人の生活・文化、職人気質を育んだ優しさという自然観、美徳を思えば、ジレンマを感じざるを得ない。
アメリカのように弁護士だらけの訴訟、権利主張社会になってうれしいか。
バランス感覚に優れたコモンセンスのある政治家を選びたい。
いつも煮え切らない国民と捕らえられがちな日本、外交ではあるが、シロ、クロを即決することが必ずしも優れているばかりでないことを、時間がかかっても順序だてて諸外国に話し続ける忍耐と勇気を持ちたい。
アメリカも今なら、イラク戦争のつまずきからこうした日本人の原理・原則も理解できるのではないかと思える。いずれにしても、日本人を取り囲むあらゆる潮流はその潮目を迎え且つ混沌としている。
今まで何度も問い直しては来たが、プラネット・アースに生かされているという実感をやっと身近に感じるような気がする「今」、明日の一歩は、ささやかでも死後の道につながってほしいと思う。
068. 上棟式
地鎮祭も執り行われ、やがて住まいが形として姿をあらわす棟上の日は、何時も最もわくわくする。図面や模型の段階で思い描いていたものがその輪郭をあらわす。柱や梁の部材がクレーンに吊り上げられて組み立てられていくのを眺めている時は、プランニングのときに住まい手とやり取りしたこと、あれこれ考えたデザインへの想いが青空を背景に次々と紡ぎ出されていくようである。
私は、ぼんやりと棟梁をはじめ職方のきびきびとした動きを見ているのがとても好きだ。段々と高場の作業になり緊張が高まっていく中で大工さん同士の軽妙なダジャレのやり取りも楽しく、協同作業の中で一つの何かが生まれかかっている、その時の高まりが心をうれしくさせてしまう。
日暮れなずむ頃、ようやくにして棟が上がり作業が仕舞い支度になる。そして、組み上がつた骨組だけの家の中に簡単な祝宴の場が設けられる。棟に挙げた御幣に向かって、居合わせる全員の礼と拍手、建物の四隅の柱に米と、塩、清酒での清めによって無事棟上式を終える。
ここからは祝宴となる。住まい手の施主としての挨拶、設計者、施工者のお祝いの一言、乾杯が行われ皆の歓談が始まる。この十月三日、新宿Y邸の上棟式では十三夜の月を眺めながら一献を傾けることになったが、その場は大東京にありながら佐渡島出身の大工さんの秋刀魚の手づかみ漁の話等ですっかり昔の日本、秋の風情を語りつつ別世界であつた。
昭和40年代の頃には酒豪の職人さんも多く、木遣り節等自慢ののどを聞かせる大工さんもいて盛りあがったが、職方のほとんどが自動車で現場に来るようになって、アルコール類を控えるため、今では結構わきまえた宴である。
それでも時々酒好きな職人さんがいて、どっと愉快なパーテイになる。やっぱり私は職人さんのおおらかさいっぱいの棟上が好きだ。どんな施主が、設計者が、そしてどんな職方が関わりあつて住まいを造ろうとしているのか、きっと昔は本音の姿で語り合い、より良い完成に向けての気脈を通じるための大切な場であつたのだろう。
都会では地鎮祭、上棟式をすることも少なくなったと聴くが、形式というよりセレモニーが持っていた形を通しての人と人との有り様や、自然、環境に対する心構えを問い直す機会として大切なけじめかと考える。もし、上棟式がなかったら、私は十三夜の月をこれほど感慨深く眺めただろうか..。
069. 松茸狩り
地球温暖化といえど、さすがに10月も中旬に向うと秋らしさが色濃く感じられる。
秋は味覚の季節、市場にも色々な旬の食材が並び美味い料理を思い浮かべながら心楽しくなる。中でも松茸は子供の頃は今の様に希少なものではなく、ごく身近に食することが出来た。
私が松茸狩に最後に能勢の山に行ったのはもう20数年前である。その頃でもそれほど豊作という状況ではなくなりつつあったので、山の斜面に沿って目を凝らし、落ち葉を掻き分け、1本の松茸を見つけると不思議なくらいうれしかったのを思い出す。
1本見つけると近くに数本が見つかりやすく、香りを嗅ぎながら「見つけたよー。」と思わず叫んだものだ。
山すそにござを敷いて松茸スキヤキをみんなでわいわい語りながら食べた。
勿論、牛肉よりなにより、松茸がなべから溢れるくらいで、皆が贅沢感に浸って幸せいっぱいだった。
今、日本では環境の変化で、松茸の収穫量は激少、松茸狩りを楽しめる機会は少ない。
そんな時、南北朝鮮の首脳会談が行なわれ、北朝鮮から韓国のお土産に4tもの松茸が送られたとの報道。内の奥さん曰く、「そんなにいっぱい、どうするのかしら。」「誰に分けてあげるのかしら」国家がもらったお土産は一体誰に、どうなるのか行く末を知りたいという。「大統領府や官邸の料理にでも使われるのでは」と答えてみたものの、秋の味覚を多くの人々におすそ分けする仕組みがあれば最高だろう。あの日本の福島だったかで毎年振舞われるサトイモ鍋の催事ように。
時々、遠方の知人達から産地の特産物を送られることがあるが、その新鮮さと同時に、季節感が心身に届くのが何よりうれしい。もう1度松茸狩がしてみたいな。
秋に想う。
070. 着物(和服の生活)
年末からの雪不足のため、今年の正月は久しぶりに京都で過ごすことになった。
京都の家で過ごすとなると思い出したように着物を着て、くつろぎたくなるのは不思議な習性ではあるが、元旦からずっと着物を着て過ごしてみると、改めて和服のなんとも云えぬ温かさとゆったり感がうれしくて『これぞ日本の心だ』と確信してしまう。
我が家の居間はフチナシタタミ敷き床ではあるが、ソファも置いてあるので、着物でソファに腰掛け新聞を読んだり、TVを見たり、お茶を飲んだり、トイレに行っても、段々と着崩れを直す要領が解かって来ると、着こなしの充実感のほうが楽しくなってくる。
「ちょっと角帯の締め具合を緩めのほうが具合がいいな」等着物にかけては達人である女房に意見を求める。それにしても、体と着物の間にふんわりとした空気層があって、その暖かさがこれほど気分をリラックスさせてくれるものだったとは、今まで実感することがなかった。
何度か和服を着てやっと少し本来の良さを感じることが出来るようになったのだろう。
言い古されたことではあるが、日本文化の持っているフレキシビリテイ、『間』の奥深いすばらしさを本当に大切にしたいと思う。
おせち料理のバランスの取れた味と栄養のくみ合わせ、色とりどりの美しさ、味わって飲む日本酒、日本間(和室)の穏やかさ、どれもこれも調和ということにおいて人間的だ。
スキーは出来なかったが、今年のお正月は久しぶりに日本人であつた。
それにしても初詣、昔に比べてあまりにも「普段着」の人が多すぎるのはどうか、せめて新年「ハレ」の精神、けじめも必要ではないか。
廣瀬 滋著
私の思考散歩・生活雑感 ぽつり草々 051〜060
051. 別荘生活雑感(その4)
別荘の地下室は33年の間に、雑然と物置場となっているが、雪国、山間・自然生活になじむために、苦楽を体験・体感してきたここでの歴史が、展示されているようなところで、私にとっては、結構心安らぐ空間である。
積雪、凍害などによる家屋のメンテナンスをはじめ、不在中に色々な生活不具合が発生するので、長年の間にその修理や改装のために色々な工具や装置が自然に増え、地下室は取り替えた部品の残骸も含めて、Do It Yourselfeの達人の隠れ家のようになっている。
多分都会生活ではめったに使うこともない道具、斧、鋤、鍬、落ち葉掃除のための熊手、草刈り機、鎌、4メートルのスライドハシゴ、電動工具一式、ドラム缶の栓・開閉バー、コードリール、左官用塗り鏝と舟及び煉り鍬、スコップ2種、つるはし、雪かき用ダンプ、スキーのメンテナンス道具一式。 子供が小学生の頃に良く遊んだ、卓球台、ダーツ、ゲートボール、バドミントンセット、虫取り網、カゴ、今は使わなくなった家族や友達の20台を超える旧型のスキー板、大小の主も分からなくなったスキー靴、ソリ3台がズラリと並ぶ様も不思議な圧巻といえる。
煙突にすすが詰まって「ドぉーン」という爆発音とともに食堂が煤にまみれて、煙突掃除の大切さを思い知った使用済のポットストーブも、わが一家の動向を今も見つめている。
ハンモックや庭の胡桃の木で作った小さなベンチセット、折りたたみ椅子、不要になった旧型の冷蔵庫2台、一度入れ替えた流し台セット、不要な暖房器具、その他、灯油備蓄のドラム缶や給湯ボイラー等、目に付くだけでもなかなかのものになっている。
明らかに捨ててしまえばいいものも短期滞在では大型ゴミ処理をする日取りなどがうまく手配できなくて、どんどんストックされていく。
じっと眺めていると、なれない作業で不覚にもケガした思い出も多いが、大抵は色々な作業の結果、使い勝手が良くなったり、修復がかなった満足感が楽しく思い出される道具たちでいっぱいである。 別荘における地下室は生活のバックヤードというか、生活支援のための必要空間であり、日常住宅ではあまり意識させられることのない主たる居住空間に対する従空間の大切さを体感させるものだ。
自給自足生活をするとしたら、もっと沢山の道具を使いこなさなければならないだろう。
自分で便利さを獲得する。自分で生活をフォローする。そのことの大変さを楽しく学習させてくれるのが別荘生活のありがたさかもしれないと思う。
052. 別荘生活(その5)年末年始
10年ほど前までは、年末年始は雪の信州、別荘で過ごすのが通例だったのだが、夫婦だけではとても冬場の雪かきをはじめ、買い物なども出来ないので、何時の頃からか次男夫妻と共に出かけることになったのだが、初めての孫が12月31日生まれということで、0歳、1歳の冬は無理。
さあ今年は楽しく孫とスキーと思いきや、二人目がまたまた新年2日が予定日。
3年連続正月を京都で過ごすことになった。
新春の京都に観光で来られる方も多いのに、私は30代初めから30年近く、ほとんど正月を雪の中で迎えることにしてきたので、最近の祇園さんへの初参りなどは、昔に比べ晴れ着姿が少ないことや、元旦から色々なお店がオープンしていてあまり神聖さがなく、ただの縁日のようで、雑踏に嫌気がする。
真っ白な雪の輝き、眩い光りが食堂に溢れ、たとえ山荘とはいえ、年末から手抜きはしないという女房の手作りおせち料理が、はなやかに並んだテーブルを囲んで、家族が新年の屠蘇で乾杯、挨拶をかわす自分達なりの新年スタートは、あたり一面銀世界の中でとてもうれしいものである。
降り積もった雪をかぶり立ち並ぶ木々の合間から、窓越に見えるゲレンデでは早くも初すべりを楽しむ人たちも見える。
いつも10時頃には初すべりにゲレンデに向う。年とともに1本目は緊張する。この歳で骨折でもすれば、もの笑いとつまらぬ意識がミエを張るからだろうか。
一気に滑り降りて「今年もまだまだ大丈夫。」晴天を仰ぐ時、本当に一年の区切りを実感する、刻々と変わる夕方の山の雪景色、本当にリフレッシュできる年末年始を今年は迎えられないので、残念。
先日、「もっと考えて、いい時期に産めよ」なんて次男夫婦に笑いながら言ってみたが、彼らも充分に雪山のすばらしさ、楽しさを知っているので、嫁は「ほんとやね」と笑っていた。再来年こそは!
053. 別荘生活(その6)
年末から新年にかけて8日間、6年ぶりに正月を山荘で過ごした。孫と雪遊びをしようと思ったのが一番の理由である。天気予報では天候は荒れ模様の予定で心配したが、山陰地方の雪害をよそに、長野県の北にある山荘ではちらちらと雪は降るものの、時に太陽が顔を出すという日や、元旦は快晴。2日は曇天であったが3日は期待以上の快晴。夜寝ている間に雪が降り、朝に新雪に囲まれた綿帽子の木立に「おはよう。」と声をかける。 窓から見える山荘の周りにはウサギや狸の徘徊の足跡が転々と記されている。「訪ねてくれたのかい」と早起きの孫と姿なき動物たちの噂話をする。
瞬く間に山々に朝日が照り返し、刻々と変化する自然の目覚めの時を、あたり一体の自然の生き物たちと共感しているという想いは、とてもうれしい気持ちである。朝食の前に外に出て道路から入り口まで30Mくらい新雪を踏み固めて通路を確保する作業は結構天職を与えられたように心楽しいものだ。
屋根からなだれのごとく落下して積もった雪の傾斜を利用したり、隣地との境界の傾斜を利用して孫がソリ遊びが出来るようにとコース整備を始めると、なかなかの重労働。孫が喜ぶと言う確信が、頑張りを授けてくれる。
食堂の窓を開けて、「お爺ちゃん、ご飯の用意が出来たよー。」と孫の声。なんと汗がびっしょり。朝食前に下着を取り替える毎日。お雑煮やおせち料理を食べても、これでは太ることはあるまい。窓からゲレンデを見るとリフトがゆっくりと山頂へと隊列運動。年末は6年ぶりのスキーでちょっと緊張したが、からだで覚えたことは案外忘れていないものと言うのは本当で、思いのほかスイスイと滑降することが出来た。
帽子にゴーグルをしているとお面をかぶったようなもので、年齢など不詳のいでたちである。2日目だったか、サングラスだけでリフト券売り場に行ったら「ちょっとお尋ねしますが、もう60歳を過ぎていらっしゃいますか?」と訪ねられた。「ええ、勿論」と答えると、60歳以上にはマスター券と言う割引制度があるというのだ。自動車運転免許を持たない私には何を持って証明するか。一瞬、折角の制度もパァかとおもった。ところがサイフの中に、まぁ、未だ役立ったことのないインテリアプランナーという資格の証明カードが入っていた事を思い出した。見ると、ちゃんと生年月日が記され写真まである。
係りの女性は「これで充分です」といって1日券¥4000-が¥3000になる扱いにしてくれた。年寄りはそんなにがんがん滑らないと言うことでもあろうか。これなら1日目ももっと年寄り風貌を見せればよかったのか、いや、幾つになってもファッションはこだわらなきゃと言う気分、年甲斐もなく2つの損得に一瞬複雑な苦笑い。
もう、40年近く、同じスキー場にお世話になると言うのだが、リフトに乗って山頂を目指すと、色々な時の思い出が蘇る。実に色々なことがあったと思うが、回りの稜線、雪山の清々しさは全てを透明に、多くの人達との出会いを感謝へと溶かしてしまう。私にとって山荘は気分転換のみならず、ある種の定点観測地のような場所だったかもしれない。
054. 本当に[もの]は思いよう。節電のこと
一気に真夏日のこの頃である。
いたるところで節電のニュースを見聞するとたいていの鈍感な人も、身近なところから何とか省エネ活動に参加しようと思うだろう。特にクーラの設定温度調整などは知らない間に叩き込まれたこのところの金科玉条である。
私の事務所はコンクリート打ち放しの建物で、東西は隣接しているため比較的ひんやりしているのだが、連続の真夏日となると、あたりの空気そのものが暑いのでやっぱり例年クーラは欠かせないのだが、今年は今のところクーラは一切使わず小型の除湿機のみ稼動させている。
午後ともなると何となく汗ばむことになるが、思い浮かぶのは過酷な被災地の人々の姿である。[もっと辛い人がいる]と思うだけでクーラには目もくれない、我慢なんて気持ちもわかない。なかなかの心掛けと自らをほめている。
日本の、この20数年来の総合的にエネルギーをふんだんに使いまくっての生活はなんだったんだろう。
工場も、オフィスも、一般家庭も心掛けで15%くらいの節電がそれほど生活に不便さを感じたり、質を落とさなくても可能というのなら、本当に今回の大震災は貴重な転機である。ものごとを「プラス思考で幸せに」等とよく言うが、本当に「もの」は思いようで、現実に暑さでも寒さでも、時にはひもじさすら乗り越えていくのが人間らしい。
人間にとって[飢え]は最悪条件であるが、そんな時、体の中に命を永らえさせる遺伝子が働くとも言う。だから腹八分目、規則正しい生活は長生きの基ということも分かってきた。 集中力の途切れた間に間にこんなことを考えながら今年も前庭、一気に咲き出したムクゲの花に相槌を求めている。
055. 新しい年の始まり 2012
時はいつもと変わりなく流れているのに、大晦日、新年・元旦を迎えるという習いの中で殊更に歳月の流れを意識する瞬間はいろいろな想いや感慨がこの身に凝縮されて光と影、半身がもはや化石にならんとする感触を思う年の瀬。
日が昇り元旦の朝、長男夫婦、次男家族が9時半には我が家に集合、8人家族の祝いの膳を囲む。毎年暮れから女房が作るおせち料理。来年からは嫁たちに作ってと言いながら今年も私だけに「くたびれた。人の作ったものを一度食べたい。」と愚痴をこぼしながらもどこか一仕事した満足感いっぱいの女房殿。
二人の小さな孫が好き嫌いをいいながらにぎやかにおせちの品定めをする。いつの頃からか略式にしてしまった屠蘇代わりの日本酒で、乾杯。今年の健康、平安を願う。
いく歳月、お雑煮のお餅もだんだん食べる数が減って、子供の頃はたくさん食べたなぁと感傷的思い出の時。孫の、「僕は酉年、鳥の食べ方、次はお猿さん」などといっていろいろな食べ方しぐさに、現実の正月。
長男が次男と孫と一緒にお年玉の福袋を買いに出かける。
おもちゃいっぱいの福袋。大人が見ても難解な組み立て玩具や乾電池がないと動かないものなど、子供には素直に感激をくれない代物の山に、私はなぜか今の世相のしらけた様を見る思いがする。
届いた年賀状を見る。人生のいろいろな場面で出会った人たちからの便り。
本当に数十年会っていない旧知からの賀状は、やはり年はじめの区切り感そのものである。
午後には近くの公園に出かけ、4歳になる孫は初めての自転車乗り、大晦日に6歳になったばかりの孫は私の大人用自転車に挑戦。少し手こずったが二人とも見事成功。
両親、爺ちゃん、ばあちゃんの見守る中で晴ればれニコニコ顔。
3時頃には皆でテイータイム。
晴天の元日。今年も私の時が始まる。今年も出来ることを精一杯誠実にやろう。
056. 今年の夏は扇風機
東日本大震災以後、関西に住む我が家でも節電意識は高まった。
長らくクーラに慣れきっていた夏の生活だったが、一昨年当たりから孫の昼寝などにも古い扇風機を引っ張り出して、なんとなくからだに優しい涼をとるなど、節電というより、昔の生活スタイルでもそれなりに暑さは凌げるものだと何となく納得しはじめていた。
古い扇風機は、昨秋、仕舞い際に分解掃除をしようとして結局壊してしまったので、本格的に節電を考えると、今時の扇風機を品定めしなければならなくなった。
家電店に出かけると、従来からの羽根の回る扇風機、タワー上の送風機タイプ、まったく羽根のない新しいコンセプトの扇風機?がずらりと並んでいる。
価格も¥2.000-くらいから¥55.000-くらいまで何処がどう違うのやら、店員さんに色々と説明を聞く。
タワー状形体のものも、色々スイッチなどためしながら調べてみたが、何となくぐらぐらと不安定で、送風範囲も我が家のリビングの設置状況を考えると対応性に不満が残るので早々に選択外とした。
外国製品である羽のない扇風機はデザインからして今までにないもので、ちょっと買う気にさせられるのだが、対応年数が3年位とのこと。しかも価格は¥35.000から¥55.000。すぐ横で¥2.000くらいの扇風機が回っているのを見ると女房と二人して考え込む。
それに、このモダンデザインは我が家にはちょっとしらけるのではないか。
その時、ベストタイミングのように定員さんが、今年の新機種、七枚羽根で静かで穏やかな扇風機を薦めてくれた。テレビでも紹介されたとかで、人気商品、今すぐ現物はないのだが調べてみましょうかとのこと。
価格は¥25,000、扇風機としては高いが、洗濯機のモータを使用、直接ファンが回っているので音も静かなんですよという説明に購入を決める。
何と早くて6月末の入荷とのこと。
急に暑くなったら困るなと思ったが、今年は扇風機商戦は早々と今がピークとか。きっと全国で節電生活のアイテムとして扇風機が復権を遂げようとしているのだろう。
新しい扇風機の風を楽しみに、これからの日本の生活のあり様を考えながらビールでも飲もう。
今年、2011年の「夏」
057. 原発問題の行方
イタリアでの原発設置反対は国民投票の94%からの圧倒的多数でイタリアは今後、原発を持たないという決議をした。
このニュースは人類と「核」の問題に基本的には爽やかな正解を示す象徴的なことであると思う。しかし、一方で人類の生産活動のためのエネルギー問題との関係で、インドや中国をはじめとする急進国や自然環境を始め色々な国情を抱える国々では、直ちに原発廃止、廃棄という答えの出せないのが現実であろう。
恐ろしい結果を残した広島、長崎の原爆の壊滅力の悪夢を、人間のあくなき探究心はそのエネルギーの強大さを、「核」の平和利用なるテーマに置き換えて、何と多くの原子力発電所が世界の人々の身近なところに設置されていたのか。今回の福島原発事故で知って驚いた人は多いことと思う。
CO2を排出しないと言う一点の長所を環境問題との関係における御旗に、日本では原発の採用は更に地域振興、活性化という社会問題解決策とする手段に利用された面が大きい。
広島、長崎で被爆、被害国家であった日本が、今回の福島原発事故で思いもかけず世界への加害国の立場になったことは重く受け止めなくてはならない。
科学技術力で先進性を顕示してきた日本ではあるが、戦争はしません、軍隊は持ちません、平和国家として世界に顔向けしてきた日本が、「核」だけは被爆国民の信念、哲学として、たとえエネルギー問題があったとしても、原子力発電などはより未来、長期的な視点に立って、放射能被害などコントロールできない問題がある以上、思い止まるスタンスを政治、実業界、国民全てが忘れてはならなかったのだ。
これから、代替、自然エネルギー開発に更に重点をおき、社会・経済にも混乱の起こらない世界の人々に役立つシステムや技術の開発を急がなければならない。スマートメータ、コンセントの設置をはじめ国民一人一人が生活の中で取り入れられル省エネシステム、節約の知恵などがすばやく情報公開されることを期待したい。
東日本地震災害による何よりの問題は、原子炉の崩壊による放射能汚染の拡がりで、住み慣れた故郷に戻れない、生活できない、人間・地域社会の破壊を引き起こしたことである。復興の遅れも原発に関わる原因が大きく、放射能除染作業なども、あっという間に4兆円以上を費やすという。原発がほんとうに経済的なクリーンなエネルギーであるのか、廃炉の作業や経費を考えると一般消費者には知らされていない問題が、まだまだ隠されているのではないか。
日本の優秀な科学技術者に原子力利用以外の胸を張っていられる研究分野で活躍してほしいと思う。
058. 多数派工作、民主主義の欠点
いかにも多数決で物事を決めるのは民主主義のルールの原点である。
政治家は何をどうしたいのかさっぱり理解できないが、この日本の非常事態に野党は管内閣不信任案を提出して、それも与党のおよそ政治家としての節操もない一派を巻き込んで多数決で何とか自分たちの立場を主張しようとしている。
1票の重さは変わらないという原則に立たないと民主主義は前に進まないかもしれないが、1票の質、こめられた思索の深さや重さはどう評価すればよいのか疑問が残る。
分かりやすく言えば、烏合の衆の1票と、いつも国民のこと、日本の将来など深く考えているものの1票の違いの差である。
イスラム教国家のように、宗教と政治があまりに一体化している国にも問題はあるだろうが、震災や原発問題を抱えた今の日本の緊急事態などでは、多数決よりも飛びぬけた識者・聖人の一声、判断のほうがうれしく待たれる。
そんな風に思うほど、今の日本の政治家のバカさかげんにはあきれる。
自民党などは特に、自らが行ってきた政治のツケが膿となって出ていることをどう受け止めているのか。野党になったとたん恥ずかしげもなく国民のために最善を尽くすことなく、いじけて、政局での主導権争いに明け暮れている。
今や、民主主義のあり方さえ問われる時代に、本当にどうなっているのか。
日本の国民は、今こそ政治家の過去の政治経歴をしっかりと洗い出し、いかがわしいものや、能力のないものを政党を問わず一掃するべきではないだろうか。
そのために、マスコミやあらゆるメデイアは全力投球してもらいたい。
059. かくされた真実、もう一つの真実
実はこうでした。本当のところは。
身近な人間関係においてもなかなか本当の気持ちは分からないことがあるが、ちょっとしたすれ違いから行き着く結果は大変違ったものになってしまうという経験は誰にもある。
又、世間の出来事も今度の原発の事故の経緯も、再審無罪になる判決も、本当はどうなんだろうと突き詰めるところに真実はなお、かくれんぼをしてしまう。
自然の驚異や生物の不思議な営みを知ることは、この上なく魅力的なので、人はその解明に向かって突き進む。しかし、何処までもかくされた真実があるようで、死後の世界さえ本当にあるのかないのか。心と脳の関係はどうなっているのか等こんなことに思いをめぐらせると、なかなか寝付けるものではない。
夫婦、親子、精一杯、絆を育んで生きているのだが、新聞の人生相談欄など読むと相談ごとはかくされた真実を何とか知りたいという想いがあふれている。
凡人には、人のことどころか自分自身の真実さえつかみかねないのだから致し方ないのだけれど、本当に何が起こって、如何なる因果関係で如何なる結果になったのか。
相手の立場を思いやったばかりに、想像もしなかった結末を迎えるということも、科学的に分析しすぎて本当のところを見落とした医療現場など、果てしない不思議な真実に身をゆだねて人は生きているというのだろうか。
静かな女房の寝息の向こうにも、もう一つの真実があるのだろうか。
深夜のラジオ便を聞きながら実に深い浮遊感を遊んでいるもう一つの真実の自分がいる。
060. 1日3杯以上コーヒを飲めば花粉症がスッキリ
1日3杯以上コーヒを飲めば花粉症がスッキリ治るなんてことがあれば、天にも昇るあり方情報なんだが、そんなことはありえないね。
大学を出て東京に就職。翌年から、わけの分からぬ風邪症状に悩まされ、とても痛い鼻の造影検査など、あれこれ検査をされた挙句、スギ花粉アレルギーかもとの診断。
様子を見ましょうと言われ、桜花見の頃を過ぎた頃から嘘の様に症状がなくなり、やっぱりアレルギーと分かってから今や40年余りが経つ。
関西に戻っても「花粉症」という病名はもはや一般的で、多くの人が悩まされていることが明白な事実。アレルギー症状では名医と、シーズンには患者が列を成す医院を見つけて抗体検査などもしてもらって、スギ花粉以外にもヒノキ花粉に反応していることを知ったのも20数年前のこと。
以来、その先生に毎年2月頃から注射を打ってもらうと1ケ月に1度くらいの注射でそのシーズンはほぼ快適に過ごせて、他人にはそんな注射は副作用があるかも、などといわれたが、なにしろ毎日、薬を飲む手間もなく快適なので、ずっと御厄介になっていたが、数年前、その名医が亡くなられたために又、抗アレルギー剤を処方される病院や医院をウロウロする羽目になった。
尤も、花粉の飛散量が少ない年は軽症で収まるのだが、それにしても心地よい季節のはずの春先がなんともうっとおしいのはやりきれない。
花粉飛散情報など、初めてアレルギー症と診断された時はまだなかっった時代である。
昭和から平成、これだけ世の中色々な技術革新があったのに、花粉アレルギーの対症策が進展しないのはまことに合点が行かぬのだが、世間の方はどうなんだろう。
1日、3杯以上コーヒを飲めば花粉症がスッキリなどというデマでも流したくなる、いやデマにもすがりたい今日この頃である。
廣瀬 滋著
私の思考散歩・生活雑感 ぽつり草々 041〜050
041. 京都は多様な生活演出、訓練の舞台
京都に生まれ京都で育った私にとって、大学を卒業して昭和40年、東京の設計事務所に就職するまで、京都の文化・風土や生活慣習の中で自分が如何に育ったのかをそれほど意識することはなかった。
うどん屋での薄口、濃い口醤油、味付けの違いから、初めての寮生活の1人暮らし、自炊のための食材買出し、市場ではなく、渋谷のデパートの地下、魚売り場でも関西では見かけなかった金目鯛の赤い姿。何かが違うと感じた東京生活の始まり感はいまも鮮明である。
勿論、言葉使いも違う。仕事での電話の応対にもしばらくは苦戦。身近に地域社会を感じられない。これが大都会か。
やがて生活舞台となった渋谷、新宿、六本木・赤坂あたりを同僚や友達仲間とアングラ劇場での演劇公演、コンサート、色々な社会問題の研究会、新しいタイプの商業施設など、若い世代のすさまじいエネルギーが溢れかえる混沌の中でその新鮮さに感動もしていた。
アメリカの月面軟着陸成功、小型IC化電卓の発売、男子服のカラー化、女史雇用労働者1000万人を越えるなど、1960年代後半からの社会の変化はあらゆる生活舞台に変化をもたらし、その渦中に日々の暮らしをしていると「進歩」「拡大」「変化」全てが自分の成長感とイコールな気分であった。日本の高度経済成長期といえるこの時期にグローバル化の潮流が起こりはじめ、生活価値観の変化が日本の文化の成育の方向性を見失わせ、表層を意図なく無差別に覆い尽くすことになったと思える。
6年間の東京生活を終えて、京都に戻ったとき、京都駅の静けさに「これはなんだ。」とわけなく驚くと同時に、本当にほっとした安息感を記憶している。
再び、祇園祭の鉾町に暮らし始めて、子供の頃と比較すれば形骸化したとは言え、町内の祭事、学区の行事、京都の四季折々の祭りごとなど生活を彩る出来事は身近で、地域社会の一員として生きている「場」の実感がある。祖父、母親、自分、そして子供と4代が通った明倫小学校が都市のドーナツ化現象による学童減少で廃校になったが、校舎がなお、芸術センターとしてそのまま、その姿をとどめていることは、不思議なほど自分の歴史、時の流れを原点化してくれる。
ヨーロッパの都市における、旧市街、新市街といった明確に区分された歴史的計画性はないが、京都には地名(町名)に名残を残すようにちょっとした一画が色々な伝統や名残をとどめて渾然と存在し続けている。そのため、いまだ市民レベル、生活者の身近なところで自然に受け継がれていく文化の土壌を失っていないと思う。
社会の変化、伝統産業の衰退にあわせて、ほんの隣にも職人のおじさんが住んでいて、色々な分野の技や芸を身近に見聞できた子供時代のようには行かないが、今でもまだまだ色々な職人魂からにじみ出る所作や言動が、自治会活動や日常の生活の中に息づいているのを知る。
「ハレとケ」「究極のコモンセンス」「特殊解と一般解」「右脳と左脳の働き」など、いずれにもバランス感覚を如何に取るかの才覚がとても重要であるが、京都は都市と田舎、伝統と現代、生活価値観としての美意識と感性が実に程よく日常生活の中に感じられるところである。
それは、1000年以上にわたる「都」としての歴史が育んだ誰もが簡単には捨て去ることが出来ない精神的、感性的DNAとでもいえるものがあるせいであろう。
時々仕事の関係で、東京に行くことがあるが、ますます複雑になった地下鉄の路線図に戸惑うように、霞ヶ関に始めて高層ビルが建ったときから、都心の開発、建築技術力世界一の日本の力がいたるところに見られ、即、インターナショナルであることが、かえって日本人の美意識の根底に潜む特殊解の魅力を捨てて一般解にしすぎてしまったように感じる。
東京には近・現代の機能主義、合理精神を象徴することに於いても、巧みに日本人の感性を表現しているところもあるが、その存在のスケールや固有性において、一人一人の人々の生活との絆を希薄にしてしまったために、日本の伝統、文化価値につながりながら新しい未来への文化創造のエネルギーを全体として育成できない「都市」になってしまったと感じる。
一方、京都は戦争による爆撃をまぬがれ、奇跡的に世界一歴史のある都市として生き残ったばかりか、その後の都市機能としての経済力の弱体化もあって大きな変貌がなく、歴史的な観光資源を始め、日本文化を担ってきた伝統的な工芸、技術や様式文化が今も残され、継続している。日本人の営みの歴史を垣間見たり、実感できる機会が身近にあるという都市環境は、やはり、生活を彩る感性を磨き、明日を生き抜く才覚を共有しながら鍛えあえる格好の「場」であるといえる。
042. 継承の大切さ
先日、ニュースで定年のない機械・機器メーカでは60歳以降も定年がないので、給料もダウンすることなく、熟年技術者と若手がペァーになって楽しく、生きがいを持って働き、技術の継承をやりながら、会社経営を見事ささえ、発展させている事例を取り上げていた。 社長は技術が継承されるこうした仕組みがなければ、会社そのものが存続できないともインタビューに答えていた。
近年、利益追求のため、能力主義偏重、デジタル的雇用が巾を利かせてきたが、人類の営み、生活を踏まえたものづくりにおいては、プラスもマイナスも含めてじっくりと継承されるシステムが必要である。
漫然とした終身雇用制をよしとは思わないが、従来の日本の企業風土は、終身雇用による共同体意識が、人々の精神的健全性をも育むゆとりをあたえてきた。
物の生産性のみならず目に見えない国家の質を維持・発展させることにも大いに寄与していたと思う。
生物としてDNAが継承する人間資質も勿論のこと、親子の間に継承される品格も、日々の生活習慣や倫理観などの伝え方、伝わり方によるところが大きい。
つまり、代々継承されるものの内、何が伝えられなくてはならないのか、色々な状況の中で正しく理解され伝わっていくかが大切である。
しかし、単身者世帯の増加、競争社会の中で切断される連帯や信頼感は、伝えるべきものの姿を見えにくく、伝わりにくいものにしている。
自然に継承されるべき日本人の特性、品格がぼやけてしまっては、将来、日本が多民族国家に移行していくとき、一層の混乱を生じるかもしれない。
環境問題は生命存続の喫緊事項ではあるが、民族の資質、文化継承は生きる意味の大切さ、人類存続の重要問題である。色々な教育環境、方法も時代に合わせて検討されるべきだが、終身雇用制が持っていたような職場生活と一体化した生活建築力の継承制度は大いなる日本の人間教育制度の一つではなかったかと思う。
現代、終身雇用制が崩壊しつつ、能力主義、非正規社員制度の拡がりの中で、新しい工夫や知恵を生み出す「場」、目に見えない大切な人の資質を育み磨く連帯感、利得抜きの思いやりが交流するチャンスが奪いさらわれようとしている。
長い間培われてきた日本人の力、戦後の経済発展を支えた力もその根底に日本の終身雇用制度や、江戸時代からの寺子屋など文化力を含めて伝える教育制度のおかげではなかっただろうか。
親子の間で継承すること、私が孫にも伝えたいことは何か。子供の頃、銭湯帰りの道で父親から色々聞かされた話を思い浮かべながら、まじめに考え込んでしまう。
姿も見えないネット交信者も、本心、何を伝えたのか聞いてみたいなと思った。
043. 新年のはじまり
元旦の朝、近くに住む長男、次男夫婦もそろって、毎年のごとく私宅で新年を祝う。
結婚以来、京都にいても山荘にいても、変わらずおせち料理をつくり続けてくれる女房殿には感謝。
「今年の黒豆の煮具合は」などいつも料理の出来具合に御託を並べる息子たちには、口にはしないが「文句を言うなら自分の嫁に作ってもらえよ」とちょっと気色ばんでいる。
それぞれ世帯を持ちながら、実家めぐりでおせち料理など作らない息子たちの気楽さ加減にそれぞれの家族のあり様はいかがかと思うものの、その実、こうして何時までも皆が集まって正月を祝える平安な時を我ら夫婦は大切にうれしく思っている。
暮れからお正月、女房殿の忙しさのストレスのはけ口は、全て私が受け止めて、小言を聞き流しつつ、ちょっとお手伝いの真似事で切り抜けて、無事新年というわけである。
次男の嫁は、今日明日にも出産という事態で、「何とか元旦、お雑煮も食べられて良かったね。」と皆で談笑。それでも12月31日に2歳になったばかりの孫の一挙手に、はらはらの連続、皆の目線を独り占め、にぎやかなことである。
私は今年も和服を着てことさらに日本の正月を味わっている。今年は帯がさっと一発で締めこなせたので気分が良い。それにしても和服は暖かい。環境問題、省エネ時代、昔の人、日本の文化は結構、循環型、自然に優しかったのだと想いが飛ぶ。
2日の夕方頃からなんとなく次男の嫁が「おなかが痛くなりだした」。夕食の後、これはいよいよだな。2歳の孫、はるちゃんを我が家に預けて夫婦でいったん帰宅し、その後、病院に行く手はずとなった。孫は一応聞き分けた様子であった。
いつものお泊りどおり10時前にはお風呂にいれって寝かしつけようとしても「母さん、心配」となんと目に涙浮かべて12時になっても眠らない。女房殿が抱っこしたりおんぶしたりでやっと寝付く。 病院のほうはどうなったやらと思いながらラジオを聴きながら寝室で添い寝をしていたら午前の4時に目を覚まし、また「かあさんは」としくしく泣き。女房殿はダウン。2階に下りて「DVDを見る」と言い出す。気を紛らわすのも致し方なしと私が抱っこして居間に降りる。機関車トーマスの物語は不安を取り除くにはだめとみえ、Kiss、キスという色々な歌が流れ、調子よくダンスが流れるDVDを所望する。
真夜中というか、あたりは静寂の中、薄明かりの中でDVD画像のみ元気よく流れる。
時々画面に反応しながら何か歌真似。もう寝るかと思いきや、「もう1回」とお目めパッチリ。とうとう朝の7時まで3度も同じDVDを見るハメになる。4度目に入るかと思いきや私にもたれてコックリコ。寝室に運んで、又、起きられてはとソファにねかせる。
あたりはすっかり夜が明けて、結局「徹夜か」と寝顔を見ながら覚悟を決める。
044. 日中関係の行方
ここ数年、日本と中国の関係は経済活動の相互関係が拡大するにつれ色々な軋轢、摩擦も又、人的、文化交流もすべてにおいて抜き差しならない関係段階になってきていたが、特に、経済活動における利害関係の先行突出が最近の尖閣列島における領有問題を機にあらわになり、隣国同士の平和な関係を築こうと目指す多くの願いを、暗雲の彼方に吹き飛ばしてしまいかねない。
共産主義と元々の中華思想に洗脳された中国の人々の色々な生活局面での振舞いは、日本人には馴染めぬことも多く、アンケート調査などでも日本人の対中国への好感度は低い。
自国民の先達が営々と築いてきた文化や技術に対する尊敬の思いなどに対する対応の違いなどは中国に、「井戸を掘った人を忘れない」などということわざがあると聞かされるのに合点がいかないことが多い。
日本の企業も,経済的合理性を,収益性を求めて、集中的に中国に投資、生産基地化につとめてきたが、すこし目覚めても良い時期なのかもしれない。
国家間の平和関係を考えるとき、冷静に正義の判断が出来ないくらい、経済関係(利害関係)の駆け引きがキーポイントになるようなことは、卑近な男女関係に等しい情けない関係とも言える。
アジアにも多くの国家民族があり、最近の中国の中華思想による覇権主義の行動は周辺国にも多大なプレッシャーを与え、アジア圏の日常的な安寧を脅かし始めている。
情報化社会、グローバル化時代、もはや確かに1国だけで色々な問題が解決されるわけではないが、だからこそ、世界の諸国は、ひと時、中国への投資を控え、中国の覇権主義への熱を冷ますことに一致協同する必要があるのではないか。中国が今の経済的発展は決して自国の力だけで達成されたものではなく、多くの国の援助があってのことだいうことを認識する時間、チャンスが必要かと思う。
日本もまた、経済効率ばかりを追い求めるのではなく、国内において人類に必要な技術開発などの研究、製品作りを人材育成、雇用創出もあわせながら智恵を出していかなければならない時代である。 20世紀後半からの人類の進歩思考はその成果の中で曲がり角、転換を求められている。現実問題としての世界、いたるところの紛争は同じ種から火を噴いている。 これからの日中関係のゆくえは?日本の政治家はどうしようとしているのか。
最近の日々の新聞、テレビなどのニュースにごまめの歯軋りをしている。
045. 孫と夜の公園遊び
いつも孫が来た時、夕飯を終えても、家に帰る寸前まで遊びの相手に爺ちゃんをこき使うのだが、今夜は夜の梅小路公園に行きたいと言い出した。ちょっと前に一度夜の公園を散歩させたことがあったのだが、「肝だめしに行こう」という今日の誘いは、きっと幼稚園でも「お化け」とか妖怪の話しが出ることがあるのだろう。
小さなLEDの懐中電灯と孫は自転車のLEDランプを取り外し、すつかり暗くなった公園に向う。今日は3歳の妹も行きたいというので、二人の孫がそれぞれにランプを握り締めて昼間は何度も来て土地勘充分の公園だが、夜はほとんど人もなく、周回小道の坂を登る。 コオロギノ鳴き声が、やたらするどくあたりの空気を震わせている。植え込みの下草の一点にLEDランプをかざして、鳴き声の主を探そうとする孫だが、姿は闇の中。妹は何度と爺ちゃんの手を握り締めて緊張している。「冒険したいのなら、二人で先頭を歩かな」というと「お爺ちゃん、絶対おどかさんといてや。いいなぁ。」と念を押して、ゆるい下り道を大きな声で何かに負けまいと叫びながら駆けていく。 公園の南側はJRの線路で、長い照明器具に変身した電車が行過ぎる。「あれは、はるか号やなぁ。」「きれい」と一瞬、昼と夜の公園の時をつなぎながらつぶやいている孫たち。ぐるっとまわって中央の芝生の広場に出る。天を仰ぐと、日頃忘れかける都会の中の星空があって、ピカリと光る金星だけは名指しで教えることが出来た爺さんは、昔はもっと無数の星たちのこともはっきり見えたし、覚えてもいたのに、星のロマンから遠のいた我を発見。 野外ステージにきたら孫が「お爺ちゃん、あっちからライトで照らして。琴ちゃんと僕がお歌唄うし。」とランプを押し渡す。何事かと思う間もなく、ふたりはステージの中央で、二人で一緒に、歌を唄い、同じ振り付けで踊りを踊る。了解。爺さんは照明係り。
LEDランプを二台一緒に、時には一人ずつライトアップ。なかなか様になっている。すっかりスター気分で心地よく二人で大きな声で唄い踊る。婆さんや息子夫婦に見せてやりたい可愛らしさがあふれていた。周りに人はなく、この公演は爺さんだけのうれしいものであった。それから遠く前方に光立つ京都タワーに向けて、はぁはぁ息ききって走る。「さ、今夜はこれくらい。お父さんが待ってるかも知れんぞ。おうちに帰らんと」といったら、孫はすかさず、「まだ帰ってきいひんわ」と父親の遅い帰宅への不満がいっぱいの返事。今の社会情勢、父親が目いっぱい働いて、子供との日常生活時間が少ないのは、やっぱり子供にとって寂しいことだなと感じる。公園からの帰宅道は「お化けは出なかったね」等と言いながら孫たちと仲良く、仲良く手をつないで帰った。
046. 日本の厄年
人には厄年があって、男女それぞれの歳に厄払いをするという風習は日本では各地に見受けられる。
厄年が何となく成長の節目に当たるところもあって、それなりに用心を心がけるのも良いかと思い、私も、神社でのお祓いを受けたものだ。
新聞の死亡事故ニュースを見て、当事者の年齢が42歳だったりすると、「この人、本厄や」などと思わずおもってしまう時がある。
日常生活において、姓名判断や縁談、家相など、ことを起こすについて占いや厄除けは身近にしみこんでいる。
今年、日本は3月の東日本大震災、津波、原発事故、真夏の熱中症、先の9月の台風による災害、円高、政治の混乱。日本の厄年と言ってよいほど酷い年である。
想定外、未曾有のなどといって災難の結果を何とか運命と受け入れようとしても、まるで人災と言えるものも目に付いて、お祓いの世界とはちょっと次元が異なる想いがする。
けれども、ノーサイド、日本にヤオヨロズの神がいるなら、総力を挙げて被災地の復興の祈願に答えて欲しい。
日本人は過去に色々な苦難を乗り越えて、再生、復興を成し遂げてきたが、どこか厄払いを身近に実行、気分一新、未来に向かって、日々の努力を惜しまなかったからかも知れない。
047. 時の止まった喫茶店
この喫茶店は京都中京区室町、呉服問屋が居並んだ街中にある。
昔は呉服関連で働く番頭さんあたりが、情報交換や、休息にたむろしていた。そのため、外から目が差さないよう、入り口以外は明り取りの小さな窓があるだけで、昭和、平成と50年以上、そのままの姿である。
室内、インテリアと言ってよいのか、空間の全てが、マスターの想い入れで満ち溢れ、それぞれが知り合いのような、それでいて思い思いに雑誌を読んだり、何をするでもなく寛いだ老齢の男女の客が演劇の一シーンのように浮かんでいるのが日常だ。
マスターは何時の頃からか、夜間、自動車でドライヴしている時に、市内の民家や会社の前に廃品として放り出された品を見付けると、その中から自分の気に入るものや、まだまだ捨てるに惜しいものを集めることが「趣味」になったといえば嘘を言ったことにはならないと思う。
そんなことでマスターがいまだ命あるものと集めた家具や、生活雑貨、工芸品、着物や帯、置物、生活用具など全てが床から壁から天井まで、薄暗い照明の中、それでも、ちゃんとマスターのセンスでふさわしい輝きをするように配置されている。
自由に触れることも出来る気安さも流れている。
客の一人が、その一つについて尋ねごとがあると、マスターの見識が炸裂する。ばらばらのように見えたお客さんたちは、一気にその語りに聞き入って絆の輪にすっぽりと心地よく浸る。
祇園祭見物の時や、たまに知人を驚かすつもりでこの喫茶店につれて行くと戸惑いながらも、わけなく「ベリーグッド」を体ごと現してくれる。してやったり。とてもうれしい時である。
マスター一家とは子供同士が小学校以来の友達で、長い付き合いである。
マスターの不思議な人脈のお蔭で私も男物の着物をゲット。孫も遊具を。特筆ものは、マスターの知人に花屋さんがあって、高級な花が売れ残れば直ちに頂けるという夢のような仕組みである。
喫茶店のほの暗い中に鮮やかなランの花などがいつもカウンターやテーブルの上に息づいているのも時の止まった思いを抱かせる。私の家の玄関におすそ分けのランが旅をしてくることも誰にも言わない秘密である。
街中の知る人ぞ知る秘密の空間。マスターは若いころファッション関係の仕事をされていたので、その目利きは半端ではない。土曜日には、店の前に集めてきた収集品や衣服(新品もある)布地などを無償で台の上に出しておかれる。数時間後にはほとんど誰がもらっていったのかなくなっている。リサイクルなどと社会現象で語られることも多いが、マスターがこうしたことを自身の生活サイクルとして楽しんでおられるのを見るたび、何とも言えない爽やかな嬉しさでいっぱいになる。私にはまねのできないことである。
048. 2011.夏、別荘生活雑感(1)
今年は次男の仕事の関係で、毎年よりも1週間ほど早い時期に別荘に出かけた。
3月の大震災の影響で、長野の別荘もどこか壊れているかも知れないし、何より、今年もハチが軒先に巣を作っているのではないか等、女房殿は心配性の優等生。
幸い出発の日は天候も回復、高速道路もお盆にはまだ遠くスイスイ。出発間もない時から、[まだお山のおうちに着かないの]という孫たちに「まだ、まだ、まだ」とその都度、何度も外の景色や、雲の形に気をそらさせながら、サービスエリアに立ち寄って、日本一長い恵那山トンネル体感を印象付けたり、指相撲やジャンケン遊びをしながらお昼前には安曇野あたりに到着。
いつも安曇野では地元の野菜などを売っている店に立ち寄り、新鮮な野菜や果物をこれからの数日の山荘での生活のために仕入れる。
それから、お蕎麦屋さん。何度もいくお店もあれば、なにしろ安曇野には蕎麦屋さんが多いので、今年は別のお店に行ってみる。
こうしたことには次男夫婦のこまめなネット情報についてゆくのみ。
3歳と5歳の孫もそばには[つう]と言っていいくらい慣れ親しんでいるので、大人が天ぷらそばなどを注文していても、「ざるそば」が好き。
わさびもネギも抜きにして、とにかくそばをつゆに付けて黙々と食べるその姿は不思議と[つう]と言いたくなる。
[ここのお蕎麦、美味しかったな。]などといわれるとなおさらである。
あと少し、白馬のスーパでビールやワイン、色々な食材を買い込んで、やっとこノンストップで別荘に着く。
スキー場の中にある別荘は夏の草の中。隣のペンションも閉鎖されて久しく、今は、私たちのみが通る小道を少し下る。敷地の数本の大きな胡桃や雑木の間は雑草が生い茂っている。先発隊として次男と私が心配性の女房殿が用意してくれた蜂よけのネット帽子をかぶり別荘に近づく。蜂は一匹ブーンと羽音を聞かせたが、軒先や外壁には巣はなさそうだ。
とにかく、皆で荷物を運び込む。5歳の孫が結構小荷物を運ぶ手伝いをしてくれるようになった。
次男が初めて、率先して草刈機で草を刈り始める。今までは私が草刈をしてきたが、そろそろ世代交代と感じてくれたのだろう。しばらくして、「意外と草刈ってしんどいな」なんて今頃、笑っている。私はほぼ40年近く、草刈をしてきたが、草刈の楽しさはもっと先に分かるだろうと言いたかったが、[そやろ、そんなに楽なもんやないで]とだけ言った。とりあえず、小道からの通路や、ハンモックを吊るスペースや、屋外テーブルや椅子をしつらえる部分の草刈の格好がついた。あたりに、かじか蛙の鳴き声が響き、すぐそばを流れる小川のせせらぎの音が、木々をすり抜け吹き渡る風は、ひゃっと心地よい。温度は24℃。夏はクーラ不要。自然のありがたさをしみじみ感じながら1日が暮れる。
049. 2011,夏、別荘生活雑感(2)海水浴へ
山の別荘に滞在しているうちの1日は、孫の「あそび気分」の充実を図って、朝、天気が良い日に日本海に海水浴に出かけることにしてる。
糸魚川に1時間足らずで出られるので、親不知のほうに向うか、直江津方面に向うか、その時の気分次第である。このあたりは若狭の海水浴場のように遠浅とはいかず、ほとんどすぐに背丈の届かぬ子供にも大人にも不安を抱かせる海である。
次男たちが子供の頃に連れて行った親不知の海岸も、孫の水遊びには不向きかと、とにかく、車は、直江津のほうに向うことになる。
糸魚川のすぐ近く、一昨年行った小さな名もなき海水浴場は地元の人専用のような、トイレの設備もないところ。
昨年行った、能生海水浴場まではちょっと距離がある上、浜茶屋の印象も良くなかったなどといいながら、走っていると、ちらりと小さな赤い文字の矢印看板。
[大和川海水浴場]「行ってみよう」車をUターンさせて海岸方向に細い道を入る。
海岸沿いに防潮堤が数百メートルも続き、その外側にテトラポット。一見何処に海水浴場があるのかと言う景色だが、よく見ると、猫の額ほどの小石が敷き詰められた海辺に2,3のパラソルが経って、20人は越えないかと言う親子ずれの声が、かすかにさんざめいている。駐車場も有料シャワールーム、監視員搭も簡易トイレもあり「今年はここにしてみよう」と意見がまとまって海水浴のモード。
持参した浮き輪や小さな浮きボートに揺られて、孫たちは大はしゃぎ。今時の浮き輪は、一部分が透明になっているのでそこに目をつけると海底が見え、小魚が泳いでいる姿も見ることが出来て大喜び。私は大きな覗きめがねを持って浮き輪に乗って、沖合いに伸びるテトラポットと岩礁群のそばを遊泳。波のうごきに合わせてゆらゆらさぁーと動く海草の中でしがみつく巻貝や藤壺を遠い昔の記憶、子供の頃の海水浴を思い出しながら、眺めていた。小アジの群れが元気に通り過ぎる。
海岸はほとんどが研磨されつくした丸い小石で、それが又、色々な色、特に、真っ黒な溶岩石の中に色々なガラス質の粒がデザインされたように散りばめられ、輝いているのは美しく、この海岸との出会いをうれしく思った。
お昼に、パラソルの下で持参したおにぎりやちょっとした嫁姑合作のおかずを食べながら、本当に周りに数人しかいない静かな海水浴場はプライベートビーチの贅沢さだねと皆で幸せ気分。防潮堤の上に組まれた看視塔には赤いユニフォーム着た2人のおじいさんが時々吹き渡る海風に白髪をゆだねながら穏やかにこの夏の景色を眺めている。
昨年、病院通いをした[日焼け]の失敗はしないぞと、日焼けとめを塗って、長袖Tシャツで防備。それでも午後の陽射しは「太陽さん、元気過ぎるよ」と言いたくなる。
水泳教室で技を見につけた孫の[はるちゃん]は昨年とは段違いに海を友達として飽きずに父母と思い出になるひと時を過ごし、それを眺める老夫婦は時の流れとその行き先がどちらも幻のようで定かでない。小っちゃな孫の[ことちゃん]はやっと浮き輪に身を任せる心地よさが体感できたのか、一人で水際でゆれ遊んでいる。
夕方、帰り道の温泉で、皆ですっきりさっぱり。それから、白馬村のイタリアレストランによって夕食と乾杯。山荘に戻れば庭のハンモックが所在気に落ち葉を寝かせていた。
050. 別荘生活雑感(その3)
何ヶ月も空けて山荘を訪れると、大抵は何かの痕跡が静かに残されている。
オーディオ機器の後ろを掃除すると、丸くかじりとった胡桃の実がいくつも転がって出る。これは野鼠の仕業だ。
何時の年だったか、クリスマスの頃訪れた時、食堂のカウンターの上をあわてて逃げる小さな薄茶色の野鼠を発見。思わず童話を思い出すほど、可愛い印象だった。
「野鼠が棲んでいるんだ。」と心和んだ記憶が深い。
その後も越冬時には、家の中のどこかにひそやかにすんでいるのだろう。
暖かい時期に訪れると、地下室のダンボールの空き箱の中、もう履かなくなったスキー靴の中などに胡桃の食べかすを置いてどこかへ引っ越している。
冬以外は野外でのどかに暮らしているのだろう。
屋外には、リスが食べた胡桃の実がいっぱい散乱している。リスの場合は、感心するくらいきれいに胡桃の実を真っ二つに割っている。
庭の胡桃はヒメクルミなので小さく一度食用を試みたが、あまりにも手間が掛かったので、その後はこうして本来どうり、リスや野鼠のご馳走になっている。
蜂が家の中、リビングに巣を残していった年もあり、その痕跡に大騒ぎしたこともあった。
ごく当たり前に、いたるところで色々な虫がサナギの抜け殻を残していたりする。
たった一人で山荘を訪れたときなどは、ことさらにこうした痕跡が、不思議なぬくもりを感じさせてくれる。生き物の痕跡…。 それは生きる命の一瞬一瞬の記録でもあり、透明なくせに、私には重さを感じさせてくれるのだ。
廣瀬 滋著
私の思考散歩・生活雑感 ぽつり草々 031〜040
031. 検査疲れに負けるな
先日、「老いの発見」の出来事のあと、頭のCT検査は問題がなかったが、突然倒れるのは糖尿病のこともありますから、日を改めてきちんと検査を受けられてはどうですかと言うことで、検査日を予約することになった。
久々に検査前日午後の10時以降は飲食をせず、神妙な気分で検査日の朝を迎えた。血糖値を調べる検査は、何しろ退屈な検査である。2時間後に、病院を出て秋晴れの街に開放されたとき、60歳をすぎれば人間ドックなど検査は受けず、成り行きのまま寿命をまっとうしようと考えていた自分が、何でこんなことをしてるのか、「ええかげんなやっちゃな」と自分を笑った。
1週間後、結果と診断の予約日。担当の女医さんは、ちょっと数値が高いです。インスリンはでていますが、機能が落ちている。今すぐ薬を飲む必要はないと思いますが、食事内容に気をつけてください。それに、肝機能が弱っているようです。腹部のエコー検査、CT検査を受けてみてください。そこで又検査の予約。
それに、眼科でも糖尿の影響が出ていないか検査してもらってはどうですか。眼科は以前に行ったことがある眼科専門病院に行きたいというと、紹介状を書きましょうとの事。
続いて、栄養指導士から日々の食事について色々と指導を受ける。どうも、毎食、繊維質をとることがすい臓などに負担をかけず良いというのがポイントで、ヒヤリングでは私の昼食、朝食に繊維質の摂取が少ないとの事。又、間食は厳禁との事。
3日後、またまた前日から飲食を控えて、腹部エコー検査とCT撮影を受ける。とにかく検査だけのため、病院側の流れに乗って身をゆだねるだけのこと。翌日は、眼科専門病院へ行く。これが又、すごい患者さんだらけ。大はやり。視力検査の後、瞳孔を開いて検査するとの事で、麻酔薬のようなものを時間を置いて点眼。初めて受ける眼科の本格的な検査にちょっとビビリ気味の我を知る。「糖尿の影響は何もありません。ちょっと白内障のケがでています。」「今、どうこうはないので、半年後に来て見て下さい。」看護婦さんが、「今日はどうしてこられました。」と聞く。「自転車できました。」「瞳孔が開いて眩しいですから、気をつけて帰ってください。」 病院の外に出ると、ほんと、眩しくて、周りがハレーションを起こして帰り道が白い。ここ2週間ばかりの検査で、久々に自分の体の状態に向き合ったが、何か疲れたなぁ「やれやれ、それでもまだ寝たきりにならなくて良しとするか。」老いの発見、老いの検証。人生、最後まで気合をいれて元気でいこうと思った。
032. 「瞑想するマネキン」
京都駅から家路に向かう時、伊勢丹のショウウインドウをふと見ると,なんと目を閉じてはるか彼方を見ているマネキンが初春のファッションを身にまとい、ぽっねんと並んでいる。見なれた目に表情を込めたマネキンがおおきなガラス越しに、こちらをながめているのではない。
かって,ブテイックを設計した時,このマネキンに服を着せると売れる確立が高いというのがあって,マネキンの展示会などもオーナと真剣に見に行く機会があったが、それは、殆ど顔立ち、目などに表情があって、しかもポーズにいろいろと工夫がされていた。
最近はマネキンの展示会に行くこともなかったので情報不足で「何を今ごろ言ってるの」と言われるかもしれないが、「め」を伏せ、瞑想するようなマネキンが、ぽっねんと静かに、しかも華やかなファッションを身に纏い立ちつくす様を見た瞬間、現代人の孤独感が実に良く表現されていると思った。
街を行く人々に漂うものを、このガラスケースの中に閉じこめ、共感と連帯を求め、訴えたのだ。この正直なアピールは消費に結びつくものになるのか興味があるが、感性マーケティングなどといわれるものの一つなのかとも思う。
情報化社会と言われて久しいが、個人が携帯電話やインターネット等によって現実に情報のネットワークに包まれると、殊更に一人一人が孤独であることがあぶりだされてしまったのだ。
何となく気付かずに気軽にやりすごしたかった人間の存在根源の重さを、多くの人々が感じざるを得ない現代こそ、その奥深い不安に打ち勝てる生命力を持たねばならないと『天』は迫っているのだろうか。
今日よく云われる「癒しの時」と言うのは、迫り来る人類の根源的変貌を予感して猶予を願う時なのかも知れない。住宅設計においても、個人の、家族の孤独のあり様が考えられなければならなくなるのではないか。
シェルターとしての機能性は留保されるとしても、日々の家事の利便性は優先されるとしても、個々の孤独に打ち勝つための生命力を磨く道場として、より消極的に捕えるとしても、癒しの『場』としての住空間のあり方がもっと重要視されるべきではないか。
住まい手とのコラボレーションを通じて共に考えていきたいことであり、過去の空間設計のディテールが具体的にどの程度有効なのかも探らなければならない。
IT革命と云われる今こそ、人類ドラマの渦の中心に在って変わらぬものを見据ヘ、瞑想するマネキンを意識していたい。
033. 「夢」
夢というのは、なかなかに深く面白みを含む言葉である。
将来の「夢」というときの「夢」は将来、何になりたいとか、自ら目指す目標に到達したいとか、意識上での願望でもある。
「夢」のない人生などというと、とても悲しく哀れですらある。
「夢」を持つことは努力してその夢に向うエネルギーを自らにうながし、日々の活動に目的意識が生まれ、生活を活性化することにもつながる。
しかし、「夢」の大きさ、実現度によっては、夢破れ、挫折感を味わうということもあり、時には一瞬の「夢」に終わることすらある。
その点、無意識中というのか睡眠時に見る夢は、実にリアルな日々の出来事をビデオを見るがごとく見ることもあれば、荒唐無稽、はっと目覚めて思わず笑ってしまう「夢」や、なかなかに恐ろしい夢や、とても幸せ感に浸れる夢など色々である。
正夢、白日夢、逆夢、夢騒がし、夢の夢など多くの人が、実に色々な夢を見ていることだろう。
夢の中では、亡くなった両親とも会えることがあるし、大学生の頃、トリュフォー監督の「突然炎のごとく」という映画を見たことがあったが、後日、主演のジャンヌ・モローと僕が小船に乗って夜の川を流れ行くシーンは「夢」とはいえ、いまだ思い出す印象深い夢である。
せめて、夢の中ででも、想いを寄せるマドンナと語り合う夢を見たいものだと思うのに、まったく夢にも現れず、ため息で目覚める青春の日々。本当に「夢」はゆめだからこそ、空想の世界に残り香のごとく楽しさを漂わせる。
いずれの夢にしても、夢を持つこと、追うことは、明日を生きる指標を意識することであり、その実現までは、たとえよこしまな欲望と紙一重でも、どこか許される美しさを感じさせるのは不思議である。
この世の現実に「夢」を追うことも、人にとっては空想のごとき人生のはかなさを感じるがゆえであろうか。
「夢」は深く透明感のある言葉であると思う。
034. からだのリセット(断食)
先日、「病気がイヤなら油を変えなさい」の著者、杏林予防医学研究所の山田豊文氏の講演を聞く機会があった。
マーガリンはプラスチックです。牛乳を飲んでいると骨代謝のバランスをかえって損ね、アタマの切れる子になったり、色々な病気のもとになる。
最近の無差別殺人事件も、社会環境などよりも戦後からの食生活の間違いが脳に悪影響を及ぼして人を殺したいという衝動をおさえられないからです。
メタボリックシンドローム、アトピーなど昔は日本で余り問題にならなかった健康障害がなぜ出てきたか。
分子生物学を研究されてきた立場からの説得力のある話に会場は静まり返っていた。
チーズや乳製品を摂取すれば、立派なからだになると思っていた人は、私だけではないだろうが、ことごとくそれが誤っていることを、研究データを示しながら話されてみると、戦後の食の欧米化を今更ながら真剣に振り返って見る必要がある。
今の医学は、崖っぷちに立たされた人が落ちないようにするのではなく、落ちてくるのを待ってあれこれいじくっている。
医療行政の仕組みもおかしい。ぽんぽんと威勢良く講演ははじける。
人間を構成している60兆個の細胞が元気になることを考えるのが基本である。
その細胞に直接関与するのが油(脂質)ということで、良い脂肪酸をとること、骨代謝が正常であること、骨の健康が長寿のカギということで、カルシュムの脱灰の仕組みを知ることの大切さ、生の食材から食物酵素を補給すること、肝機能を高め有害物質を解毒すること、腸をきれいにすることを力説された。
自動車を車検に出すことはごく当たり前に行なわれている。どうして人間のからだをリセットしないのか。断食という手法。研究の結果、必要な養分をとりながらの断食法は有名なプロ野球選手や芸能人などが山田氏に師事、健康的にその成果を挙げているという。
リセット。人は、日々のストレスから開放されるために色々な工夫を行なっているが、自分の体をリセットすることが「断食」ということでもあることに意外と気付いていないのではないか。リセットはある意味ポジテイブな生き方でもあるとの説である。
断食というと3日、7日、21日と期間もあるそうだが、ちょっと覚悟もいるかと思いながら、挑戦、いや、リセットをしてみたいと思った。
しかし、結果的に断食に必要な栄養分と言う高価な液体を販売するセールストークにつながっていたので、食生活の健康に影響大なることやリセットの意味合いは理解しながらも、どうせ人間は死ぬ。寿命は定めという諦観も持ち合わせる身には、その液体をその場で買い求める仲間にはなれなかった。
035. 困った隣人
いっぱいゴミガラクタを溜め込んでゴミ屋敷になって近隣住民を困らせたり、野良ネコや犬などに無分別にエサをやり、結果として悪臭や騒音、環境汚染などで近隣住民に迷惑をかけても一向に意に介さない人がいることが度々テレビ番組でも取り上げられているが、国家レベルでの困った隣人と呼べるのが北朝鮮である。
話し合い(6カ国協議)にものらりくらりとその場を交わし、都合が悪くなればだんまりを決め込む。そして開き直って隣人を威嚇する。 全ての朝鮮人の品性がこれほどひどいと思いたくないが、今の指導者や支配階級の自得一辺倒の生き様は本当に反吐が出そうである。
中国やロシアも国連の理事会では決まって北朝鮮の肩を持ち、何が国益なのか良くわからないが、貧相な国民性を世界にさらしている。歴史上、中国支配民族・権力者のすさまじい強欲地獄を反面として、孔子や孟子などの賢人が出たのかとさえ思わせる。
近年の地財権に関する対処にしても、一般庶民を無視した都市開発にしても、一党独裁の政治システムだけでは語れない中国人権力者のバランスを欠いた中華思想が大いに影響していると思われる。困った隣人が持ち合わせている性格、品性である。
見渡せば、アフリカでも中東でも困った隣人同士が果てしない強欲の突っ張りあいをしている。
この性格、焼きなおさなければ直らないなどと言うが、人間とはそもそも困った存在なのだろうか。こうした混乱の世界情勢の中で、元来、日本人は比較してみれば結構バランス感覚に優れた民族であり、助け合い「結」の精神性などが、社会システムとしても暗黙裡に機能する姿は、震災復興活動などにも垣間見えて、世界から注目されている。
東洋の島国、日本は今まで情報発信力が弱いというか、自己主張をあまり得意としない国柄であったため、商人道に於ける「三方よし」のような精神が生活の根底にあることがあまり世界に知られていなかったのではないか。困った隣人には皆が和やかに生きられることこそ幸せな社会であることを、理屈抜きで承知してほしい。
昨今、中国でも共産主義の破たん傾向から仏教信者が3億人にも達するという。前を向いて生きようなどと、自身、叱咤激励しているが、困った隣人、北朝鮮の核実験、ミサイル発射のニュースは人間存在に疑問を抱かせて怖いものがある。
036. 生活美人について
いろいろな人間活動、その「道」のプロフェッショナル、達人はよく知られています。
しかし、身近な日々の生活の中で自分の生活を活性化できる感性と才覚を持つている人。日常性と非日常性の自分なりのバランス感覚を持っている人。
生活の中で、快適、美しい、落ち着く、便利など生活を左右する感性を空間(環境、現実の住居などを含めて)、もの(家具や道具など)、システム(手順、作法、所作なども含めて)として演出、表現、展開できる人。別な言い方をすれば、生活シナリオを想い描き(ストーリ化)、その実現・演出のために必要なものや手段を工夫、考案できる人。そのような人のことを私は「生活美人」と名付けています。
生活美人と「片付けの上手な人」、「お掃除の上手な人」、「お料理の上手な人」など家事の達人とは異なります。
生活美人はある意味、生活シーンの多様な状況の中から新しい発見、気付きに鋭敏で、その時々の最適な方向性や問題解決にバランスの取れた才覚を発揮できる生活ジェネラリストといえます。その道の業師としてのプロと言うのではなく、老若男女、誰でも生活美人になれ、かつ生涯生活美人としての資質を磨き続けることが求められます。生活美人にはゴールはありません。人間国宝とか、技能士といった資格検定もありません。
しかし、生活美人として生きるという自覚を持つことが出来れば、そこからいろいろな展開に可能性が生まれるでしょう。
自分の日々の生活、行動の中に、絶えず新鮮な感性情報を取り込み、又確認する習性をつけることから、新しい生活スタイルをイメージする、生活のシナリオ化を試みることを楽しみましょう。
体験的に、生活美人への道は、家庭生活においても、職場や学校生活においても、その場、その時の場景や事象の中に何かを気付き、新しい問題意識を持ち、その解決に向けて知恵、アイデアを創出することを心掛けることに見出せると思います。このプロセスは、プロデユーサやデザイナーの研修、職能体験に近いものがあると感じています。
あなたの中に生活美人としての資質、感性、才覚がどれだけ隠れていますか。
気付いていない、意識していなかった、あなたの生活美人度を覚醒しましょう。
おしゃれに生きる力が実感できるようになり、幸せ感が身近にイメージできるようになると思います。
037. 「仏教の来た道」展を見て
自宅のすぐ傍、西本願寺の前に龍谷ミュージアムがある。
まだ開設されて2年にもならないのだが、展示会が不定期なため開館しているときが読めず、散歩がてらにのぞいて見ようと思って行くと、何も催しの無い時だったりして、気になる施設でありながら外から眺めるだけであった。
4月の終わりから、特別展「仏教の来た道」が開催されていて、これは見逃せないと思いつつ、6月になって仕事の気分転換を兼ねて昼下がり出かけてみた。
20世紀初頭に西本願寺代22世門主、大谷光瑞師によって組織された「大谷探検隊」のもたらした資料を中心にシルクロードにおける様々な民族・言語・文化の交流の有様を多角的に紹介している展示会である。
仏教の源流を感じさせてくれるガンダーラの仏立像等の石像や仏伝浮彫にあらわされたその教えや説話の数々は、なぜか心を吸い取られるようで心地よかった。
又、西域の仏教文化と多様な宗教の関係も丁寧に解説展示されていて、ゾロアスター教やマニ教など日頃区別もつかない無知な世界にいる自分だが、とにかく、人類が何か心頼りに「命」のありかを求めて、祈りの気持ちをかくも美しい仏像や壁画に表すエネルギーを持ち合わせていたという歴史に感激した。
インドで誕生した仏教がガンダーラ、西域を経て中国へ、そして日本にまで伝播してきた人類の血の流れのようなものが見て取れて大谷探検隊の活動の意味が、今のこの時代にこそ、その価値を輝やかさせていると思えた。
ウイグル語の経典など、なんとも読むことすら出来ないが、一生懸命書き写された様子はひしひしと伝わる。
仏教の経典にも阿含経、般若経、妙法蓮華狂、維摩経,無量寿経、阿弥陀経、金光明経などいろいろあって,その特徴的な教えがシンプルに書かれた解説もいっぺんに賢者になれるような気にさせてくれる。
音声ガイドを聞きながらとても充実した時間が過ごせた。
NHKと龍谷大学共同のCGによるペゼクリク石窟の再現映像もとてもすばらしかった。
038. 新年散歩
正月3日、運動不足を解消と女房と二人で散歩。
年の暮れに人から「神様は怠け者、いつも寝ていることが多いので、余りいろいろ頼んでも、ご利益をかなえてもらえることはない。」と聞かされた。
本人の努力や研鑽がなくて、神頼みなんて言うのはそりゃ無理なことだろうと思うが、ズバリ言われると新年の初参りも、込み合う神社へ出向く気が薄くなる。
近場の東寺界隈にでもとブラリ。東寺へはガラクタ市や21日の弘法さんなど比較的散歩がてらに出かける定番コースでもある。いつものように北門から境内に入ると石畳みの道。弘法さんの日にはこのあたりも出店でいっぱいの通り道であるが、さすが正月3日。ほとんど人通りもない。
やや行くと掘割があるが、橋の脇すぐ、堀の中、いつもは亀が甲羅干しなどしているわずかな平場を持った石台の上に、なんと「サギ」が1羽身じろぎもせず佇んでいる。冬の風に胸元の長い毛のみがそよいでいる。「珍しい。鷺や」「ゴイサギとは違うな」となんとなく高揚した気分で私が言うと、女房はすかさず「あんた、お正月から詐欺に会うてどうしますね。はよ通り過ぎんと」と腕を引っ張る。ああ、なるほど、サギと「詐欺」ね。女房はいつもこうしたことに頭が回るので、「吉本興業に就職したらよかったのに」と冷やかしながら境内の奥に行く。
いつもの様に弘法さんにお参りして、南門を出ると、通りの向かいにまっすぐ南に向かう道があるのに気が付いた。きっと昔は南門に向かっている何か由緒ある道かも知れないと初めてその道を南下することにした。京都に住んでいても、この辺りは初めてくる。
二人で街並みのどこか京都らしくない、密度のないことをあれこれ評しながら10条通りまで下る。城南宮まで行ってみるかと東に向かうが、結構、寒風が厳しく、油小路通りでは阿吽の呼吸で北に向かう。この通りも拡張工事が長い間続いたが数年前、大阪方面への連携道路として完成、今や幹線道路の感がある。
こうした街並みの切り口には京都らしさよりも今の文明がいたるところに顔を見せているので、こうして散歩する視線には煩雑すぎて疲れる。ほんのわずかな距離ではあるが、自宅の近辺を歩いてみると、あらためて今の京都の歴史・文化と現代の文明との混在を知らされる。ヨーロッパの都市計画と日本の街並み計画の出発点、焦点のあてどころの違いを感じざるを得ない散歩でもあった。
039. 究極のコモンセンス
辞書にはCommonsense(コモンセンス)とは常識的な、常識でわかる、明白ななどの意味づけがされているが、元々、Commonには普通の、共同の、公衆の、などの意味があり、Senseには感覚、観念、思慮、意味、多数の意見などの意味合いが込められている。日本語の「常識」には、普通一般人の有す、又有すべき標準知力。専門知識でない一般知識と共に、理解力、判断力、思慮分別を含むとある。
何が一般的なのか、世間の常識に照らし合わせて如何なる言動を振舞うか、日々の生活の中で人々は刻々とコモンセンスという規範袋の中から生活観念、判断指標などを選択しながら生活を営んでいる。常識を超えた判断力が時と場合によって色々な窮地を救うこともあれば、常識に従ったお蔭で災難から逃れることもある。
つまり、一般に、生活シナリオは、いわゆるコモンセンスを基軸に成り立っているのだが、それぞれ個人が自分なりの生活シナリオを描こうとすれば、ストーリの展開される場所(空間)や、時、意味合いなどによって異なった表現、演出を巧みに選別しながら行動をしなければならない。
異なったストーリ展開、演出であればこそ個性が感じられ、人々は自らも、又、他人にもその存在を確認させることが出来るからである。
しかし、ここで大切なことは、よく言う「相手の立場に立つ」などコミュニケーションの原則のように、自らのシナリオが相手に理解されることが必要になるので、コモンセンスの許容範囲、容量を如何に捕らえておくかという問題が生じる。
究極のコモンセンスとはまさにこうした変幻自在の状況変化の中で、如何にバランスを取りながら、自らの感性、才覚を発揮させうるかという極意の「もと」のようなものである。究極のエゴイストとして生きるなどと、わけなく粋がっていた若い頃の自分の思考回路と、どこか似通っているように思える。
わかった様な分からぬ「究極」という見解であるが、ある意味、決め付けてとらわれた感覚、思慮、意味などをもたず、自由に生活シナリオを展開するという心意気を持って、かつ、天下に、人々に迷惑をかけない、どこか「美」という価値尺度を掲げた道理、それを究極のコモンセンスと呼んでみたいと考える。 共感が得られるか定かでなないが。
040. 理想への狂気
世界の至るところでの争いはその根底に人間の理想や夢に対するあこがれ、あるいは願望への執着がもたらす狂気ではないか。
日本における終戦記念日8月15日前後には、いろいろな報道特集やテレビ番組で、日本が第2次世界大戦に突入、特攻隊、最後は原爆投下に至る敗戦のあらゆる局面を改めて知らされる機会が多いが、その背景には「大東亜共栄圏」を築くという願望・命題がいつの間にか多くの国民を巻き込み、学徒出陣をした若き精鋭たちにも戦争という現実の暴挙を、壮大な国家命題に志向する、理想への参画という幻影に重ねて、狂気への麻痺を受容したと思える。
今、ヨーロッパ共同体(EU)も積年のドイツ、フランスの戦闘をはじめとする戦乱の歴史を清算して、共存共栄の欧州圏を築こうとする理想、願望が発端である。
その提唱が「大東亜共栄圏」のように日本一国ではなく、複数国家の協議、外交力によって進められたこと、多分に第2次世界大戦の教訓も含めて狂気に至ることなく進行しているが、個々の国がひとたびその願望や理想の方向に独自の利得を抱けば、たちまち狂気が頭をもたげ、理想そのものの崩壊につながる危険をはらんでいることも先のギリシャやスペインの経済破たん問題の処世に感じ取れる。
また、「アラブの春」以来、イスラム教と政治とのかかわりもそれぞれの集団や民族がいかに自分たちの理想や願望に忠実であろうとするか、狂気の戦いである。
聖戦という発想は「狂気」以外の何物でもないと思える。
もし人々が、日々の生活を穏やかに過ごすこと、お互いが思いやり助け合って暮らすこと、現実のあり様を基本として大切に生きることをモットーとするなら、至るところの紛争はかくも過激になることはないであろう。
しかし、人間は夢や理想を持つこと、創造的に環境を生きる特性を持ち合わせ、そのことが生み出すいろいろな利得をも享受してきた。「少年よ大志を抱け」をはじめ、人は成長の過程で絶えず理想や夢を持って生きることを教育され、確かに日々の生活はその価値観によって緊張を保ち、進歩、達成感によって活動のエネルギーは代謝しているといえる。
宗教と科学の究極の対決もまた、それぞれの理想の極みへの狂気の思い入れであり、過去には宗教裁判などで多くの血を流しているという史実がある。
つまり、人間にとって理想や夢を抱くことは大いに活動の原動力になるが、その理想や夢が独善的、独りよがりのものとなり、その達成のためにはいかなる犠牲も払うという狂気に達した時、その理想は意義を失った無意味なものとなり、破壊と、混乱、滅亡を現実化させる。狂気の熱情。そして究極のコモンセンス。岐路に立った時、いかに生きるか。終戦記念日のころはことさらこのことが気になって重い。
廣瀬 滋著
私の思考散歩・生活雑感 ぽつり草々 021〜030
021. 大いなる不安
今日も事務所を訪れた設備関連業界の営業マンの方と話しをしていたのだが、結構、不景気というのか、言葉では言い表せないこれからの日本社会に押し寄せるプレッシャーがいたるところの企業周りで語られているという。
ここ2年来、我々の設計業務においても、何か風向きが変わったというか、臭いがしなくなったというか、今までとは何かが違うという思いがひたひたと押し寄せているのを感じていたが、単純な経済不況というものではなく、今まで色々な困難を乗り越えてきた日本人のDNAの資質をもってしても、いや、その日本人のすばらしいDNAが溶けて突然変異を起こし始めているような流れが感じられる。
○○さんと呼ばれていた職業が、機械化、合理化の波に飲み込まれ立ち行かなくなった事例はたくさんあるが、地球環境問題におけるCO2削減目標の実行、M&Aのような企業買収・合併など今までになかった事由で中小レベルの企業や職業が一瞬に消滅していく時代では、その背景にあった生活・文化は津波にさらわれるように遠く旅立ってしまう。
たとえ、記憶が、歴史が記録として残っても、この傷痕は日本人のDNAに突然変異をもたらし、もはや日本人は新種の日本人になるのではないか。バブル経済崩壊後の不毛の10年、そして構造改革という日本人の精神解体の時代を経て、一体、我々の日本はどうなってしまうのだろう。とても気味悪い不安感が漂う中で、多くの人々が次の一歩を、明日の生活をどうしようと悩んでいる。
あちらこちらで噴出している社会現象の根深いところでの変異を知ってか知らずか、もっとも舵取りをしなければならない政治家は、今日も政局ゲームをしている呑気さである。
大概、人生においてはプラス思考で取り組んでは来たが、今、感じる空気は得体の知れない何かを感じさせている。資本主義社会の経済活動が、貪欲な金融システムに支配されることで、人間本来の活動を越えたブレーキの利かない社会体制を生み出し、貧富の格差、そこに連関する多様な社会格差をもたらし、人々はあえいでいる。
こうした状況にあっては、主義・主張やイデオロギーをまこと淑やかに振り回し、上から目線で何を論じたところで現実は一向に改善されない。アベノミックスなどはその最たるところであろう。女性が社会で活躍する社会は良いことであるかもしれない。しかし、そのことで、男性の給与所得が相対的に抑えられ、女性は非正規雇用でうまい具合に低賃金で労働提供することになっている。男女の基本的な役割の崩壊が、育児の問題(保育所不足・待機児童問題)少子化の問題など、波及的に引き起こしている。IT技術の進歩の今、女性の仕事のあり方は、より先進的なかたちで、工夫されれば、育休問題も改善されるだろう。男女平等を、主義として正当化するとしても、男は子供を産めない。職能のあり方も今一度根本を見つめないことには、この日々のなにげに不安な心情は、連鎖的に人々をあきらめの世界に導く。それは不幸の始まりだと思う。
022. 過去のリアリテイ
時々、若者と雑談する時があって、私の小学生時代、昭和25年頃、京都の街中を日通の荷馬車がのんびりと荷を運んでいて、学校帰り道、御者の目を盗んで、荷車の後ろに飛び乗って友達と「らくちん、楽珍」と、遊んだこと。
今でこそ市街地となった山科地区もその頃は京都市近郷農村で、そこからナスやトマトなどの野菜の行商が日々市内に来ていたこと、ましてや、その農家が、し尿の汲み取りのために牛に引かせた汲み取り桶を積んだ荷車を引いてきたある日、牛が突然人家の前で産気づいて、お百姓の叔父さんがあわてて私の家にぼろ布切れを探しに飛び込んできた。
数分後だったか記憶は定かではないが、アスファルトの道路の上に敷き詰められた筵や布切れの上で、湯気をたてながら無事小牛が生まれ出たのを、大勢の近所の顔見知りも、通りすがりの人もなんとも言えぬ一つになった雰囲気、空間で見守った話しをすると、話しを聞いた若者も「ほんとですか?」などと言いながら目が点になった顔をする。
先日も、「いや、本当に激変の時代を実体験されてきたことが羨ましいですよ」という若者もいて、確かに過去を振り返れば、テレビや家電製品、自動車の普及、今のパソコン、携帯電話など文明の発展を伴う工業化社会、情報化社会、コンセプチュアル社会の,時の流れを兎にも角にも実体験で生きてきた。翻弄されることも多々あった。
20数年ばかり前に、アメリカのNASAでも使用されたという6000万円もする汎用コンピュータを関係していた教育機関が導入、その講習を緊張して受けた新しい体験等も今でも生々しく思い出す。
ところが、あっという間にパソコンが市場に出回り、学生の研修には一人一台の時代。6000万円もしたコンピュータは5年で場所ばかり取るお邪魔ものとなり、導入時の大騒ぎはなんだったんだとため息。
過去のリアリテイを実体験・体感した世代が、今やバーチャルな世界をも覗いている。
この現実が、いつか併せて過去のリアリテイとして如何に感じられるのか興味は尽きない。
それにしても、世代を超えて若者と色々話し合うことは大いに楽しく人生を心地よくさせる。時代の継承には、色々なメデイアもあるが、あい対面して、語り継ぐことによって、その語り合った瞬間が、若者にとってはリアリテイな記憶となり、やがて「こんなことがあった」と過去のリアリテイに変化する。おもしろいことである。
023. ビールに敬意を
ちょっとした催しのオプションでサントリービール京都工場の見学に行った。
ビ-ルの原料・素材である天然水、麦、ホップに対するこだわり、厳選。さらに仕込み、発酵、貯酒、濾過という製造段階でのこだわりや技術の注入など現場を見ながら説明を受けると、ビ-ルも凄く贅沢なものなのだと感じ入った。
ザ・プレミアム・モルツの製造ラインを見学したが、麦芽本来の旨みと深いコクのある味わいにするために、仕込み槽で徐々に麦汁の温度を上げながら、一部の麦汁を2回煮沸するダブルデコクション製法や、ホップの香を最大限に引き出すためのアロマリッチホッピング製法の採用など興味深いものであった。
温度管理や最後の決断が経験を生かした作業技術者の判断で適時行なわれているのも、ビ-ルがまさに生き物であるという証拠のようだ。
「愛情を込めて」といってもおかしくない人間くさい作業が、ピカピカに磨き上げられた工場で、整然と進行している様はなかなかの時空である。
見学後、最適に冷やされた出来立てのザ・プレミアム・モルツをいただく。
グラスへの好ましい注ぎ方まで説明を受けたが、あれほどに作る段階でこだわりがあるなら、飲む段階でもそれなりの流儀を求めてもしかるべきかなと、納得して聞いた。
参加者の一人が、「最近は発泡酒を飲むことが多いので、久しぶりにコクのあるビールを飲みました」とビ-ルの奥深さに気付いた一言を発言、アテンダント嬢の笑顔が一段と晴れやかである。
私は、旅先ベルギーでの薫り高いビ-ルを思い出しながら、とても心なごむ午後のひと時を味わった。 ずっと以前、日本ではビ-ルと言えばキリンビールが圧倒的シェアを占めていて、独特のほろ苦さがビ-ルの味と思い込まされていたが、サッポロビ-ル、アサヒビール、そしてサントリービ-ル、やがては地ビ-ルが出回るようになり、ビ-ルにもさまざまな味わいコクやキレなど風味が競い合って、売り出されると、なるほど色々味わいの違いがあって、それぞれに好みの味わいが市場を分け合うようになった。軽井沢で、「よなよな」と言う地ビ-ルに出合った時も、感動したが、今度の見学で、その道、プロはいろいろ試行錯誤しながら絶対と言う根拠のない味覚の世界で、かくも戦っているというその努力、研鑚の結果、ワインのように香の世界まで含む新しいビ-ルの世界が拡がってきている。発泡酒、ノンアルコ-ルのビ-ルもどきなど、何処まで何が生まれ出るのか。ともあれ、ビ-ルにも、生まれいずる幾多の物語、苦労のあることを想い、敬意を払い、大切に飲もうと思う。軽々に「日本酒党や」「ウイスキ-がいちばん」「やっぱりワインやね」などとほざくのはやめよう。どれもみな、作り手の命がけなんだ。
024. 地域の歴史
我が家のはす向かいに住む古老は、地域の歴史に大変興味を持っておられ、特にこのあたりの古地図から色々な歴史的事実を読み解いたり、想像するのが楽しい様子である。
以前、平安宮の区画図と、寛永10年(1628年)、明治35年の実地測量図のコピーをいただき、地図を比較、参照しながらその変遷を通して歴史の「なぜ」「これはどうして」など話を聞かせてもらった。
今、私の住んでいる場所は、平安京の頃に存在した、東市、西市という市場の東市のすぐ南に当たるということで、ちょうど市場帰りの人たちが、息抜きをした繁華街に当たるそうだ。東市の専売品は、衣類、織物、文房具、兵具など34品目があり、鎌倉、室町時代時代には七条市場として栄えたとのこと。今は拡張された堀川通りから僅かに西に入るためその面影はない。
時代は下って、新撰組の面々も、まさに現在の家の前をうろうろしていたと聞くと、とても不思議な気がする。
先日は、安政5年(1858年)のこの下京地域の大火、文政13年(1830年)の京都大地震の瓦版のコピーを現代訳と共にいただいた。テレビ等ない時代のこと、瓦版がその生々しさを語っている。
被害の様、老若男女、人々の周章大かたならず,昼夜のわからなく、東西にほんそうし、あるいは親をすて、子をうしない、其のそうどう大かたならず。あわれおびただしき事筆紙につくしがたし。右にしるすは当二日七ツどきより五日中のことにて、今に地震ゆりやまず。まことに古今のちんじ故、まづ、あらましをしるす。なをくわしくは追而出はん(版)。とある。
地球環境問題など、未来に向っては多くの関心が払われ、時代意識は鮮明に現れるが、振り返れば、ほんの200年、いや1000年、我々の先祖は天災、戦争、差別など色々な出来事の中を多情な葛藤も伴いながら、生き抜いてきたのだが、歴史という圧縮された時間認識の中で過去に関してはあまりも感情を伴わずに生きている。
記憶の風化現象、「わすれること」はほんの僅かの間、生かされる人間へのささやかな癒しとしての天からの贈り物かも知れないが、もう少し過去に、歴史に感性を移入して学ぶ必要があるのではないだろうか。
戦後間もないころ、類焼を防ぐため、取り壊された家の後が広場になっていて、三角ベースボールや鬼ごっこで遊びまわったところも、今は昔、ビルや家並みで時の彼方に跡形もない。その時代時代の地図は色々な物語を想い抱かせ、不思議な魅力を醸し出す。
古地図の通り名をたどりながら、今の京都を重ねて、空想散策してみた。
025. 弘法、筆を選ばず
子供の頃、何かと成績の上がらぬとき、関わる道具のせいにして、もっと良い(高い)物を使いたいと親にねだったら、「弘法、筆を選ばず」という本当の諺かどうか知らないが、とにかく腕や能力のある人は、いちいち道具なんかのせいにしないものと、まずもっと努力しなさいと一喝されたものだ。
昨今、話題の水着はどうだろう。昨日も、スピード社製の水着を着た選手が、日本新記録を連発したというニュース。
ハイレベルのオリンピック出場予定選手が、着用しての結果であるから、やはり、水着に性能の高さがあるという明白な証明である。
ゴルフのクラブの性能、棒高跳びのポールの性能、シューズを始め競技道具の性能は、今までも色々と話題になったが、今度の水泳のようにシンプルな競技において、水着のテクノロジーの差によって、人間の能力をスピードという尺度で測るとき、その結果が異なるというのはある意味、人類の知能の凄さを感じさせるものでもある。
競泳力の真実を知りたいなら、選手は素っ裸で競い合ってみるしかない。
競泳におけるオリンピック代表選考は百分の一秒を争う熾烈なものである。代表派遣として設定されたタイムに達しなければたとえそのレースで一位になっても代表にはなれないのだ。水着の性能はますます気になる。
競技のためだけでなく生活用具においても、切れ味や精度、耐久性など機能性において明らかに違いの分かるものは、いつしか数値化、ブランド化がはかられ、購入する前から、そのよしあしが判別できるようになっている。
しかし、ファッションにおけるブランド品などは、機能性以上に美的センス、ファッション性に選択の基準をゆだねることが多いので、ある意味、つくられた情報を選ぶことになる。ブランド品を身に着けることで、情報の共有化がはかれ、身なりの印象から、営業成績を上げる結果になることもある。
本当のところ、ごく日常生活においても、高級品といわれるものは、何がしかの競争原理上の優位性を持っている。だから、人と競い合わないなら、何事も気楽なものだが、日常なにがしかの競争社会を生きる身には、弘法、筆を選ぶところに人間味もあろうかと我が身に振り返って苦笑する。
026. 都会の蛍
子供の頃には、戦後、祖父母が疎開していた南丹地方、園部の川辺で、何度か蛍狩をしたが、その後、環境の悪化と共に何時しか都会では、蛍も夏の夜店で売り物になるほど自然のものではなくなった。
一昨年、数十年振りに南丹市、日吉の里に蛍見物に出向いて、真っ暗闇の里山近く、かなり高いところの木々まで蛍が光る木の実のようにいっぱいで、時々その幾つかが、ふわぁつと浮き流れた静かな美しさは、訳なく幾多の感慨をかき立てたものだ。
思わずあの時、一緒に遊んだ従姉妹たちはどうしているだろう。
祖母と一緒にキリギリス捕りに出かけた夏の日のことなど懐かしさが甦る。
私にとって、蛍はどこか夢物語の世界、懐かしい記憶の世界になったと思う昨今、なんとすぐ近くの梅小路公園に蛍が出るとの情報をお隣のおばさんから聞く。日頃散歩に何度も出かけ、確かに小さなせせらぎもあるが、まさか「蛍」が出るとは信じがたい。
早速女房と二人で、夜の8時頃出掛けてみた。公園は治安上外灯も点灯しているので、真っ暗闇というわけではない。なんとなく子供の声が聞こえてくる。
小川のあたりに近づいてみると、どうして聞きつけたのか、蛍を見に来た親子ずれ、若いカップルたちが結構いる。目を凝らしていると、なんと数えることの出来るささやかな蛍の群れがほのかに見えてきた。
「いる、いる」「あっ、とんだ」
蛍より多勢の人がひそやかではあるが、高ぶった気持ちでささやいている。
近くに飛んできた一匹を、手のひらに包み持つと、「おお。蛍だ。」という光りが手のひらの中にぼおっとにじみ輝いた。
京都駅エリアといっても良い、こんなど真ん中の公園にどうして「蛍」が。なんとも自然感がなく、さりとて人工的、擬似感というのでもない不思議な舞台である。
山里の木々に鈴なりの光の実、示し合わせたように一群が瞬く光のリズム。息をのむ一瞬。都会の中の公園の蛍は、そんな世界があるとは知らず、ふわりふわりと単独飛行。
それでも都会人、若いカップルや子供たちにとっては、こんな蛍との出会いはやっぱり一夜の思い出になるかも知れない。
孫にも「都会の蛍を見においで」と電話しょうかと思ったが、これは孫に見せるほどのことはない、見せるならやっぱりもっと蛍の里ごと見せよう。そんなことを呟きながら帰宅した。
後刻、聞くところでは、昨年あたりから誰かが蛍の幼虫を小川に放したらしいとの事。嘘から出た真ではないが、本当にこの都市公園が蛍の名所になったら、すばらしいだろうなと思いながら、ささやかな蛍の命運との更なる出会いを期待したいと思った。
027. 海外旅行
私が始めて海外旅行をしたのは1973年、建築家仲間9人と「20世紀のアメリカ建築見て歩き」21日間のアメリカ横断旅行である。もともと仲間が時間を掛けて計画していたツアーだったが、参加予定者が急なキャンセルということで、ピンチヒッターというところであった。
大学卒業後、叔父の会社のアメリカ主張所に行かないかと誘われたことがあったが、帝国主義のアメリカには興味がなく、拒絶反応をしていた。ニュヨーク、シカゴ、オクラホマ、フェニクス、アリゾナ、サンフランシスコ、ロスアンゼルスとほぼ横断旅行をして、見ると聞くとは大違い、当時のアメリカの民主主義の奥深さ、人々の生活のリアリテイに圧倒された記憶は今も鮮明である。
以来、実際に見聞することの重要性を痛感、建築を通して生活と文化を体感するべくヨーロッパやアジアをも旅することになった。何度か、生活と文化の旅と称した企画を自身で立て、旅行代理店の協力でオリジナルなツアーを毎年1回計画・実行、知人仲間と楽しく旅をしたこともある。
文化の違いを体感することは、こんな世界もあるのだ、こんな生き方もあると身も心も膨らむ快感があった。夏のヨーロッパなどはなかなか太陽が沈まないので、午後の7時から闘牛場に出かけ、10時頃からレイトショーをみる。真夜中も酒場で一杯、一日が、人生が急に倍になったようだった。
昔は、修道院であったり、貴族の館であった建物がホテルに転用されているところをなるべく選んで宿泊すると、そのインテリアから、周りの環境から生活の厚みが一杯感じられ、とにかく映画やテレビ番組で見て感激していたすばらしい世界が体感できる。
色々見てまわるうちに、日本の味、日本の空気の穏やかで、爽やかで、華やかな良さが少し感じられるようになると、その根底に理性と感性のバランスのあり方、違いが見えてくる。 気に入った国に定住して活躍する日本人も多いが、何時の日か日本人の感性や考え方が、欧米の人達と交流していけば、きっと平和な人類の道筋が出来るに違いないと確信する。人種のるつぼのアメリカ、はじめての海外旅行で直感したものが、少し実体としてイメージ出来る今の年齢になると、多くの日本人がもっと世界に出向いて、日本人的人間バランスを見直す機会を持てば良いと考える。理屈ぬきに楽しい海外旅行ではあるが、その効能にも期待したい。
028. 祇園祭雑感
7月になりました。いよいよ祇園祭気分です。
生まれてからずっと40数年、放下鉾町で過ごした私にとって、祭りの中心地、鉾町を離れて20年になるが、今時になると祭りの賑わいが、お囃子の音が体の中で舞い上がるのを感じる。
飽きることなく、鉾の組立作業を眺めていた子供の頃、鳶の親方の下、若い衆が見事に縄だけで鉾を組み立てる。毎年1回の出会いだが、見覚えのある子供達に愛嬌バツグンの若い衆が、だんだん出世して、私が社会人になった頃には、采配を振る組頭になって、威勢良く掛け声をかけている様を、わけなくうれしく感じたのを思い出す。
はじめは寝かされて組み立てられる鉾の胴体に、町内の露地塀の庇の下にひそかに保管されていた鉾の心棒の上の竹の部分が町会所の蔵から運び出された幾多の部材・部品と一体になる。いよいよ鉾建てである。職方は勿論、町内びとも繰り出して音頭に併せて綱を引き、鉾を立てる。無事にシャキット鉾の心棒が天空に聳えると、どこからともなく拍手。
車掛けという結構難しい作業が残っているが、半ば完成のひと時である。
鉾の組み立て、鉾たてにも実は日頃なんでもない道にちゃんと装置化された仕掛けがあって、基本柱を組み立てるときには目印になる四角形の御影石が4つ埋め込まれている。心棒を立てるときには、皆が引いた綱を巻き取るための冶具をとり付けるため2箇所に12センチくらい、深さ60センチくらいの穴が掘られ、通常は目立たない蓋がされている。
一見まっすぐな道路を区切った鉾町であるが、鉾が立つ町会所の部分は、ややふくらみがある。鉾が立てば、鉾に乗り移るために町会所の軒庇が稼動して欄干橋状の装置が取り付けられる。それに、蔵から部材が運び出されるが、装飾品は主に蔵の2階部分にあるので、祭りの時は仮設の搬入用空中橋が中庭を横切って母屋に向って掛けられる。
昨日まで普通の町屋のような町会所の建物が、あっという間に姿を変え、祭り仕様になる様は、本当に何度見ても気分一新の爽快・感動ものだった。 祖父が横笛の師匠格であったので、7月といわず、5月はじめ頃には、その年から笛方になりたい人たちが〈鉦方を卒業した若い衆〉我が家に来て練習を始めるのだが、ピィピィ、ひゅうひゅうと頭の痛くなる音を出すのが、今にして懐かしい。 祭りの前の縁日、夜店や屋台の並ぶ数日の、我が家に帰るにも一方通行で時間がかかるなど、祇園祭には色々な思い出が一杯である。
029. 疲労骨折・人生疲労
近頃、スポーツ選手に「疲労骨折」で休養を余儀なくされる事例が目に付く。
骨折といえば、骨がポキリと折れてしまう様をイメージしてしまいがちであるが、疲労骨折はトレーニングのし過ぎで、ひび割れた骨が修復される以上に酷使され、亀裂が入り、痛みなどの症状が伴う状態ということだそうだ。
トレーニングも限界を超えると「過ぎたるは及ばざるが如し」。
しかし、疲労骨折を起こすくらい繰り返し練習をつまないと、なかなか一流のレベルに達しないというのも本当のところと云えるのだろう。まじめな努力家タイプの選手に多いともいえる。
人生においても、順風、何事もさしたる努力なく生き抜ける人は別として、たいていの人は、日々繰り返しの生活の中で色々な努力をしている。
肉体疲労、精神疲労、トータルで人生疲労と呼びたい疲労現象が、忍び寄ってくる。
人間の回復力、免疫力などは結構強靭なものではあるが、疲労骨折のように、ある限界を超えてストレスなどの負荷に耐えているとある日、突然、修復のバランスを失って人生疲労の症状に陥る。
向上心を持って、より高い目標に向って、がんばるのは元来すばらしい資質と思うが、人生はオリンピックのメダルをとるかどうかで評価が決まるというものでもないので、身の丈にあった、なるべく一番好きで楽しくやれる世界を見つけ、そこで、出きる限りの自分流パフォーマンスが出来れば、人生疲労でのリタイアを少しでも回避できるのではないか。
そのためには、その時々の自分の年代を生きる、20代には20代の、その時にしか出来ないことを、優先して実行する事が大切だったと振り返って思う。
大雑把な言い方をすれば、そうした生活の中で、色々な人との出会いや出来事の思い出をたくさん持つことが、人生の終焉に向って人生疲労を比較的軽やかに受け止められることにつながるような気がする。これからの残りの人生も、人生疲労症候に陥らないよう、いろいろなバランス感覚を磨きたいと思う。
030. 年寄は気を付けなければ。老いの発見。
数日前、仕事仲間の方と大阪でほどよく飲んで、地下鉄に乗って大阪駅に着き、京都に帰る電車を待っていたのだが、連絡路や階段をせっせと駆けあがったせいか、なんとなく酔いが回ってきているなと感じていたら、「大丈夫ですか、大丈夫ですか。メガネがわれていますよ。」
「血が出ています、」という声が聞こえて、我に気が付く。
なんと、しりもちをついたような格好で、倒れこんでいる自分を発見。一体何がどうなったのか、まったく記憶がない瞬間。
ちょうど電車が到着。
立ち上がって乗ろうとしたら、周りの方が「乗れますか、大丈夫ですか」と声をかけてくださる。 「メガネのガラス破片が顔についていますよ」と教えてもらう。顔を触ると、粉々のガラス破片がきらきら光っている。空いた座席にかけさせてもらう。
その時、誰かが通報してくださったのか、駅員の方が駆けつけ、2人ウロウロと乗車口の辺りで、通報の事情を探しておられるのが人ごみの間に垣間見えた。「お急ぎのところ申し訳ありません。ただいま救護要請がありしらべております。しばらくお待ちください」との車内アナウンス。
まだ酔った頭ではあったが、これは自分のことだと恥じ入ると同時に、周りの方の親切をありがたく感じた。
4分出発が遅れたとのアナウンスがあった。意識を失って倒れるのも初めてだったが、大怪我や事故にならずに幸いだったこと、近頃の社会は冷たい風潮だと思っていたが、周りの方の親切にも感謝した。
京都駅に着く直前にも、延着をわびる車掌さんのアナウンスがあって、少し酔いもさめたので、なおさら申し訳ないとおもいつつ、助けてくださった方にお礼を言って下車した。
イヤー、やっぱり年をとったんだという思いが切々とした家路であった。メガネもなく、血のついたシャツをきてぼーっと帰宅した主人を見て女房殿は「どうしたん。」と絶句。
事の顛末を聞くや、すぐに病院に行って、頭の検査をしてもらえという。もう夜分、今は意識もはっきりしている。大丈夫だといってその夜は眠る。翌日はあいにく管理建築士の講習があって、病院にはいく暇もなかった。次の朝、顔面、特に唇が切れたあたりがいまだうずくものの、意識はしっかりしていたが、脳血栓などの予兆かも知れないと、息子達からもいわれて、病院に検査にいく。
内科から脳外科をまわってCTスキャンなどの検査をして、転倒時の外傷から来る問題はないとの診断を得たが、意識を失って倒れるというのは、糖尿病から来ることもあるので、糖尿病の検査、そしてMRIなどの検査をして下さいとのことである。
とにかく、年をとったのだから、お酒を飲んで今回のような無様なことにならぬよう、自重しなければならないと思った。ほんとに自分の老いの発見そのものであった。
廣瀬 滋著
私の思考散歩・生活雑感 ぽつり草々 011〜020
011. テイータイム
女房が『母の日』に長男の嫁から中国茶の茶器セットを貰った。
以前から興味があったのだが、その時から、かつてコーヒのあれこれに凝ったことがあったように、我が家では中国茶のテイータイムが少なくとも1日3度は持たれる事となった。
中国茶のいれ方から道具、茶葉の種類など、手ほどきの入門書を買ってきた女房が、数種類の茶葉を買い入れてきたので、次々と入れ方や茶葉の味わいを賞味することになった。
東寺の弘法さんに出かけ、私はうまい具合いに、小さな錫製の茶托を掘り出すことに成功した。食器棚の中から多分叔母が過って使っていたと思われる銅製銀メッキの急須が雰囲気よろしく日の目を見ることにもなった。
さらにウイーンの骨董屋で買って置いたフインガーボールとおぼしき錫の器と嫁に貰った工夫茶器の朱泥の蓋がぴったりのサイズ、組み合わせるとグッドセンス。
おおいに気分が盛り上がる。しかも、朱泥の茶器の時と違って、湯を注ぐと錫の器に滴る湯音が風琴窟のように音を立てるのには感激した。
なにより、色々と作法のように手順を繰り返している間、息子達ともあれこれ会話が弾むのも楽しいことである。極めれば、中国茶の作法も大変なのかもしれないが、日本の茶道と比べれば『一期一会』等の厳しさよりも、色々な茶葉の香りや味を楽しみ、気軽に茶卓を囲んで、健康談議が出来る実用性が好いなと感じた。
数日後にはガラス製の茶壷や杯、色々なドライフルーツ等の茶菓子も買ってきてジャスミン茶を楽しんでも見た。二男は、「まもなく我が家のブームは去るでしょう。」等と笑っているが、まんざらでもないのかテイータイムには結構、機嫌良く付き合っている。
さらに数日後には、茶器を置く棚が有れば良いと女房が言い出して、骨董屋の店、家具を記憶の中で確かめる。中国茶器を入れられるようなものは今まであまり気に掛けていなかったので、思いは空を切る。
先日、出先から帰ると、二男がガレージで電動工具を音立てていた。何の事はない女房に言われ食卓脇のカウンターの棚を改造しているのだ。休日等には、二男はおもむろに中国茶を入れている。まだなれない手付きを冷やかしながら、私と女房も茶菓子を口にする。
テイータイムは住いを彩って余りあると思う。
012. 眼科病院にて
何十年ぶりというほど久し振りに『め』にものもらいが出来て眼科に出向いた。
東寺の近くにある眼科専門病院である。ここは一体何処かと思うほど老人、中年,そしてOL嬢らしき女性があふれかえる。察するに、加齢に伴う視覚障害と、コンピュータ業務などによる視力障害の増加であろうか。待合室は、学童時の集団検診を想い起させるほど不思議な賑わいが漂っている。
どういうわけか、受付でちゃんと『ものもらいのようです』と申告したにもかかわらず、とにかく視力検査のところに並ぶことを指示される。3列に配置された検査椅子に次々に患者が呼ばれ、視力検査を受けるのだが、順番が来るまでに、後続の患者が絶え間なくあとを埋める。
『何を患うよりも、目が見えなくなるのは怖いです』と呟きながら、ほとんど検査医の指し示す視力検眼表の記号が読み取れず、情けなそうなお婆さん。
『今日はよく見えていますね』とほめられている常連患者らしいおじいさん。
何か、指し示される記号に正解が答えられないのは、私自身プレッシャーを感じる。
やっと巡ってきた検査。色々レンズをハメ変えて、現状のめがねの度数が問題のないことを調べてくれるのだ。眼圧検査のあとで、やっと眼科医の診断である。
『要するに、ものもらいですね』と言いながら眼球の断面イラストを示しながら病状の原因、経過、今後の対応を説明してもらう。
なかなか優しい青年医である。『有難うございます。』と心から礼を言いたくなるタイプ。
看護婦さんが発給する目薬2種類と軟膏の説明をした後、受付で待つことになる。
やがて、名前を呼ばれて、再び目薬の説明を受けたのだが、先ほどはピンク色のキャップの目薬であったのに、今度は黄色である。『先ほどの説明のものと色が違うのでは。』と質問をすると、係りの人はカルテを持って内線電話で診察室に問い合わせをした。
『先ほどはピンクの目薬でご説明しましたが、どちらも殺菌薬で、今、確認しましたが、この黄色のもので間違いありません。ご安心ください』とのこと。
処方薬の説明が、診察室と医局(受付)で二度行われたのはチェックシステムとして有効なのかも知れないが、お年寄り患者の多い医療現場では些細な手違いは発見されにくいだろうから、不安が残る。
眼科専門病院というのは、建築計画的に見てまだまだ診療所レベルで、これだけの患者数を診察するには改良の余地がありすぎると思った。診察、受付など動線計画があまりにも無計画で、スタッフや患者が入り乱れてワンルーム的空間にうごめいているのが、入った途端の不思議な賑わいを感じさせたのだろうか。
ほとんどの生活が視覚に頼ることが多い人間にとって、視力の衰え・障害は結構重大問題であると考えさせられるひと時であった。
013. 食事のスタイル
近頃の日本の一般家庭での食事スタイルは、共働き家庭が増え、食事時間がまちまちになったり、健康管理のためそれぞれの食事メニューが異なるなど,多様化した食生活のため,食事時間に全員がそろうことが少なかったり、個別に盛られた料理を其々が食べる会席風個別スタイルなど多様である。
山賊飯などと揶揄していた、食卓の中央に幾つかに盛られた料理を、家族がおもいおもいにとって食べるスタイルは鍋料理の時は別として大変少ない。
個別スタイルであれば、自分のものは残さずきれいに食べるというような行儀作法もたちまちチェックされてしまうが、山賊スタイルのように誰が何をどれくらい食べたのかも解からなければ行儀作法など堅苦しいことは問題にならない。 理知的なスタイルと野蛮なスタイルと云えるかも知れない。
同じ釜の飯を食うということがあるが、山賊スタイルの食事は、家族(メンバー)の親密度、和やかさなど人情の暖かさを自然に育んでくれる。
色々な会話もはずみ家族が知らず知らずのうちに連帯していくチャンスがある。
どうして食事スタイルが改めて気になったかというと、先年、韓国を旅行して韓国の料理の形態が(多品種メニュー、まとめ盛り付け、多様な鍋料理等)どちらかといえば山賊スタイルであったこと。そして皆が大変食事を自然に楽しく、和やかに行い、しかも振る舞いの中に自然と目上のもの、年長者を敬う所作が随所に見られたことに感じるところ、心うれしさがあったからだ。
思い出せば、遊牧民にしろ、少数民族にしろ、自然や社会の生存競争の厳しさと戦う民族には、今だこうした山賊スタイルの食事空間が流れている。
食事という人間にとって基本的な行為を共有、連帯のうちに出来ればこそ、家族、社会の自然な人間らしい姿を身に付けることが出来ると実感、直感するのだ。
アウトドァにおけるバーベキュー、鍋料理パーテイなど人間関係を補完する為の食事スタイルがあるが、もっと家族の絆を、人間の熱き心を実感できる山賊スタイルで食べる料理メニューを日々の家庭料理の中に増やせば良いのではないかと思う。
核家族、個人主義、男女平等など、戦後、我々が進歩として獲得してきた欧米風価値観が、生活スタイルに反映される時、家族が食事行為と団欒を通して育んでいた連帯観、人格形成、生活の智慧や文化、風習の継承と言った大切な面を希薄にしてしまったと思う。
今、「食育」として小学校でも、食生活に関する教育が行われているが、食と健康など実利的側面が前面にあって、食生活の奥底にある人間と自然、人と人の互恵の関係などをを感学させる場にはなっていないのではないか。
旅における韓国料理は、健康メニューで実に人情豊かな空間を感じさせてくれた。
014. 姓名とイメージ
知人から自分の名前からゲーム感覚で、「脳内イメージ」が判別できる超人気サイトがあると教わった。
ちょうど、今、私にとってやがて2人目の孫が生まれることになって、一体どんな名前が良いかと次男夫婦が楽しみながら思案している。昔のように家長たるお祖父さんが名付け親に名乗りを上げることは、今では、叶わぬ願いで、私たち夫婦して『こんな名前はどうかな?』と話題に首を突っ込んで拒否されている。
それにしても生まれる赤ちゃんは自分の名前を選ぶことが出来ないのだが、大抵、色々な親の願いや希望が込められ、運命も左右されかねないという真剣な想いが、日常気にも留めていなかった「姓名判断」という篩にかける行動をとらせたりする。
漢字の画数がこれほど脚光を浴びるダイニングまわりはなぜか眩しい気配ですらある。
人は、芸能人や作家が芸名を持つ場合を除けば生涯ひとつの名前ですごし、死して戒名を持つのが一般的である。私の母は、何時の頃からか『易』や姓名判断が好きで、私が社会人になると同時に、「これからは周りとの協調も大切、親の面倒もちゃんと見てくれる人間に成ってもらわないと困るから」とまったく突然に、一存で私に本名以外の名前を姓名判断の先生に決めてもらったと言うのだ。
高校生になる直前に父親がなくなったのをいいことに結構やりたい放題で、母に苦労や心配をかけたこともあったのか、自分でも驚くくらい抵抗なく母の申し出に従った。
今から思えば如何なる心境であったのか思い出せないが、以来、母が亡くなるまで20年近く俗称を使うことになった。自営業として色々な取引先からいただく報酬や、講師などの給料扱いのものなど税務申告時には混乱をきたし、ある年は、本名と、俗称2つの名前宛に申告書が送付されてくることもあった。
また、旧来の知人、親戚のおばさんですら本名で呼び続ける人もいて、ジキルとハイドではないが、2つの人間、人格を生きるのは「ひょっとして、こんな感じかな」と思うこともあった。
母がなくなり、親孝行という口実もなくなれば、銀行取引や色々の実生活での不便は煩わしく、本名で再び生活することにした。こうした体験を持つ故に「脳内イメージ」とやらで、俗称と本名を比較してみると、過ぎ去った日々のあり様を結構反映しているイメージ図が浮かび上がり、面白いと思った。どうしてこんなソフトが開発されたのか興味深い。
それにしても、未熟児で生まれた私が無事に生育するようにと想いを込めて父が名付けてくれた本名は、俗称で生活した20年余り、やはり運命的に私の深奥に寄り添っていたように感じる。もし、生まれて来る時、自分で名前を選べるとしたら、人はどの様な「運命」をゆだねてオギャーと一声をあげたいだろうか。
親の専権とはいえ「名付け」は結構意味深いと思った。
015. 私と携帯電話
いまや携帯電話は社会生活には欠かせぬモノとなっている。
私も時代に後れることなく、PHSの出はじめから使いはじめ、まだ地下街などで携帯電話が通信出来なかった時にはPHSと携帯電話の2台を持ち歩いていたこともある。しかし、第一世代の携帯電話では事務所に居るか、仕事で出掛ける時も比較的行き先の明らかなことが多い私にはほとんど自宅への「帰るコール」しか利便がなく、充電や携帯のわずらわしさのため携帯を持たないことにした。
その後、携帯電話は進化し続け、カメラ機能も備えるまでになった。ちょっと建築現場写真も取ることが出来そうで少しは自分のライフスタイルにも役立ちそうだと思い始めていた3年前、息子夫婦と旅行をすることがあり、出先でのバラバラ行動と集合連絡のためトランシーバの役割かわりに持って便利という理由が動機となり再び携帯電話を持つことになった。
しかし、その後も仕事関連を始めほとんどが従来の固定電話で通話するため、多様な機能を搭載する携帯電話もしばしば身につけることを忘れる有様である。
先般、東京出張の折、会議が終わってコートのポケットに入れておいた携帯電話が無いことに気が付いた。何箇所か会議、面談で移動したため、コートを着脱、どこで落としたのか定かではない。同行のM氏が私の携帯に通話しても「電源が入っていないか、電波の届かない所云々」の応答しかなく、訪問先の方にも捜索をお願いして一区切りをつけた。
けれど、何かとても不安で落ち着かない気分である。普段はさほど重要とも思っていない携帯電話なのに、無くなったとなると自分の体の一部が亡くなったような不思議な感じがする。
同行のM氏は3台の携帯電話を所持、使い分ける達人。「とにかく、通話停止手続きをしましょう」という。ちょっと見渡すとちょうどNTTドコモ虎ノ門店があった。ずらり並んだカウンター。整理番号をもらって待つ。手続きは思いのほか簡単。生年月日、住所、携帯電話番号、機種を確認され本人とわかるとパソコンであっという間に利用中断手続きが完了。
再通話のための解除暗号番号を決め、手続き書の控えをもらって外に出た。他人が成り代わって通話することが無いということで少しほっとした。
「本当にどこで落としたのか」「ひょっとして、朝の新幹線かも知れない。荷物棚にコートを置いた。」つぶやく間もなくM氏は東京駅忘れ物センターに電話を入れ問い合わせてくれている。結果のわかるのは明日の11時以降とのこと。帰京。
ほとんどあきらめ、機種変更もやむなしと思ったが、最後にもう一度と翌々日忘れ物センターに電話した。確認質問の後しばらくあって、「届いておりますよぉー」と私のうれしさを見透かすように芝居掛かった係りの男性の声がした。「ありがとうございます」さらに翌日、ペリカン便で携帯電話は帰ってきた。
016. 相撲の世界
時津風部屋での新弟子のしごき、死亡事件がマスコミをにぎわしている。
30年近く前に叔父の知人で相撲のタニマチと呼ばれる施主の住宅を設計することがあって、その竣工祝いに叔父と私が招かれた時、その方の親交のある親方と2人の弟子が呼ばれ、チャンコなべを作ってくれ、ご家族と一緒に楽しいひと時を過ごした思い出がある。
その時何より感心したのは、お酒が強いとか、スポーツマンの叔父のウエストが現役を引退した親方の太もものサイズでしかないというような事ではなく、あまりの博識というのか、大抵の話題に臆することなく、フランス語も操る親方のまれに見るホストぶりであつた。
その時、聞くところでは、お相撲さんは色々なタニマチのところに出かけ交流を深めていくうちに、知らずしらず、ものすごく色々なことを学ぶという。
日本相撲協会はだからお相撲さんだけで運営することができる人材が育つのだとも聞いた。以来、本当に相撲の世界は特別のものと感心していたのだが、先般の朝青龍のゴタゴタ以来どうも組織として機能していないと思い始めていたところ、今回の事件が発覚。
世の中、あらゆるところでモラルというのか、人間としての基本的所作が失われ、今まで考えられない事件、犯罪が多発し始めている。
相撲の世界でも指導する親方も外国人の弟子や現代っ子との価値観の隔たりに、いささか、とち狂ったのだろうか。
相撲取りは勿論のことスポーツ選手は厳しい勝ち負けの体験を通して早くに人生の奥義を味わう機会が多いので、同じ年齢の一般人よりは、はるかに達観している人が多く尊敬していたが、指導者として次世代を育てる段階で、この様な事ではいささか残念といわざるを得ない。
勝負事であり、型を守ればよい、勝てばよいというものでもない相撲において、いわゆる「相撲道」の今後の在り方は何かと曲がり角にある日本人の「今」を考える上でも、一考に値するテーマではないだろうか。
何事も「道」と名のつくプロフェッショナルな世界は、単に技や流儀を覚え、型どおりにこなすという世界ではなく、当事者の精神性、個別の文化資本が折り重なって表現されるところに美しさを伴い、観るもの、他者に感動を与えるのであるから、これと言った正解があるわけでないところに、奥深さが感じられる。
春の大阪本場所を桝席で観戦した時、勝負が展開される土俵に観客の「気」が集中する、その熱気が、自分がその場に居合わせることの充実感、幸せな時を感じさせてくれた記憶が、今も鮮明によみがえる。それは、相撲道に生きる関取の一瞬の対決の火花が、わけなく一直線で心に届けられるからだろうか。相撲は日本の国技、さもありなんと思う。
017. パン食雑感
明治、文明開化といわれる時代から日本におけるパン食は肉食の解禁、製粉技術の向上、米の不作時の代替食、在留外国人や海外移民の帰国、キリスト教の発展、外国人向けホテルなど、様々な要因、影響を受けながら、生活の欧米化の流れの中で大いに発展してきた。
アンパンの考案のような和洋折衷の巧みさは日本におけるパン食を今日、日本の食文化、食生活の中心にまで押し上げたといわれている。 確かに、昨今、街の中に製法や味わいに特徴のあるパン屋さんが続々出店、メデイアにも取り上げられ、少々辺鄙なところでも行列が出来るパン屋さんさえある。
ヨーロッパを旅して、ホテルでの朝食バイキングではパンの種類の多さはむろんのこと、周りに並べられた単品料理やデザート類、関連の飲み物類の多様さにわくわくさせられる。
米食のように主食と副食〈おかず〉という関係ではなく、パンは並べられた食品の一つで、むしろ御添えものの様にさえ思える。日本における主食である「米」の位置付けとは何か違うように感じる。しかし、西欧で、「パンのみにあらず」の様に生き方を示す程のキーワードになるくらい西欧人にとってはパンは食生活における概念として主食なのかなとも思う。
それにしても、近年の日本人の「米」離れは、グローバル化の潮流とともに、日本の農業を根底から壊死させてしまいそうです。食の自給率が40%を割る。もしもの時、日本人はどうして生きていくのか。最近こうしたニュースやドキュメンタリーがテレビ番組にも採り上げられている。
はなやかな欧米文化とともにパン食を享受してきた我々が、一方で、知らず知らずの間に、米食文化=日本文化という図式をはるかに超えて、経済至上主義、進歩礼賛風潮の流れの中で、色々な日本人の文化、美徳を失いつつあること、食文化の変化が日本の根底を揺さぶりつつあることを知らされる。
自身、朝食はパン食で、昼は、麺類やサイリュウム、米食など色々、夕食は米食、おやつなどにケーキ、菓子類と結構小麦を取り入れた多様な食生活を送っている。
日本の「米農家」を死滅させないために適正なコメ価格を政治的に守ることと併せて、日本におけるパン食と米食のバランスというか、食生活のあり様を、多くの日本人が、文化レベルとの関連において考えあわせ、日本文化の基盤でもある「米食」を、今後どのように考えていくのか、とても大切な時期に来ているのではないかと思う。
018. 東寺の弘法市
毎月21日は東寺の弘法市の日です。
10月21日は日曜日で天気もよく、散歩をかねて出かけました。
私宅からは徒歩15分くらいで北門に着きます。
秋の観光シーズンは弘法市を訪れる人が一段と多く、人出を当て込んで、最近では東寺の境内からはみ出た道路際にも、その日限りのお店構えで、色々なものを並べています。
弘法市は骨董品を扱う出店が多かったことで有名でしたが、今では、和服の古着、京都近郷の特産食品、フリーマーケットでも見られる手づくりの工芸作品、植木、縁日につきものの屋台など、何でもかんでも、てんこ盛りの賑わい市です。
雑然と並ぶ出店も大体は位置取りが決まっていて、何度も来ていると結構冷静に巡回できます。それでも、同じ店で先に「なかなか味のある品」と目をつけておいた物が、まだあったり、なかったりというのは、なんとなく、「心」コロコロの楽しさです。
また、一体何に使うものだろうかと、さっぱり得体の分からない骨董品に人間の生活の歴史を感じることも、同じ道具でも色々な造形の趣があって、思わず感動することもあります。弘法市、ブラブラ歩きの醍醐味です。
時々、買い手と売り手の値交渉のやり取りが、周りの人をどっと笑わせるのもご愛嬌でしょう。
今回は、たと紙に入った新品同様の銘仙の古着を買いました。またシャツに仕立て直してもらうつもりです。
それにいつも出ている韓国オムニのスルメキムチを買い、南門から出ましたが、門を出ても、まだ弘法市の熱気の中でした。
12月21日は今年最後の終い弘法です。毎年、年末のあわただしさと「市」の活気があいまって、日頃の東寺の静かな境内を知る者にとっては、別世界。のんびり、まこと品定めの楽しさなどは無理な人ごみと熱気。
同じ東寺での毎月第一日曜日の「がらくた市」は知る人ぞ知る、骨董市の風情の残る縁日です。生活の智慧やいろいろな想いが道具や家具、工芸品に歴史と文化の香りを載せて魅力的なかたちに展開され、無造作に並べられています。
今は、元の持ち主を離れて、次に心かよわせる人を待っているという空気感はなんとしよう。これもまた、以外に「ちょっと京都」の味かも知れません。
019. 慰めの楓
我が家から南側の通りをはさんで向かいの屋敷跡、ながらく駐車場になっている敷地の奥に大きな「楓の木」がある。
先週あたりから真っ赤に色づき、居ながらにして晩秋の気配を満喫しながらテイータイムなど過ごせるのは、ここに引っ越してきて以来の自然の恵みである。
一軒東隣のT家の80歳のおばあさんは、3ケ月の病院生活から戻られ、介護の必要な身になられたので、急きょ、浴室を改装することになり、身近な設計士として、そのお手伝いをすることになった。
数年前、配水管が壊れた時、業者を紹介した縁で、はじめて少し話す間柄になったのだが、おばあさんは、趣味で木彫をたしなんでおられ、その作品の見事さに感心したものである。今度の改装工事中は色々話しかける機会があったが、おばあさんにとっても寝室から見える紅葉の移ろいは、ふさぎ勝ちな気分を、ことのほか慰めてくれるとのこと。二人して窓から「楓の木」を眺め、とてもうれしい気分になった。
この「楓の木」は、冬には枝振りがそれなりの語りかけをしてくれるし、春の芽を吹く一瞬から、夏に向ってむくむくと翼が広がるように緑いっぱいに堂々とする様は、本当に感謝状を差し上げたい都会の中の宝である。
いつもは我が家でありがたい借景と喜んでいたが、おばあさんにとっても長年うれしい「大木」だったことを知って、ぐるりと見渡せば、きっと多くの隣人が、この木からやすらぎや慰めをもらっているのだと、おおいに気が付いて、本当に感謝である。
気丈に振舞って居られるけれど、すっかり抗がん剤で容貌が変わられたおばあさんが、なお、自然の美しさを共に語ろうとされるとき、なぜか胸迫るものを感じた。
改装工事後、数ケ月後、おばあさんは亡くなられた。おばさんの木彫された姿見鏡を形見のごとくいただいたが、事務所に掲げて、ちらり姿を見るたびに、あの語らいの一瞬が思い出される。心の中で、「楓の木」と命名しておばあさんと僕の感謝の想いを記憶にとどめようと思った。
020. 手編みのセータ
わが女房殿は編み物が達者である。子供や私のセータ、カーデイガン、ベスト、マフラー、帽子など数十点を、その時その季節に編んでくれた。勿論、愛用してきた。
いまや、孫のために次々と作品が出来ていく。
ほんの1年前の孫のセータも、もう小さくなって又せっせと楽しみを紡いでいる。
孫のものはサイズが小さいのであっという間に仕上げていく。近年私のセータは3年がかりでいまだ袖が出来ない。
多分、孫には手編みのセータを着ている可愛いさがあふれているのに、爺さんには着せ甲斐がないらしい。
先日、嫁が産後の養生に実家に帰っている間に、次男が孫の最新のアンゴラの手編みセータ、(ちょっと編みづらい苦労作)を、こともあろうに、他の洗濯物と一緒にばっさり掘り込んで洗ってしまったとのこと。すっかり縮んで、着られなくなったと、誠に申し訳なさそうに報告したとか。 女房殿の落胆振りは、はた目にも気の毒であったが、そこは達人の偉いところ、次の作品を編んでいる。
3日前に来た孫が、毛糸の玉を見て、「これ、セータにして」といった一言が俄然やる気を起こさせてしまったらしい。
手編みのセータはちょっと編み物の経験のある人には、すぐそれとわかるらしく、私がセータを着ていると大抵、「手編みですね」と声をかけられることが多い。そして、きちと正確な編み目や、ディテールの仕上がりにとても上手に出来ているとお褒めの言葉をいただく。「女房が編みました」と作り手を告げるのは、その労に感謝して、思わず出る一言。
ときには、デザインや色合いに私のアイデアを入れてもらうこともあるので、既製品にない思い入れがあって、二十数年、愛用のものも多々ある。うっかり、「ちょっとここが」と云おうものなら、アッという間にほどかれてしまって、カーデイガンが一着消えてなくなる。
編み物を見ていると大変な手作業の繰り返しで、そんなに簡単に毛糸の玉に戻すなど思いもよらないが、手編みの達人にとっては、文句を言われた作品が、そのまま形に残るのが許せないらしい。二、三度そんなことがあってからは、めったなことは言わず、ありがたくマイシーズン愛用することにしている。
私や息子のものから孫のものまで、温もり一杯の手編みセータ、チョッキなどに包まれて、家族、皆がうれしい日々は、色々なスナップ写真に残されている。いつの頃からは、出来上がる度に記念写真を撮って、思い出の作品集と称してアルバムに残すようにしているが、孫の来ていたセータなど、ママ友の幼児に払い下げられて、行方知れずのセータもある。一目一目に思いのこもる手編みの心が何処かを巡るのも楽しからずやである。
廣瀬 滋著
私の思考散歩・生活雑感 ぽつり草々 001〜010
001. シンプル
価値観の表現の一つとして、シンプルという言葉を使うことがある。
シンプルデザインなどと言われるのはその例であるが、〔simple is best〕などと言うように、おおむね誰からも理解され、同意を得られやすい現代の価値観の指標でもある。
住宅設計のプロセスにおいても、住まい手との打ち合わせの中で、一度や二度は、「シンプルな方で選びましょう。」などと言いながら了解点を見出していることがある。
本当のところ、我々の見た目の姿や生活行為・ライフスタイルは氷山の一角であり、氷山の水面下の部分にあたる多大な心理的な堆積物、夢、願望、しみついた習性などはシンプルとは限らない。
何かがあるような気がするが、意識することも出来ない。
住宅設計は、その水面下の部分をシンプルという選択・概念イメージで少しでも水面上に形として浮上させ認識できるように頑張っている行為でもある。
決定の一瞬において、「シンプル」と言う概念は、答えを求めていた悩みの時から解き放たれた爽快な気分、意思決定による確かさ、安心感を与えてくれるが、同時に、水面下に残されているものの重さを感じさせる。
そんな時、水面下の声なき声、無意識化の心を最大限に生かすため「シンプル」にフレキシブルさを加えよう、持たせようと努力する。
住宅設計カウンセリングにおいては、まず、住まい手の生活をいろいろなアプローチからシンプルに切り取ってみる。シンプルに切り取った時、どこか悲鳴を上げる水面下の世界、部分があれば、それは、「いや」「嫌い」などの拒絶反応を起こす。
処方箋として、時間軸を取り込んだ空間の多重使い、光と影、自然の移ろいを同時に意識させることで「シンプル」にフレキシブルさを加えることが必要になる。
つまり多面的な受け止めの可能な表現、新しい機能性を見つけ出すことが必要になる。
しかし、これが過ぎると「シンプル」はシンプルでなくなる。
意思決定、選択の結果、知性の働きでその住まい手のコンセプト・文化資本を形にするはずであった設計の目論見が失われてしまうからだ。
とはいえ、水面上に表れたものがトータルにシンプルであれば、シンボリックでわかりやすいが、他者から見たシンボリックなシンプルさは、住まい手にとっては必ずしも満足を与えない。
色や形の統一、様式化は容易にコンセプト・文化を表現する可能性を持つが、かたちとして表現されなかった、生まれなかった住まい手の水面下の何かを、如何にシンプルに同調させるかは、ものづくりへの信頼関係を通じて、「愛」とか「神」といった見えないものへの共感を共有する以外に不可能なのかもしれない。
002. 道歌
ロシア人女性の日本文学研究者が、日本人の心、日本文化を非常によく表しているものとして「道歌」についてお話しをされていた。日本に留学して、勉学の傍ら合気道を習っているとき、その教えを端的に表すものとして道歌に出合い、以来、研究テーマを「道歌」に変更してまで取り組まれたとのこと。
和歌、短歌、俳句、川柳や自由詩というジャンルのあることは知っていたが、「道歌」という言い方を知らなかったので、大変興味深く聞いた。
道歌とは「道徳・訓戒の意を、わかりやすく詠んだ短歌。
仏教や心学の精神を詠んだ教訓歌」(広辞苑)ということだが、実際には、仏の道、武道、茶道をはじめ、○○道と名のつくいろいろな世界における教訓や極意を詠んだ短歌の総称ということでよいかと思う。
後日、調べてみると、「なせばなる なさねばならぬ なにごとも 成らぬは人の なさぬなりけり」、「はけば散り はらへば、またもちり積もる 人の心も庭の落ち葉も」といった今までにも、ごく日常生活の中で親や先輩に聞かされたことのあるものをはじめ、「初鴉 きくも心の 持ちようで 果報とも啼く 阿呆とも啼く」、「咲く花の 色香にまして 恋しきは 人の心の 誠なりけり」、「世の中に わがものとては なかりけり 身をさへ土に 返すべければ」等々、ともすれば見失いがちな生活の指針、人生の有り様を再確認させてくれる歌が満ち溢れていた。
ライブドァ事件、天下り問題、耐震偽造事件など、まさにこの「道歌」に戒められてきた日本人の心の在り方、生き方をもう少し確かに引き継いでおれば、ここまで呆れ返ることにならなかったのではないかと思う。
ロシア人の日本文学研究者が、古きよき日本を「道歌」を通して発見、その人間としての生き様のすばらしさ、精神を読み取って賞賛されているのに、当の日本人が、「道歌」に歌われているような道徳や振る舞い、心の持ち方などを説教くさいと斥けてしまうのはさびしい限りである。 たとえ、一道、一芸を探求する立場になくとも、先人の色々な「道歌」を噛みしめて、日常生活を「生活道」と捉えてみれば、なにか道歌のひとつも読んで人生を終えることが出来るかも知れないと思う。
「後の世と 聞けば遠きに 似たれども 知らずや今日も その日なりとは」
「なるように なろうというは 捨て言葉 ただなすように なると思えよ」こんな道歌を口ずさむと、日々の己の生き様が寒い。
でも、そんなに一直線に求道的生き方が出来ないからこそ葛藤の中で先人も道歌を詠み,人の愚かさを戒めようとしたのかも知れない。
「ぼちぼち頑張ります。」誰にともなく言いかけながら、日本人の精神文化の透明感は失たくないと思った。
003. 決めごと
三日前に、形にこだわって現場に指示したことが、夜、寝ていると突然「あれで良かったかと」気になりだす。
気持ちを集中して、出来上がりを想像してみるが、どうもしっくりしない。
いけない。近くの現場であれば、翌日すぐに現場に行くことも出来るが、今回は東京の現場であるためそうもいかない。
翌朝、現場監督に電話を入れる。もう一度、詳細に納まり寸法をチェックしながら打合せてみると、元の設計図通り、「自然な形、施工のしやすい案の方が良かった。」と、なぜかはっきりとしてくる。
「すまないが、この前の案は取りやめて、元の設計にしてくれる。」と頼む。
「私もその方が良いと思っていました。」いつも控えめな監督が答える。
「じゃぁ、それでお願いします。」と電話を切ったら、昨夜来のモヤモヤがすっきりした。
が、私の決め事が現場監督、職人さんたちを振り回してしまったことに、もっとビシット決めなくてはと反省の重い気分にもなる。
プランニングの始めから、住宅の完成まで「決めごと」がなくては全てが進まない。住い手の決め事を大切にしながらも建築家としての「決めごと」が決定的な結果につながることが多いので、プロとして、生活シーンの流れを見誤らない「決めごと」が出来る様にならなければならない。
いつも、選択条件はセオリー通りではなく、「神のみぞ知る」を繰り返しながら「決めごと術」を磨く。これが楽しめなくては住宅設計はやっていられない。
今朝もそう思い、気分に区切りをつけるのだが、本当にAかBかの選択、三者択一など、決断をしない限り事が運ばないことの繰り返しの中で、捨て去った選択は結果に残らない。例えば、実現した赤い壁の空間と実現しなかった青い壁の空間は、実現した赤い壁の空間から受ける感性の満足度からしか、その評価を受け取れないので、結果としては、どれだけの納得度、言葉を替えれば、まわりの共感度を察知して、その体感・体験を次の「決めごと」に経験値として生かすことになるのであろう。
人生においても、「あの時、あの選択をしていたら」と思い返せば色々な決めごと時がある。その意味では、建築設計という生業は、きめごとの訓練を日々行っているともいえる。
何事にも、結構決断が速いと自負しているが、早まった買い物で、思いがけぬ失敗を家人からたしなめられるのは未熟さの極みであろう。
「決めごと」には正答がない。暗黙にそのことを感知して、清水の舞台から飛び降りるスリルを楽しんでいるのかも知れない。
004. 日焼けの危険
近所の医院は皮膚科を廃止していたため皮膚科専門病院を紹介してもらう。
とにかく背中は水ぶくれ、相変わらずの痛み。
年老いた病院理事長の先生は、シャッを脱いだ私のからだを見るなり、「あなた、これは火傷ですよ。2度。体の1/2近くも火傷した状態です。」
「普通は入院して状態を見るケースです}「悠長なことを言っていると、まれに死亡しますよ」吐き気や、体温が下がる、上るなどの兆候は危険。
ほっておいて容態が急変し、救急病院に駆け込まれても、こうしたことに経験のある医師は少なく、結果手遅れで死亡すると言うのだ。
私よりはさらに老年の先生は、子供を諭すように、ここまでほっておいて病院を訪れた無知さ加減を叱る口調で、かつ、子供を諭すように話される。
とにかく写真を撮るという。
こうした火傷の場合、体温調節が出来なくなって、急に心臓に負担がかかり、心不全で死ぬケースがあるそうだ。その時、医師のほうから適切な指示がなかったとかで裁判で医師が負けることがある。そんな場合に備えて、初診の段階の状況を記録しておくと言う。
又、カルテに火傷の怖さを説明し、私にもカルテにそのように書かれたことを確認させた。「近頃は自分の対処を棚に上げて、医者が悪いと言う人が多すぎる。」
「私は自業自得と思いますから。」などと、普段の医者とあまり話さない会話の中でこの老先生の人柄を味わった。
待合室には自らの人生訓を書いた墨書が額に掲げられてもいたし、先生自らの花の油絵が数点飾ってあつたことも合点がいく次第。
「こんなことは1度体験するとまず2度とはしない。子供さんたちにも火傷の怖さを良く伝えてください。」と、教育的締めをされて診察は終了。看護婦さんにE軟膏というものをべったりと塗って貰う。
包帯は窮屈になるので、2,3枚シャツを捨てるつもりでシャツを包帯代わりにとのアドバイス。帰路、スポーツ、飲酒はだめとの指示もあり、自転車をゆっくりとこぎながら人生、最後までいろんなことを学ぶものだと、まさに体験のうれしさを感じていた。
005. 当事者の心情
ミャンマーのサイクロン被害、中国四川省の大地震、色々な災害や犯罪事件、事業成功者、色々な賞の喜びの受賞者、世界一の○○など、人間社会には様々な出来事が瞬時を待たず連続して起こり、それぞれに対峙する当事者といわれる人が存在する。
「その立場になって見なければ分からない。」と言われるが、喜び、悲しみ、怒りは勿論のこと憎悪、落胆、嫉妬、愛護などきりがないくらい多様な人間感情や想いが当事者にはあって、直接その場に居合わせたり、報道される映像を見ている側の他人にも当事者と同様の感情が少なからず沸き起こったり、立場の違いで、当事者とはまったく逆の感情を抱いたりする。人はいつ当事者になるのか。
「一寸先は闇」と言うのも冷静に思えばすぐに理解の出来ることだが、なかなか相手のその立場になれないのが凡人の常である。
自然による地震災害などは、あまりにも大勢の当事者が存在するため、立場の違いなどと言う以前に、何とか当事者の助けになりたいと祈ることや救援募金など、せめて間接的にも人間としての連帯を実感・実行したいと思う他人心情も盛り上がる。
自然の驚異が相手である場合などは、理屈ぬきに支援行動が行なわれる。しかし、親兄弟、親族、身内の命を奪われた当事者の心情は、自然に対して安全対策を怠った当局や、手抜き工事をした業者などに感情の矛先が向けられる。
その無念の心情の深さは、当事者以外の他人には決して分かり得るものではないだろう。
ごく日常の中でも、日々、人々は色々な出来事の当事者であり、部外者でありと変転、流転している。
自己存在意識は何時も当事者の心情を喚起するが、その時々の心のバロメータを大切に記憶すれば、いつか他者・部外者になった時、少しでも当事者の心情に近く反応できる自分を見つけることが出来るかも知れない。
されど、「住む世界が違う」と言うほどに立場の違う人々が、実際は存在することもあるので、当事者の心情は空転し行き場を失うこともある。
最後に「死者」と言う全ての人々が共通の当事者になった時、もはやその心情を語ることは出来ないのはなんとも皮肉なことのように思われる。
006. 効能感
頭痛を訴える人に「これは大変よく効く薬です」と言って極端な話、メリケン粉を渡してもそれを飲んだその人がよく効く薬と思い込んでいれば、効能が表れることがあることはよく知られている。
「良薬は口に苦し」と言うのも、これだけ苦いおもいをして飲む薬だからきっと良く効くと、自ら暗示を掛けるせいかも知れない。最近の研究では、人がそう思い込んだり、その気になれば、脳内から効能を発揮する物質が出され、痛みや色々な症状が緩和されるということがデータとして証明されてきた。
これを人間のもつ「効能感」というそうだ。
また時々、現代の西洋医学的診断では死亡もやむなしという状況から蘇る人がいるのも、人それぞれが範囲数値を超えた特殊性を持った生命力を備えているからだと思う。本当に人間の持つ潜在的能力はすばらしく奥深いと思うが、この事は同時に、従来の西洋医学による科学的、合理的病気診断と治療の限界を暗示している。
従来から日本においても健康維持・増進、また西洋医学で治癒することが難しい病気などに対して、鍼灸や漢方、温泉療法などが民間では行われてきたが、近年、日本より欧米においてこうした西洋医学を補完する意味合いで、東洋医学や代替医療の試みが急速に行われ説得性を持ち始めている。
英国を始め欧米ではすでに保険により西洋医学以外の治療を受けることが出来ると聞く。
病気になってしまう前に如何に健康を維持するか、健康増進を図るかという事に関しては、東洋医学やCAM(相補・代替医療)により未病の段階から自らの心身のバランスを整える、健康状態をチェックするという積極的な認識や生活習慣への気配りが大切である。
世界第2の長寿国日本、高齢者の「健康で長生き」という願いは切なるものがある。「病は気から」などは、誰もが自らの精神的窮状を切り抜けるとき呟いた記憶があると思うが、本当に人間の免疫力を始め「効能感」など、生命維持・回復力の心身一体の凄さに改めて感心している。
鍼灸,漢方、サプリメント、アロマセラピー、ヨガ、アユルヴェーダなど、昨今、美容と健康をうたい文句に巷でも色々な健康関連ショップが展開されているが、各人が、生活全体の流れの中で、「私の心とからだ」の在り様、バランスを視点として良く意識して上手に利用することが大切であろう。
人間の潜在的能力の知られざる部分が、人類の英知によって明らかになって行くという、限りない循環は恐ろしいほどに魅力的といえる。
「効能感」を操れる仙人を夢に眠りに就こう。
007. 京都の夏
温暖化という以前から、京都の夏の暑さは夙に知られ、有名でもある。
それでも、京町家では、座敷を挟む2つの庭(前庭、中庭、主庭、坪庭など)の温度差から生まれる気流を、紗、羅という薄地の暖簾で捉えて、かすかな「風」を視覚化したり、風鈴で聴覚でとらえたりして、感じ取る涼のとり方、打ち水、簾、藤の床敷き、夏季用の建具などのしつらい、生活の仕方や道具、料理まで、色々と智恵をいかして感性豊かに暑さをしのいできた。
自然と共生・協調しながらの生活の智恵が京都の夏を過ごすには必須であった。
京都は古風で且つ斬新な都市であるが、それは日々の生活を生き抜く智恵を大切にする気風が大きく影響していると思う。
しかし、バブル期の地上げ、不動産の買いあさりによって、街並みは歯抜けのようになり、近隣同士、風通しも配慮されていた家屋の配置も壊れ、多くの家は、空調機を備え、窓を締め切り、高気密、高断熱、諸設備を設置、技術で押し切って文明生活をしている。
午後の2時頃、一歩、大通りから入った京都の街は、アスファルトの路面が銀色に太陽光を跳ね返し、人影もない。
多くの人々の生活に根ざした智恵が、京都の生活を支え、文化を育んできたが、「京都の夏」酷暑を生き抜くすべ、生き生きとした生活風情は、もはや、鴨川に掛かる床席や、保存される料亭、町屋などにおいて観光資源となって残るのみなのだろうか。
京都市民が、文明を享受してはならないというのではない。文明・文化の発信者、創造者として、日本文化の歴史の一端を担ってきた京都人として気概を持つ時、今一度、市民一人一人が、酷暑を感性で受け止め、生活の智恵を鍛えることが大切ではないかと思う。
同時に、市民共通の認識として「京都の夏」と言う自然と生活の関係を見直すことから、生活のあり様に新しい気付きや発見をし、現代文明も取り入れながら、それぞれの住まいとその連担としてのまちなみのあり様への解答を文化発信力として育むことが出来るのではないだろうか。
そのためには、隣近所や町内、学区というコミュニテイの中で、誰もが感知する「京都の夏」酷暑の克服と言う課題は、取り組むのにとても良い切り口のように思える。
俗に、苦境や苦難を乗り越えてこそ、色々な智慧や解決策が生まれるというが、「京都の夏」を乗り越える調和のある、自然との対峙の仕方をさぐってみてはどうだろうか。
エコ時代ともいわれる今、文明の利器に頼り切ることなく、もう一度原点に返って、「京都の夏」を味わい尽くしてみよう。それにしても暑い。
008. 京都の地蔵盆
8月23,24日、京都では「地蔵盆」が大抵の町内で行なわれる。
最近は世話をする人の都合もあり、側近の土日に開催されるところも多くなった。
私の子供の頃に住んだ祇園祭鉾町では、町会所があり、祇園祭の関連収蔵物と同じ倉に地蔵盆の祭事道具も収蔵されていた。
朝から、町会所の表格子をはずし、表の間を掃除、倉から祭事道具を運ぶ。
長老の指示のもと、子供たちが世話当番の大人に手伝ってもらいながら、わいわいにぎやかに楽しく「地蔵盆」の準備をしたものだ。
今は子供も少なく、大抵の町内では大人が準備をしている。
各戸にちょうちんを配ることやお供えを集めにまわるのも、10時と3時にお下がりを届けるのも、数珠回しや福引といった行事の開始を知らせるために「カラン、カラン」とリンをならして合図するのも全て子供の役割で、子供のためのイベントを子供が仕切っているという趣があった。
物事の段取りを覚えるという訓練、それぞれの役割の責任、義務、社会人の真似事が自然に行なわれていた。また、町会所でのゲームや色々な遊びを通して、年上の子と幼少児の交わり、ふれあいがいっぱいあり、子供たちの夏休み最後の楽しい行事、それが地蔵盆の思い出である。
福引の景品なども、前もって長老に連れられ、おもちゃや駄菓子を扱っているお店を訪ね、あれこれ希望を言ってそろえてもらう。自分の希望した品が福引で自分に当たるかどうか。どきどき、楽しみなことであった。
今は、どちらかといえば、各家庭に均等に日用雑貨品が配られ、子供たちには図書券やお菓子が渡されるという、世話当番の大人の都合によって簡略化されてしまっている。
地蔵尊に手を合わせ祈願するという宗教心、発心の大切さもさりながら、私は「地蔵盆」の行事を子供が取り仕切る行動の流れの中にこそ多くの大切なことがあったと思う。
少子化、地域コミニテイの希薄化などで、「地蔵盆」というじつに貴重な生活教育のシーンが形骸化していくのはさびしい。
それでも、地蔵盆の頃の京都の街中には、いたるところに地蔵尊が祭られ、各町内に子供達のための修験の花が咲き、日頃には見られない趣が漂う。
足洗いと言って、片づけが終わった夜、一席を設けて、みんなで食事を楽しむのも町内コミュニテイを確認するささやかなひと時であろう。
「昔はよかった」と言ってみたところで仕方がないが、世代を超えて交わる地域・町内行事が身近にあって、生活の中で自然に色々な学びの場があった。地蔵盆はいつもそのことを懐かしく思い出させる一つである。
009. 久田の火祭り
8月24日の夜、知人の別荘・ログハウスに泊まり、京都市左京区久田・広河原の火祭りを見物した。鞍馬の火祭りは有名だが、長年、京都に住んでいても久田・広河原の火祭りは初めて見た。
山間のそれほど広くない丘陵地に1.5メートルぐらいの丈の松明が数百本、谷あい沿いに次々に燈され、野火のごとく広がり、せまり来る漆黒の山並みを背景に、ちらちらと揺らめきながら照り輝がやかし、あたりをこの世から浮遊させ不思議な舞台に変えていく。
カン、カンと鉦が規則正しく打ち鳴らされ、見物人の心が整列させられるような重なりの時を経て、次第に松明の明かりが赤黒く火勢を落とす頃、祭事広場中央あたりに高々と建てられた大松明に向って、掛け声とともに大勢の村人が火玉の固まりをくるくるとまわし、勢いよく夜空に聳える大松明の頂に向けて投げはじめます。
運動会の玉入れの籠のような頂は20メートル近くの高さはあるだろうか。なかなか命中とはいかない。松明の途中に引っ掛かって、予期せぬところが燃え上がり始めている。
次から次と掛け声、鉦、太鼓の音とともに投げ上げられる火の玉。
いつの間にか、観客から群衆と化した人々は、すんでのところで命中しそうな一投に落胆の悲鳴。
やがて、やっと待ち望んだ命中の火の玉。大きな拍手と歓声。はじめの一つが決まりだすと、次々に命中弾。大松明は赤々と燃えて、あたりに立ち上る白煙を照らす。
人々の願いごとが、炎と白煙と一体となって旅立つかのように漆黒の天空に吸い込まれていく。数分もしないうちに、燃え盛る大松明はどっと90度水平に雪崩落ちて、火の粉と火焔が巻き上がる。火祭りの終焉。
じつに粛々と行なわれるこの火祭りは、鞍馬の火祭のような勇ましさ、荒々しさはないが、広河原の村人の純朴な祈りの気風を、時を越えて伝えているのではないかと思い、好感を覚えるのです。
祭事が終わると、感嘆のざわめきと共に結構、観光バスで繰り込んだ観客がいることが分かった。この火祭りもいずれメジャーな観光資源になるのかなと予感が走る。
昔ながらの山村の祈りの空間でこそ、祖先の畏敬の心のあり様を伝えることができるのに。それにしても、こんな火祭りが、都会で身近な風情として味わえるのも、「京都ならではないだろうか。」とうなずく一夜でした。
010. 素人の大家
「職人の立場から見た町屋の住み方と監理について」という話を左官職佐藤嘉一郎さんから伺ったが、何より記憶に残ったのが、「素人の大家」という言葉である。
京都では戦前20%が持ち家、80%は借家であった。
その時代、大家さんたる本家、さらに一族の分家、別家、そして借家と係累の所有する家屋が多数あるため、お抱えの職人集団がきちんと張り付いていて、職人自体が、自分たちの仕事を生み出すためというか、積極的に建物を巡回、目配りをし、メンテナンス事項を大家に注進しベストタイミングで家の修繕・補修を行ってきたという。
戦後というか、昭和40年代以降の高度経済成長期から、持ち家政策が進行する中で、現代の京都では、持ち家80%、借家20%と比率が逆転。ほとんどの家は、建てっぱなしというか、家の手入れについて知識を持ち合わせない佐藤さん曰くの「素人の大家」の持ち物になってしまった。
住まいも生き物、大切に手入れをしてこそ長持ちもするが、ほとんど手入れすることに気づかずに多くの「素人の大家」が急増したため、その間、貴重なメンテナンス技術を継承する職人も生きていけない時代になった。
建物の工法、材料、仕様も変化したため過去と同じようには扱えないことも勿論あるが、家が使い捨て耐久消費財になってしまったといえる。
しかし、昨今、環境問題の切迫から、スクラップ&ビルドを慎もうという動きがあり、メンテナンスも重要な課題になっている。
サスティナブル・デザインなどという概念が不動産業界にまで云々されるご時世である。
しかし皮肉なことに、素人の大家さんの持ち家が、耐久消費財として早すぎる寿命を迎え始めたため、リフォームと称して日本の戦後の急激な変化の矛盾の産物を繕おうとしている。
政治における構造改革のように。今こそ、素人大家から「賢い大家」に目覚めなければならない時が来ている。納得のいく住まいに安心して住み続けられる様、業者任せのリフォームではなく、住まい手が自ら住宅建築の基本的仕組みや生活の在り様を学ぶことも必要である。そのため、建築家をはじめとする適切なパートナーにそのノウハウを学び、コラボレーションのための報酬や自らのこだわりや住まいに対する希望をまとめてもらう設計料を払ってでも、住まいと生活のかかわりを大切にする価値観を持ちたい。
「素人の大家」からの脱皮は、住まいのあり様を見直すことであり、自らのライフスタイル、生き方を見直す有意義なきっかけ、チャンスでもある。しかもそのことが、日本人のこれからの姿を変えることに繋がっているともいえる。
廣瀬 滋著



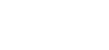







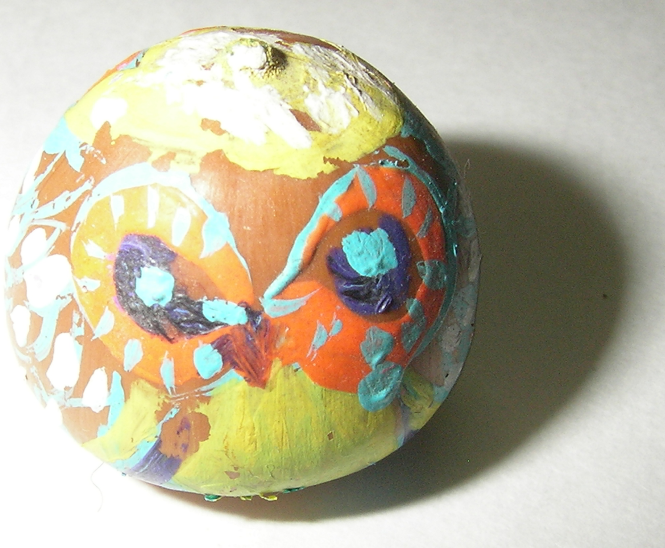











 キーワード検索
キーワード検索 商品カテゴリー
商品カテゴリー お勧め商品
お勧め商品 インフォメーション
インフォメーション 営業日カレンダー
営業日カレンダー